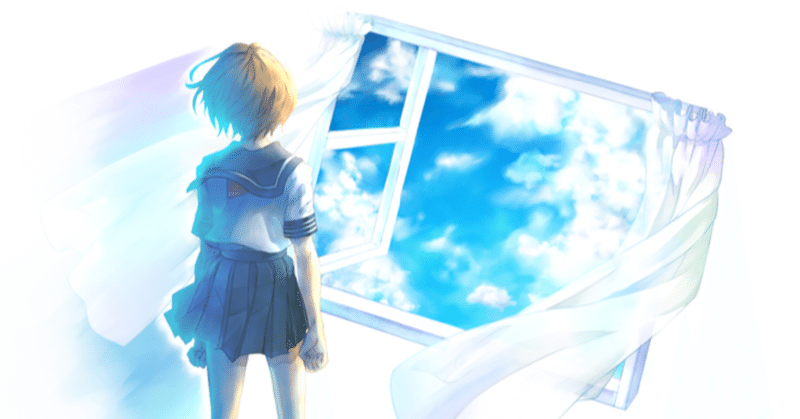
空のそら|第2章|長編小説
第2章…01
いつものように、皐月のベルが私を呼んだ。彼女がいつ来ても飛びだせるように、着替えならとっくに済ませている。素早く立ちあがり荷物をもつと、いっきに階段を駆けおりる。
階下で仕事をしていた母が、そんな私の姿をとらえ手をとめた。こちらへ歩きながら、どこへ行くのかと問うている。遊びにいくとだけ言葉をかえし、私はそのまま外にとびだした。
足を止めまともに向きあえば、母のお小言に付きあわされるはめになる。下手をすれば、出掛けられなくなる可能性もあるのだ。母は自分の都合で私の友達を追いかえす、そんなことを平気でする人なのだ。
「待ちなさい! ……待たんかーー!」
そんな母のおおきな声を背に、私は皐月の後ろにとびのった。外まで追いかけてきた母をみて、皐月も慌てたように強くペダルを踏む。
「おばちゃん、機嫌わるっ……」
「あんなん、いつものことやん」
「いつもよりやばくね? ……今日、そうとう怒られるんじゃねえんな」
「大丈夫よ、門限やぶらんけりゃ。兄ちゃんがおるし、なんとかなるわ」
「門限か、時間みちょかなやんな。っていうかさ、……朱里の兄ちゃん、よう認めてくれたでな」
「認めるっちゅうか、見張っとくんじゃけえのって、言いよったけどな」
あの日、出掛けるといって家をでた光羅。しばらくして帰宅した兄は、私の部屋へとやってきたのだ。そして自分が言いつけていたことを、しっかりと考えてみたかと訊いてきた。
彼らがやってきたことは、いけないことだと理解できるとこたえた。過去のことはどうしようもない、しかしこれからはさせないように自分も頑張るとつげた。
ため息のようなものをついた光羅だったが、その表情は落胆のものではないように見えた。「あいつも似たような感じだった」という兄のことばで、隼斗のところに行っていたのだと気づいた。
認めたのではない、見張っておくと言った光羅。その真意はわからない、それでも行くなと言われるよりはましだと思った。
「……ん? 誰もでてこん」
「まだ寝ちょんとか? ……まさかでな」
いつものように玄関まえで少しだけ迷い、やはりチャイムを押してしまった私たち。しばらくじっと待ってみたが、中からの反応がないことに戸惑う。
皐月の目が、「どうする?」と私をみる。すこし悩んだ私は、ゆっくりとドアノブに手をかけた。しかしすぐに手をはなして振りかえり、「やっぱ無理」と瞳でこたえる。苦笑いの皐月が、ふたたびチャイムを鳴らした。
扉に耳をよせて、息をひそめて中のようすをうかがう。しばらく経つと誰かが玄関に近づいてくる、そんな気配を感じとることができた。しかしこれは隼斗ではないな、そう思わせるようなゆっくりとした気配だった。
「……だれ?」
「あ、おばちゃん……ごめん」
扉のむこうから聞こえた声は、彼の母親のものだった。私の声を確認すると扉をあけて、呆れたように肩のちからをぬいた。
「あんたら、ばかじゃないんね。鍵あけちょんけえ、勝手に入れっていつも言いよんじゃろうがね。ほんっと、もう……」
「だってぇ……」
「なんが、だってかよ。おばちゃんは朝まで働きよんじゃけん、こんな時間はまだ寝ちょんって言ったろうがね」
「ごめぇん……」
「ごめえん……じゃねえで、はよ入らんかよ。なんし隼斗みたいな馬鹿に、あんたらがくっついちょんのか、ほんと……わからんわ」
雑なことばを放ちながらも、背中に手をそえて優しくなかへと誘ってくれる。玄関の内側が広くかんじることに違和感をかんじ、足もとをみてから彼の母親の顔をみた。
私の顔に文字でもかいているのか、彼の母親は隼斗たちは出掛けているとこたえた。そして行先はしらないが、私たちが来たらなかで待つようにと伝言をことづかったと続けた。
すぐに帰るのかと訊けば、行先もしらないのにわからないと笑う。はやく部屋にいけと言わんばかりに背中をおして、冷蔵庫から勝手に飲み食いしなさいよという言葉をのこし奥の部屋へときえていった。
「なあ、買い物ってなんやとおもう?」
「んー、わからんけど。……煙草か、なんかやねんな」
「茅野もいっしょやろ? 煙草くらいやったら、ひとりで行くじゃろ」
「ああ、そっか……。けど、すぐ帰ってくるやろ」
わざわざふたりで出掛けたということに、なんとなく疑問をいだいてしまった。もうすぐ夏休みも終わってしまう。そうなれば長い時間をともに過ごすことは困難になってしまう。
残された貴重な数日だとおもうと、彼たちが留守をしていることに多少の不満をかんじてしまった。しかしここは皐月のいう、すぐに帰るということばに望みをかけ待つしかない。
畳のうえに散らばった落書帳をひろいあつめ、こたつ台のうえに揃えておいた。そこから一冊のノートを手にとった皐月は、畳に寝ころがり落書きをはじめる。そんな彼女のことをみて、器用だなと感心してしまう。
心地よい室温の、静かな和室。壁にもたれてノートを見ていたはずの私だが、時折すうっと意識を失っていることに気づく。ふと見れば、皐月の手もとまっている。
そっと彼女に近づいて、同じように横に寝ころがり顔をのぞきこむ。こくりこくりと揺れるあたま、するりと彼女の手からペンが落ちた。笑いをこらえながらペンをひろい、キャップをしてノートの横においた。
彼女の書きかけの落書帳を自分によせて、なにを書いていたのかと覗きみた。だがしかしそれを読み終えるまえに、私の意識もかんぜんに持っていかれてしまった。
どのくらいの時間、眠ってしまっていたのだろうか。電話の音に目をさまし、部屋のなかを見まわした。窓からの陽光の角度は変わっているが、隼斗たちはまだ帰っていないようだ。
鳴っていたのは、玄関ちかくに置いてある固定電話だった。隼斗の母親がやってきて、よそいきの声色で電話にでた。すこしして重い返事をした母親は、電話をきってこちらへやってくる。
「ちょっと、朱里……開けるで」
「……うん、どしたん?」
「おばちゃん用事ができたけん、あんたら今日は、もう帰りよ」
「え、なんで? 隼斗たち待っちょったらいけんの?」
「……んー、おばちゃん遅くなりそうやけん。……鍵、かけるけん。とにかく、もう帰りよ」
鍵はしないから、勝手にはいれ。誰もいなくても、あがっていい家。たしかにいつも、そう言われていた。母親が出掛けるにしても、じきに隼斗たちが帰ってくるはず。なぜ今日にかぎって、母親は帰れというのだろうか。
私たちは慌ただしく立たされて、急かされるように玄関へと促された。多くは語らない隼斗の母親の、たどたどしい理屈も気になる。
「なんな! あんたら……まだおったんな。おばちゃん行くけんな、もう帰んなさいや」
気忙しいようすで出てきた彼の母親は、玄関のまえに立ちつくしている私たちをみて渋い顔をした。すぐさま本当に鍵をかけて、慌てたようすで階段をおりていった。
全く状況がつかめないままに、追い出されてしまった私たち。どうしてだと質問を投げかけながら、彼の母親のあとを追って階段をおりていく。
階段をおりきってしまうと、そこには一台のタクシーが待機していた。彼の母親は私たちのほうを見ることなく、そのタクシーに乗りこみ行ってしまった。
その場に残されてしまった私たちは、成す術なくタクシーを見送る。ふたり言葉をかわすことすら忘れ、しばらくぼんやりとその場に立っていた。
「……え、どうする」
「鍵、されたしな……。どうしょっか……」
「朱里のおばちゃん、機嫌わるかったし……。鍵かかっとるけん、入れんし。……もう、帰る?」
「……そうよな、入れんしな。帰ろう……か……」
来るときとはちがって重い気持ちで、自転車には乗らずに押してあるく。隼斗と別れるまがり角より、ひとつ手前の角で皐月とわかれた。
自宅に向かうにつれさらに足取りは重くなり、なんども立ち止まっては振りかえった。いつものまがり角まできて、ふたたび立ち止まり振りかえる。そして私は進路をかえて、いま歩いてきた道をもどってしまう。
市営団地のしたまでもどった私は、階段のしたにすわりこむ。ふと思いがよぎり、立ちあがって階段をのぼった。三階の玄関のまえに立ち、勇気をふりしぼりドアノブをまわしてみた。
期待していた状況にはならず、肩をおとして階段をおりた。ほかの利用者の邪魔になってはいけないと、団地のまえの駐輪場のそばの石段に腰をおろした。
すっかりと辺りは暗くなり、門限の時間などとっくに過ぎていることは明らかだ。どうして隼斗は帰ってこないのだろうか。心細くなりながらも、ずっとその場に座りつづける。
ひとの気配がすれば立ちあがり、ちがうとわかれば再びすわる。隼斗の家以外の家のあかりは、すべて灯されているように感じる。
静かになってしまった団地の道路に、車の音が聴こえたきがして立ちあがる。角をまがってきた車のライトが、こちらへ向かって近づいてきた。
目のまえに停車したのは、隼斗の母親が乗っていったタクシーだった。もしかして隼斗も乗っているのではないか、そんな期待もむなしく降りてきたのは彼の母親ひとりだった。
「朱里? あんた……まだ、おったんな! ばかじゃないんね、この子は……」
「だってな、おばちゃん。……隼斗がな、まだ帰ってきとらんので」
「あのバカなんか待っちょらんで、いいけん……はよ帰りなさい」
「けど……」
「けどじゃないやろうがね! ……親が心配するやないね。……いいか、もう帰るんで。いくら待っちょっても、今日は……あん子は帰ってこんのやけん」
足をとめることなく階段をあがる、彼の母親のあとを追った。玄関のまえについたとき、彼の母親はふり向き隼斗は帰らないといった。
どうしてだと質問を投げかけたが、それに答えはかえってこず扉は閉められてしまう。急いでドアノブに手をかけたが、なかからは施錠される音がひびいてしまった。一気に押しよせる虚無感に、鼻の奥がつーんと痛くなった。
「……お前、こんな時間まで……ここで何しよんのか」
階段から声がして、そちらを振りかえり涙がこぼれた。扉のまえで立ちつくしている私のもとまで、声のぬしはゆっくりとあがってくる。
こんな時間といわれ、はっと現実に引き戻された。そうだ、こんな時間なのだ。門限を少しすぎたなどの、そんな軽いものではなかった。また母親に叩かれる、そう思った。
階段をのぼりおえた声のぬしは、ほっとしたように私を抱きよせた。心配をさせてしまったことを、後悔してしまう。やはり皐月と帰ったあのときに、そのまま家に帰るべきだった。
「……こんな時間まで、外におっちょったら心配するじゃねえか。……なんかあったら、どうすんのか」
「……ごめん、兄ちゃん。門限……また怒られる……」
「大丈夫っちゃ、お母にはなんも言うなっていっちょるけん、今日は怒られりゃあせんけん」
「あんな、……隼斗を待っちょったんやけどな、おばちゃんがな……」
「そん話はいいけん。……ほら、もう帰るぞ」
光羅は話をさえぎって、私の手をとり階段をおりはじめた。本来ならば門限をやぶった理由を訊いてくるはずなのに、まるでその話をさけるような雰囲気だ。
隼斗は帰らないといった、彼の母親の言葉がよみがえる。もしかしたら兄もそのことばの意味を、隼斗が帰らない理由をしっているのだろうか。
帰路の途中の街灯のした、見あげた光羅の横顔がこころなしか不安気にみえた。そんな兄の顔をみて、私はなんだか泣きそうな気持になる。
第2章…02
ベランダの窓を全開にして、部屋にこもっている煙をそとに追いだした。真夏とはいえほどよく吹く風のせいか、そこまでの暑さは感じられない。
団地のしたで遊ぶ、子供たちの声がきこえてきた。もうすぐこの楽しそうな声もなくなるのだなと、夏休みの終わりが近づくことを再認識する。
「うーっす。……あれ、まだあいつら来てねえんやな」
「そろそろ、来るんじゃねんかや」
「そりゃそうとさ、あれやん。夏休み、終わったら……どげするん。七瀬が言いよったみたいに……」
「ああ……、あれやろ。そうなぁ……一応、考えはしよんのじゃけんど」
夏休みが後半寄りの半ばにさしかかるころ、いつものようにここで過ごしていたときのことだ。誰からともなくはじまった、夏休み後の過ごし方のはなし。
学校がはじまってしまえば、こうして朝からここにくることは難しくなる。そんな現実にきづいた朱里は、わかりやすく寂しそうな顔をした。
そんな彼女をみた七瀬は、俺にむかって「学校にくれば?」と涼しくいったのだ。いやみで言ったのか、本気でいったのかは定かではない。しかしその提案をきいた瞬間の、あの朱里の瞳の輝きが脳裏からはなれない。
それから俺は、ずっと悩んでいるのだ。朱里がここへ来れない平日、もちろん毎日など無理なはなしで、普通の学校生活など無茶なはなしだ。
それでも彼女を喜ばせたい、すこしでも多く彼女にあいたい。そんな気持ちが芽生えていて、あの屋上に通ってみようかと考えているのだ。
ふと茅野の手にある、落書帳に目がいった。ぺらりとめくられたノートの頁に、朱里の楽しそうな顔がかさなった。その笑顔はその落書帳を、この部屋にもちこんだ日のものだった。
「なあ、お前ってさ。だれかに物とかって、やったことある?」
「は、物? え、やるってプレゼントってこと?」
「プレゼント……。まあ、とにかく……ひとに何か渡したことっちゅうか」
「なんかそれ、ようわからんな。……まあ、どっちしてもあんまり記憶にはねえけんど。あれや、幼稚園んときとか、交換とかはしたような気がするで」
「……幼稚園。交換か……、なんか聞いても意味なさそうやの」
「なんか、その意味ねえっちゃ……。あれか、椎名の誕生日かなんかあるんか」
「いやの、そのノート持ってきたとき朱里って嬉しそうやったやん? ひとに物を渡すんって、そげえ楽しいんじゃろうか……って思ったんよ」
茅野にいわれて、自分が彼女の誕生日を知らないことに気づく。朱里がきたら訊いてみよう、そしてなにか贈り物をしてみよう。
そこでふと、よけいな思いが脳裏をよぎる。もしも誕生日が、ずっと先だったらどうするか。いますぐ知りたい、試してみたい。俺のなかの変な願望が、どうにも騒がしくあばれだした。
「なあ、茅野。買い物、いこうや」
「なんの?」
「なんの? ……わからん」
「は? なんそれ……。まじでお前、へんやぞ」
俺に対して変だと吐きすてた彼が、「あ……」といってにやりと笑う。その意味ありげなたいどに「なんか」と問うが、彼はふくみ笑顔のまま首をよこにふった。
俺にたいして変だとほざいた茅野だが、ことのほかすんなりと立ちあがり玄関へとむかった。なんなら早々に靴まではいて、まるで俺を急かすかのような視線をむけてくる。
とりあえず街へは出てきたものの、購入する物がいまだ決まっていない。なんせ今日このときまで、誰かのために何かを買ったという経験がないのだ。
ましてや相手が女子となると、尚のことさっぱり見当がつきはしない。外から店内のようすをうかがって、女子が多そうな店をさがして入店してみた。
店内をうろつく俺たちに、店員らしきひとの視線が釘付けになっていた。それは疑いの眼差しだと直感した俺は、近くにあったカゴを手に取り客であることをアピールする。
「……なあ、居心地わりいよな」
「ん、うん……。けど、なんか買うんじゃろ? ……はよ選べの」
「選べっちゅっても……さっぱり……。朱里って、どんなんが好きなんやろう。全くわからんのじゃけど」
近くから聞こえた可愛いということばに、俺はすかさず振りかえった。ふたり組の女が手にしていたものを確認する。手から商品が棚にもどされ、彼女たちがそこを離れるとそれをカゴにいれる。
そんなことを幾度もくりかえし、少しちいさめのカゴがいっぱいになってレジへと向かった。俺たちのあとを追うように店内を歩いていた店員が、「贈り物ですか」と言いながらやってきた。
「え、あ、……いや、そんなんじゃねえで。……えっと……」
「……一応、可愛いめの紙袋にお入れしましょうか?」
「……あ、えっと。……はい」
黙って会計をすませれるものと思っていた俺は、予想だにしなかったことに赤面した。会計を済まし袋詰めをする間、ほかの客の視線が居心地のわるさを煽ってくる。
お待たせいたしました、と言って手渡された紙袋。そのおおきさと可愛さが、さらに俺に好奇の目をあつめることになった。用事はすんだ、こんなところにはいつまでも居られない。
視線から逃れるように、俺たちはいそいそと店の出入り口へと向かった。外の空気にふれた瞬間、やっとまともに息ができるようになった気がした。
「お! 久我じゃね? なん、久しいやん。こんなとこで何しよん」
「んあ? 別に、なんもしよらせんわ。……茅野、いくぞ」
「なぁんか、そげえ慌てて行かんでもいいやんか」
「うるせぇ、ひとを待たせちょんのじゃ」
「なんかそれ。最近、いっこもこっち顔ださんじゃんか。お前おらんと、なーんかつまらんのよの……。その待たせちょんやつ放くって、俺らと遊ぼうや」
「……お前らとは、もう遊ばん」
「はああ?」
相手の顔つきがかわった。へらへらと後ろで笑っていたやつらも、いまにも掴みかかってきそうな態度にかわる。俺だって馬鹿ではない、会話だけで終わることができるなんて思ってはいない。
こんなことに、茅野を巻き込むわけにはいかない。そしてこんなことで、朱里への贈り物をだめにするわけにもいかない。
「茅野、悪りいけんど、これお前んちに持って帰っちょってくれんか」
「え、じゃけんど……」
「いいけぇ! 帰れって……。朱里たちには、なんも言うなよ」
紙袋を茅野の胸におしつけ、家に持ち帰るように指示をする。なかなか帰ろうとはしなかった茅野だが、この贈り物を守りたいという俺の気持ちは通じたようだ。
仕方なさそうに紙袋をうけとり、なんども振りかえりながらこの場をはなれる。茅野の姿がみえなくなったのを確認して、俺は連中のほうに振りかえった。
どういう態度に俺がでるのかを、相手はさぐっているようすだ。そこで改めて今後つるむつもりはないと、俺の意思を相手につたえた。
おもったとおり連中は発狂し、裏切るつもりかと拳をぶつけてくる。挑発するような罵倒をあびせられながらも、俺はそれに乗ってはいけないと思い耐えた。
「なんか、久我! なんもやり返してこんつもりか」
「女にのぼせあがっちょるっちゅう、うわさ。あれ本当なんじゃね」
「まじ、どんな女か見てみてえわ。ここ終わったら、探しに行かんか?」
「やっべえ……。なんかもう、おれ興奮してきたんじゃけど。さっさとこいつぶっ殺して、ヤリに行こうや!」
朱里が危ない。瞬時に俺の脳みそが、なにかの指令をだした。そして俺が把握できないほどの速さで、俺の身体は指令に従っていた。
とおまきに見ていた通り客の中から、女の悲鳴があがった。そして俺の目のまえには、立て看板を頭にくらって血を流しているやつがいた。
幾度となく、あがる悲鳴。しかし俺の脳みそは、既に制御不能になっていた。いまここでこいつらを殺ってしまわなければ、朱里が危ない。そう、誰のこえも聞こえない。そして、パトカーのサイレンも聴こえていなかった。
「……また、お前か。なんし仲間内で、こげんことになったんか」
「は? 仲間とかじゃねえし」
「まぁな、……確かに、最近は見かけんな……とは思いよったんやけどの。んで? ……なにが原因か」
「べつに、なんも」
「なんもねえで、こげな大事にならんやろうが……。知っちょろうけんど、……喋らんと帰れんぞ」
「……あ。……なあ、ちょっと……。あのひとと話、させてくれんかや」
「……ん? あのひと……って……」
警察署のなかの狭苦しい部屋。すでに顔見知りになってしまっている警察官は呆れた顔をしている。仲間、仲間とくちにする男に、内心は苛っとしていた。
申し訳ていどの窓のむこうに、母親と億劫そうな北斗の姿がみえた。そしてそんな北斗のうしろに、怒りにみちた顔の光羅の姿をとらえた。
警察官は俺の視線をたぐるように窓のほうへと視線をうつし、ここへ入れるわけにはいかないと苦笑いをした。それなら別にいい、ここからも口を閉ざすだけのこと。
一切の質問にそっぽを向いて喋らない俺に、警察官はわかりやすく疲れを顔にだした。光羅のするどい視線は、ずっとこちらを向いていた。
机のうえで両腕をくんでいる警察官のひとさし指は、秒針よりもはやいリズムで時を刻んでいる。ぱんっと全ての指がつくえを叩き、警察官は立ちあがった。
「おい、こら、隼斗! お前、ようもこげえ簡単に裏切ってくれたのぉ!」
「違っ……ごめん、光羅兄……」
「なにが違うか! 言うてみぃ! なにが違うんか!」
なにがあって、喧嘩になったのか。俺は、順をおって彼に話はじめる。茅野は先に帰したこと、朱里たちに対しての口止めのこと。
彼女には、知られたくない。なにより彼女を、巻きこみたくないこと。いまにも殴りかかってきそうだった、そんな光羅の拳がおりた。
「……お前、そこまで朱里を気にできたんなら、なんでもうちっとう……我慢できんやったんか」
「……だって、だってな。あいつらが……朱里にな……」
連中が朱里の存在をしっていて、興味をもっていたことをはなす。俺が仲間にもどれば彼女は安全かもしれない、しかしそれはしたくなかったと。
そとに出ていた警察官が、部屋へともどってきた。俺と光羅のはなしは、警察官に聞かれていたのだろうか。それはわかりはしないのだが、やけに絶妙のタイミングだった。
警察官は光羅の背中をかるくたたき、そとに出るようにと顎でしめす。
「光羅兄!」
「……わかっちょん。すまんの……隼斗。……無茶……すんなや」
きっと彼は、このことを彼女には伏せてくれるだろう。伏せてはくれるだろうが、今後のことはどうなのだろうか。いままで通り、会うことを許してはくれるのだろうか。
扉のむこうに、呆れた顔の北斗がみえた。振り向かない、光羅の背中。警察官によって扉がしめられるまで、俺は不安なきもちでそれを見送った。
第2章…03
翌日、私たちは隼斗たちには会えなかった。翌々日も、そしてまたその翌日も隼斗に会うことは叶わなかった。
光羅から交際を禁止されたわけではなく、外出を禁じられているわけでもない。私たちは毎日、隼斗の家へ通っていた。
しかし玄関には鍵がかかっており、なかへ入ることは出来ずにいる。扉のむこうに、ひとの気配を感じることはできる。それなのに、鍵があけられることはなかった。
「なんで、開けてくれんのじゃろうか……」
「……わからん」
「もういっかい、……ならしてみる?」
私たちのチャイムに、いちどは玄関まで誰かがきている。しかし少しするとその気配は、奥へと去ってしまうのだ。
私たちだと確認したうえで、無言の対応をしていると判断をする。チャイムに伸ばされたひとさし指が、それを押さずにゆっくりと帰ってくる。
そこに居るのは誰なのだろう、どうして扉を開けてはくれないのだろう。わたしは嫌われてしまったのだろうか、だとしたら何をしたからなのだろうか。
心のなかでひとり問うてみても、答えなどでるはずもない。不安ばかりが募っていき、その場にいることにも戸惑いを感じてしまう。
夏休みの、最後の日。今日はどうするかとの皐月からの電話に、わたしは行かないと返事をした。しかしそれは、わたしがついた嘘だった。
あのどんよりとした雰囲気のなかに、まいにち彼女を巻き込んでいるのが申し訳なかった。どうせ今日も開けてはもらえない、それならひとりで行こうと思ったのだ。
団地のしたに着いたわたしは、それを見あげてため息をついた。どうしてこんな事になってしまったのか、理由がわからずに気持ちのやり場がない。
重たい心をぶら下げたまま、踏みしめるように階段をのぼっていく。三階のその扉のまえで、やはりひとりは心細いと感じて後悔をした。
ふとのぞき穴が目につき、おもわず右手でそれを塞いだ。いまこの情けない顔を、なかの人物にみられることが心もとなかった。左のひとさし指が、チャイムを押す。
「……だれな」
「…………」
玄関までやってきた気配は、しばらくすると問うてきた。それは、隼斗の母親のものだった。怯んだわたしは、声をだすことができずにいた。
まさか、中からの反応があるなんて。わたしだと伝えたい気持ちと、いますぐ逃げ出したいきもちがぶつかった。頭のなかの整理がつかずに、そのまま固まってしまう。
「……どちら……さん?」
「あ、えっと……」
「……ん? ……朱里か?」
「……あ、うん」
勢いよく扉があけられ、ほぼ同時にあたまに平手打ちをくらった。リアクションに戸惑ったわたしは、とりあえずへらっと笑ってみせる。そして二発目の平手打ちを、ふたたび頭にくらった。
「この馬鹿娘が! あんた、穴かくしちょったんやろ」
「うん、……ごめん」
「ごめんじゃねえが、ほんと困った子じゃな。……誰かと思うて、びっくりするやろうがね!」
「おばちゃん、隼斗……おる?」
玄関は開けてもらえたが、なかに入れてくれる様子ではなかった。そこに彼のくつがないことは見て取れたのだが、私のくちはそう問いかけていた。
案の定、居ないという返事。そして続けて、しばらく帰らないだろうと付け加えた。ことばの意味はわかるのだが、この状況が把握できない。
そしてそれを問うてみても、彼の母親からの説明はなかった。しばらく粘ってはみたものの、結局は最後まで教えてはもらえず、帰ったら連絡をさせるからと追い返されてしまった。
あの日からいちども隼斗に会うことはなく、二学期は始まってしまっていた。もしかしたら来るのではないかという淡い期待が、私たちを屋上へと入り浸りさせる。
この数日間ここでこうして休み時間をすごし、放課後になれば団地へといき無言の仕打ちをうける。私も気まずいが、彼の母親もきっとうっとうしいと感じているだろう。
「なあ、あれから久我と連絡とかとれたん?」
「いんや……。家とかも、行ってみよんのやけど。おらんみたいなんよな……」
「そうなんや? ……あれっきり、茅野にも会っちょらんよな」
「そうでな、一緒におるんやろうか……」
「どうするん? 今日も、家にいってみるん」
校舎のなかに、チャイムが鳴りひびく。まもなく昼休みが終わるという知らせだ。ため息をつきながら重い腰をあげ、それぞれの教室へとかえっていく。
席替えにより、わたしの席は窓ぎわではなくなった。しかし私はためらうことなく、窓ぎわのせきへと着席した。そうここは教室にいない、茅野の席なのだ。
なんの授業がはじまったのか、あまり把握できないままに時間がすぎる。わたしの視線はずっと外にあり、ときおり時刻を確認するためだけに教室にもどる。
正門から、一台のタクシーが入ってきた。タクシーで来校するとは、なんとなく珍しい客ではないだろうか。中央にある池をまわって、タクシーは正面玄関のまえに停車した。
「うそや!」
「……どした、椎名。嘘じゃねえぞ、まだ授業中ぞ。はい、ちゃんと座れ……あ、こら! どこ行くんか、戻らんか!」
「うるせぇ!」
「う、うる……。こら! 戻れー!」
停車した車のドアが開き、そこから姿をみせたのは隼斗だった。自分の椅子をなぎ倒し、大声をだして立ちあがってしまう。
教員をふくめクラス全員が注目したが、わたしはそれには気づいていなかった。教員がなにかを言ったが、耳障りな音にしか聴こえない。
そのまま教室を飛びだして、わたしは中央階段を駆け下りた。三階からの距離、どんなに急いでも間に合わなかった。寸でのところで行きちがい、隼斗は職員室へと吸い込まれてしまった。
それを追いかけるように、職員室の扉に手をかける。しかし扉のむこうにいた教員に、入室は阻止されてしまった。
「こらこらこら、まだ授業おわってなかろうが。ほら、教室にもどりなさい」
「あ、いや。……ちょっと、用事が」
「なぁんの用事があるんか。……嘘はいけん、うそは」
「嘘じゃねえっちゃ。いま、久我がきたじゃろ? ちょっと用事があるんって」
「久我に? ……ああ、担任の矢野先生と大事な話やけん、なおさら入らせるわけにはいかんな」
担任と、大事なはなし? 担任の、矢野? ここではじめて、皐月と隼斗が同じクラスだということを知った。
何がなんでも通すことはできないという教員にまけて、わたしは仕方なく引きさがる。しかし教室にもどることはせずに、正面玄関のなかの来客用靴ばこの前に座りこんだ。
授業中である校舎のなかは、とても静まりかえって落ちつかない。事務窓口にいる職員の視線も、居心地のわるさの要因になっている。
職員室の扉がひらく音に、わたしは立ちあがった。目視をしたわけではないが、挨拶を交わすやりとりから隼斗たちだとわかった。
来る……、もうすぐ彼がくる。近づいてくる気配に、泣きそうな気持になる。駆け寄りたい衝動をこらえ、廊下を曲がってくる隼斗を待った。
「……あ……あかり……」
「……は……や」
「隼斗! ……いくで、はよ!」
わたしの姿に気づいた彼は、一瞬だけ立ち止まった。しかし私たちの会話を阻むように、彼の母親が隼斗の腕をひいた。
空気が重い。そして彼の表情も、とても重い。怒っているそれとは違う感じで、眉間をよせ目を逸らした。なぜ、なぜなのだろう。靴をはく彼の背中に、答えはみつからない。
やっと会えたと思ったのに、少しの会話も許されないこの状況に頭がついていけない。隼斗の母親は、なにをそんなにぴりぴりとしているのだろうか。
「隼斗! ……なんで? どしてなん」
「…………朱里、ごめんな。……ばいばい」
放心していたわたしは、靴をはいた彼を見送ってしまっていた。隼斗が玄関をでてしまったことに気づき、慌てて声をかけて追いかける。
タクシーのドアのまえ、隼斗の動きがとまった。しかし彼は振りかえらず、つぶやくように言葉を残し車に乗り込んだ。
訊きたいことなら、たくさんある。なのにそれが、スムーズに出てこない。彼の母親の合図で、タクシーのドアが閉められた。隼斗と二度と目があうことはなく、車はゆるやかに発車した。
第2章…04
扉が完全に閉められてしまい、光羅とのつながりを断ち切られた感覚をおぼえる。彼は俺にあきれてしまっただろうか、愛想尽きてしまっただろうか。
向かいの椅子に腰かけた警察官が、「いまの人とは?」と俺と光羅の関係性を問うてきた。俺は先輩であるということだけを伝える。
きっとこいつは中の話を聞いていた、もっと詳しく訊きだそうとしているに違いない。これは俺が勝手にやったこと、光羅たちを巻き込むわけにはいかない。
「……なあ、帰っていいかや? もう今日みたいんは、ねえと思うけん」
「ほお、えらい自信ありげやの」
「…………」
「まあな、なんとなく……お前の考えちょることは、わかるような気もするんやけどの。……じゃあけんど、……のぉ……」
ああ、俺はここに泊りなのか。こいつの濁し具合で、容易に察しはつく。どうせ何故だとたてついても、過去があるからだと返されるにちがいない。
こいつらの考えていることは、おそらくこうだ。取り敢えずひとばん牢にぶちこんで、すこし反省でもさせておこう。現実に、そんなことで反省するようなやつはいない。
たったひとばん自由をうばわれたとて、寝てしまえばあっという間に朝はくる。雨風しのげる寝床をあたえられた、それくらいにしか思わない。
思ったとおり、俺はそのまま留置所に連れていかれた。途中、帰っていく北斗と光羅の後ろ姿をみた。母親の姿は、見当たらなかった。
俺にしてみれば、久しぶりの留置所。なにも苦痛ではなく、すぐに眠りにつけるはずだ。ほとんど見えない夜の空、月のあかりすらあるのかわからない。
朱里は、どうしているだろうか。戻らない俺を、どう思っただろうか。怒って家に帰ったのだろうか、それとも心配させてしまっただろうか。
明日、きっと何をしていたのかと訊かれるだろう。俺はどう言い訳をして、どう謝るべきなのだろうか。なんだかやけに、今日は夜が長いな。
「おーい、久我……起きろよ。親に着替えの連絡するけん、なんか必要なもんあるか」
「……は? なん、着替えって」
「なんって、ずっと同じパンツ履いとくわけにゃ、いかんじゃろうが。とくに無いなら、親の判断でもってきてもらうけんの」
状況は、嫌でもわかる。しかし今回にかぎって、なぜ長居することになったのか。訊いてみたところで、とうぜん詳しい返答などあるはずもなく。
俺を呼び起こした警察官は、鍵をあけることはなく去っていった。俺とやり合ったあいつらが、重体にでもなってしまったのだろうか。
数日後、母親が着替えの取り換えにやってきた。なぜ自分がこんなに長く帰れないのか、母親に訊いてみたが「知らん」とひとこと返された。
俺は声をおとして、朱里のようすを問うてみる。母親も同じように周りを気にし、ちいさな声で「あん子にはなんも言うちょらん」といった。
居留守をしても追い返しても、彼女は懲りずに毎日やってくるという。「もういやだ、うんざりだ……」最後に母親はそういって、着替えを置いて部屋をでた。
「……なあ、兄貴。……俺って、どうなるんかや」
「さぁな。……なんか、家裁のよびだしやらで、ババア……だっちょんみたいやわ」
「家裁……。まじか、……施設……かやぁ」
何度目の、家庭裁判所だろうか。俺はわかりやすく落胆し、机のうえに肘をつき頭をかかえこんだ。もう後はない、前回のときに忠告をされていたのだ。
大丈夫だと北斗はいうが、それは単なる慰めのことばでしかないと知っている。望みがうすいことは薄々かんじてはいるが、捨てたくはないとため息にかわる。
もどされた留置所のかたい床のうえ。寝ころがって無機質な天井をながめていた。夏休みは、あとどのくらい残っているのだろうか。
彼女は、どうしているだろう。まだ毎日のように、家に通ってくれているのだろうか。あまりにも時間がありすぎて、昼夜の感覚がわからなくなっていく。
持て余すほどの時間は、俺に色々な思考をあたえてきた。あれをやってなければ、これを止めておけば。はじめて留置所のなかで、俺は後悔という感情をいだいた。
月が替わりしばらくしたころ、母親がいつものタクシーで迎えにきた。「ばかたれが」そういって俺たちを乗せ、運転手は市営の団地へとむかう。
「さっさと風呂はいって、はよ支度しよや……」
「……支度、……家裁な」
「どこでんいいけん、はよ! はよ風呂いってきよ!」
自宅に着くや否や、気忙しく身支度をさせられる。おそらく家裁の呼び出しにあわせ、俺を迎えにきたのだろう。気乗りなどするはずもなく、だらだらと支度をする。
「隼斗、時間がねんぞ、はよせえよ!」
「うるせぇ、ジジイ……」
団地の駐車場に車をとめた運転手は、玄関をあけるなり俺にむかってそういった。そのまま台所へとあがりこみ、冷蔵庫から麦茶をとりだしラッパ飲みをする。
そんなあいつを横目でみながら、俺は風呂場へとむかった。俺がジジイと呼んでいるあいつは、母親のお抱え運転手ではない。男と女の関係であることくらい、ガキの俺でもしっている。
俺をかろうじて繋ぎ止めていた、心もとない微かなのぞみ。それは連れていかれた家庭裁判所で、こっぱみじんに打ち砕かれてしまった。
いまの生活から切り離されてしまう、それが確定してしまったのだ。おそらくもうお手上げだと、母親が家裁に泣きついてしまったのだろう。
あの日、北斗は母親も繋ごうとしていると言っていた。しかしそれは彼のうそ、こんな俺を家においておくのは面倒だったに違いない。
「……ジジイ、どこ行きよんのな」
「…………」
ルームミラーで俺をみた彼は、何もいわずに目をそらした。すぐに母親から、学校だとつげられる。その行き先をきいた瞬間、俺の脳裏には朱里の顔がうかんだ。
一瞬でもいい、会うことができるだろうか。いや会わなくていい、遠くからひとめ見るだけでいい。話したい、いや辛くなるだけだ。俺のなかで、何かがせめぎあう。
正門をぬけた瞬間、俺の視線は彼女のすがたをさがしまわっていた。どこにも生徒のすがたがないことに、いまが授業中であるとわかった。
なんてタイミングが悪いのだろうと思う反面、好奇の目にさらされることはないと安堵もする。
「あ、久我さん。……ここでは、あれなんで。向こうの部屋にいきましょう」
職員室にはいるなり、ひとりの男が走りよってきた。痩せこけた男に、母親は深々とあたまをさげている。向こうの部屋、それは職員室よこの応接室だった。
職員室と繋がっている内扉をあけ、男は俺たちをそこへと誘導した。ソファーに座り向かい合ったこの男は、矢野と名乗った。どうやらこいつが俺の担任らしい。
俺が留置所に泊まっているあいだに、あらかたの話は済ませてあったのだろう。母親は矢野に、最終結果だけをつげた。
廊下側の扉のまえが、なにやら騒がしい。なかへ入らせろと騒いでいる声に、俺は胸が締め付けられた。そのやり取りはしばらく続き、そしてやがて静かになる。
「久我、わかったか? ……先生な、お前のこと待っとるけんの。真面目に、……しっかりと頑張って、はよう帰ってこいよ」
「……え? あ、……ああ」
とつぜん話をふられて返事をしたが、正直どんな話をしていたのか聞いていなかった。俺の意識は完全に、扉のむこうの朱里に持って行かれていたのだ。
担任は待っているといったが、俺は余計なお世話だと思った。俺が待っていてほしい人間はただのひとり、朱里だけだと思ってしまった。
職員室側にもどり、そこにいる全ての教員に頭をさげた。そうしなければならないような、そんな雰囲気に覆われていたからだ。
息苦しいそこから解放され正面玄関へむかうと、そこに情けない顔をした朱里が立っていた。おもわず立ち止まり、名前をくちにしてしまう。
いまにも泣きだしてしまいそうな彼女の顔に、俺はどうしていいかわからない。それを察したのか、母親が俺のなまえを呼んだ。はっと我に返った俺は、彼女の前から離れ背をむける。
「隼斗! ……なんで? どしてなん」
「…………朱里、ごめんな。……ばいばい」
振りかえれなかった。なぜこんなことになっているのか、何があったのか。理由を訊きたいという彼女の訴えに、正面から向き合う自信がない。
振りかえることなく絞り出したことば、それが今の俺の精一杯だ。泣かせてしまった、苦しませてしまった。こんなことになるとわかっていたならば、俺たちは最初から出会うべきではなかったのかもしれない。
第2章…05
上履きのスリッパのまま飛び出した、正面玄関のまえ。立ちつくし見つめる、正門のその向こう側。そこにはすでにタクシーの姿などはない。
職員室の窓があき、そこで何をしていると声がかかった。教室に戻れと手ばらいする彼に対して、特になんの感情もいだけない。
そのまま無言で背をむけ、校舎のなかへともどっていく。頭のなかで繰り返される、「ばいばい」という言葉。階段をのぼるその足は、鉛でもついているかのように重かった。
三階までのぼったところで、茅野の姿をとらえた。屋上へとつづく階段の一段目、そこに彼はすわっていた。
「……茅野。そこで、……なんしよん」
「椎名……。おまえんこと、待っちょった」
「なんでな」
「渡すもんがあるけん。……屋上、きてくれん」
まえを歩く茅野の足取りも、私とおなじほど重くかんじられる。彼は何かをしっているのだろうか、渡すものとはなんだろうか。
私がおどり場あたりに到着したとき、彼はすでに最上階についていた。つくえの横からなにかを手にとり、それを持って階段をおりてくる。
茅野の右手にあるのは、大きな紙袋だった。その場で立ちどまり彼をまっていると、私のまえにその紙袋をさしだした。
「……なん、これ」
「久我から……」
「は? 隼斗なら……さっき……。なんであんたから渡すんな」
「……俺が、預かっちょったけん」
なかなか受け取ろうとしない私の右手に、紙袋を強引ににぎらせる。茅野から目を逸らさない私に、なかを見ろと言わんばかりに顎をつきだした。
紙袋のなかみより、目を合わさない茅野のほうが気になる。そうだ、このタイミングで茅野がここに来ることも、彼が預かっていたという事実も不自然すぎる。
「……いいけん、見てん。なにがいいかわからんっちゅって、楽しそうに買い漁りよったんじゃけん」
「買い漁る……。あの日の……こと? 一緒に買い物して、なんであんたがこれ持っとるん。なんで帰らんかったん。あんたもずっと一緒におったん?」
「いや……、その……。俺は預かっただけやけん」
「じゃけん、預かったのはわかったけん。……なんで帰らんかったんかって訊きよんのやん」
「いや、……ほんとうに俺は……なんも」
知らないとしらをきり通す茅野に、知っているところまででいいと懇願した。身体はこちらを向いているのに、彼の視線はずっと空をみつめている。
私は質問をかえて、なぜ買い物にいったのかと訊ねた。それに対して茅野は、隼斗が贈り物をしたいと言いだしたとこたえる。
どこに買い物にいったのかと問うと、街へいき適当に店にはいったとこたえた。この紙袋のなかみは、すべてそこで買ったものだとはなす。
「……それなら、そのまま帰ってくればよかったやん。まだ他のとこ行ったんじゃねえんな」
「いや、ほかには行っちょらんので。店を出たら、前の仲間……あっ……」
「……なか、ま? シンナー遊び……の?」
「あ、いや……。その……」
「……そいつらと、……遊びにいったんな」
「違うよ! 隼斗は、せんってはっきり言ったんで!」
「じゃあ、なんで帰ってこんかったんな!」
茅野は渋い顔をして、あたまを激しくかいた。そしてその場で袋を渡されて、帰れといわれたという。その後のことは本当にしらないと、私の目をまっすぐにみる。
きっと茅野は、本当にそこまでしか知らないのだと感じた。そのあと隼斗になにがあったのだろうか、その仲間となにかやってしまったのだろうか。
数日間も帰れない状況とは、その間はどこに居たのだろうか。ずっとその連中と、行動を共にしていたのだろうか。もしそうだとしてそれが光羅の耳にはいったら、きっと兄は彼をゆるさない。
「……なんで、おばちゃんと今日きたん」
「いや、そこは……本当に俺は詳しくはしらんけん」
茅野の瞳を、じっと見据えてみた。彼は視線をそらすことなく、ふるふると首をよこにふる。嘘ではないのかもしれない、と感じた。
紙袋をふたたび茅野の手にもどし、わたしは彼に背をむける。「椎名?」と不思議がる彼になにも言わず、わたしは階段をおりていった。
そのまま職員室のまえに戻った私は、その扉を勢いよくあける。驚いたようにこちらを見ている教員のなかに、矢野の姿をみつけた。
戻りなさいと前に立ちふさがる教員を、腕で払いのけながら矢野のもとをめざした。わたしと視線があっていることで、彼も自分に用事なのだと悟っているようだ。
「矢野先生! さっき、隼斗が来ちょったよな!」
「え、あ、ああ……。えっと、君は……」
「一年八組の椎名朱里です。隼斗は何しにきたんですか!」
「あ、ああ……椎名。えっと……なんで、そんな質問を」
「知りたいからです」
「……いや、知りたいと言われても。……久我個人のことじゃけん」
「彼女でも? 彼女でもきけんの?」
もともと痩せ細った体形の体育教師である矢野は、疲れたような表情で椅子にこしかける。まるでわたしの存在を忘れたかのように、机にひじをつき頭をかかえた。
彼がなにを思い考えているのか、わたしには知るよしもない。その間もわたしはずっと、どんな話だったのか隼斗になにがあったのかと問いつづけた。
「椎名……、あのな。あいつの事が心配なんは、……わかる。じゃけんどの、個人の家庭のことは部外者には……いくら彼女やっても先生のくちからは……」
「……部外者」
そのひとことに、はげしく突き放された気がした。わかっている、家族ではないあかの他人だと。それでも心配な気持ちは、家族となんら変わりはないのに。
鼻のおくがつーんと痛くなり、わたしは息をとめた。息を吐けばそれといっしょに、涙があふれ出てしまうと思ったからだ。しかし、それと呼吸はべつものだった。
いっきに目頭は熱くなり、ぼろぼろと涙をあふれさせてしまう。それをみた矢野は困ったような顔で、ひきだしからティッシュをとりだし差しだす。
「し、椎名……ちょっと、向こ……ほら、ちょっと向こうの部屋に……」
ほかの教員たちの視線をあつめてしまい、そのことに矢野は慌てて立ちあがる。わたしの背中をかるく押すように、職員室の扉へと誘った。
その扉のよこにある、応接室への扉がひらかれる。ふたりそこへ入ると矢野は振りかえり、いそいそとその扉をしめた。
そんなに泣くなとなだめてくるが、泣こうと思って泣いているのではない。軽くうなづきながら、わたしは何枚ものティッシュを使った。
向かい合って座った応接室のソファー。ときおり深いため息をつきながら、矢野はわたしが泣きやむのを待つ気のようだ。
「久我……なんやけどの……」
わたしの涙が落ちついたのを見計らうように、矢野がぽつりと声をあげる。
「しばらく……の、学校には、来れんことに……」
「……もともと、来てねえやん」
「いや、まあ……そうなんやけど。なんていうかの……そういう事じゃねえで。児童自立支援施設……って、わかるかの」
「じどう、……じり、つ……」
聞き馴染みのないことばに、復唱がままならない。知らなくて当然だと言わんばかりの表情で、彼は更生を促すための施設だといった。
そして続けて「そこに入ることになったから」といって、気まずそうにわたしから視線をそらした。彼がくちにした、入るという言葉がひっかかる。
そこまで話してしまったのだ、彼からすれば話ついでだろう。それがどのような目的の施設であるか、そしてここからどれくらいの距離の場所にあるのか話し始めた。
くわしい所在地を教えてくれというわたしに、それはお前には教えるわけにはいかないという。そもそも知ったところで訪ねていけたとしても、彼にあうことは叶わないといった。
「……会えん、のや」
「うん、家族以外は……な」
「……どのくらいで、帰ってくる?」
「どのくらい……、か。そうやの、本人次第なんじゃけんど……二年、いや……一年。先生も、……わからん」
家族以外は面会の叶わないという場所で、短くても一年は暮らすことになったという事実に呆然とした。矢野はまだ何か話しているようだが、わたしの頭には入ってこない。
ここから六十キロほど離れた土地だといわれても、その六十キロがどの程度の距離なのかすら理解にくるしむ。ただ理解できたことといえば、もう会えないのだということ。
一年間、彼のことを信じて待ってやれという矢野の言葉も、ありきたりの取ってつけたセリフに感じる。何を根拠に、信じるということばが出てきたのだろうか。
そうだ隼斗は最後に、ばいばいとわたしに告げたのだ。そうそれはまさしく、もう会えないという別れのことば。きっと彼も、二度と会うことはないと覚悟したのだ。
ゆっくりと立ちあがったわたしに、矢野は心配そうに「大丈夫か」といった。なにが大丈夫なのかわからないけれど、わたしは彼にあたまをさげ、応接室をあとにする。
第2章…06
さっきまでよりも重いあしどりで、わたしは屋上へともどった。茅野は帰っておらず、わたしの足音に敏感に反応して立ちあがる。
まだ居たのかと視線をおくると、どこに行っていたのだと訊かれた。矢野ところだと答えた瞬間、茅野の顔色がかわった。
「……あんた、知っちょったんや?」
「え、あの……」
「なんで、教えてくれんかったんな」
「そんなん、……俺からいいきらんわ……」
泣きそうな顔をしている茅野をみて、責めたてる気持ちがうせる。つねに行動をともにしていた、友達との急なわかれ。
そうだつらいのは私だけじゃない、彼だってつらいに決まっている。そんな彼のことを一方的に、わたしが責めていいはずがない。
その場にすわりこみ、紙袋をじぶんのほうへと寄せた。ホッチキスでとめてある口をひらき、なかに手をいれて確認をした。
手かがみや可愛いノート、ヘアメイク道具やぬいぐるみ。隼斗には似つかわしくない物が、次からつぎへと出てくるではないか。
これらをどんな気持ちで、どんな様子で買い漁ったのだろうか。そんなことを思うと、ふたたび涙腺が崩壊してしまう。
「……なあ、椎名。大丈夫か」
「……うぶな、……大丈夫な、わけ……ねえやんか!」
「ごめん……」
「もう会えんので! ……ばいばいって、言ったんで! 大丈夫なわけねえやんか!」
茅野にあたることは、お門違いだということは承知している。それでもつい、声をあらげてしまった。うつむいた茅野は、動かなくなってしまう。
やつあたりをしてしまった自分に腹がたつ。離ればなれになってしまった現実に、やるせなさがおそう。気持ちのやりばがみつからず、ただ泣くことしかできない。
階下にざわつきを感じた。生徒が廊下へとなだれ出たことがわかった。少しして皐月の声がきこえ、下校時間なのだと理解した。
ほどなくして私の鞄をかかえた彼女が、軽やかに階段をあがってきた。おどり場をまがった瞬間に、彼女の顔がこわばる。
「朱里-。かえ……ろ、どしたん!」
すばやく駆けより、わたしの背中に手をそえる。くいっと茅野を睨んだ彼女は、彼の異変に気づきわたしの顔を覗きこんだ。
話そうとするが、思うように言葉がでてこない。慌てなくていいと、皐月はわたしの背中をさすった。ときおり茅野に視線をうつす。しかし彼はうつむいたまま、なにも語ろうとはしなかった。
「あんな、……隼斗がな、来ちょったんよ」
「え、……学校に?」
「……うん、……おばちゃん、と……な……来てから……」
ひっくひっくなる合間をみて、ゆっくりと説明をした。なかなか話はすすまないが、皐月は急かすことなく聞いてくれる。
わたしの話をきいている茅野が、うっすらと瞳に涙をためていた。堪えきれなくなったのか、すんっと鼻をならし服の袖で涙をぬぐった。
ひととおりの話をおえると、ふたたび涙があふれだした。すでに茅野も歯止めがきかなくなっており、次からつぎへと溢れる涙をぬぐっていた。
どのくらいここで、こうしていたのだろうか。やがて階下は静まりかえり、運動部のこえだけがとおくに聞こえている。紙袋を手に立ちあがった私たちは、誰ともなしに歩きはじめた。
「朱里!」
くつばこをはなれ外にでると、わたしは名前を叫ばれた。ふと顔をあげてみると、正門に光羅と北斗の姿がある。
なまえを呼んだ光羅は、わたしに向かって駆けよってくる。そのうしろを不安そうな表情の北斗が、ゆっくりと歩みよってきていた。
ああ、このふたりも知っているのだ。わたしはすぐに理解した。そして皐月とわたしだけが、そのことを知らされていなかったのだと項垂れた。
「あんな、朱里。あいつな、絶対にはよ帰ってくるけん」
「……なんで? なんでそんなん言えるん」
「あいつも馬鹿じゃねえけん……、絶対に頑張るっちゃ」
「……いつな」
「え、……それ、は」
「わかりもせんくせに、そんなん簡単に言わんでよ! なんでな、なんで隼斗は施設なんかに行ったんな! だれが行かせたんな! なんで、なんで……」
なぐさめようと声をかけてくれた北斗に、おもわず掴みかかってしまう。わかっている、彼に盾つく場面ではない。そんなことは、言われなくてもわかっている。
それでも堪えきれなかった。誰かのせいにしなければ、いまをやりすごすことが出来そうにない。手から紙袋がすべりおち、あしもとに中身が散乱した。
体当たりをするいきおいで北斗にあたるが、彼はだまって全てをうけとめてくれる。やめろと言いながら、光羅がわたしを引き離そうとする。
やらせておけとくちにする北斗の顔は、誰よりも寂しそうな顔をしていた。
「皐月ちゃん。わりいけんど、それ……しばらく預かっちょってくれんかや」
「……あ、はい」
あしもとに散らばった隼斗からの贈り物を、ひとつずつ拾い袋にもどしている彼女。そんな彼女に気づいた光羅は、彼女にそれを持ちかえるように指示した。
強引に引きはなされたわたしは、半ば引きずられるようにその場をあとにする。それでも最後まで、なぜ隼斗が施設に送られたのかと叫びつづけた。
敢えてなにも口にはしない光羅だが、ときおり強くひく腕のちからが物言っている。
泣きながら腕をひかれる光景は、それは異様なものだろう。しかしそんなことなど考える余地もなく、わたしは子供のように泣きつづけていた。
自宅がちかくなり、いくらかの落ち着きをとりもどす。しかし思いきり泣いたわたしの顔は悲惨なもので、呼吸もひっくひっくとしゃくりあげている。
そんな状態でもどってきた兄妹を、従業員たちは好奇の視線でむかえた。とうぜん母も気づいてはいるが、あえて気づかぬふりで私たちをみおくった。
「……じゃあけん、隼斗はいけんって、兄ちゃん言ったやろうが!」
部屋に入るなり振りかえり、光羅は声をあらげた。せっかく治まっていた涙が、ふたたび視界をかすませる。
いつものように兄の胸に顔を埋めるが、まわされた腕がいつもと違って感じる。優しくというよりも、激しくといったほうがしっくりとくる力強さ。そして心なしかその腕は、震えているようにも感じ取れた。
「なあ、兄ちゃん。なんで隼斗は、施設なんかに行ったん」
「……そんなん、知らんわ。じゃけど、今までいろいろやっちょんけん」
「けどな、兄ちゃん。……隼斗ってな、わりいひとじゃねえんで」
「わかっちょる! ……そんなんは、……兄ちゃんだって……知っちょんのよ」
知っている、わかっていると繰り返す。その声がなんとなく悔しそうに聞こえてしまうのは、わたしの思い過ごしなのだろうか。どちらにせよ、光羅の言葉にすくわれる。
頭ごなしに彼を悪者のようにいう大人とはちがい、光羅はわかってくれているのだ。そう思うと少しは気持ちが軽くなる。
光羅の腕の中で安心して泣きはらし、そのまま意識が遠のいていくのがわかる。急な展開に疲れた脳みそが、現実から離れたいと感じたのだろう。
うすれ行く意識のなかに、微かに光羅が鼻をすする音がきこえた。泣いているのだろうか、確認をする余裕はないままにわたしは意識を手放した。
第2章…07
暑かった夏も過ぎ去ってしまい、肌寒いと感じることがおおい季節になった。天窓からさしこむ陽ざしが、ほどよい暖かさをつくりだし心地いい。
茅野が隼斗のためにみつけたというこの場所は、いまでは平日のわたしの居場所になっている。それは時にはひとり時にはふたり、またときには三人の居場所となっていた。
隼斗は数回しかここへは来られなかったが、いまでもしっかりと彼はここにいる。ひとりでいると切なくなってしまうこともあるが、それでも大切なわたしの居場所なのだ。
それにしても茅野のやつ、めったに登校などしていなかったくせに、よくこんな場所をみつけたものだ。さすがさぼり隊は違うな、と感心する。
階下が騒がしくなってきたことで、午前の授業がおわったのだと気づく。ぱたぱたと軽やかな足おとが、ここへの階段を駆けあがってくる。
このかわいい足音は、皐月のものに違いない。そろそろだと思ったとき、やはりおどり場に現れたのは彼女だった。お弁当をかかげ、にかっと八重歯をみせ笑う。
「朱里-、弁当くおうぜぇ。腹へったぁ」
「いいよな……。あんたんとこの弁当は、旨そうやけん」
「えーっ、朱里のおばちゃんも、忙しいって言いながらちゃんと毎日つくってくれよんじゃん」
「……つくると詰めるは、ちがうと思うけんどな」
「やばっ。そうとう、根にもっちょんやな」
ちょこんと最上段に尻をつけた皐月は、ひざのうえで弁当をあけた。やはり今日の弁当も、しっかりと色彩ゆたかで美味しそうだ。
わたしは鞄から弁当をとりだし、おそるおそる蓋をすかして中をみる。手のこんだものなど入ってはいないが、これなら人並みだと安堵する。
そんなわたしの一連をみていた皐月が、怯えすぎだと笑いはじめた。こうなってしまったのは、そうあの日の母の弁当のせいなのだ。
わたしの弁当は、まずいろどりなど考えてつくられてはいない。店内にあるものをそのまま弁当箱へ、それが忙しい母の弁当スタイルだった。
それはそれで、慣れていたのでよかった。ただ、あの日の弁当だけは許せなかった。思いきりあけた弁当箱のなかみ、そこにあったのは白米だけだった。
別のちいさなタッパーが気になる。おかずを別にいれたのか、めずらしいこともあるものだ。開けてびっくりした。それは昨晩の残りの、カレーだったのだ。
許せなかった、いや許せないというよりも恥ずかしかった。それはわたしだけの事ではなかった。光羅もその日、わたしと同じ恥ずかしさを味わっていたのだ。
とうぜん、わたしは母に文句などいえない。しかし光羅はちがう。だが母親にぶちぎれた兄は、母親の逆切れに見舞われた。
「じゃけんど、朱里のおばちゃん、さすがって感じよな」
「……さすがじゃねえし。詰めていいもんと、わりいもんがあるやんな」
「兄ちゃんも、弁当あけたときびびったやろうな。……なあ、なんか下が騒がしくね?」
わたしの悲惨な思い出ばなしに笑っていた皐月が、弁当をよこに置き立ちあがる。手すりを掴んで階下をながめ、首をかしげて階段をおりはじめた。
階下のことなど放っておけばいいのに、と思いながら食事をすすめる。すこしして彼女が、慌てたように階段を駆けあがってきた。
「どしたんな」
「ちょ、ちょっと……。なんか知らんけど、三年の男が朱里んこと、探しよるみたいやで!」
「三年? ……誰やろ、っちゅうかなんやろ」
「し、知らんけど……どうする……」
どうするかと訊かれても、どうすればいいのかわからない。探される心当たりなどなく、男子だときけば尚のこと見当もつかない。
隠れるように最上階まで駆けてきた皐月が、だれもあとをつけて来ていないか確認をした。手すりから顔をだした、その行動が裏目となる。
「おった! 先輩、椎名ここにいます!」
顔をのぞかせた皐月に気づいた生徒が、階段のおどり場まであがってきたのだ。しくじったと言わんばかりに、皐月の顔がゆがむ。
逃げ場のないわたしたちは、ただその場でことの成り行きをまつしかない。おどり場でこちらにひとさし指をむけている生徒のまえに、その三年の男子という人物があらわれた。
わたしの居場所を指さす生徒は、その人物にあたまをさげ走りさる。振りかえったその人物は、悪びれなく手招きのようなしぐさをした。
視線はあっている、合ってはいるがわたしではないかもしれない。きょどったようなわたしのしぐさに気づいてか、彼は椎名と名指しをしてきた。
その場にとどまったまま、返事だけをかえした。彼はすこし困ったように眉をひそめて話があるとことばにし、先ほどよりもおおきめに手をまねいてみせた。
行ったほうがいいのではないか、と皐月の肘がわたしを突っついた。よこから彼女に弁当をうばわれ、視線で待っているからと告げられた。
廊下をひた歩く先輩のうしろを、おどおどとついてあるく。三年様の御成りに、みんなは廊下の端によった。心配の視線や好奇のまなざしが、わたしに向かって集まってくる。
「わりいな、急にきてから。俺んこと、知っとる?」
「え、あ……。和泉先輩、……ですよ……ね」
「おお! 知ってくれちょんのや」
廊下のいきづまり、そこは生徒用トイレのまえだった。立ち止まった彼は振りかえり、自分を知っているかと訊いてきた。
とうぜん知っている。校内で彼のことを知らないひとがいるのだとしたら、いますぐここへ連れてきて欲しいくらいだ。それくらいに彼は、不良として目立っている存在だった。
「んでさ、いきなりであれなんじゃけど。俺と付きあってくれんかや」
「……え、」
かたまってしまった私のまえには、笑顔をキープしたままの和泉がいる。無表情のわたしと不良の笑顔が、しばらくの間みつめあっていた。
「……あ、えっと。わたし、先輩のことよく知らない……です……」
「ああ、そうじゃなぁ。……知らんけん、こたえられんっちゅう感じ?」
「あ、はい……」
「ほんなら、知ってもらいにまた来るけん」
「あ、あぁ……。え……?」
和泉は笑顔キープのまま、軽く手をあげて去っていく。廊下のかどを曲がったのを見とどけると、わたしは急いで屋上へもどった。
食事をおえた皐月は、つくえのうえに寝ころがっていた。わたしの戻りに気づくと、身体をおこし聞きの態勢にはいった。
「俺らもな、一年ときはここでさぼりよったわ。……やっぱ、ここっていいでな」
「あ、……あぁ、そうなんですね……」
「なんな、まだ敬語なんじゃな。そげえ警戒されるキャラでも、ねえと思うんじゃけんどの」
あれから一ヶ月ほどが過ぎていた。和泉は何のまえぶれもなく、ここ屋上へとやってきている。きっとこれがあの時に言った、知ってもらうということなのだろう。
言いながらわたしの手もとの弁当を覗き、そのなかから肉団子をつまみ食った。お返しだといって自分の弁当のだし巻き卵を、わたしの口のまえへと運んでくる。
条件反射で開けたくちに、卵焼きが放り込まれた。そんな光景に唖然とする皐月だが、とうぜん先輩にむかって物言いなどはできるはずもない。
それは皐月にかぎったことではなく、共にここを利用している茅野もおなじだった。そして和泉は見かけによらず、陽気な人柄なのだと感じたのも三人同意見だった。
そんな微妙な状況のなか、二学期もおわりにさしかかる。隼斗の家、という放課後の居場所。それを失くしたわたしたちは、そのまま帰宅かどうするか話ながらくつばこへ向かう。
くつばこで茅野とわかれ、皐月とふたりで外にでた。正門のほうをみた皐月が、「あ……」といって立ち止まる。
みればそこには、和泉のすがた。彼はわたしたちに気づくと軽く手をあげ、笑顔でこちらへと向かってきた。
「和泉先輩、どうしたんですか」
「ん? いや、帰るんやったら、送っていこうかなって思って」
「いや、これから……」
「あ! そうやった、用事あったんや。ごめん、朱里……わたし帰る、な」
和泉の視線に、皐月は負けた。相手が先輩となれば、それも仕方のないことだ。本当はこのままわたしたちは、皐月の家にいく予定だったのだ。
悪いな、またな、という彼のことばは、半ば皐月を追い払っているように聞こえなくもない。そんな和泉が、わたしの荷物をうばいとる。
自分で持ちますと返したが、それは男として格好悪いから嫌だといわれる。わたしからすればそれは格好良さではなく、人質ならぬ物質だ。
仕方なく歩きはじめようとしたとき、ふわりと肩に温もりを感じた。それが今しがたまで和泉が着ていた学ランだと気づき、わたしは顔が熱くなってしまう。
「せ、先輩……寒くないですから……」
「いいじゃん、かけときよな。マーキングなんじゃけん」
「え、は? ……マーキング」
「そげん、びっくりすんなの。ふざけちょんだけっちゃ」
いたずらっ子のように笑う和泉をみて、わたしもおもわず吹きだしてしまう。そんなわたしに彼は、よかったといって微笑んだ。
こんなふうに笑ってもらえて、すこし安心したと指で鼻をかいた。ふたたび前を向きなおした和泉は、わたしと隼斗のことは知っていると続けた。
胸のおくが、ずきっと痛んだ。まさか和泉のくちから、隼斗の名前がでてくるとは思いもしていなかった。
「あんな、こげん言い方したら、おまえ……怒るかもしれんのじゃけんどの。……施設いったやつで、ここに戻ってきたやつ……ひとりもおらんで」
「え、……なんで、そんな」
「なんでって。わかっちょんやん……」
自分は最初にあったときに、その理由は話しているという。そうだ確かにそうだった、彼の最初の用事はそれだった。かといいわたしは返事をすることができず、うつむき歩きつづけていた。
和泉がいうには、この中学から施設にいった人数は決して少なくはないという。そしてそのうち誰ひとりとして、在学中にもどったものはないという。
前例がないだけであって、隼斗がどうだと断定はできない。しかしその可能性は、きわめて低いものなのだと彼はいった。
「……怒った?」
「いや、怒っては……ないです……けど」
「腹たったとしてもいいけんよ、俺と付きあってみてくれんかや。絶対にわりいようには、……せんけんさぁ」
「わりいよう……って。そんなんじゃなくて……なんか、ま……」
「ちょっと待った! まって、やっぱまだ返事せんじょって! もうちょっと、こんまま行こうや。変なせんぱーいでいいけん、……な?」
大声でわたしの言葉をさえぎった彼は、もちまえの笑顔で親指をたてる。正直、すくわれた。どちらの答えだとしても、それはとても気の重いものだった。
和泉は決して嫌な先輩ではなかった。このままあやふやな友達関係のほうが、ずっと楽しくやっていける。ずるいけれどそれが、わたしの正直な気持ちだ。
自宅が近くなり、ここでいいと足をとめる。羽織っている学ランを手渡し、わたしの物質はかえされた。それを受け取るとき、和泉は探るようにわたしの顔を覗きこむ。
ありがとうございましたと笑顔でかえすと、彼もほっとしたように笑顔をみせた。またなと手をふり去っていく先輩の後ろ姿は、決して頼りないものなどではなかった。
第2章…08
国道沿いを流れる川をわたりすこし走った場所、小高い丘に囲まれたたずむ県立豊徳学園。ここが今回、俺がおくりこまれた場所だ。
児童自立支援施設などといえば、舌をかみそうなうえに堅苦しい感じがする。しかし実際のここは、そこまで堅い雰囲気ではなかった。
大自然とまではいかないが、このあたりは田舎で自然がゆたかな場所だ。緑にかこまれた敷地のなかには、本館である学校と体育館やグラウンドがある。
中庭のようなものを挟んで男子寮と女子寮があり、敷地をかこむ高い塀のようなものはない。みたところ普通の学校と、なんら変わりはない施設なのだ。
「なあ、……俺さ、思うんじゃけんど」
「なんが……」
「これってさ、普通に逃げれるくね?」
健全な心は、健康な身体から。そんなことを掲げているこの施設では、早朝のトレーニングと称して施設のそとをランニングする。
そう、施設の外なのだ。朝はやくから畑仕事をする年寄りや、犬の散歩をしているひとと普通にすれちがう。ともに走る職員も多くはなく、見張られている感覚はほとんどない。
川沿いの県道をはしりながら、右手にみえる川のさきをみる。体力に自信のあるものなら、あの橋をこえ国道にでることは容易いこと。
「……お前、やめとけよ」
「え、すりゃあせんけど……」
「うん、……そんならいいんじゃけんど」
ここの新入りたちは、必ずといっていいほど同じことをいうらしい。なかには実行に移してしまい連れ戻され、繰り返し行ったものはそれなりの処置をうけたという。
入園期間の延長だけならまだいいが、ほかの施設への移動となるとかなり面倒な生活になるという。他の施設を経験しているものや話を聞いたことのあるものにしてみると、ここの学園はとても恵まれているそうだ。
ランニングを終えると一息つくひまもなく、朝食へと食堂へむかう。朝食が終われば、またすぐに本館へと移動する。本館では八時半から十七時まで、授業や部活動できたえられる。
小学校からまともに学校へは行っておらず、中学は屋上以外を知らない俺だ。学生の生活というものに面倒は感じるが、新鮮であるのも確かだった。
いちにちを終え寮にもどると、夕飯までの少しの自由がまっている。数字や漢字でがちがちになった脳みそで部屋に戻ると、同室の男がくつろいでいた。
「なあなあ、久我ってさ……なんで、そんげえ真面目にやりよんの?」
「年末の帰省、……取り消しくらいとうねえやん」
「え、帰りてえん? ……ろくなことねえで、帰ったって」
「ちゃんと話しちょらんやつが、居んけん……」
「……話? まさか、女とか言わんよのう。……やめちょけよ、会わんほうがいいと思うで」
呆れたような顔で俺をみて、最後にガキ臭いと鼻でわらう。この男いわく、居なくなった者はすぐに忘れられるのだと。さっさと新しい男をつくって、毎日たのしくやっているのだという。
一瞬、不安が過らなかったわけではない。しかし俺は彼女に限ってそんなことはない、きっと俺を待ってくれていると信じている。
ただ気がかりなのは、最後のことば。あまりにも急なことすぎて、俺はなにも考えることができていなかった。あのセリフは、致命的だと焦りをかんじている。
だから俺は、何がなんでも年末の帰省をする必要がある。ちゃんと朱里にあって、事情を説明しなければ。そして待っていて欲しいという、自分の気持ちを伝えなければならない。
年末の三十日から明けの三日までの五日間の帰省。自宅以外への外出は禁止、家族以外との接触は禁止。そんなありきたりな決まりごとを言い渡され、念願の地元へと帰ることができた。
いつものジジイのタクシーで、片道一時間ほどの道のり。こんなに遠いみちのりだったろうか、こんなに一時間とはながいものだっただろうか。
「おーう、不良少年。どげえか、真面目にやりよんのか? あれじゃが、茅野には言うちょるけん、多分そろそろ来るとおもうで」
「兄貴……。朱里……には?」
「いや、あいつには……まだ言うちょらん……」
あの日、北斗は俺と入れ違いで朱里にあったという。彼女はかなり取り乱しており、それは大変だったと話した。
そんな朱里を光羅が強引につれかえり、自分はそれっきり彼女には会っていないといった。
朱里をここへ連れてくることは可能だろうか、それとなしに北斗に尋ねてみる。彼はすこし渋いかおで、あまり期待はできないかもしれないといった。
そうだった、俺は光羅との約束を果たせなかった。殺されてもかまわない、そう啖呵をきっておきながら。こんなにも簡単に、彼女を苦しめてしまったのだ。
会わせてもらえるなんて、容易く考えてはいけないのかもしれない。きっと光羅は、俺のことを憎んでいるにちがいない。
「まあ、だめもとで……椎名んとこ、行ってみちゃんけんど。……期待せんで待っちょけ。……おっ、茅野……あいつ帰っちょんわ、あがれの」
「ちいーっす。……帰るんですか?」
「ん? いや、朱里んとこ行ってみろうと思って」
「……え、椎名ん……あ、ああ……そうなんや」
出掛けようと玄関にいった北斗は、やってきた茅野とはちあわせた。彼は北斗の行先をたずね、表情をくもらせる。
「おい、なんしよん。はよ、あがれの」
「えっ、ああ……。なんか隼斗、元気そうやん」
「おう、健康的な生活しよんけんの。……ちゅうか、朱里になんかあったん?」
「……なんで?」
「いや、あんまりいい顔しちょらんけん」
それこそあの日、俺が学校にいった日は大変だったと苦笑いをする。それからしばらくは会話もすくなく、笑顔なんてなかったと話す。
しかしそれも徐々に緩和され、いまでは元気な笑顔にもどっていると。心配しなくていい、彼女は大丈夫だとくりかえす。
こいつは、嘘がへたくそだ。いちども視線をあわさない、その時点でアウトだ。きっと朱里について、あまりよくない知らせがあるのだと感じる。
「……なあ、嘘やんな?」
「え、嘘じゃねえし」
「そうなん? あいつ、部活とか入ったんかや。……ちゃんと勉強しよんのかや」
「部活? そんなんするわけねえやん、授業もでよら……あ……」
「……学校、……行きよらん……とか……」
「いいや、学校にはちゃんと来よるで! ただ、……屋上に……」
授業をまともに受けていないと、うっかり漏らしてしまった茅野。どうやら彼の話をきくと朱里の生活態度は、以前とはちがってしまっているようだ。
それもこれも、もとをただせば俺のせい。俺が彼女のこころを不安定にさせてしまった、ちゃんと話をしなければならないと感じた。
確かに、あの屋上は居心地がいいだろう。あの場所で過ごしているという彼女のことを、頭のなかで想像してみる。もう一度、俺もあの場所にかえりたい。
「……居心地、いかったもんな」
「んー、まあな。……じゃけんど、最近は和泉……っ! あ……いや、その」
「なん、和泉……って……。三年の、和泉んことか」
思いもよらない名前に、俺のこえが低くひびいた。苦虫を噛んだような表情で、茅野は意識的にしせんをそらした。
茅野は話をそらそうと、施設でのようすを問うてくる。彼の胸ぐらをつかみ、無言でじっと顔をにらみすえた。
ぽつりぽつりと話し始めた彼のはなしに、俺は怒りをおぼえた。かたくにぎった拳を、ぶつける場所なくふるわせる。爪が手のひらにくいこんで、深いきずをつくってしまいそうだ。
朱里を和泉に奪われてしまうのだろうか。なぜこんなことに、どうして和泉なんかに。そうすべて俺のせい、俺のせいなのだ。
「けどな! 付き合ってはねえんで……」
「……うるせぇ、帰れ」
「……え、」
「うるせぇ! いいけん、帰れ!」
その場をなんとかして取り繕おうと、茅野は焦ったようにつけくわえる。朱里は断ったのに、和泉が勝手に入り浸っている。
そうか、入り浸っているのか。彼女のそばに、いつもあいつが居るということか。それは和泉は諦めていないということで、今後どうなるかわからないということだ。
目のまえの落書帳をつかみ、茅野にむかって投げつけた。そうでもしないと、この拳をぶつけてしまいそうだった。
だめだ、まだ俺の気持ちが治まらない。こたつの両端をつかみあげ、大声をだしながら壁になげつける。おおきな物音に、母親がはしってくる。
「やめんか、隼斗!」
「うるせぇ、くそババア!」
廊下へといき手当たりしだい物をつかみあげ、ちからまかせに投げ散らかした。玄関へと飛ばされた茅野は、おそらく俺が突き飛ばしたのだろう。
駆けつけたジジイに起こされた茅野は、ジジイの指示で帰っていく。そう体格のいい男ではないが、全身をつかい俺を羽交い絞めようとした。
自由を奪われながらも、俺は必死で抵抗する。そして目のまえにいた母親を、思いっきり足で蹴り飛ばした。
倒れこんだ母親も、もう限界だと感じたのだろう。泣きながらどこかへ電話をかけている。相手がだれなのか考える余裕はなく、俺は全力で暴れつづけていた。
「……北斗は!」
「し、知らん……。どっか行ったけん……」
ジジイのことばに、はっとした。そうだ北斗は、朱里を迎えにいったのだった。こんな姿をみせるわけにはいかない。冷静になった俺は、ごめんとつぶやき座りこむ。
がちゃりと玄関がひらき、俺は期待の眼差しでふりかえる。そこに姿をみせたのは、児童相談所の職員だった。そう、母親が呼んだのだ。
俺は朱里の到着をまつことなく、職員によって学園へと連れ戻されてしまうことになった。
第2章…09
今年も、残すところあと二日。いつもであれば直接にやってくる皐月から、めずらしく連絡がはいった。近くの駐車場にいるから、出て来てくれないかという。
近くまで来ているのならば、そのまま家にくればいいものを。そんな気持ちをちらつかせながらも、わたしは支度をすませ家をでた。
「……えっ、……せんぱい?」
「わりい! ……ごめんな、びっくりしたわな。俺が七瀬に頼んだんよ」
「どうして、……ですか」
「俺が電話したら、……断るじゃろ」
皐月が待っているはずの駐車場には、苦笑いの和泉の姿があった。わたしの姿を確認するやいなや、顔のまえで申し訳なさそうに手のひらをあわせる。
自分の誘いであれば断られる、彼はそう思い皐月を利用した。素直にそういうと、いつもの笑顔でわたしをみた。
確かに、断っていただろう。しかしこうして正直にいわれると、どう反応してよいものかわからなくなる。彼の笑顔にたいして苦笑いをかえし、なにか用事かと問うてみた。
「……いや、とくに用事っちゅうわけじゃねえんやけど」
「え、……あ、そう……ですか」
「どげえしよんのかの……とか、思って」
「……どげぇ? ……えっと……とくに、なにも」
ほんとうに用事もなく呼びだされたのだと感じる。まったく進まない会話に、居心地わるく視線がさまよう。真冬だというのに、まったく寒さすら感じなくなってしまった。
無駄にひろい駐車場のかたすみ、買い物客の視線が気まずさに追い打ちをかけてくる。この子たちは何をしてるんだ、まさしくわたしたちはここで何をしているのだろうか。
そんな視線に後押しされたかのように、和泉が変な提案をした。自分の仲間のいえにいこう、そんな言葉にわたしは怯む。
「……先輩の、なかま……です、か?」
「あっ! いや、仲間っていっても……あれやで! そげえ変な……あれじゃねんで。……椎名の知っちょんやつもおると思うし」
わたしの知り合いとは、いったい誰のことなのだろうか。皐月であればそう言うであろうし、なによりそこに彼女が居るはずはない。
無理強いではないと強調しながらも、ながれは和泉がつかんでいるように感じる。ことわるタイミングを逃したまま、わたしは彼の後ろについて歩いた。
ちらちらとこちらを振り返りながらあるく和泉の顔は、心なしか嬉しそうにみえた。それに対して、わたしの不安は募っていくばかり。
「なあ、……なんか、心配しちょん?」
「えっ……いえ、そんなことは……」
「皆な、わりいやつらやねえけん、心配せんでいいんで」
自分がなにを不安に感じているのかもわからず、和泉がなにを宥めているのかすらつかめない。会話もたどたどしく、気なぐさめにほどたらず。
心細くなる自分をつなぎとめるように、わたしの知り合いとは誰なのかを必死に考える。考えているつもりであっても、脳はなにも導き出すことはできてはいない。
どのくらい歩いたのだろうか、ふと和泉が足をとめた。一定の距離をたもっていたわたしも、的確なタイミングで歩みをとめる。
振りかえった和泉の瞳が、ここが目的地だとつげている。木造平屋の、ちいさな戸建て。その窓を、彼はノックした。
「……なぁんか、和泉か。向こうから上がりゃいいやん」
勢いも弱くひらいた窓から、いっきに淀んだ空気が逃げだしてきた。しかしそれは見知った空気で、煙草とアルコールだとすぐにわかった。
いわゆる、たまり場というもの。そのくらいのことなら、わたしにも理解できる。ただ中にいる人物の特定は、遠慮がちに離れたこの場所からはむずかしい。
「……え。なん、和泉……女、連れちょんの?」
「いや、まだ彼女ではねえんじゃけんど」
「そうなん? ……まあ、いいやん。そっちの彼女もあがれば?」
窓ぎわで話していた男が、ひょこっと窓から覗くようにこちらをみた。そうすることによってその人物が、三年の石川先輩であるということがわかった。
おそらくこの家の住人であろうその先輩のことばに、興味をしめすように数人が顔をのぞかせる。さらし者のようになったわたしを気にして、和泉は彼らを手ではらうしぐさをした。
振り向いた和泉のかおが、あがるかどうするかと問うている。男の先輩たちのたまり場に、あがりこむ勇気などはさすがにない。
苦笑いでちいさく首をよこにふると、和泉は残念そうに微笑んだ。遠慮をするなと中から声がかかるが、愛想わらいでごまかす。
「……え、なんでお前が……先輩と……?」
最後に顔をのぞかせた男が、わたしを見て目をまるくした。同級の石川だ。
窓ぎわの石川先輩をみた時点で、和泉の言っていた知り合いの意味には気づいていた。ただ、この場にいるとは思っていなかった。
石川の態度に興味をしめしてか、もうひとり窓のそばまでやってくる。その人物は増田であり、これもまた同級の男だった。
「なんか、おまえら知り合いなん? んなら尚さら、遠慮なんかせんであがりゃいいやん」
「おう、……遠慮なんかすんなの。むこうまわりゃ玄関あるけん、あがってきよな」
兄弟そろって誘ってはくれるが、わたしは決して遠慮をしているわけではない。できることなら今すぐにでも、この場から離れてしまいたいとまで感じているのだ。
相手が先輩とあって、無下にことわることもかなわず。当たり障りのない程度に、愛想よさを心がけながら断りの意をほのめかすようにふるまってみる。
彼女を狙っているのかと和泉にちょっかいをだす者にたいして、意味深な笑みをうかべる和泉。皆がおもしろがって、彼をいじりたおしている。
「……じぶん、名前なんちゅうん?」
「あ、わたし……ですか? ……椎名です」
「えっ、……椎名……って、もしかして」
わたしに名前を訊いてきた石川先輩の顔から、一瞬で笑顔がきえた。そして何かに追われるように、和泉に向かってくちを開こうとする。
遠くで聴こえていたエンジンの音が、すぐ近くまで迫ってきていた。何気なくきいていた排気音が、ごく近い場所でとまる。
和泉に対してもの言おうとしていた石川先輩は、ことばを呑み込みこんだ。そして視線の矛先を、和泉よりも遠くにうつしたのだ。
顔面蒼白といえばおおげさであろうか、しかしそれに近い面持ちではある。その表情につられるように、わたしたちは視線のさきをたどった。
「えっ……」
「こらぁ! 和泉ぃーー!」
そこに居た人物が光羅だと認識するが早いか、和泉が胸ぐらを掴みあげられるが早かったか。気がつくとすでに、和泉は兄によって壁へと押しつけられていた。
うしろからゆっくりと歩いてきたのは、あきれ笑いのような表情の北斗だった。いったい何がおきているのだろうか。和泉もおどろいたように、光羅をみていた。
呆然とするわたしの腕を、北斗がつかんで引いた。この場から離そうとする北斗に、行かないと首をふった。
「朱里、……むこう行っちょけ」
「でも、兄ちゃ……」
「いいけん! いけっちゃ!」
光羅のおおきな声にびくっとなり、おもわず北斗の顔をみた。彼はすこし微笑んで、ふたたびわたしの腕を引く。
石川の家からずいぶんと離れ、姿だけならず音すら届かない場所で北斗がとまる。どうしてここまで離れる必要があるのだろうかと、訊いてみるが答えはない。
「なあ、北斗兄。……なんで、ふたりがここに来たん?」
「ん? なんか、七瀬から連絡あったらしいで。おまえが和泉から呼びだされた……っちゅって」
「……なんで、ここってわかるんやろ」
「あのなあ、朱里。……椎名の情報網な、なめちょったらいけんで。とくに、お前のことに関しては……異常なくらいやけんな」
わたしの正面にたち、腰をかがめて目線をあわす。まるで幼いこどもに言い聞かすように、ゆっくりと丁寧なしゃべりかた。しかし北斗の視線には、みょうに力が込められていた。
そうだ、そうだった。隼斗との件でも、光羅の情報入手の謎がとけていないままだった。いろいろなことが目まぐるしくおきて、すっかり忘れてしまっていた。
それだけ兄に大切におもわれているのだと、北斗は私の額をひとさし指でかるく突いた。
「じゃあけん、あれやで。……朱里も、兄貴を悲しませんようにしっかりしちょかな。……おっ、もどってきた」
シャツのすそに拳をこすりつけながら、光羅がこちらへと歩いてきていた。シャツをみると、そこには血がついている。
「兄ちゃん、血……」
「なんでもねえ、……おまえが気にすることじゃねえけん」
気にするなと言いながらも、光羅は拳を背後にかくす。そのしぐさ自体もじゅうぶん気になる要素だが、ふれてはいけないことなのだと察してしまう。
見たかぎりでは、光羅に外傷はみあたらない。その時点で、その血は和泉のものだとわかってしまった。
気にすることではないというが、なぜこんなことになっているのか気になってしょうがない。しかしわたしがそれを問うことは、決して許されないのだということもわかる。
複雑な気持ちで光羅をみれば、彼は何事もなかったように微笑んだ。続けて北斗をみてみたが、やはり彼もおなじだった。
「なんしよん、……いくで」
「あ、うん……」
石川の家の近くまでもどり、光羅のバイクのうしろに乗った。けたたましいエンジン音が響きわたり、二台のバイクが走りだす。
自宅が近くなり、それを通りすごしたことに不思議におもった。どこに向かっているのかと問うてみたが、声は光羅の耳には届かなかった。
見知った地区にはいりこみ、団地のしたでバイクは停まった。バイクを降りたわたしのヘルメットは、北斗によって脱がされた。
「あのバカな、……帰省しちょんのよ」
「え、……隼斗が帰っちょんの?」
ここまで連れてこられて嘘をいわれるはずもないのに、おもわずわたしは聞き返してしまった。会える、隼斗にあえる。
込みあげた嬉しさのすぐあとに、あの日の別れの言葉がよみがえった。不安になったわたしは、光羅に視線でうったえる。
「……隼斗がの、おまえと話がしてえっち言いよんらしいわ」
「はな、し……」
「おう、なんか……あれらしいぞ。この帰省んために、そうとう頑張っちょったみたいやぞ」
そのはなしとは嬉しいはなしなのだろうか、それとも悲しいことなのだろうか。それを思うと不安がないわけではないが、会えるという喜びのほうが勝ってしまう。
戸惑いを隠せないわたしの背中を、光羅がそっと押してくれた。その勢いをかりるように、わたしは北斗のあとを追う。
一段またいちだんと階段をのぼっていくたびに、わたしの鼓動はおおきくなっていった。三階にたどりついたとき、わたしの中の不安な気持ちはどこかへ消え去っていた。
「なんか、……これ」
「……どしたん」
あけられた玄関の扉のむこうがわは、空き巣にでも入られたのだろうかという状態だった。まるであの時の兄弟の遊びのあとのように、物というものが散らかっていた。
そこにひとの気配はかんじられない。玄関のなかには、靴のひとつもありはしない。深く考えずとも、家は空の状態だとものがたっている。
「……だれも、おらんの?」
「んん、みたいやな」
「え、なんで?」
「……暴れたんじゃろうの、あのバカ」
「あばれ……、けど……なんでおらんの」
「戻ったんかもしれん、……施設。あれじゃ、茅野がおったはずじゃけん、あいつが何か知っちょんかもしれん」
会えるとおもっていた隼斗は、わたしの到着を待たずに戻ってしまったのだろうか。帰省のために頑張ったという彼に、いったい何があったのだろう。
夏のとつぜんの出来事から今日まで、わたしには理解に苦しむことばかりだ。あふれる涙をぬぐいながら、振りかえり光羅の顔をみた。
なにかわかったら連絡をしてくれと残し、光羅はわたしの腕をひいた。最低最悪の、苦しいばかりの年末。
このまま二度と会えないのではないか、そんな思いが胸を支配する。やはりわたしたちは、出会ってはいけないふたりだったのかもしれない。
第2章…10
片道一時間、とんぼがえりのドライブ帰省。自宅への滞在は、ほんの数時間だった。こんなはずじゃなかった、こんなことをするためにまじめに頑張ってきたんじゃない。
施設にもどってから、指導室でみっちりとしぼられる。母親もべつの部屋に呼ばれたようだ。きっと何があったのかと、ねほりはほり訊きだされているのだろう。
ババアは俺と茅野の会話はしらないはずだから、朱里の名前がだされることはないだろう。
「久我、もう帰ってきたんな」
「うるせぇ……」
「いとしの彼女とやらに、会ってきたんな」
「……うるせえっち言いよろうが」
「ふんっ……。じゃあけん、言ったやん。期待して帰ったって、ろくなことねえでって。……あたらしい男、つくっとったじゃろ? 女なんか、そ……」
部屋にもどると、同室のおとこの冷めたことばがふってきた。まるですべてを知っていたかのような物言いに、俺はかっとなった。
ベッドに横たわっている男に馬乗りになり、それ以上しゃべらせないように顔面をなぐった。おとこも黙ってなぐられるはずはなく、おおごえをあげ殴りかえしてくる。
さわぎに気づいた職員が、すぐに部屋へとやってきた。取り囲んでくる職員をふりはらうように、俺はおおきく腕をふりまわし職員を殴ってしまう。
数名の職員によって抑えつけられた俺は、おとこから引き離され部屋から引きずりだされた。同室のおとこは、あざわらうような視線で俺をみおくっている。
「久我ぁ……、おまえどうしたんか」
「べつに、……どうもしてねえけど」
「どうもって、……せっかくの帰省もこんなんで。もどるなり喧嘩までして……なんか、お前らしくないぞ」
宿直室のすぐよこである部屋に、俺は荷物ごと移された。おたがいに落ちつくまで、しばらくここで過ごすようにと言いつけられる。
俺からしてみれば施設にいるという事実がすべてであり、部屋なんてどこだって同じだ。もう我慢なんてしない、もう努力なんてしない、もう期待なんてするものか。
「……はぁ……。おまえの頑張りは、職員みんなみとめちょんのに」
「べつに、……そんなん、どうでもいいし」
「なんしか! かなりの高評価で、春には……とまで言ってくれる職員もおったんやぞ」
ほかの誰よりも後悔をあらわにし、地元に帰りたいという気持ちがつよく見えていたという。そのためにするべき行動を、しっかりやっていたという。
ここの連中に評価されようなどと、ただのいちども考えたことはなかった。朱里に会いたい、ただその一心だった。
だがじきに彼女は俺をわすれるだろう。あの町に俺の帰りをまつものも、待っていてほしいと願えるものもいなくなってしまった。目的をなくした俺は、なにを目標にここですごせばいいのだろうか。
しばらく家族との面会もできないという生活に、すこしの寂しさも感じはしなかった。母親のしかめっ面をみたところで、なんの励ましにもなりはしない。
いっそのことこのままだれも会いになど来てくれなくていい、そんな気持ちのまま月日はながれていく。
「久我、頑張れよ。……次は、そとで会おうやな」
「おう、お前も……あれじゃ、……頑張れな」
「なんか、そげん顔すんなの。……おまえ、出たら絶対に連絡してくれえよ」
「わかっちょんっちゃ、ほら……はよ行け!」
そこそこ気のあっていたやつが、ここを出ていくことになった。喜ばしいことではあるが、やはり別れというのは寂しさを感じずにはいられない。
手をふり去っていくあいつのよこで、桃の花がゆれている。外で会おうという約束を、俺は果たすことができるのだろうか。
最初からその気がなく約束したわけではないが、正直なところ頑張るということがよくわからなくなっている。
年末の帰省から、もうすぐ三ヶ月。勢いにまかせ追い返してしまった茅野は、どんな気持ちだっただろうか。北斗は、朱里を連れてきたのだろうか。
だとしたら誰もいない家をみて、彼女はどう思っただろうか。所詮そんなものだと、愛想をつかしてしまっただろう。そしていまごろは、和泉と付きあっているのだろう。
「おい、こら! 久我!」
「…………え、」
いつもの早朝ランニングで、俺は職員に抑えこまれていた。アスファルトの高さから、畑のおばあさんのおどろいた顔がみえる。目のまえの雑草がゆれた。
自分は道路にうつ伏せであり、ふたりの職員が覆いかぶさるように背中にいる。引き起こされたとき、自分が列から離れていることがわかった。
みんな走ることをやめて、こちらを見ていた。好奇の目、哀れみの目、いろいろな視線が俺にあつまっている。俺は、逃げたのか?
朝のランニングは、中止になった。そのことを喜ぶように、各々が部屋へと帰っていく。両腕を抱えこまれたままの俺は、そのまま別の場所へと連れていかれた。
そんなにしっかりと掴んでいなくても、俺はここから逃げようなどと思ってはいない。いや、実際に逃げたからこうなっているのか。
「……おい、久我。どうしたんか、なんで逃げた」
「…………わかりません」
「わかりませんって、……なんだそれは」
「いや、本当に……。分からない、……んです」
自分のしたことがわからない、そんな話が通用するはずはない。しかし本当に、なにも考えてはいなかったのだ。呆れたように職員はため息をつく。
本来ならば部活にいく時間になっても、俺をこの部屋からだすつもりはないようだ。部屋のまえで、母親の謝罪のこえがした。
「……呼んだんですか」
「そりゃ、呼ぶだろ。……やっちゃいかんこと、お前がやったんだからな」
いちいち呼びつけて報告をするのか、面倒くさいシステムだ。それから延々とつづくお小言も、ほとんど頭にはいれてはいない。
最終的に走ってしまった事実は認めざるをえないが、その理由はいえないまま時間がすぎる。こんなことを繰り返すようなら、それなりの処置をすることになる。職員は最後にそういった。
くりかえすつもりはないが、繰り返さないという自信もない。なぜなら、これは無意識にやってしまったことなのだから。
それでもいいと思った。まんがいち繰り返してしまい入園期間が延長になろうが、さいあく少年院に行くことになろうが、それならそれで俺はかまわない。
「おーい、久我。親御さん帰るから、すこし会うか」
「いや、別に……会わなくていいです」
「どした、……少しくらい」
「部屋、……もどっていいですか」
母親とはなしを済ませた職員が、部屋へとやってきた。なにをそんなに殻にこもっていると、困ったように首をかしげる。なにか悩んでいるのかと問うてくるが、俺に悩みなどあるわけがない。
正月の帰省からどうかしている、お前らしくないとくちにするが、その俺らしさというのは何なのだろうか。もともと俺はこんな人間で、すこしも変わったおぼえなどない。
「部屋にもどって、部活にいきます……」
「あ、いや待て。……おまえの担任の先生が、なにか話があるって言いよったぞ」
「……たんに、ん?」
「おまえの一年のときの担任よ。そのまま持ち上がりになるけん、いまもお前の担任は同じなんぞ」
施設にいどうしたとしても元々の学校に籍は残ったままなのだと、いまこの時点ではじめてしった。そして俺は卒業するまで、ずっと矢野の生徒なのだと知らされた。
ババアに会う気持ちにはなれないが、あいつには会ってみようか。すこしの迷いが生じたおれは、ふたたび椅子に腰をおろす。
呼んでいいかといわれ、おもわずこくりと頷いてしまう。あの報告の日に一度だけしか会っていない矢野が、いったい俺になんのはなしがあるのだろうか。
職員のうしろを、痩せこけたあいつがついてくる。気をきかせて出ていく職員に、ぺこぺこと頭をさげる姿がなさけなくうつる。
「……久我、大丈夫か」
向かい合った椅子にゆっくりと腰をおろした矢野は、おれにそんな言葉をかけてきた。なにに対して大丈夫かと問うのか、返事にこまってしまう。
ここの職員から、常に報告はうけていたらしい。とても頑張っていると聞いて、自分も安心していたのだと話す。なにがあったのだと、矢野は情けない顔をした。
ぶっきらぼうな俺の態度に矢野は、頭を抱えこむようにしておおきく息をはいた。
「なあ、久我。……俺は、おまえを信じて待っちょるって、言ったよの」
「……べつに、待ってくれとか言ってねえし」
「待つなって言われても、俺はまつよ。おまえの担任なんじゃけん」
「担任とか、たまたまなっただけやん。……ここのんが、住みやしいし。頑張るとか、もうわからんけん……もう帰らんかもしれん」
「ほんなら、……椎名は、どうなるんか」
「……は?」
矢野のくちから、朱里の名前がでたことにおどろいた。そのおどろきは言葉にならず、ただ呆けたかおで彼をみる。
矢野はふっと微笑んで、自分が朱里と俺のことを知っている理由をはなしはじめる。職員室に乗りこんできたときの、彼女のようすを聞かされた。
正直、俺はおどろいた。朱里が矢野に対して、彼女に知る権利はないのかと直談判したというのだ。
彼女に自分のくちからはなしてしまったことは、申し訳ないとあたまをさげた。そして母親を介して、彼女からの伝言があるという。
「伝言……。それって、いつのはなしなん」
「ここに来る直前っていいよったな。施設から電話もろうたとき、椎名……おまえんちに、おったらしいぞ」
俺がいない家に、朱里がいたという矛盾。そんなことは気にならないほどに、胸に熱いなにかがこみあげてきた。
続けて聞かされたはなしによれば、彼女たちはいまだに俺の家にかよっているのだという。それはいったいどういうことなのだろうか。
そして母親から矢野に託された、彼女からの俺への伝言。矢野のくちからそれを聞いた俺は、恥ずかし気もなく大声でこどものように泣きくずれてしまった。
第2章…11
あっという間に終わるはずの冬休みが、わたしにとっては長く感じられた。年末のできごとがあってから、外出がしづらい状況になっていたからだ。
まったくの禁止をされていたわけではないけれど、監視の目が厳しくなっていることを感じとらずにはいられなかった。それならば出かけないほうがまし、そんな冬休みだった。
新学期がはじまるということが、こんなにも気持ちを楽にさせるなんて今までにない。いつもより早く家をでて、あの屋上へとむかう。
きっともう和泉は来なくなり、あの屋上はわたしたち三人の居場所にもどる。確信があるわけではないのだけれど、なんとなくそんな気がする。
「うわ……、ど、どしたんな。茅野、なんでこげえ早よう来ちょんの」
「あ、椎名。……ごめん!」
「は? ……なんがな」
教室へいくことなく、そのまま屋上へと直行した。おどり場をまがった瞬間、頂上で立ちあがる茅野が視界にとびこんできた。
こんなに早い時間からここに来て、しかもわたしを見るなり頭をさげ謝罪した理由はなんであろうか。それを訊くべく、彼の近くまで歩みよる。
わざとじゃない、あんなことになるとは思っていなかった。しかし自分の失敗だ、申し訳ないと頭をさげつづける。
「ちょっと、ごめんけど……なに言いよんのか、全然わからんのじゃけど」
「……久我。……帰省、しちょったやろ」
「あ、ああ……みたいやな。……会えんかったけど」
会えなかったという私のことばに、茅野は顔をゆがめる。そして先に行っていた自分は、隼斗に会ったのだといった。
そういえば北斗はあの荒れ散らかった状況をみて、茅野が何かしっているかもしれないと言っていた。
いまのこのようすからすると、おそらく茅野は何かをしっている。決して穏やかなはなしではないことくらい、このわたしですら察しはついた。
ほんの少し身構えて、わたしは彼のはなしを聞くべく階段にすわる。心の準備をするように、ゆっくりと深呼吸をしながら。
「……隼斗、元気そうやった?」
「え、あ……うん。思ったより顔色もよかった……、俺がいらんこと言うまでは……」
「いらん、……ことってなんな」
「俺のせいや、俺のせいで椎名が久我と会えんかったんや」
茅野は自分を責めつづけ、なかなか本題に入ろうとはしない。とにかく自分がわるいといって、しきりにわたしに謝ってくるのだ。
よほど話しづらいことなのだろうか、わたしは急かさずに黙って聞いていた。どんな内容だとしても、それはもう過ぎてしまったことなのだから。
自分が隼斗の家についたとき、ちょうど北斗が出かけるところだった。自分が北斗に声をかけ、わたしの名前に動揺してしまったのがいけなかったと話す。
隼斗の質問にのせられて、つい和泉のなまえを出してしまったという。俺のせいで誤解をまねいてしまった、なにもないと話しても聞き入れてもらえなかったと。
「……それで、部屋」
「うん、久我が暴れだして、俺じゃとめれんじゃった」
「おっはよーう。なん、ふたりとも早え……」
「皐月。……どうしょう、わたしのせいや」
「……は? なんのはなし」
かばんを放り置いた皐月は、どかっと私のよこに腰をおろした。深刻な表情のわたしたちをみて、自分だけ掴めないことに顔をゆがめる。
どこから話せばいいのだろうか、あたまが混乱していてまとまらない。年末の和泉のはなしから始めると、今度は茅野が顔をゆがめた。
光羅と北斗がやってきたとこまでいき、やっと茅野は話のつながりがわかった顔をする。光羅の拳に血がついていたことは、ここではあえて言わなかった。
ふたりに連れられて隼斗の家に行ったこと、部屋は散らかり誰もいなかったこと。翌日の北斗からの連絡で、隼斗は施設にもどされたと知ったこと。
「え、なんで久我の兄ちゃんが迎えに行ったん」
「隼斗が、わたしと会って話したいって」
「俺が! ……俺が余計なこと言ったけん、会えんかったんよ」
茅野のことばに、皐月は首をひねった。なにを言ったのかという皐月の問いかけは、すこし低く怒りをおびているようだ。
ふたたび茅野の説明がはじまる。だまってそれを聞いていた皐月は、納得したようにうなづいた。
「ようするにさ、久我は和泉先輩に、やきもち妬いたってことやんな」
「……やきもちっちゅうか、俺が誤解させてしまったけん」
「じゃあけぇ……誤解して、怒ったんじゃろ? 久我は、朱里んこと好きやっちゅうことやん」
「……ああ、そうでな。そういうことよな。椎名、ごめんな。俺のせいで、ちゃんと話ができんなってしまって」
終わってしまったことは仕方がない、これからどうするかを考えようと皐月がいった。家族なら面会ができる、伝言なら隼斗に届けられる。そう提案したのも、彼女だった。
さっそく行こうという茅野に、わたしたちも立ちあがる。放課後までなんて、待っていられない。放ってあった荷物をかかえ、そのまま学校をとびだしてしまう。
通学路をあるく生徒の群れのなか、逆走していくわたしたち。不思議そうに振りかえる同級の視線も、まったく気にはならなかった。
団地の三階、玄関にはとうぜん鍵がかかっている。すこしの戸惑いを振りはらい、おもいきってチャイムを鳴らした。何度目のチャイムだろうか、玄関がひらいた。
「……あんたら、学校はどげえしたんな。隼斗もおりもせんのに、なんしに来たんな」
「お、おばちゃんに……頼みがあって……」
「……なんな」
「隼斗にな、伝えてほしいことがあるんやけど」
「会えもせんのに、どげえして伝えられるかよ。……あんたらな、もうここに来るのやめよ」
つめたく突き放すような、隼斗の母親のことばに固まった。隼斗と関わっても、ろくなことにならないと母親はいう。
自分の息子を卑下することばを、どんな気持ちで吐き出したのだろうか。返すことばを失ってしまい、沈黙に寂しさをおぼえてしまう。
三人もそろっていて、誰ひとりとしてくちを開こうとはしない。想いはきっとみんな同じ、しかし言葉にすることができなかった。
翌日も、そのまた翌日も、言葉にできないかわりに、わたしたちは隼斗の家に通いつづけた。ろくに相手になどしてはもらえず、門前払いの日々がつづく。
隼斗の母親のいうとおり、いつ戻るかわからない主の部屋。それでも彼を想いここに居るのだという、なにか形となることをしたいと思った。
「……あんたらなあ、いい加減にあきらめよって」
「だって……」
「うちのバカ息子も、たいがいじゃけんど……。あんたらも、そうとうのバカタレじゃな。……あんたら、学校にはちゃんと行きよんのじゃろうな」
「うん、行きよる……」
「……鍵、あけとっちゃるけん。じゃけんど、学校はちゃんと行くんで! 放課後と休みの日だけっち、それはちゃんと約束できるか?」
思いが通じたのか根気で負かしただけなのか、主のおらぬ部屋ですごす許可をもらえた私たち。三段ボックスの落書帳も、ひごとに冊数をふやしていく。
読むことが専門だった茅野ですら、自ら書きこむことをするようになっていた。
「なあ、茅野ってさ……。そんくれえ授業でノートかいたら、頭よくなるかんしれんでな」
「は? うっせえ、ばーか」
「っちゅうか、まず授業でてねえし!」
「それっちゃな! ……てか、やばくね。もうすぐ二年なるんでな。うちら、同じクラスになったら楽しいと思わん?」
「ほんとや、もう二年になるんや……」
もうすでに桜は満開をむかえている。この休みがあければ、わたしたちは二学年になるのだ。はじめて制服に手をとおしたあの日から、あっという間の一年だった。
しかしながらこの短いあいだには、処理しがたいほどの色々な出来事があった。あらためて振りかえり、きゅっと胸がしめつけられる。
新しい学年のスタートに、もしも隼斗がもどってきたならば。そんな望みがわきおこり、ちょっぴり切なくも感じてしまう。
「はい、久我です。……え? あ、はあ……。あ、はい……わかりました」
しんみりとした雰囲気を邪魔するように、玄関ちかくの固定電話が鳴りひびいた。隼斗の母親は、とくに慌てるようすもなく電話のそばへとやってくる。
ここへ入りびたっていて気づいたことだが、隼斗の母親のこのスタイル。それは決して寝起きだけにとどまらず、つねに動きがゆったりとしているということ。
会話というかいわのない電話に、すこしばかり違和感をかんじる。気になったわたしはそっとふすまを開けて、母親のようすをうかがっていた。
ごく短い通話のあと、母親は置いた受話器に手をそえたまま動かなくなっていた。しばらくすると深いため息をつき、ふっとわたしの方をみる。
「なんな、朱里。あんた、見よったんな」
「うん、ごめん。おばちゃん、どしたん?」
「んん……。出かける用事ができたけん、あんたら今日はもう帰りよ」
「すぐに帰れん用事なん?」
「そうじゃな……、遅くなるかもしれんなぁ」
「…………隼斗の、こと?」
ためらうように視線をおよがせる、隼斗の母親。そして意を決したように、しっかりとこちらを向きなおす。
「隼斗が逃げた」という母親のことばに、背筋が凍りつくような感覚をおぼえた。ほかのふたりも同じなのだろう、落書きの手をとめ顔をあげる。
隼斗の母親がちかづき、わたしの頭を両手でつつんだ。そして、「なんね、その顔は」といいながら軽くゆする。
揺られるあたまのなかに抱いているイメージ、それは映画などでみる脱獄の図だった。おそらくとても強張った表情で、わたしのあたまは揺さぶられているのだろう。
彼の母親の胸にだきよせられ、ことの状況を聞かされる。ランニングの途中ふらっと列をはなれ、その場で職員に連れもどされたのだという。
計画的な行動ではなさそうなので、繰り返さなければ問題はないだろうと聞かされた。施設に呼びだされたから、自分はいまから行ってくるという。
「おばちゃん、隼斗に会うん?」
「どげえじゃろうか。行ってみらんと会えるかどうか、わからんわなぁ」
「そんなら、もしな! もし、隼斗に会えたら、訊いてきて欲しいことがあるんやけど」
「……なんな、言うてみよ」
彼女のうでのなかから抜け出たわたしは、正面にたちしっかりと瞳をみつめる。部屋に座っていた皐月と茅野も立ち上がり、わたしのうしろへと揃って立った。
わたしたちが、まいにちここへきて過ごしていることを知らせてほしい。それが隼斗にとって迷惑に感じないか、それを訊いてきてほしい。
わたしたちは、この場所で隼斗の帰りをまっていたいと思っている。もしも迷惑だと思われたとしても、ずっと待ちたいと思っている。
「じゃけんな、むちゃくちゃなことせんで……はよ帰れるようにな、頑張ってほしいって伝えてくれんかやぁ。わたしな、ずっと待っちょくけんって……」
◇空のそら|第3章へ…つづく↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
