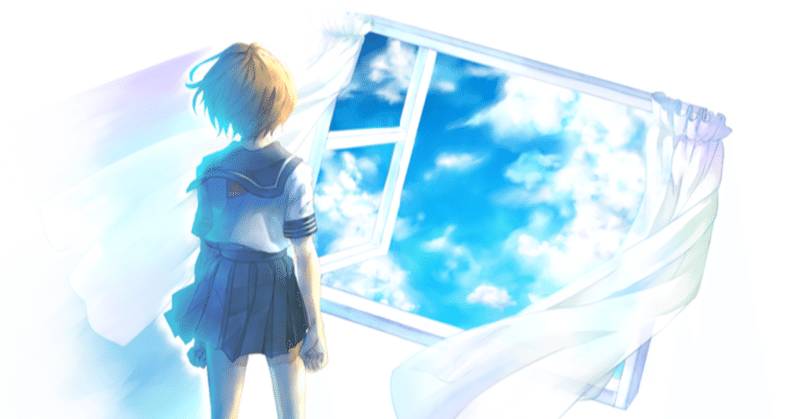
空のそら|第4章|長編小説
第4章…01
放課後のくつばこで石川たちに声をかけられ、案内したい場所があるとつげられた。ついて来るかこないかと問われ、ふたつ返事で行くとこたえる。
ふたたび行き場をなくしてしまっていたわたしたち、そこがどんな場所であろうとかまいはしない。ためらうことなく、彼らのあとをついていく。
大通りをさけるかのように、ふだんは通らない住宅地のなかをひたすらあるく。もうずいぶんと歩いたように思い「まだか」と声をかけようとしたとき、住宅地のなかに線路があらわれた。
さびついて壊れそうな線路、くさって還りかけた枕木。わたしたちが生まれるよりもずっとむかし、ここは海軍専用のひきこみ線だった。
「なあ、まだ歩くん……」
「うん、まだ……もうちっとあるかな」
「いい場所って、どげんとこなん」
「久我んとこ、行けれんなったけん……」
「家?」
「……まあ、そうやな」
ぼんやりとした会話をしながら、石川たちは線路をあるきはじめる。それを越えるものだと思っていたわたしと皐月は、顔をみあわせ立ちどまった。
振りかえることなくすすむ石川と増田のうしろで、茅野が振りかえり手をまねく。寂れた引込み線のうえ、駅のほうがくへと歩みをすすめた。
途中にあらわれた橋梁をまえに、わたしたちはひるんでしまう。せまい横幅にくわえて、けっこうな長さの橋なのだ。
振りかえった増田の、気をつけてなという涼しいことば。言われなくても気をつける。つまづきでもしようものなら、まごうことなく川のなかだ。
誰からともなくいち列にならび、線路のうちがわを会話なくあるいた。なにごともなく渡りきったとき、石川が前方をゆびさした。
「あの踏切、……あれ越えるけん」
「はあ? まだ歩くんな」
「駅のまうらまで行くで」
「うそやろ。……だれんとこに行きよんのな」
見れば指さされた踏切というのは、まだまだここから遠いところにある。そこからさらに駅のまうらまでと聞かされ、途方にくれそうな気持になった。
踏切のてまえ、信号のない横断歩道。運転マナーは底辺だと称されるだけあり、なかなか車はとまってはくれそうにない。ふて腐れぎみに、皐月がくちをとがらせた。
それをみた茅野は呆れたようにわらい、車道へとふみだし強引にくるまを停車させた。「やるじゃん」と機嫌よくわらい、わたしたちは向こうがわへと走りわたる。
「篠木宏之って、知らんかな」
「……ささき?」
踏切をこえて、駅のうらの地区にふみこんだ。木造のふるい住宅が、ところせましと建ちならんだ地区だった。線路沿いのみちを歩きながら、石川が告げたなまえ。
フルネームで聞かされたなまえだが、おもいあたる人物像がうかびあがらない。おなじように皐月も首をかしげている。
「茅野も、知っとんひとなんでな」
「知っとるよ。……椎名たちは、そっか会ったことねんか」
「……ねえな。っちゅうか、どこであうんな」
「一年ときは、たまに学校きよったで」
「え、どういうこと」
「ん? ……ああ、同級なんで。……一応は」
茅野の同級だという発言に、当惑した。たとえ生徒数がおおいとしても、二年間いちども顔をあわさない同級生などありえるのだろうか。
茅野がいうようにたまにしか登校しないとしても、その存在くらいは知っていてもおかしくはないはず。篠木という人物につながる、なにかしらの記憶がないかとふりかえる。
一学年のわたしたちは、そのほとんどを屋上ですごしていた。あたまのなかは隼斗でいっぱいで、きっと誰のことにも関心を持てていなかったのかもしれない。
茅野のくちからも誰からも、篠木というひとの名前を耳にした記憶はよみがえりはしなかった。二学年も似たようなもの、あえずに気になる人物などおりはしなかったはず。
「……あ、」
「ん?」
二学年の記憶をたどっていて、ふと気になることをおもいだした。毎朝の点呼であがったなまえに、いちども返事がかえったことがないこと。
それこそ最初のうちはよばれていたその名前も、じきに点呼されなくなっていた。おそらく数回は聞いていたであろう名前だが、わたしのなかには残らなかった。
「……ひとと、つるまんっちゅう……うわさの」
「ああ、そうそう。二年になってから、いっこも来ちょらんけんな」
「うそやろ……、わたしら行っていんな。やべえんじゃねんな」
「なんが? べつに構わんじゃろ」
どういういきさつで篠木の家にいくようになったのか、今日わたしたちが行くことを彼はしっているのか。聞けば篠木には、なにも伝えてはいないと返る。
彼はビリヤード場の常連だったという。ひまをもてあましていた石川たちは、そこで篠木とはなすようになったそうだ。
ひととつるまないという噂のおとこが、この三人とつるんでいるということに疑問をかんじた。その疑問をくちにすると、茅野はそれを否定した。
篠木は、じぶんたちとつるんではいないという。その場のなりゆきで会話をして、なんとなく家に足をはこんでいるだけだという。
「なんそれ、勝手にいきよんのな」
「失礼じゃな。勝手にとかいわんでや、いちおう許可は……たぶんもろうちょる」
「なんそれー! まじ、やべえやつじゃん……。わたしら、なんしに来たんとか言われるんじゃねえやろうな」
「それはしゃあねえは、篠木は俺らがおってん居らんでん、関係ねえみたいやけん」
三人いわく、つるまないという彼のうわさは本当みたいだ。ただそれは寄せ付けないという意味合いではなく、深入りはしないという意味のようだという。
はなしかければ普通に会話もするし、むこうからばかを言って笑うこともあるという。ビリヤードなどを教えてもくれるし、ひとを突き放すような冷たさはないという。
ただ必要以上に関心をしめしてくることはなく、つぎがあるような約束などはしないという。ひとに合わせることよりも、じぶんの意思でこうどうをする人物だといった。
どうしても拭いきれない、一匹狼という篠木のイメージ。心配はいらないからとつけくわえた茅野のことばに、ふあんが消え去るだけの説得力をかんじない。
「ちょ、待ってな。……おーい、篠木」
木造平屋の借家らしき建物のまえで、三人はあしをとめ篠木の名をよんだ。しんと静まりかえったとき、わたしの不安が緊張にかわるのをかんじた。
玄関のよこの部屋のなかで、ひとの気配をかんじる。しかしそれははっきりとしたひとの形ではなく、気だるくのばされた腕のすがただった。
下方からのびたそのうでが、ゆっくりと窓をスライドさせる。すこしだけ開いたその窓から、「勝手にあがれ」という声がきこえてきた。
「ひとを連れてきちょんのやけど」
「んあ? なんか、ひとって」
窓のむこうがわに、篠木の上半身がうつしだされた。さらに開いていく窓をみて、わたしと皐月は手をつないだ。
そう、おたがいに逃げおくれのないようにだ。軸足にちからをいれて、いつでも走りだせる心づもりをする。しかし厳つい姿をとらえた瞬間、ふたりの足はすくんでしまった。
「……逃げそびれたんな。そげなんじゃったら、最初から来ないいやん」
「…………。」
「んで、……あんたら、だれな」
ほそい瞳をさらにほそめて、冷淡にいいはなつ。だれかと問われているようだが、おもうように声がだせそうにない。篠木が、怪訝なかおをした。
答えないわたしたちに、苛立ちをかんじたのだろう。かるく舌打ちをしてから、たばこに火をつけおおきく吸いこんだ。吐きだされた煙のむこうに、するどい眼光がみえかくれする。
意識的にではなかったが、二年前の屋上をおもいだしてしまう。そして目のまえのおとこと、あのときの隼斗をくらべてしまった。
「……しゃべれんの?」
「あ、こっちが七瀬でな……こっちが椎名っちゅんやけど」
「しいな? ……ああ」
だんまりをしていたわたしたちの代わりに、石川がふたりの名前をしょうかいした。窓わくにひじをついている篠木が、うすら笑ったような気がした。
そのひとみが、なにかを言いたそうにわたしをみる。そんな篠木のしぐさに不快をかんじ、わたしは不機嫌に顔をそむけた。
「あんたが隼斗の、あれか……。あんたら、いつまでん外に突っ立っちょらんで、あがれば?」
あんた、という言いかたに苛っとした。続けざまの隼斗のあれ、というセリフに疑問をかんじる。このおとこは、わたしたちの何をしっているのだろうか。
なんにせよ、おもしろくない言われようだ。なにかしらのもやもやとした感情が、胸のなかでゆらゆらと揺らめいている。初対面にこんなに腹がたったのは、いつぶりであろうか。
わたしの顔色をうかがうように、そっと茅野がちかづいてくる。石川と増田はかまうことなく、さっさと玄関のなかへと入っていた。
茅野の「行こうや」という声に、皐月のひとみがどうするかと問うてきた。わたしが篠木のたいどに不快をかんじている、それをふたりは察知しているのだ。
「……あがる」
「え、でも朱里……」
さげすんだような表情で、わざとらしく煙をはいている篠木。そんな姿をみて、ひきさがれないと思ってしまう。
不安そうな皐月の手をとり、わたしは玄関へとむかった。ふんっと鼻でわらった篠木のことは、しっかりと視界のすみにおさめている。
勇んで踏みこんだその部屋は、おもっていたよりも男のへやだった。四畳半ほどしかないせまい空間に、ベッドとこたつとカラーボックス。
どこをどう見てもくつろげそうな場所はなく、いりぐち付近で立ちつくしていた。石川をはじめとする三人は、すでにこたつを囲んでいる。
ひとりベッドのうえでくつろぐ篠木が、「すわれば?」とすずしく言いはなつ。ゆいいつ残されたベッド横のせまいスペースに、皐月と肩をならべ腰をおろした。
「なあ、あれらしいな。あんたん為に、隼斗の兄貴が殴りこんだらしいやん」
背後からのおもいもよらない言葉に、わたしはベッドから背をはなした。こいつらのなかに犯人がいる、そう思ったわたしは茅野をにらむ。
目があった茅野はそくざに首をふり、増田は気まずそうに石川をみる。ちかくにあった雑誌を手にとり、わたしは石川めがけて投げつけた。
「おまえが喋ったんか!」
「ごめん! っていうかさ、あんな事件……めったねえし、言いたくなるじゃんか」
「石川、それはちょっとデリカシーなさすぎじゃわ。朱里が、かわいそうやんか」
「……なんが、かわいそうなん」
石川を責める皐月にたいして、篠木がはなしのこしを折った。ことばに詰まった皐月の代わりに、わたしは篠木のことを睨む。
両手をあたまのうしろに組んで、知らんかおでくつろいでいる篠木。視線がじぶんに向いていることは、きっと空気でかんじているはず。
閉じられたまぶたはぴくりともせず、まったくこちらに関心をしめそうとしない。無の表情から、彼の感情はまったくよめない。
ばかにされているのだろうか、完全に見下されている感覚に戸惑いすらおぼえてしまう。この部屋のぬしでなければ、文句のひとつも言えるだろうに。
「あんたのために、やってくれたんじゃろ。それ喋っただけやん、べつにいいじゃん。……あ、ちょっとどいて」
いいながら起きあがった篠木は、かわらず無表情のままベッドから片足をおろす。あいだに足をおろされたわたしたちは、引きはなされるように身体をそらした。
いっぽうの足をベッドに残したまま、彼はボックスからレコードを取りだした。そのままのたいせいでプレーヤーに手をのばし、手にあるレコードをセットする。
ことが終われば素知らぬかおで、ふたたびベッドへと戻っていった。そして何事もなかったかのように仰向けになり、ひとり足をくみくつろいだ。
気をつかってくれとは言わないが、あまりにも無神経すぎるのではないだろうか。ぬしだから仕方ないといえばそうだが、居心地のわるさこのうえない。
「……あんたら、目でしゃべっちょらんで普通にはなせば?」
「っ! ……」
皐月とのアイコンタクトで、さんざんにぐちをこぼしているときだった。篠木の意外なことばに、おもわずふたりして振りかえる。
天井むいてのうのうとしている彼のかおは、さほど関心なさげにこちらを向いている。視線がぶつかりはしたが、その後なにかを言うわけでもない。
ただ彼のひとみが物言うてくる。「言いたいことがあるなら言えばいい」と。わたしの勝手な想像なのかもしれないが、なんとなくそんなふうに感じた。
かといい言えるはずもなく、わたしたちは想いをのみこんだ。呑みこまれた想いは処がせますぎると、わたしの顔からあふれだした。
部屋にひびきわたる澄んだ音。レコードだからなのか、高音が切なくこころに沁みてくる。許されない恋のせつない歌詞が、わたしの意識を篠木から引きはなす。
だれが歌っているのだろうか、どんな想いでかかれた詞なのだろうか。この伝説がほんとうならば、きっとわたしもそれに生まれかわれる。
「……だれの、うた」
しずかに曲がおわったとき、目のまえの篠木に問うてみた。だまったまま見つめ合い、時間だけがすぎていく。目のまえのわたしの言葉は、篠木にとどいていなかったのだろうか。
なんという曲であるか、うたっているのは誰なのか。もういちどゆっくりと、はっきりとした口調で問いなおした。しかし彼からのこたえはなく、その表情にすら変化はみられない。
完全にばかにされている、こいつはわたしを無視しているのだ。それであればこちらも同じく、こいつの存在はわすれてやろう。
おなじように振りかえっていた皐月の腕をつつき、ふたりして篠木に背をむける。苛立ちはおしこめて、無になれじぶん。
「なあ、……あんたって、おもしれえな」
「! …………」
「下のなまえ、なんちゅうんな」
「…………」
「教えたくねえん? ……べつにいいけど、好かんのじゃろ。あんたって言われるの」
もの申したい気持ちがこみあげるが、ぐっとこらえて言葉をのむ。聞こえない、見えない、反応してたまるものか。
鼻でわらった篠木は、おもむろに身体をおこした。たばこに火をつけてから、ベッド横のまどを全開にする。目視はしていない、あくまでも気配で感じていることだ。
わざとらしく煙をはいて、ふたたび鼻でわらったのがわかった。どうしてこうまでも見くだされなければならないのだろうか、くやしさから振りかえってしまう。
「負けたな、わかりやす……。シカトしょうと思っとったんじゃろ、残念じゃったな。……で? なまえ教える気になった?」
悔しすぎるし、簡単なじぶんがなさけない。そして言い返すことばを失ってしまったいま、この場にいること自体がたまらなく苦痛になった。
会話がなくとも見透かされてしまう、目のまえのおとこから離れたい。初対面でありながらずけずけと内をあばいていく篠木、こいつが苦手だとかんじた。
立ちあがったわたしに後れをとらず、皐月もまた立ちあがる。それをみた篠木は、金魚のふんといってばがにしたように笑った。
部屋をでようとするわたしたちに、もう帰るのかと茅野が問う。屈託のない三人のかおが、わたしのことを脱力させる。
「ふーん、逃げるんや? ……また、くる?」
「……しらん」
「怒ったん? ま、いいけど。うち、鍵とかしちょらんけん、いつでも来れば? 俺とかおらんこと多いし、勝手につかえばいいで。……あ、か、り……ちゃん」
「……んなっ」
「なんな、そげん怒んなの。そっちん女が呼びよったやん。じかん早えーけん、送らんけど気をつけて帰りよな。……朱里ちゃん」
小馬鹿にしたような物言いに、こぶしをにぎった。くつろげる場所として案内されたこの家で、わたしはいったい何を得ることができただろう。
苦手意識と苛立ち、それしか得るものがなかった気がする。知らない曲にであえたが、その曲のタイトルの歌手もふめいなまま。
玄関からそとに出て、もどるべき道をみすえた。角をまがるそのまえに、いちどだけうしろを振りかえる。開いた窓から、なかのようすはうかがえない。
その窓から吐きだされた煙草のけむりが、すうっと風にかきけされる。不登校のいっぴきおおかみは、よそ者を受け入れるつもりはない。そんなふうに感じて、わたしは煙に背をむける。
第4章…02
さすがに中学三年にもなれば、廊下でほうきを振りまわすような幼稚な男子生徒もいなくなった。昼休みというながい休み時間、お喋りがメインの女子は盛り上がっている。
この学校の生徒ならばすでに、隼斗の少年院いきをしっている。なにをしてそうなったのか、興味がわくのは当然のことであろう。
とくに、このクラスの生徒ならばなおさらだ。本来ならばおなじ教室にあるはずのすがた、うわさ話が大好物な女子の関心はむきだしになっていた。
そう、あの事件があったからだ。北斗のとった行動が、彼女たちの好奇心に火をつけたのだ。そしてそれは、ここに存在しているわたしへと向けられた。
「なあなあ、椎名さんって……まだ、久我と付きあっちょるん?」
「久我の兄ちゃんって、なんで殴りこんできたん?」
「久我って、いつ帰ってくるん? 椎名さんって、面会とかできるん?」
どこからともなく湧いてくる、デリカシーのない女子のむれ。聞こえないふりをして窓のそとをながめやりすごす、その胸のうちはもやもやとするばかり。
まだ付き合っているのか、そんなのこっちが訊きたいくらいだ。隼斗の母親には、はっきりと終わりをつげられた。しかし本人と話せないいま、それはわたしにもわからないことなのだ。
いつ帰ってくるのか、それも先におなじくだ。たとえ少年院の所在をしったところで、わたしは面会など許されることのない立場のにんげんなのだ。
じぶんにできる最後のことだ、といって殴りこんできた北斗。その彼も、あれからわたしのまえには姿をみせてはいない。
「……朱里、しょわねぇ?」
「ん? ……ああ、……うん」
「みんな、何なんやろうか。……朱里ん顔みりゃ、久我、久我っち言ってから」
「まあ、しょうがねえじゃろ……」
「じゃけんど、腹たつやん。朱里が言い返さんけんって、みんな調子にのっちょんやん」
たしかに腹はたっている。しかしそれを相手にぶつけないのは、面倒なことになるのがいやだからなのか。いやきっとそうではない、じぶんがいちばん訊きたいにんげんだからなのだ。
わからないから答えられない、それがよくわかっている。わからないと正直に告げればよいのだろうけれど、それをくちにするのが嫌だった。
宙ぶらりんになっているふたりの関係、それを認めてしまうのがこわかった。そんなわたしの態度は、そのうち生意気だといわれるようになった。
不良と付きあっているからと、いい気になって態度がわるい。そんな陰口が、いやでも耳にはいってくるようになった。
「……言い返せばいいねん、なんで言わんの」
「めんどくせえやん。そんたびに、わからんって答えるしかねえなるし……。それよりさ、つぎの授業……矢野なんよな。出とうねえんじゃけんど……」
中庭の向こうがわの校舎をみあげ、ひじをついておおきくため息をつく。まんなかにとび出た場所、そこはわたしたちの居場所だった懐かしい屋上だ。
そこはすでに、あたらしい生徒を迎えいれているのだろうか。どうであれ、もうわたしたちが踏み入れていい場所ではないことだけは確かだった。
この新校舎には、わたしたちの隠れられる場所がない。それならば外にでるしかすべはないのだが、どこへ行けばいいのかおもいつかない。
ボウリング場にでも逃げこもうか、一瞬だけそんなおもいが脳裏をよぎる。しかしにぎやかすぎる場所、そこにわたしたちの居場所があるだろうか。
「……茅野ら、どこに逃げこんどんのじゃろ」
「ほんとっちゃな、行くとこなんか……、あ……まさか」
おもいあたる場所が、ひとつだけあった。いつでも鍵があいていて、勝手をしろと言われた場所。きっとそうだ、そうに違いない。
皐月と目があったとき、もしかしてが確信にかわった。そしてふたりのあいだに、音のない会話がはじまる。確かめにいくか、いかないか。
学校をぬけだすことに関しては、たいした抵抗などありはしない。ただ気がかりなのは、篠木ほんにんだ。彼とわたしは、決して馬が合うとはおもえないのだ。
しかも小馬鹿にされ、逃げかえったという事実がある。ふたたびこちらからのうのうと出向いていくのには、少しばかりの戸惑いをかんじる。
「歓迎は、……されちょらんかったでな」
「うん、まあ……たしかに」
「見くだされちょったでな」
「ん、……それはあったな。……けど逆にさ、こっちも気をつかう必要はねえっちゅうことなんじゃね?」
ほかにめぼしい場所が思いうかばないいま、わたしを言いきかそうとする皐月の必死さがつたわってくる。始業五分まえのチャイムがひびいた。
あわてたように走りだした皐月は、どうやら二階へと荷物をとりにいったらしい。「くつばこで待っちょってよ!」というこえが、階段のうえからきこえてきた。
くつばこで合流したわたしたちは、いようなほどに落ちついて外へとでていく。このおおきな校舎のおかげで、職員室からわたしたちが見えないことを知っているからだ。
ただ厄介なのは、学校のすぐそばに警察署があるということ。運がわるければすぐにみつかり、うれしそうに警察官がでてくるにちがいない。
建物のかげで立ちどまり、安全そうなルートを思案する。かなり遠まわりになりはするが、やはり石川から教わった道をいくしかないと答えをだした。
「……ちょ、ごめん。わたし、無理やわ」
「え、うそやん。ここは、朱里が声かけてくれんと」
「なんでな、べつにわたしじゃねえでん良くね?」
「いやいや、……やっぱ朱里じゃろ。声がむりなら、窓……たたくとか」
篠木のいえのまえまでは、迷うことなくたどりつけた。ただ勝手にあがることに対して、やはり迷いが生じてしまっていた。
あたりの静けさに負けないくらい、彼の部屋も静まりかえっている。窓がしまっているこの状態では、そこに本人が居るのかいないのかもわからない。
そっと玄関のなかをのぞいて、茅野たちが来ているか確かめようか。そんな勇気があったなら、こんなところで言い合いはしていない。
窓をノックしろという皐月の腕をつかみ、じぶんが行けと窓のほうに押しやる。
「うるせえ!」
「! ……」
「……昼寝ん、じゃま」
勢いよくあいた窓から、不機嫌なこえがきこえた。おそらくベッドにいるのであろう、篠木のすがたは確認はできない。
予想していたよりも不穏なくうきに、わたしたちは声もだせずにしりぞいた。来なければよかった、そんな後悔がおそってくる。ゆっくりと後退していて、ふとおもい足をとめる。
「……あ、あの」
「なんな、あがればいいやん」
「いや、そうじゃねえで……」
起きあがった篠木の顔をみた瞬間、ふたたび言葉をつまらせてしまう。たったひとことだけ言おうとおもっていた。そのひとことすら出てこなくなった。
しかし声をかけてしまったのはわたしのほう、なにも言わずにやり過ごしていいはずもない。
なんとかしてひとことを絞りだすために、わたしは篠木から視線をそらす。見なければいい見えなければいえる、そう考えたからだ。
「なんな。言いてえことあんなら、さっさと言えの」
「……ごめん」
「は?」
「ひるね……」
視界にはいっていた皐月が、おどろいた顔をしてわたしをみた。篠木の反応はわからない、かえってくる言葉はなにもない。
いうべきことを言ったわたしは、多少の満足感で彼に背をむける。その場を去ろうとするわたしを追いながら、皐月はなんども振りかえった。
篠木がずっとみているという彼女に、怒っているようすかと問うてみた。れいのごとく無の表情で、なにを思っているのかよめないとかえる。
「あ、なあ! あんたら、石川たち探しにきたんじゃねんな」
「……え、」
「だって、あんた俺のこと好かんじゃろ。おれに会いにくるわけねえもんな。……きちょんよ、あいつら」
おもいついたように呼びとめられ、当初のもくてきであったことの答えをきかされた。わかりやすく皐月がよろこび、おもわずわたしの気もゆるむ。
あがる気になったかという篠木の問いかけに、首をたてに振りそうになり思いとどまる。そう簡単すぎては、また見くだされてしまうと思った。
わたしの変なプライドに、皐月が反応した。腕にからみつきわたしを見あげ、くりくりとした瞳でみつめてくる。
わかっている、わかってはいる。この家をのがしてしまえば、わたしたちに行く場所なんてないということ。わたしの強がりを制止するべく、彼女は必死にうったえているのだ。
「しー! 声……でけえって……」
皐月の上目づかいに負け、しぶしぶと玄関のなかへと入る。篠木の部屋ではない正面のへやから、石川たちの声がきこえた。
そういえばわたしたちが来たとき、篠木は昼寝をしていた。おそらく三人は気をつかい、べつの部屋であそんでいるのだろう。
もともとわたしたちは、三人の居場所をさぐっていた。そこに彼らがいるのであればと、まようことなく正面へとむかう。
「朱里!」
聞きなれのない声でなまえを叫ばれ、おどろいて肩をあげ立ちどまる。すでに右手は扉にとどいていたが、それを開けることはかなわなかった。
手首をつかまれ、扉から引きはなされていた。そのつかまれた手首は、すこしだけ痛みをかんじている。なにをそんなにむきになり、強くつかむ必要があるのだろうか。
「こん部屋は、いけん」
「え、でも……茅野たちん声……」
「とにかく! ……行ったらいけん」
痛みをかんじる手首をさすりながら、いわれるように部屋をはなれる。わたしたちが強行にでないと知ってか、篠木はさっさと自室にもどった。
じぶんの部屋のとびらをあけ、振りかえってこちらをみる。わたしたちが玄関へいかないのを確認した篠木は、それを閉めることなく中へとはいった。
三人のいない部屋は、このまえより少しだけ広くかんじる。いやこれは広さではなく、心細さなのかもしれない。やはり篠木はベッドにくつろぐ。
こたつの周りがあいているにもかかわらず、わたしたちは前回とおなじ場所に落ちついてしまう。
「な、なあ……。なんで、むこうの部屋……」
「うるさい。……訊かんでいい」
言いかけてことばを呑みこんだ。いろいろと訊くなといった篠木のひとみが、あまりにも鋭かったからだ。
今後も、あの部屋へは近づくな。だれに何をいわれても、絶対に入ってはいけない。そう続けた篠木に、わたしたちはうなづくことしかできない。
てきとうに相づちをうっているのではないか、おそらく彼はそれを疑っているのだろう。するどい視線は、しばらくの間わたしたちをとらえていた。
「……あ、これ」
「気にいったんじゃろ、これ」
「うん、音が……きれいやけん……」
「おと? ……うそばっかり、歌詞なんじゃねん? じぶんらと重ねちょんのじゃねんな」
前回のときに、教えてもらえなかった曲がかけられた。その澄んだ音にひきこまれ、ざわざわとしていた心が落ちついていくのを感じる。
そんななかでの篠木のことばに、心臓をわしづかみされ呼吸をわすれる。痛くてたまらない、掴まれた心臓がにぎりつぶされるように痛い。
痛みからか怒りからか、身体があつくなっていく。そんなわたしをあざ笑うように彼は、隼斗とはまだ付き合っているのかとつづけた。
こいつもか、こいつも他のやつらと同じなのか。興味本位で近づいてくる、うわさ好きなやつらとなんら変わりないのか。
めんどくさい、聞きあきた、うっとうしい、わたしの視界から消えてしまえ。腹のなかであくたいつきながら、いつものようにやり過ごそうとした。
「答えんのや……」
「あんたに、こたえる必要ねえじゃん」
「おれに教えたくねん? それとも、……教えてほしいのは、じぶんとか? すてられたんじゃろうか、どうなんじゃろとか、おもっ……」
「……うるせえ」
「え……?」
「皐月、かえるで」
篠木のことばに、あたまが真っ白になった。いや正確にいうならば、わたしのすべてが黒にそまった。いまこの場で、こいつを殴ってしまおうか。
冷静なのかどうなのか、じぶんで自分が理解不能になっている。もしもこの場にかならず勝てるアイテムがあるとしたら、迷わずわたしはそれを振りあげる。
かわいいと称する女であれば、ここで涙のひとつも見せるのかもしれない。しかしわたしの持ち合わせにそれはなく、怒りのほうが先にたってしまった。
篠木のなかで予想の展開とくいちがいがあったのか、ひるんだようすで言葉につまる。バックグラウンドには、わたしの気にいっているあの曲。
立ちあがり部屋をあとにするわたしの心中は、的を得られてどうしようもないというやるせなさ。そして、それを悟られたくないというもどかしさ。
「なんな、そげえ怒らんでいいじゃん」
「……むかつく」
「ようあることやん、男……つくれば? 学校でも、面倒になっちょんのじゃろ」
「うるせえ、……だまれ」
去ろうとするわたちたちを追うように、うしろを着いて変わらずことばを吐いてくる。おんなの私に勝ち目はないが、本気で殺意をいだきそうになる。
強気な殺意は、玄関をでたところで悔しさにかわる。くやしくて、みじめでたまらない。傷をえぐられ、その痛みが水となりこみあげてきそうだ。
背後に篠木の気配はかんじていた。しかしわたしは振りかえることができなかった。怒りにかまけ振りかえれば、きっとその時点でわたしは負ける。
「朱里、だいじょ……」
はなれずそばに着いていた皐月が、言いかけてことばを呑みこんだ。みなをくちにしてしまえばわたしのタガが外れてしまう、彼女はそれを悟ったのだろう。
「ちょっと、待ての。そんげえ、怒ってかえるほどのことで……も、……え、おまえ泣き……」
「うるせえ! さわんな!」
角をまがったところで、追いかけてきた篠木に腕をひかれた。振りかえるつもりはなかったのだが、その強さに身体は向きをかえる。
言葉とはうらはらなわたしをみて、彼がひるんだのは仕方のないこと。みられてしまったわたしは、悪あがきのように腕を振りはらうしかできない。
篠木は、それ以上は追いかけてはこなかった。気にして何度もふりかえる皐月が、彼がずっとこちらを見ていると告げてくる。
第4章…03
ことしのこの時期は、昨年のそれよりもじめじめとした暑さを感じる。夏服への衣がえにはまだすこし早すぎるが、みな早々と衣装をきがえていった。
しめっぽい教室のなかに、うっとうしい矢野の声がひびいている。息ぐるしさを感じたわたしは、じぶんのよこの窓を全開にした。
「椎名……は、……うん、来ちょんな」
さすがの矢野も、空気をよむようになっていた。どうせ返事がないことがわかっているのに、そこに時間と気力をついやすのは無駄だとまなんだようだ。
ぶなんにやり過ごし満足そうな矢野をよこめに、舌打ちをして中庭へと視線をにがす。南校舎のかげから、ひとりの男子生徒があらわれた。
その生徒はくつばこへとは行かず、中庭をこちらに向かってあるいてきた。ほどなくそれが石川だということがわかり、わたしに向かってきているようにも感じた。
おもったとおり彼はわたしのまえで足をとめ、ついて来れないかときいてきた。あまりたのしい予感のしない表情に、返答をしぶってしまう。
「ん? 石川か。……こんなとこ来て、なんしよんのか」
「ちょっと椎名に用事あんけん、呼びにきたんじゃけんど」
「用事があるんなら、ホームルーム終わってからでよかろうが。ほらっ、教室にいけ、ほらっ……ほらっ」
わたしと石川が話をしていることに気づいた矢野が、ホームルームを中断してやってきた。教室のなかはざわつき、好奇の目がこちらにあつまる。
野良犬でも追いはらうかのような、矢野のしぐさに腹がたつ。とうぜん石川もだまっているはずがなく、矢野にむかって敵意をあらわにした。
しかし石川がくちを開くより、わたしがつくえを叩くほうが早かった。両手でたたかれたつくえは、おおきな音で矢野をおどろかす。
それと同時にわたしが立ちあがったことで、矢野はこころなしか怯んだようにみえた。ひかえめな口調で、座りなさいというセリフを吐く。
こちらとしては多くをかたる気持ちはない。否、ことばを吐きだすことすらうとましい。従うつもりはない、そう瞳でかたるだけでじゅうぶんだとその場をたちさる。
「……椎名、教室に……もどりなさい……」
「なあ、しょわねえん? ……あれ」
「ん? ああ、……どうせ追いかけて来きらんじゃろうし」
廊下でおちあった石川は、ちからのない矢野のこえに視線をなげる。北斗の件からあと、矢野はわたしに強くでないとほくそ笑んでみせる。
いちどは気にかけた石川も、わたしの発言にうなづいた。そのおもわくも間違いではなく、じっさいに矢野は追いかけてはこない。
「ところでよ、なんの用事なん」
「あ、そうじゃった。……ちょ、一緒にきてくれんかや」
「え、どこにな。なんか、いやな予感しかせんのじゃけんど」
「なんな、そげん言わんでよ。……あっち」
苦笑いながら、くつばこのほうを指さす。そとにでるのであれば荷物を、と教室へむきをかえたわたし。その必要はないと制止され、くびをかしげた。
話があるのであればここですればいいものを、いったいなぜくつばこまで移動するのであろうか。さきを行く彼のようすは、なぜか落ちつかないようにもみえる。
どんな用事だと問うてみても、にごすような態度しかしめしてこない。いったいなにを隠しているのだろうか、挙動不審な背中はものをいわない。
「……っと、おれはここまで」
「え、なんなそれ!」
くつばこの手前でわたしの背中をおすと、石川は外へととびだしていった。つんのめってしまったわたしは数歩まえへすすみ、だれかの足のまえでぎりぎり止まる。
学校のくつばこにふさわしくない、私服のじんぶつに違和感をかんじる。ゆっくりと顔をあげそれが篠木だとわかり、おもわず顔をゆがめてしまった。
「そげん、いやな顔せんでいいやん」
「……なんな。なにしよんのな、こんなとこで」
「なんって、あやまりに来たんじゃけんど。こんまえ、怒らしたみたいじゃったけん」
「は? べつに怒ってねえし、あやまって欲しいとか思っちょらんし」
謝りにきたという篠木は、なぜか妙にうえからの態度だ。怒っていないならなぜ家にこないのか、そんな答えようのない質問をなげかけてくる。
なんとなく彼の視線からにげたくなり、わたしはその場のちいさな段差にすわりこむ。おなじように屈みこんだ篠木は、執拗に顔をのぞきこんできた。
ふたたび問われる、なぜ来ないのかという質問。きっと何かしらの返答をしなければ、この問いかけはつづくのだろうと思わせる雰囲気だ。
行かないことに理由はない、それがわたしの答えだった。そんなこたえに篠木はため息をつき、「ごめんな」とわたしのあたまをくしゃりと掻いた。
「やっぱ、おもしれえな……わかりやす。とにかく、謝ったけんな。機嫌ようなったら、またあそびにこいよ」
見くだされているという感覚が、ふいに心地よさにかわった。篠木の表情が、いままでのものと少しかわった気がする。
これは、わたしのご機嫌をとっているのだろうか。それともこれが、彼の本来の雰囲気なのだろうか。わたしが構えすぎていただけなのかもしれない、そう感じた。
とくにつぎの言葉をくちにするでもなく、彼はじっとわたしのようすをうかがっている。きっと何かしらの反応をまっている、そう感じてうなづいてみせた。
「……犬、みたいやな」
「…………はあ?」
わけのわからない言葉をのこし、くつばこをあとにした篠木。みえる範囲でみとどけていたが、彼はいちども振りかえりはしなかった。
よみがえる篠木のセリフに、いまさらながらもやもやと胸がかすみだす。犬とはどういうことだろうか、わかりやすいとはなんだろうか。
おもしろがられ、おちょくられているのだろうか。わたしは馬鹿にされているのだろうか。やはり見くだされている、完全に下だとおもわれている。
この立ち位置は、このままずっと続くのだろうか。ひっくり返せる日がくるとは、とうてい思えないような気がしてしまう。
「……あ、椎名。ちょっと、……話、いいか」
「なんな、」
「週末なんじゃけんどの、……久我んとこに、行ってこようと思っちょんのじゃけんど」
「ふーん、……それがどしたんな」
立ちあがり振りかえると、そこに矢野がやってきていた。やって来たといってもわざわざではなく、職員室にもどる途中に出くわしたという感じだ。
おそらく北斗にいわれたことを全うしにいくのだ、わたしは瞬時にそう理解した。隼斗に会いにいくときかされ、動揺がなかったわけではない。
しかし矢野にたいしておおきな反応をしめすこと、それは今のわたしにはできなかった。いや絶対に、したくなかった。
「なんか、伝言……とか、ねえか?」
「なんそれ。……そうでな、あんたは会えるんやもんな。いやみったらしいな、あんたに伝言とか頼まんわ」
「嫌みとかじゃ! ……いや、すまん。そげん感じたんなら謝るけん。椎名の言葉があれば、……あいつも頑張れるっち思うけん……応援、しちゃってくれんか」
隼斗をはげましたい、応援したいきもちは当然ある。しかしわたしがそれをしていいものなのか、隼斗自身がもとめているのかわからない状態だ。
いまのわたしたちの関係性を、矢野は把握できていないのだろうか。もしくは知っていながらも、わたしの関与をもとめているのだろうか。
目のまえの矢野は、頼りなさげにこちらをみている。わかっている、かれは本当に隼斗のことを心配している。
そのくらいのことは感じとれているし、もちろんわたしだって心配でたまらない。会いたくてたまらない、どう過ごしているのか知りたくてしかたない。
「……勝手に、ひとりで行ってくれば?」
ほんとうの想いとは裏腹に、わたしは冷たく言い放った。わずかな期待もくだけたと、矢野の顔がものがたる。わかりやすく肩をおとした彼は、教室へときえるわたしをみつめていた。
つくえからかばんを取り廊下へもどると、そこにはまだ矢野のすがたがある。手にあるかばんをみた彼は、はっとしたように右手をのばした。
「ど、どこに……いくんか」
「べつに、どこだっていいやん。あんたには関係ねえじゃろ」
「関係あるやろうが……、担任なんじゃけ」
「……勝手に、担任なんかならんでくれんかや。……うぜぇ」
ふりはらわれた矢野の腕は、ちからなくぶらりと垂れおちた。教室にもどれという声にも覇気はなく、とうぜん追いかけてくることもない。
どこまで見送られたのかは定かではないが、強引につれもどすつもりはないようだ。しょせんそんなもの、教師なんて、担任なんてそのていどのものなのだ。
いざ学校をでたはいいが、ひとりでどこに逃げこもうか。皐月が居たとていく気になれぬボウリング場など、ひとりではなおのことだ。
思案しながらあるいていて、ふと自分のいる場所にあきれてしまう。てくりてくりと歩いているのは、あの引込み線のうえだった。
なにをやっているのだという自分と、しかたないだろうという自分。なにやら脳内ではふたりのじぶんが、かってに言い争いをはじめていた。
そっと玄関のとびらを開け、だれかのくつがあるかを確かめた。おんな物のくつがいっそくと、おとこものが二足ある。しのぶように家へとあがり、しずかに篠木のへやをのぞいた。
どうやらあのあと篠木は家へはかえらず、ほかの場所へいっているようだ。おくの部屋にひとの気配をかんじ、ためらいながら扉をあけた。
「……あ、あの。……茅野たちは」
「え、茅野? ああ、あいつらなら……まだじゃけんど」
「そうですか、すみません……」
へやのなかには、くつと同じだけのひとがいた。さんにんとも高校生だろうかと思わせる背格好だったが、制服などはまとっていなかった。
しめきられたカーテンから、うっすらとあかりが差し込んだ部屋。篠木の部屋よりかは広めではあるが、それを感じさせないほどにどんよりとした雰囲気だ。
そこに彼らがいないとわかり、いそいそと扉をしめ退散する。行ってはいけない、という篠木のことば。忘れてはいないわたしは、多少のうしろめたさを感じていた。
すばやく篠木のへやにとびこんだところで、言いつけをやぶったことは帳消しにはならない。しかしわたしはそうすることで、少しだけじぶんの気持ちをにがした。
だれも居ないへやというのもは、なんだか逆におちつかないものだ。せめて皐月をさそうべきだった、と後悔をしつつも彼らをここでまつことにする。
「なあ、ちょっといいかや?」
「え、あ……。はい」
おくの部屋にいた女性が、こちらの部屋へとやってきた。こたつのまえに腰をおろした彼女は、灰皿をよせながら「たばこ、へいき?」と聞いてきた。
こくりとうなづくわたしをみて、にこりと微笑みたばこに火をつける。かわいさを持ちそなえたような、きれいな女性だなとみとれてしまう。
吐き出される紫煙すら、うつくしいものに思えてしまう気がした。ふとこちらをみた彼女と、視線がぶつかりおもわず照れてしまう。
「なまえ、……なに、ちゃん?」
「あっ、……朱里……です」
「あかりちゃん、か。……朱里ちゃんって、宏之の彼女さん?」
「えっ! ち、ちがいますよ」
「あ、そうなん? なんだ、彼女じゃねえんや……。そんならさ、あっちの部屋いって、わたしらと遊ぼうや」
「え、でも……」
あたまのなかに、篠木の言いつけがよみがえる。しかしなんとなく、それを目のまえの彼女にはいいづらい。
差しさわりがなくぶなんな逃げことば、それがおもいつかずに戸惑った。くすりと笑いたばこをもみ消した彼女は、わたしの手をとり立ちあがる。
ろこつな拒絶もできないままに、気づけば奥のへやのなかへと踏みこんでいた。つながれたままの手は、そのまま部屋のおくにあるベッドへと向かっていく。
うながされるままにベッドのはしに腰かけると、ひとりの男性がちかづいてきた。わたしのまえに座りこみ、好奇のしせんで見あげてくる。
「なあなあ、久我の元カノってうわさ、ほんと?」
「……え、……ああ、……まあ」
このての質問は同校だけでなく、高校生からもあびせられるのかとうなだれた。いつもは聞こえないふりでやり過ごしているが、さすがにここではそれは不可能だろう。
なかばあきらめ気味で返事をすれば、つぎからつぎへと質問はかえってくる。やったのか、という質問にことばをうしなう。なぜ初対面にそんなことを訊かれなければならないのだろうか。
返答がないことに彼らは、わたしが質問の意味をりかいしていないとよんだらしい。セックスをしたのかと、ふたたび言葉をかえて問うてきた。
いまさら気づいたテレビの画面をみて、わたしは脳からの指令をうける。ベッドから立ちあがろうとした身体は、目のまえに居たおとこによってとりおさえられていた。
「え、もしかして……処女? へぇ……、意外じゃな。宏之も、手だしちょらんのや」
「や、やめて……ください……」
「うっそ、まじか。……テレビ観てん。……な? 痛くねえようにしちゃんけん」
あらがおうとすればするほど、制服がみだれていく。おとこから顔をそむけたとき、よこに座っていた彼女と目があった。助けを乞う視線にたいして、彼女はにこりと微笑んでみせる。
わたしがバカだった。彼女のあそぼうという誘いは、こういうことだったのだ。篠木のいいつけの意味も、きっとこういうことだったのだ。
いまさら気づいたところで、もうておくれなのだと悔やむ。どうあがいても、この男のちからには敵いそうにはないのだ。おとこの右手がゆっくりと、スカートのなかへとすすんできた。
「なあ、なんしよんのな」
「あ、宏之……かえったん」
「姉貴、なんで朱里がここにおんのな」
「ひとりで退屈そうじゃったけん、誘ってみたら……きたけん」
篠木の顔がけわしくなり、わたしのことをにらんでいる。ちがう、みずから望んで来たわけではない。ふるふると首をふるが、思いは篠木には届かないようだ。
おこっている、篠木はものすごく不機嫌なかおだ。約束をやぶったからだろうか、だから助けてもくれようとはしないのだろうか。
「やめて、くだ……やめ、れ! さわんな、ころすぞ!」
「はい、残念。おわりじゃな」
下着のなかに指がすべりこんだ瞬間、さいごの抵抗だとおおごえをだした。それを合図にするように、篠木がおとこを引きはなす。
引きはなされた男はわたしのよこで起きあがり、あぐらをくんで篠木をにらんだ。そんなことには構いもせず、篠木はわたしの手をとり引きおこす。
「なんか、宏之。おまえん女じゃねえんじゃろうが」
「んー、まあ……そうなんじゃけんど」
「そんなら、なんも問題ねかろうが」
「どっちんしても、こばまれた時点で……アウトじゃけん。……あんたらとは、ちがうけん」
篠木につれられ部屋にもどったことで、助かったのだという実感がわいてきた。そんな安心からだろうか、へなへなとしたにすわりこんでしまう。
腰をぬかしたようによつんばいで、ベッドよこのあの場所へと移動した。この場所がいちばんおちつく、なんとなくそんな気がした。
あきれたように息をはき、篠木はあの曲を大音量で再生する。その澄んだ歌声に、もやもやとした感情がながされていくような感じがした。
「おまえなぁ……。あん部屋には、いくなって言ったよな」
「……茅野たちが、おると……おもって」
「おらんじゃったやん。……なんし、なかに入ったんな。ばかじゃねん」
女性につれて入られた、などとは言えないとおもった。なぜなら、篠木のお姉さんなのだと知ってしまったから。なにも言い返せず、だまってしたをむく。
あらためて言われなくともわかっている、わたしはなにも考えず行動をするばかなのだ。まえもって忠告をされていたいいつけすら、まともに守りきれないばかなのだ。
あのまま篠木が帰ってこなければ、わたしは確実におわっていた。そんなことすらも、あとで知り後悔をするような馬鹿なのだ。
だいすきな曲すらも、あたまに入ってこない。ただぼんやりと、ずっと遠くできこえているような感覚だ。ふいに髪の毛がすくいあげられたことに気づく。
くるくると指さきであそばれている自分の髪の毛に、ほんのすこしだけ意識がもどってくる。
「……なあ。……俺ん、彼女にでもなる?」
「…………。…………はぁ?」
「にぶっ……」
「いいよる意味が、ようわからんのじゃけど」
「え、ふつうに彼女って言っただけなんじゃけど。おれ、おんなに不自由してねえけん、変なことせんって約束できるし、……すげえ、条件いいとおもうんじゃけど」
「…………わからんのじゃけど」
いくら馬鹿なわたしでも、彼女ということばの意味くらいはわかる。わたしが訊きたかったのは、なぜこの状況でその発想がうまれたのかだった。
篠木の吐きだしたことばの真相、それをたずねたつもりだった。しかし返ってきたことばによって、ことはさらに深く迷宮入りすることとなる。
もしかして、またばかにされているのだろうか。くだらない女だとおもい、見くだしておちょくって遊んでいるのだろうか。反応をみて、腹のなかで笑いものにするつもりにちがいない。
「……え、なんで彼女になる必要があるん」
「そんほうが、いいんじゃねえかと思ったけんやん」
「わりいけど、……まじで……あんたの考えちょんことが、わからんのじゃけど」
「じゃろうな、不信感……だだもれしちょんもんな」
返すことばを失った。ほんとうに理解しがたい状況なのだ。たがいに好意をいだくことなく、とつぜん始まるものではないと思った。
なにをもって条件がいいという思考にいたったのであろうか、そのほうがいいとはどういう意味なのだろうか。不信感をいだかれるとわかっていながら、この事案をもちだす意味はなんだろうか。
「そんげえ、拒絶されるほど……俺ってきらわれちょんのかや」
「いや、そういうわけじゃねえんやけど」
「そんなら、なんも問題ねえじゃん」
「……っちゅうか。べつにさ彼女じゃねえでん、いまのままでいいんじゃねんな」
「嫌っちょるわけじゃねえんなら、べつに彼女になったっていいんじゃねえんな」
このやりとりは終わらないのではないか、そんな予感すらおぼえてきた。はなしをしていくうちに篠木の発言のほうが正しいのではないか、そんな気持ちにすらなってくる。
最終的にわたしは、首をかたむけながらうなづいてしまう。それをみた篠木は満足そうに口角をあげ、いまこの瞬間から下のなまえで呼べという。
「……いやだよ、呼べるわけねえじゃん。そんなら、宏兄って呼んじゃるわ」
「は? ばかじゃねん、彼氏に兄とかつけんじゃろ、ふつう」
「……知らんわ、そんなん」
わらいながらベッドをたたき、瞳があがってこいとささやいていた。わたしの勘違いだといけないとおもい、かれの手もとと顔とをみくらべる。
軽くうなづいた篠木のようすに、わたしは安心してベッドへとあがっていった。彼女としての特典は、このベッドを利用できるということみたいだ。
窓のそとに、石川たちのこえがきこえてきた。篠木がさりげなく窓をあけ、そとの三人と目があう。かたまった彼らは、かおを見あわせ瞳ではなす。
「そういうこと、……じゃけん」
そうくちにした篠木は、わたしの肩にうでをまわしにやりと笑ってみせた。半信半疑な笑みをうかべ、うなづきあう石川と増田。
そのよこで茅野だけは、なんだか不安かつさみしそうな表情をした。そんな茅野をみて胸がぎゅっと苦しくなったことは、誰にもいうことはできない私だけのひみつだ。
第4章…04
俺にとってここでの生活は、おもっていたよりも気がらくなものとなった。それはきっと、諦めるということを学んだから。そうせざるを得ないことを知ったから。
豊徳学園をあとにするとき、地元にかえることをあきらめた。朱里のことはあきらめろ、それも北斗から教えられた。
かといい記憶からけしてしまうことは困難であり、時間をもてあませば考えてしまう。起床してから課業開始までの約二時間、そこは俺にとって必要としない空き時間となっていた。
その間に朝食をとるといっても、そんなものに時間はたいしてひつようとしない。片付けや自主学習をといわれるが、それほどがむしゃらに学びたいなどとも思わない。
できることならばもっと時間をつめて何かしらの作業があり、忙しくあってくれたらいいのにと思ってしまう。
「久我、ちょっとまちなさい。夕食のまえに、面会だ」
「え? ……面会、ですか?」
課業がおわり部屋へもどろうとする俺に、教官がこえをかけてきた。そのことばに耳をうたがい、おれは足をとめ首をかしげた。
ここへきて二ヶ月が経とうとしているが、いちどでも母親があいにきたことなどないのだ。いまさら会いにくるとも考えられず、会いにきてほしいともおもわない。
もしかしたら北斗だろうか。彼もおなじくここへは来たことはないが、可能性があるとするならば彼だ。だとすると俺のしるものに、なにかよくないことがあったのかもしれない。
「……兄貴ですか」
「いや、お兄さんじゃなくて。中学の……担任だ」
「え、担任……。ああ、それなら会わなくて大丈夫なんで」
「それは、おまえが決めることじゃないな。とにかく、どうしても話しておきたい……というから、着いてきなさい」
ここでは俺の意思もなにも、あってないものと同じらしい。自立支援という目的の施設ではなく、更生をしいられる機関なのだとおもいしらされる。
重いあしどりで教官のあとをついていき、面会室のとびらのまえでかるくため息をつく。開かれたとびらのむこうに、神妙なおももちの矢野のすがたをとらえた。
数ヶ月まえのすがたとちがい、ずいぶんと顔色もわるくやせたようにみえる。三学年の担任というものは、そこまで気苦労のたえないものなのだろうか。
ああ、もしかして俺なのか。おれが矢野の気力も体力も、ことごとくすり減らしているのだろうか。厄介なにんげんの担任になってしまった、そう思っているにちがいない。
「久我、ひさしぶりじゃの。……顔色もよさそうで、安心した。どげえか、がんばりよんか」
「あ、まあ……。はなしって、なんですか」
「あ、ああ。じつはな、おれの軽率な言動で……椎名をな、傷つけてしまってな。申し訳ねえことしたなと思うて、おまえに謝りとうてきたんじゃけんど……」
「いや、自分にあやまってもらっても……」
おそらくあの日のことを言っているのだろう、そう感じた。おもむろに椅子をたった矢野は、おれに向かってあたまをさげる。
つられるように立ちあがった俺は、どうしていいかわからずにうろたえる。部屋のすみでメモをとっていた教官が、ふと顔をあげてこちらをみた。
「先生、おすわりください」という教官のことばに、おれは救われたような感覚をおぼえる。こういうのは苦手だ、はやく帰ってはくれないだろうか。
新学期のはじめに、北斗にあったとはなす矢野。おとうとのことを本気で心配していたぞ、と弱々しくほほえんだ。
いったいなにが言いたいのだろうか、なんのはなしをしに来たのだろう。謝罪がもくてきであったとするのなら、すでに用件はおわったはずだ。
「……あんな、椎名なんじゃけんど」
「なんかっ! ……あったん……ですか」
「あ、いや……すまん、そんなんじゃねえで。椎名の担任になったんを、言いたくて」
「担任。……そうなんですか。元気に、してますか」
矢野が担任であるということは、おれと朱里はおなじクラスなのだということだ。
彼女の望みのひとつを、叶えてあげられるはずだった。それを俺がだいなしにしてしまったのだという事実に、ひざのうえで組んだ手にちからがはいる。
そしてこの現実をまのあたりにした彼女は、おそらく激しく傷ついてしまっただろう。悔やんでもくやみきれない、どうしようもない想いに胸がいたむ。
「ちゃんと、……学校にいってますか」
「椎名か? ああ、……うん、ちゃんときよんよ」
じぶんは体育の教師なので、ほかの授業のことはあまり把握はしていない。しかし悪いほうこくは受けてはいないので、しっかりとやっているだろうと答えた。
やっているだろう、とはどういうことだろうか。担任でありながら、彼女のことを把握できていないという発言に矛盾を感じてしまう。
おれの怪訝な顔をみてか、執拗に彼女は元気だとくりかえす。訊きかえしてもいないのに、そこまで強くいうのにも違和感がある。
矢野はうそをついている、それは明らかだった。ただどの部分がうそなのだろうか、元気もしっかりも気やすめか。そもそも本当に彼女は登校しているのだろうか。
「うそ、……ですよね」
「えっ、先生がなんのうそをついちょるって言うんか。あいつは本当に、元気に毎朝きちょるけん」
「……毎朝。……あさしか会ってないとか、ですか? あ、茅野たちとは」
「おお、連中とはなかよくしちょんみたいやぞ」
「そうですか。……朱里んこと、ちゃんと見てやっちょってください」
「ああ、それは約束する。ちゃんと見とくし、……つぎは、必ず伝言を預かってくるけん」
次はといった時点で、今日の伝言はないとしれた。あのころの朱里であったとしたならば、かならずや伝言をたくすはず。
それがないということは矢野との関係性がよろしくないか、すでに俺とのことには見切りをつけてしまったか。どちらも多いにありえることだ。
ほかに好きなやつができれば忘れるだろう、という北斗の言葉がよみがえる。これでよかったのかもしれない、彼女には俺のそんざいは重すぎる。
「伝言とか、いりませんから。あと、……もう、面会とかもいいですから」
「なんし、そげなこと言うんか。……おれは、おまえの担任なんぞ。心配するんは当然じゃろうが。伝言くらいなら、伝えてもいいっち院のひともいいよんのじゃけん」
「いや、朱里ん邪魔になるんも嫌ですし……」
「じゃまって、なんか……。なんし、そげなふうに考えるんか……。なげやりにならんでくれ、久我。……そんげえ、先生のことが……」
すべてを聞かぬまま、おれは立ちあがりあたまをさげた。尻つぼみに会話がとぎれた矢野のひとみは、だまったまま俺のすがたを映している。
話がおわったことを知らせるべく、そばにいる教官にこえをかけた。状況をみとどけていた彼は、おれからの強制終了であることをしっている。
わざわざこんな遠くまできてくれているのだ、ちゃんと先生と向きあいなさいと忠告をうけた。たかが教師と生徒のあいだがら、なにをそんなに話すことがあろうか。
「すみません。……わたしが頼りないばっかりに……」
「いえ、先生。そう卑屈にならないでください」
「……はい、しかし」
「みんなこんな感じですよ。ここに来たばかりの子たちってね」
こんな感じとは、どういうことなのだろうか。おれは至ってふつうに、とりみだすこともなく矢野に接したつもりだ。言葉にも気をつけて丁寧にはなしたつもりだ。
弱々しいため息をつき、ゆっくりと立ちあがった矢野。支えがひつようなのではないかと思うような、ちからのない立ちすがただ。
「大丈夫ですか」などと教官にいわせるようなやつに、頼もしさを感じろというほうが無理がある。久我は大丈夫ですなどと、根拠のないことばで矢野をはげます。
「その、椎名さん? とかいう生徒さんのことも、しっかりと……ね、先生」
「あ、はい。それはもう自分の生徒ですから、そこはしっかりと……」
「久我のとこにも、足をはこんであげてください。大丈夫ですから」
「はい、そうします。……久我、また来るけんの」
しっかりと、というそのことばに不安をかんじる。いまの矢野で、朱里のことをささえていけるのだろうか。もともとウザいといっていた彼女が、矢野のことを受け入れるだろうか。
気がかりではあるけれど、俺にはどうすることもできない。矢野を介して彼女の日常がかいまみれたとしても、ただ知りながらひとり想うことしか叶わない。
それであれば、なにも知らされないほうがいいのではないか。そう思いながらも、また来るとの矢野のことばに期待をしてしまう自分がいる。
第4章…05
「……あれ? 宏くん、おらんのや」
「あ、椎名。なん、今日めちゃ遅せえやん」
「ん? ああ、ライブ前じゃけん練習いっちょったんよ」
夏休みも終盤をむかえていた。そのながい休みの最後のライブにむけて、わたしはスタジオにこもっていることが多くなっていた。
なんとなくそのまま帰宅する気になれなくて、ベースを抱えたまま篠木のいえにきてしまう。やはりこの顔ぶれをみると、ほっと気持ちが楽になってしまう。
ぬしである篠木は、めずらしくはないが留守にしていた。慣れというのはこわいもので、まるでここの住人であるかのような馴染みぶりの皐月のすがたもある。
「起きたときには、もう篠木はおらんじゃったけんな」
「は? なんな、起きたときって」
「っちゅうかさ……、きのうん夜、出ていってから帰ってきてねんじゃねんかや」
「……あんた、ここに泊まったんな」
「え、あ……うん、その……」
言葉をにごしながら、増田の視線はへやのとびらを飛びこえている。その視線をたどらずとも、篠木の姉のところにいたのだとわかってしまう。
わたしや皐月の出入りを禁止している篠木だが、石川たちの出入りをとめてはいない。その目的は、言わずと知れているのにだ。
どんな気持ちなのだろうか、精神的にきつくはないのだろうか。弟としての篠木のメンタルも気になるが、ふつうに接してくる姉の気持ちも理解しがたい。
「あんたらさ、いい加減にしちょきよや。猿みたいなことすんなや」
「さ、さる! 椎名、それはひでえは……。おれ、泣くで」
「泣いちょけ、ばかたれ」
さんにんの男たちは、暖をとる猿のようにかたまった。えんえんと泣くまねをして、そしておおげさに笑いはじめる。その場にあったクッションを、猿の群めがけて皐月がなげる。
わたしはベッドのうえに膝をたて、まどを全開にして煙をにがした。ついでのように外のようすをうかがうが、篠木の帰ってくる気配はまだない。
わたしが初めてこのベッドにあがった日からほどなくして、校内にわたしと篠木のうわさがながれた。ふたりが付きあっているというそれは、またたくまに広がっていった。
茅野のはなしによれば、流言を指示したのは篠木ほんにんだという。なるべく速く、できるだけ広く、そう篠木はいったらしい。
「あれなんじゃねえかや。……ほら、椎名……隼斗んことで……」
「え、なんな。なんで隼斗……」
「いや、ほら。みんなに訊かれて、うざそうやったやん」
「ああ。……で、なんの関係があんのな」
「うわさ広めたん、それんせいじゃねえかや……って。じっさい、隼斗んこと訊いてくるやつ、おらんなったじゃろ」
いわれてあらためて考えてみると、たしかにその手の質問はなくなっていた。篠木とつきあっているんだね、そんなことばは耳にした。しかし後につづくことばはない。
「すげえな」という皐月のつぶやきに、わたしは確かにとうなづいた。もしもそれが事実であるとしたならば、あまりにもかっこよすぎるはなしだ。
「……ところで、皐月。あんた、何時ごろきたんな」
「んん……、昼過ぎくらいかや」
「そうなんや。そっから宏くんって、いっかいも帰ってきちょらんのな」
「うん、まだいっこも会っちょらんで」
とくにふかい意味はなく、そんな会話をふたりでしていた。ふと石川の態度が、ぎこちないように感じてしまう。こちらの会話にまきこまれたくない、そんなふうに見えてしまった。
よくよくみれば増田もそうだし、茅野もできれば加わりたくないというようにみてとれる。さんにんの頭のなかに浮かんでいるもの、それはおそらく私とおなじ。
篠木は、例のへんなことで夜にでかけたのだろう。すでに相手とはわかれ、ちがう場所にいどうしているかもしれない。いや、していないかもしれない。
「あんたら、篠木がどこに行っちょんか、知っとんのやねんな」
「え、そんなん。おれらが知っちょんわけ、……ねえじゃんなあ」
「うそいいよ……、そん顔はぜったいに知っちょん」
さんにんの不自然なふるまいに、皐月が気づいてしまった。彼の居場所をつきとめたところで意味はないが、聞きださずにはいられないのだろう。
なぜなら皐月のなかで、篠木はわたしの彼氏なのだから。そしていき先にこころあたりのある彼らが、それをくちにできない理由もおなじ。
篠木の彼女になってからというもの、彼はもちろんのこと周囲のたいどもかわった。大切にされている、気をつかわれている、それがとても伝わってくる。
へんなことはしないと約束をした篠木は、実際にそれを守ってくれている。なぜならこの交際はいつわりであり、彼女というのはわたしの称号でしかないからだ。
しかしその事実を、ここにいる四人はしらない。だますのであれば身内から、それは基本中のきほんだということなのだ。
「皐月、もういいっちゃ。……別に、どこに行っちょんとか知りたくもねえし」
「え、……でもさ。なあ、朱里……いつから、そげん怖キャラになったんな」
「は? なんかそれ、なんも変わっちょらんしな」
彼女の発言に目をまるくして、ふっと鼻でわらった。茅野のたばこをうばいとり、ベッドにもどって窓のそとにけむりをはく。
ふわっと空中にただよったそれは、かすかな風にかきけされた。わたしと篠木の関係ににている、そんなことを思いながらみつめる。
篠木がわたしにあたえた称号は、おそらく彼のおもわくどおりに進んでいる。ともだち以上、恋人みまんのそんな関係でたのしくすごせてもいる。
ただ、彼はやさしすぎる。あえてなのか素なのかはわからないが、あまりの紳士ぶりに戸惑いをかんじることもある。彼の多くをしってはいけない、知ればきっとじぶんが傷つくことになる。
「……門限、きびしいんじゃねかったんな。……なんで、……なんでおるんか」
おきにいりの曲をバックグラウンドに、わたしは眠りについてしまっていた。聴こえなくなっていた曲がよみがえると同時に、だれかの声がしたような気がした。
それは茅野たちのものではなく、ここに居るはずのないもののこえ。きっと夢をみている、これはどういった夢なのだろうか。
たばこの香りがちかくなり、ほどなくお酒のにおいがした。嫌いなかおりではないうえに、心地よいぬくもりを感じてしまう。これはきっといい夢だ、なんとなく幸せなきもちになれる。
「……まじか。……なんし、こげえ無防備なんか」
無防備とは、どういう意味なのだろうか。いったいわたしはどんな夢をみているのだろうか、この感覚はもしかして。おもわずなにかを抱きしめた。
「……おまえ、なんしよん……。ちゃんと抵抗してくれんと……」
わたしが抱きしめていたのは、胸元にかおをうずめた篠木だった。彼みずからつくったルール、それを忘れるほどに酔っているのだろうか。
なにをしている、抵抗をしろ。そんなことばと裏腹に、彼の行為はすすんでいく。他人のはだの温もりが、こんなに心地よいとはしらなかった。
もっとも繊細であろうわたしのなかへ、優しくはいってくる彼のゆび。「抵抗しろ」というセリフは、篠木のくちからは出てこなくなっていた。
彼の動きにあのときのような不快はない、そしてそれが篠木自身といれかわろうとすることにも、怖いという気持ちはおこらなかった。
「……うごかんで。……がまん、できんなる」
「え……、うごいてない……」
「ちがう、……なか」
すんでのところで何かをおもうように、うごきを止めた篠木。なにを言っているのだろうか。そしていま、なにを思っているのだろうか。
約束をやぶることへの後ろめたさ、抵抗をしなかったわたしへの苛立ち。いまさらそんなことを考えているのだろうか。篠木のひとみが、さみしそうにわたしの瞳をとらえる。
「なあ、朱里。……おまえ、隼斗んことすてて、俺ん本当の彼女になる覚悟、……あるか」
うしろで流れていたあの曲が、はっきりと耳にとびこんできた。しっかりと篠木自身のぬくもりを感じていながら、意識をどこかに忘れたように息をとめる。
なんて残酷なのだろうか。篠木のこうどうも、このわたしの反応もざんこくだと思った。あまりにも現実的なルールのくずしかたに、これが篠木の世界観なのかとことばをなくす。
「……まじ、……か」
「宏くん、……わたしなら、だいじょ……」
「大丈夫じゃねえじゃろ! ……忘れきらんのじゃろ、隼斗んこと」
一瞬でもこばまれたらアウト、それが篠木のポリシーなのだ。服をよせあつめ手渡し、みずからも衣服をととのえ背をむける。
そのうしろすがたに、声がかけられない。そもそもこんな場面でかける言葉など、このわたしが持ち合わせているはずもない。
そしてなにより、篠木のことばに思いしらされていた。そうだ、忘れていないのだ。隼斗との宙ぶらりんな状態から、わたしは抜けきれていないのだ。
「宏くん、ごめんな……」
「ごめんじゃねえで、……どこ行くんな」
「うん、……かえる」
「帰るじゃねえやろ、こんな時間に……」
「……うん、大丈夫よ」
とびらのまえで立ちどまり、背中ごしの会話をした。いつものように送るとはいってもらえない、そんなことはわかっていた。すべてじぶんがまいた種、わたしの優柔不断がまねいたこと。
とびらを開けてかたまる。目のまえに篠木の姉がたっていたからだ。苛立ちをあらわにした彼女は、いったいいつからそこに居たのだろうか。
一瞬ひるんだわたしだったが、彼女に会釈をしてよこをぬける。しかしその腕をつかまれ、抜けきることはできなかった。
「宏之! あんた、くずやで! こんな時間に、おんなひとりで帰らせるんか」
「言われんでん、わかっちょんわ」
「だいたいな、たかが元カレんことくらいで怯んじょん、あんたがけつまらんわ!」
「うるせえ、くそビッチ! おまえらなんかと、一緒にすんなや」
いきおいよくベッドからおりた篠木は、そのままの勢いで姉をけりとばした。静まりかえった深夜のへやに、ふたりの罵りあいがひびいている。
こんな男はやめておけという姉にたいし、うるせえとわたしの腕をひく篠木。どうしてこんなことになってしまったのだろうか、成す術なくふたりのけんかをみつめてしまう。
「朱里、こっち来てん」
しばらく続いたけんかもおちつき、篠木の姉は部屋へともどっていった。ベッドのうえでこちらをむいて、彼が手まねきをしている。
いわれるままにそばに寄ったが、そこへあがる勇気がなかった。ベッドのはしに腰をおろし、篠木にたいして背をむけた。
「なんしよん、……こっち来いって」
「いや、……でも」
「でもじゃねえやん。……こっち、向いてん」
腕をつかまれ、強引にひきよせられる。月のあかりだけでみる互いの顔は、どことなくぎこちなさを感じさせる。なにかを言いかけてのみこんだ篠木の、足のあいだにおさまったわたし。
せつない伝説の曲はずっと流れつづけていて、会話のないこの状況にふくざつな気持ちになってしまう。まともに顔がみえなくてよかった、そんなことをふと思った。
「なんで、隼斗にしっかり棄てられてくれんかったんな……」
ぽつりとこぼした篠木のことばに、びくんと心臓がはねた。もしもそうしていたならば、なにかが変わっていたのだろうか。
しっかりと別れをつげられていたならば、こんなことにもならなかったのだろうか。篠木の優しさにあまえ、利用するようなかたちになってしまった。
そして最終的には、篠木のことを傷つけた。そんな不甲斐ないじぶんがなさけなくなり、じわりと涙がこみあげてきた。
「宏くん、……やっぱ帰る」
「ごめん、もう言わんけん行かんで。……帰るとかいわんで」
帰らないでくれということばが、こころの深いばしょに沁みる。ずっと押し込めていた感情が、ひとのくちを介して吐きだされたような気がした。
置いていかないでほしい、戻ってきてほしい、そばに居てほしい。そんな想いを、二年間おしころしていた。自分にむけられたその想いで、やすらぎを得られるのは何故なのだろう。
「眠てえんじゃねん? ……寝ていいで」
「んん……、大丈夫で。……なあ、宏くん……わたしらってさ……」
「いうな。……いらんこと、考えんでいい」
「……うん」
ふかくを考えるなといった篠木だが、わたしたちはもう気づいている。偽物をつらぬくことができず、本物にもなりそびれてしまった。
出会いかたがちがっていたならば、なにかが違っていたのかもしれない。しかしそんなことを今更かんがえたところで、なにも意味なんてありはしない。
わたしたちのこの関係は、きょうここで終止符をうつことになるだろう。かくんと首がおちるわたしをみて、くすっと笑い抱くうでにちからをこめる。
「子犬の寝落ち……」とつぶやく声に、「寝てない」とちからなく言いかえす。なにを言われても腹がたたない、そんな関係になれていたのに。
「……朱里? 寝たん? ……なあ、おまえ……俺んこと、避けんなよ」
ほとんど意識をもっていかれていたが、篠木がなにかをしゃべっているのはわかった。胸にうずめている頬からつたわる彼のことばが、まるで子守唄のように優しくきこえていた。
第4章…06
夏を走りぬけ秋をとびこえて、制服は冬服へとかわっていた。真冬のそれにはまだ及ばないが、肌寒さをかんじるほどにはなっている。
静まりかえったくつばこで、できるかぎりゆっくりと上履きにはきかえた。のろのろとした足どりで廊下をあるき、どのクラスのホームルームも終わっていないことをしる。
さらにわたしの足どりはゆるくなり、じぶんの教室のまえまできてしまう。なかにはまだ矢野がいる、それを知るわたしの足は手前でとまった。
「お……、椎名。なんか、……遅刻か」
わざわざ言葉にせずとも、みれば遅刻だとわかるであろう。それを敢えてくちにされたことで、おもわず舌打ちをしてしまう。もう少しおそくに家をでればよかった、そんな思いが脳裏をよぎる。
ぷいと顔をそむけとびらに手をかけたところで、ふたたび矢野がくちをひらいた。
「なあ、椎名。いつも早退しよんみたいじゃけんど、どこに行きよんのか」
「べつに、……どこでんいいやん。あんたには関係ねえことじゃろ」
ひとりで居るのか、誰かといるのか。矢野の質問はつづいていたが、わたしは振りかえることすらせずに黙秘をとおした。
いくら問いかけようが答えない、と諦めたのだろうか。ことばをとぎれさせた矢野は、ふかいため息をついた。それを終了のあいずと捉えたわたしは、教室へと片足をふみこませる。
「あっ……ちょっと。昼休みじゃけんど、ちょっと職員室にきてくれんか」
「なんでな」
「ちょっと、……はなしがあるけん」
「そんなら、いまここで言えばいいじゃん」
「いや、ちょっとここでは。……あれ、じゃけん」
わかりやすく視線をおよがせる矢野。なんとなく予想がつく、きっと隼斗絡みのはなしだ。矢野は足繁くかよっていて、わたしはいくどとなく声をかけられた。
伝言はないか、近況をしりたくないか。知りたくないと言えばうそになるが、隼斗からの伝言がないのも事実。あれば訊こうとせずとも、矢野のほうから言ってくるはず。
そんなあやふやな状況をつきつけられ、わたしから何の伝言をたのめようか。これはなんの罰なのだろうか、あまりにも非情すぎる仕打ちだとしかおもえない。
一限目も二限目も、いったいなんの授業があったのだろうか。教室にこそいたものの、その内容はまったく記憶にのこっていない。
陽あたりのよい窓ぎわのせきは、この季節には昼寝にさいてきだ。じっさい眠ってしまったとしても、起こしてくる教師などは居なくなっていた。
起きていられるとやりにくい、寝ていてもらったほうが助かる。おそらく教師のだれもが、そんなふうに思っているにちがいない。
「あかーり、せんぱい!」
屈託のない笑顔が、窓のむこうがわにやってきた。彼女としりあったのは、夏のライブの会場だった。たまたま手にしたチケットで、会場にやってきたという彼女。
ちょっぴり風変わりないんしょうをもつ彼女は、その日いらいこうして懐いてきているのだ。くりくりとおおきな瞳をかがやかせ、窓をあけろとジェスチャーをする。仕方ないなと窓をあけ、その全力の笑顔にといかけた。
「どしたんな……」
「ちょっとだけ、訊いてもいいですかぁ?」
「なんな、言ってみよな」
「朱里先輩って、いつも一年の校舎をみてるじゃないですかぁ?」
「……は? ……見て、ねえし」
「やっぱり! うちのクラスの男子が、朱里先輩がじぶんをみて笑ってくれたって……。あいつの勘違い、まじうける」
たしかに、屋上ならばみていたことはある。しかし一年がこちらを見ていたことは、いまのいままで知らなかった。ただの一度も、だれかと目があった記憶などないのだ。
ましてや誰かに微笑むなど、そんなことがあるわけがない。もしも屋上をながめ無意識でほほえんでいたとするならば、それはそれで問題ありだと背筋がひえる。
そのむねを彼女につたえると、彼女は気まづそうに背後をきにする。彼女いわく、その生徒はその気になってしまっているというのだ。
「朱里先輩って、いま……彼氏とかいるんですか?」
「え、……彼氏」
夏休みのあの一件のあと、はじまりの時とおなじように校内にうわさが流れた。もちろん流言の指示は篠木がだしたものだが、その内容が驚愕だった。
篠木の五股がばれて、椎名からすてられた。その内容というのもとうぜん彼ほんにんが指示したもので、さすがのわたしも篠木に物もうした。
あまりにもぶっ飛びすぎている、そこまでする必要があったのか。そんなわたしの言葉に、彼自身はすずしく笑ってみせたのだ。
じぶんの五股は意外とゆうめいなはなしであるし、じぶんの反則行為からこうなったのだからという。このくらいの罰をうけなければ、じぶんの気持ちもおさまらないと。
そして無事に称号をはずせたあとも、これに免じて反則をゆるしてくれという。今後は元カノという称号で、いままで通りにあそびにきてくれというのだ。
それからわたしは元カノというかたちで、篠木のいもうとのような立場にいる。
「んん……、彼氏か。……おらん、のかな」
返答をにごしてしまうのは、やはりわたしのなかに隼斗がいるから。篠木に言い当てられてしまったように、しっかりと終わりを告げられていないから。
その返事をきいた彼女は、ちらちらとじぶんの背後をいしきした。さっきからなにを気にしているのかと、わたしも彼女の視線をおってみる。
制服に着られているような、ういういしい男子生徒がたっている。わたしがそちらを見たことで、その男子はひとりその場で空回りをしはじめた。
なんだ、あの可愛らしいいきものは。そう思わずにはいられないほど、小動物のようにきゃぴきゃぴとしている。ためしに微笑んでみせると、小動物は飛びはねはじめた。
「あの、朱里先輩。あいつがですよ……、先輩に気持ちをつたえてくれって言うんですよね」
「……気持ちって、なんな」
「好き、らしいんですよ。それで、返事をきいてほしいって頼まれたんですけどぉ……」
「……付き合う系の? 気持ちはうれしいんじゃけどな、年下は……ちょっと、な」
「ですよね! わたしも、やめとけって言ったんですけどね」
「なんそれ。まあ、付き合えんけど、ありがとって伝えちょって」
「はい! ざまあみろですよね!」
うれしそうに振りかえった彼女は、男子生徒にむかってあたまのうえでおおきく腕をクロスしてみせる。露骨に落ちこんだ男の子をみて、腹をかかえて笑うしまつだ。
なんと無邪気ないじわるをするのだろうと、男の子が気の毒になった。わたしたちも一年のころは、こんなふうに無邪気だったのだろうか。
もしもそうだとしたならば、いつからこんな面倒くさい性格になってしまったのだろう。去っていく彼女をみおくってからまた、あの屋上をみあげてしまった。
「……話って、なんな」
「おう、椎名。ちょっと、むこうの部屋にいこう」
朝にいわれていた矢野からの呼び出しを、そのまま無視してしまおうかとも考えた。しかし放送でよびだしをされるのも面倒だと、すなおに足をはこぶことにした。
じぶんの呼び出しにわたしが応じたことが、よほどうれしかったのだろうか。わかりやすく目尻をさげて、応接室へと軽やかにゆうどうする。
ソファーにこしをおろすなり、隼斗のはなしを始めた。会うたびに顔色がよくなり、こころなしか肉付きもよくなっているという。
うれしい報告ではあったが、興味がないふりをした。それでも矢野は話をやめず、彼はまじめに頑張っているとつづけた。
いまの調子でいったならば、思っていたものよりは早くに退院できるかもしれない。そんな矢野の発言に、おもわず眉間にしわをよせにらみつけてしまう。
「来週じゃけんどの、また会いにいってみようかと思いよんのよ」
「……ふーん、それがどしたんな」
「久我に、……なんか伝えること……ねえか」
無関心をよそおっていたわたしだったが、おもわず脳裏にことばがよぎる。そんなわたしの微かなうごきに、矢野は敏感に反応した。
めがねのなかの小さなひとみが、倍ほどのおおきさにひらく。期待にみちた表情で、身体をまえのめるようにした。そんな矢野の反応に、わたしは逆に冷静になることができた。
あぶなかった、あやうく自滅してしまうところだった。矢野は隼斗からの伝言を、いちどだって持ち帰ったことがないのだ。
そんな状況のなかで、わたしの確認作業はこたえがみえている。わざわざ傷のうわぬりをして、ダメージをひろげる必要はない。
「べつに、伝言とかねえし。ひとりで勝手に会ってくりゃいいやん」
「椎名! ……おまえは、大丈夫なんか」
「は? ……なんそれ」
立ちあがり背をむけ歩きだそうとしたとき、呼びとめるように矢野がこえをだした。久我は頑張っているんだぞ、ということばに奥歯をかむ。
「なんな、それ。……なにが言いてえんな」
「久我は、まえを向いて頑張りよんのぞ。じゃあのに、お前は……どうなんか。なんかに本気で頑張ってみらんか? 高校のことも、ちゃんと考えてみらんか?」
「……意味、わからんわ」
隼斗はしっかりと前をむいて、じぶんのみちを歩きはじめたというのだろうか。いつまでもここでぐずぐずしているのは、わたしだけだというのだろうか。
わたしだって、このままでいいなんて思ってはいない。しかしそれは漠然としたもので、なにをどうすればいいのかがわからない。
こころはあの屋上に置いてけぼりのまま、なにをどう頑張ればいいのかわからない。やりたいこともみつからない、やるべきこともわからない。
時間ばかりがすぎていき、自分だけが取り残されていく感覚。そんななかでどこにむかって歩きだせばいいのか、わかっていたならばそうしている。
頑張れなどということばを、そんなに簡単にいってほしくない。矢野のことばが苛立ちをよび、わたしは応接室のとびらを壊してしまいそうな勢いでしめてしまう。
◇空のそら|最終章へ…つづく↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
