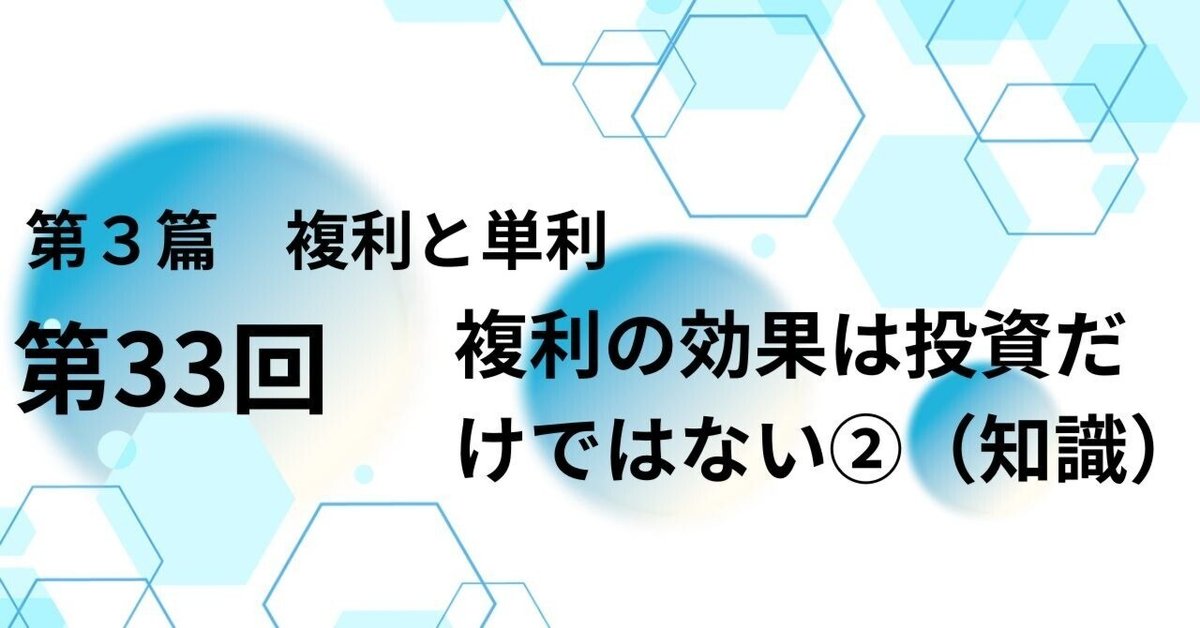
第33回 複利の効果は投資だけではない②(知識)
前回は、経済での複利の効果の説明をしました。
経済と投資は同じ範疇でしょ、と考えている人も多いと思います。
また、あの説明だけで複利の効果を実感し、このままの日本ではダメだと考えることが出来たのなら、それは意識が高い系の人です。
普通の人は、結局は良く分からないと感じただけでしょう。
なぜなら、経済の話なんて、普段の生活からは遠い世界の話だからです。
なかなか自分の問題だと身近に考えることは出来ないものです。
そこでもっと身近に複利を考えられることがあります。
それが知識量です。
昭和時代、日本では詰め込み教育が実践されていました。
軍隊式に、知識を覚え込ませるというものです。
戦後の日本は、この教育方法で先進国の仲間入りを果たしたのです。
バブル崩壊直前には、日本人は、日本はアメリカを抜いて世界一だと思い込んでいました。
アメリカの雇用制度は良くなくて、日本の雇用制度が最良だと、本気で思い込んでいました。
だからこそ、アメリカの逆襲が始まります。
まずは、日本の好景気、つまりバブルを崩壊させました。
更に、日本の商慣行は閉鎖的だとして、日本の至る所に圧力をかけました。
その圧力の矛先が、学校教育にも向かった訳です。
日本が戦後40年余りで先進国に追いついたのは国民性が優れていたからであり、その国民性は学校教育の賜物だと判断したからです。
当時の日本の教育現場では、日教組が中心に活動していました。
彼らは当時の学校教育を「詰め込み式」だと反対し、「ゆとり」ある教育環境の実現を訴えていました。
そこにアメリカが便乗しました。
すると、遅々として進まなかった改革も、あっという間に「ゆとり教育」として実現したのです。
義務教育で、日本人として必要とする最低限の知識を得なくても良くなりました。
その結果、労働者としての日本人の質が、みるみると落ちてしまいました。
なぜなら、最低限の知識を保有していない人たちは、労働力としても価値が低いからです。
ここでちょっと自分自身のことに置き換えて考えてみて下さい。
嫌いな学校の勉強は、何度聞いても覚えられないという経験はありませんか!?
逆に、自分が趣味としていることは、一度聞いただけで簡単に覚えられませんか!?
ここで私の個人的な例え話をします。
江戸幕府の徳川将軍15人、初代から順番に、家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家宣、家継、吉宗、家重、家治、家斉、家慶、家定、家茂、慶喜となります。
因みに、家康の祖父は清康、父は広忠です。
日本史の苦手な人から、同じような名前でこんがらがると良く聞きます。
が、得意な人にとっては、そうはなりません。
それは、名前を覚えるために必要になる他のことも覚えているからです。
まず、日本には「通字」という文化があります。
徳川家が「家」、豊臣家が「秀」、織田家が「信」、伊達家が「宗」のように、一族に引き継がれる名前の一文字です。
徳川家康は、最初は元信、次いで元康、そして家康と名乗っています。
元信は、当時仕えていた今川義元と、義元が同盟関係にあった武田晴信から一字ずつを貰って名乗りました。
ところが、「信」の字は、今川義元と敵対する織田信長の一字でもあったので、祖父清康から「康」を貰い、元康と改名します。
そして最後に、今川義元が織田信長に打ち取られた後独立して、家康と改名しました。
以後の徳川家にとって、家康は最大の功績者ということで、「家」が通字になりました。
秀忠は、家康がまだ豊臣秀吉の配下にいた時に元服したことから、秀吉から「秀」、祖父広忠から「忠」を貰いました。
因みに、家康から「康」を貰わなかったのは、既に兄が秀吉、家康から一字ずつ貰い秀康と名乗っていたからです。
家光は、通字に「光」を付けました。
家綱は、通字に「綱」を付けました。
綱吉は、時の将軍である兄「家綱」から「綱」を貰い綱吉と名乗りました。
家宣は、時の将軍である伯父「家綱」から「綱」を貰い綱豊と名乗っていましたが、将軍に就任した時に改名し、通字に「宣」を付けました。
家継は、通字に「継」を付けました。
吉宗は、時の将軍である「綱吉」から「吉」を貰い吉宗と名乗りました。
家重は、通字に「重」を付けました。
家治は、通字に「治」を付けました。
家斉は、通字に「斉」を付けました。
家慶は、通字に「慶」を付けました。
家定は、通字に「定」を付けました。
家茂は、通字に「茂」を付けました。
慶喜は、時の将軍である「家慶」から「慶」を貰い慶喜と名乗りました。
ここで、通字を使わなかった将軍は、全て元服した時に、その時の将軍から一字を貰っています。
これを「一字偏諱」という文化です。
主君や目上の人の名前から一字を貰い、その人にあやかるというものです。
「通字」や「一字偏諱」の文化を知っていて、将軍の名前を知っていれば、後は芋づる式に覚えられます。
例えば、高校の日本史で覚えないといけない人物に、「上杉綱憲」と「上杉治憲」がいます。
因みに、上杉綱憲は藩校興譲館を創設した藩主、上杉治憲は藩政改革を行った藩主です。
この2人、不得意な人からすれば、一字違いでややこしいということになります。
ところが、「一字偏諱」を知っていれば、それぞれ「家綱」時代、「家治」時代の人物だと分かります。
藩校創設など文化的な事業は綱吉時代に大きく発展しますから、必然的に「上杉綱憲」だと見分けがつく訳です。
また、藩政改革は、享保、寛政、天保の改革という江戸時代も後半の話になることから、「上杉治憲」だと見分けがつく訳です。
また、既に気づいている方もいると思いますが、「憲」は上杉家の通字です。
つまり、歴史が得意であれば、このようにパズルのピースのように、知識が当て嵌まっていくのです。
このことにより、知識は更に吸収され、すればするほど吸収スピードも速くなるのです。
これを「知識の複利」と私は名付けました。
一方、日本史に疎ければ、既に「上杉○○」ということくらいしか頭に残っていないでしょう。
下手をしたら、「上杉謙信」と置き換わっているかもしれません。
結果、知識の上積みが出来ず、このような話は聞かなかったことになっていて、数週間後にはきれいさっぱり忘れていることだと思います。
仕事でも、このことは同じです。
日本人の8割は、自分の仕事を面白いと思っていないと言うデータが出ています。
つまり、さっきの例で言えば、歴史が嫌いという範疇に入る人たちです。
そんな人たちが、生活の糧を得るために、嫌々仕事をしている訳です。
そんな状況では、「知識の複利」の効果は得られず、海外から生産性で引き離されるという現実は、当然のことでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
