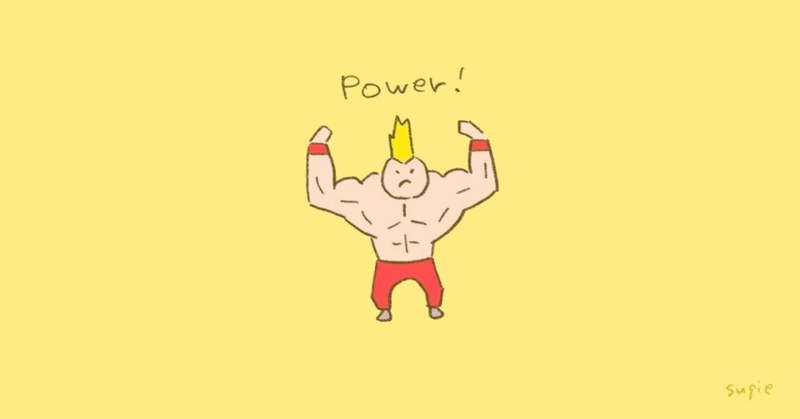
思考の体力・耐力をつける
久しぶりのnoteな気がする。文章書くのが苦手だからなかなか「書くぞー」とはならないのよね。
気ままに気分で書いていきたいと思う。
今回読んだ本は細谷 功さんの「地頭力を鍛える」。
以前読んだ「具体⇄抽象トレーニング」と同じ著者の本で、この本が頭に入ってきやすかったので同じ著者の本も読んでみた感じ。
この本ではフェルミ推定を通して地頭力というものを説明している。
(1)わからないところは仮定・推定することで先に進む
主に仕事の業務を進める中で、「わからないからこれ以上は進めれない。話を聞いてから進めよう」と思って知ってそうな人にヒアリングすることがよくある。
ただ、このときに質問は考えるものの、どんな答えが返ってきそうなのか・その答えから自分がどういう行動を起こすのかを何も考えずにヒアリングしに行っている。ほとんどの場合がそんな感じ。
だからなのかフワッ(曖昧な感じ)と理解して、ヒアリングした後の行動もフワッとしている…
このやり方の改善方法の1つとして「仮定・推定することでとりあえず思考をゴールさせる」ことが大事な気がした。
一旦自分なりにゴールテープを切るところまでを考え切ることで、筋道がある程度わかるだろうし、実行に移すときの行動も変わってくるように思った。
(2)具体⇄抽象の行き来はやっぱり大事
以前読んだ「具体⇄抽象トレーニング」に書いてあったことが今回の本でも書いてあった。物事を単純に理解・説明するには抽象化が大事らしい。
一見同じような内容でも、“このときはこうするけど、別のときには違った方法をとる“といったことがあると頭が混乱して結局よくわからないっていうことに陥る。
本質的なこと、違いではなく共通していることを理解しようとすることを意識していきたいと思う。
(3)「全体から」の思考で漏れ・ダブりをなくす
仕事でも自分ができること、目先解決しないといけない課題にばかり注力してしまって、全体を俯瞰する意識が自分は弱いなと思う。
全体を俯瞰する意識を持つことで、自分の作業の位置付けを理解できて、考えの偏りや検討漏れがあることに気づくことができるんだろうなと思った。
漫画の「アオアシ」で出てくる”俯瞰“ってやつやね。
この本に書いてあることをやろうとしたときに体力がいるなぁ〜っと思った。仮定や推定するのは頭を使いそうだし、疲れそうな感じがする。
ただ、こういった思考の体力(耐力?)は鍛えないと強くなっていかないんだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
