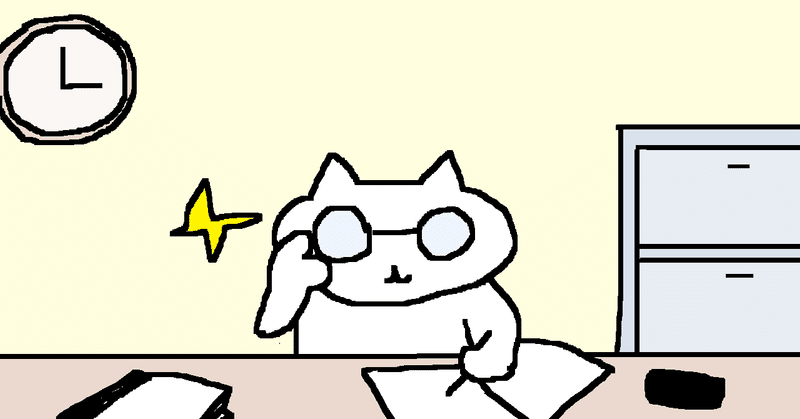
本から学んだ意識したいこと
noteで人気を博している牛尾剛さんの『世界一流エンジニアの思考法』を読んでみた。
noteを見ていてもこの本の感想を書いている記事は何個か見たことがあり人気があり有名なんだろうなと感じた。
読んだ感想としては「読みやすい!」だった。こういった文章ばかりの書籍は漫画と違ってなかなか読むスピードが出ない傾向だったのだが、元々noteをベースにしているからか難しい単語や言いたいことがわかりにくい文章ではなかった。
(1)「理解」には時間がかかる
頭の回転が早く頭のよい人でもスキルや知識を身につけるのにはしっかりと時間がかかるということ。自分は早く成果が欲しい性分でそれのために途中部分を飛ばしたり、あやふやにしたりしてとにかく最後まで行きたいタイプだったりする。すると、一時的に早く成果が出ることもあるが、何も身についていないパターンが本当に多い。
なので、理解には時間がかかることを念頭において、ゆっくり時間をかけて勉強やらスキルアップに取り組んでいきたいと思った。
時間をかけても良いんだ!っていう安心を持てたように思う。
あとそれと集中力を身につけたいという思いも芽生えた。
いろいろなことが頭をよぎって1つのことを集中してやっている記憶が社会人になってから感じたことがほとんどない気がする…
10年ほど前に読んだ『脳の右側で描け』という本はなかなか印象的で、要は「めっちゃ集中して見えているものをそのまま描け!」という内容だったと記憶している。
本の通りに描くと自分が描いたと思えないレベルで細かく描けたと思う。
そういった集中力も必要だなと思った。
(2)サイクルを速くする
やってみる→失敗→フィードバック→修正のサイクルを速く回すようにすると良いみたい。
自分は検討する時間が長いものの、時間の割に進捗が良くないパターンが良くある。ただずっと進捗が遅いというわけではないと思っていて、最初のほうは早いペースで進むものの途中から極端に遅くなる印象がある。
この段階に来ると自分だけではもう手詰まりになっていて他の人からコメントをもらうなど外部からの刺激がないと進まない状態なのだと思う。
ただ、それは認識はしているものの他の人に見てもらったり自分の手からリリースするのが謎に怖くてなかなかできていないのが実際のところな気がする。
もちろん最低限の形は成っていないとダメだろうけど、サイクルを速くする意識は持とうと思った。
(3)脳の負荷を減らす
業務中は脳が疲れる。ランニングしたあとの呼吸のようにハァハァ言っている声が聞こえてきそう。
脳を使っているから当然疲れるのだろうけど、疲れ方が気持ちの良い疲れ方ではなくて悪い疲れ方をしている。
本を読んでその要因を考えたとき、思ったのは「トライする気持ち」「楽しい気持ち」というのがないからだという気がした。
あとよくわからない業務があったり、優先度の低そうな作業に時間を取られたりと減らすことができる業務に脳を取られているのも要因と思われる。
なので、「トライする気持ち」「効果的なことに集中する」意識を持とうと思った。
本は自分じゃない人の考えていることを覗き見ることができるのが良いなと思う。
普段の生活だけだと他の人の考えていることなんて覗き見ることできないからなー。
どんなにAIが発達しても人はやっぱり人に興味あるからSNSなど他の人のことが知れる場はなくならないような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
