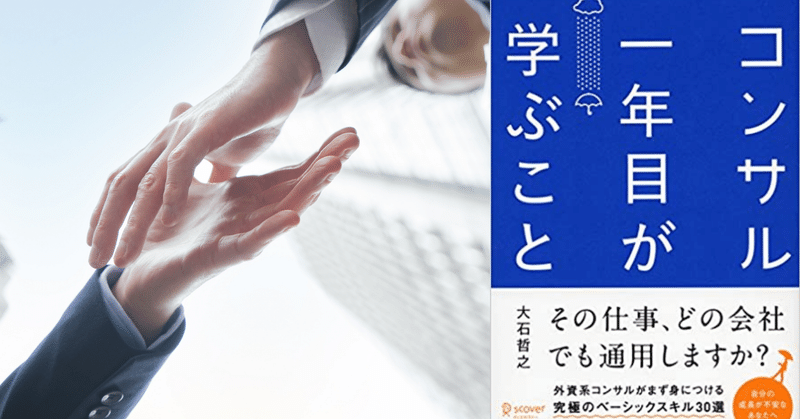
読書レポート:コンサル一年目が学ぶこと
■書籍紹介
著書:コンサル一年目が学ぶこと
著者:大石 哲之
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

1.話す技術は「期待値」で上手くいく
私がやっている「毎日の学び」の中で、ビジネス上のコミュニケーションでは次の3つを重要視するようにと言われていることが多くありました。
①結論から話す
②数値で話す
③論理的に説明する
この本でも同じように上記は重要であると書かれていましたが、著者が特に重要と書かれていたことが「相手の期待値を把握する」ということでした。
ビジネスにおいて一番大事なこと、それが相手の期待を超え続けるということと著者は言っています。
これは、どんな職業・業界問わず、ビジネスでは基本中の基本です。
しかし、私自身「相手の期待を超える」という考え方はできていませんでした。
この本では、「相手の期待を超える」ためには、相手の期待の中身を把握することから始まります。
これは、対クライアントだけではなく、対社内でも考えるべきことです。
顧客や消費者、上司が自分に何を期待しているのかがわかったら、その期待以上の成果を出すことを目指しましょう。
一例ですが、クライアントから「直近の検索語句の傾向のデータを出してくれ」と言われた時、そのまま検索語句のデータを出すだけではダメ、ということです。
データを出すことは求められていることに対する100%ではありますが、それが最低ラインです。
相手の期待値を超えて120%にしなければビジネスでは成功ではないと本書では書かれています。
実際の現場で考えてみると、クライアントが欲しい情報を都度出しているだけでは、コンサルタントの意味ないですよね。
クライアントが欲しい情報+α を送るのか、それとも欲しい情報に対してより細かなデータも付けて送るなど考えていかなければなりません。
これを考えるために、相手の期待値がどこにあるのか、どの程度までか、ということを把握するためのコミュニケーションが必要となります。
2.仮説思考は「問題解決に早くたどり着ける」思考法
コンサルの思考術としてよく言われているのは下記の3つです。
①論理思考
②仮説思考
③問題解決
この中で、著者が重要視しているのは「仮説思考」です。
理由を次のように述べています。
コンサルタントの思考のエッセンスは仮説思考の中に詰まっており、一度身に付けてしまえば生涯使えるからです。
これは著者以外の人たちもこのように「仮説思考」が重要と述べており、社長からも「仮説が弱い」と社内で共有をいただいています。
改めて「仮説思考」について整理します。
仮説思考とは、「はじめに仮説ありき」という考え方で、ストーリーに沿って、あらかじめ調べるポイントを絞り込む思考法のことです。
業務中では、週次報告や月次報告、打ち合わせ資料作成の時など、とにかくデータを集めて、その中からポイントとなる部分を見つけて作成していることが多々あるように感じました。
もちろん、すべての案件でそうしているわけではないですが、時間がかかり非効率的なところがあるなと感じました。
■具体的にどうすれば「仮説思考」となるのか
この仮説思考を実行するには「仮説」「検証」「フィードバック」のサイクルを回していく必要があります。
この本の事例が分かりやすいので事例を上げます。
■課題
A店の売上が悪い
【仮説】
サービスが悪いのでは?
↓
【検証】
アンケートを取った結果「店員の接客態度が悪い」という事実が判明
↓
【フィードバック】
サービス改善のために「社員教育」を行う
仮説思考で考えることで、スピード感を持って動くことができ、問題解決ができるというメリットがあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
