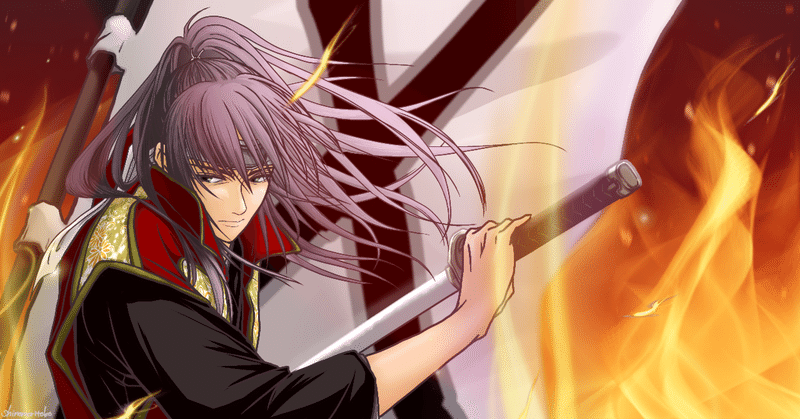
【鬼と天狗】第三章 常州騒乱~嶽の出湯(4)
眼の前で手を叩く音が起き、鳴海ははっと顔を向けた。権太左衛門が、槍を振ってみせている。どうやら、あの傲岸不遜な鎗三郎に勝ったらしい。
「よくやった」
鳴海も、権太左衛門に笑顔を向けた。正に二本松藩士の面目躍如である。後で屋敷に呼んで、褒美として何か饗してやろうと鳴海は思った。
「鳴海殿のご家来は、なかなかやりますな。あの鎗三郎は、謹慎が解かれたら藩校の槍術師範に推挙しようと、拙者が思っていたほどの腕の持ち主なのですが」
苦笑しながらも、ようやく平八郎は明るい声を出した。彼もまた、部下の耳目を気にしたものだろう。今しがた鳴海に聞かせた話は、部下には決して話せない平八郎なりの愚痴かもしれない。
「御頭。もう一勝負よろしいでしょうか?鎗三郎殿が、このままでは引き下がれないと申されております」
権太左衛門が声を張り上げた。まったく、守山藩一同の偵察に来たのも忘れ、権太左衛門はすっかり寛いでこの槍試合を楽しんでいたらしい。
「構いませぬな?」
鳴海は、隣に座している平八郎を見つめた。やれやれとばかりに、平八郎も苦笑を浮かべる。
「あの者も長らく邸内に押し込められていたものですから、良い気晴らしになったのでしょう。ここは一つ、二本松の方々のご厚意に甘えさせていただきまする。松川表で不穏なことばかり申すものですから、御家老らのご不興を被って差控を申し渡され、守山に送られてきたもので」
そう言うと、平八郎は慌てたように口を噤んだ。今のは、平八郎にとって失言だったに違いない。すると、やはりあの者らは、平八郎の思惑を外れて激派の色に染まっているということか。
二試合目の様子をちらちらと伺いながら、鳴海は厠に立つふりを装い、少し離れた席で待機していた政之進に声を掛けた。
「――先に城下へ戻り、源太左衛門様らに申し伝えよ。守山藩の逗留組については、妙な動きを見せぬよう、拙者が三浦平八郎殿を通してお頼み申すと」
その言葉に、政之進が目を細めた。
「大丈夫なのでございますか?確か三浦平八郎殿は――」
鳴海は、軽く肯いた。政之進の心配は、尤もなことである。かつての平八郎であったら、鳴海も手出しをしにきたと勘違いしていたであろう。だが、先程の平八郎の失言で鳴海は確信した。あの男は、今回ばかりはこの地に逗留を願い出ている者等を使嗾し、二本松にちょっかいを掛けに来たわけではない。むしろ、彼らが先走って妙な動きを見せないように、見張りに来たのだ。激派の色に染まりつつある部下たちが、水戸藩や守山藩に禍の種を蒔かないように。今までとは事情が異なる。
「鳴海様は、如何なされます?」
「権太左衛門の槍試合を見届けてから、城下へ戻る」
「承知いたしました。それでは、これにて失礼致します」
政之進は軽く会釈をすると、そのまますっと姿を消した。鳴海も番台に心付けを置き、守山藩士らの分の茶も縁側へ運ぶように命じると、再び平八郎のいる濡れ縁に戻った。
「勝負はつきましたかな」
鳴海が朗らかに声を掛けると、平八郎も微笑を返した。
「いやいや、そう簡単に負けるようでは我等が困ります。それがしも鎗三郎を槍師範に推挙するのに、二本松の御方に負けたとは報告致しかねまする」
「でございましょうな」
それからしばし、平八郎は槍合わせを眺めていた。その横顔を見ずに、鳴海は再び気にかかっていたことを尋ねてみることにした。
「――京に滞在しておる我が藩の者より、かつて三浦殿が庇われた藤田芳之助の姿を見掛けたとの知らせがござった」
「それは、まことでござるか?」
平八郎が、こちらに鋭い視線を投げかけた。
「まことでござる。大和でも京でも別々の者によって目撃されておる故、まず見間違いはございますまい」
鳴海は何気なく水を向けたつもりだったのだが、平八郎の顔には明らかに動揺の色が浮かんでいた。この様子であれば、平八郎は本当に猿田愿蔵や藤田芳之助が京都方面にいたのを知らなかったのだろう。守山ではなく水戸本藩にその身柄を預けたために、逐一事情を把握していないだけかもしれないが。
眼の前で鎗三郎が権太左衛門の槍を跳ね上げた。これで、勝負は一勝一敗となった。だが、その様子にお構いなしに、平八郎は何か考え込んでいる。
「芳之助らの在京の件については、ご存知なかったのでござるか?」
焦れて、鳴海は平八郎の様子を伺った。ようやく、平八郎が小さく息を漏らした。
「猿田愿蔵が大和天誅組の一行に加わっていたかもしれぬという噂は、水戸家中でも耳に致しました。小川郷校の藤田小四郎らほどではないにせよ、あの者も野口郷近辺では人望篤き者として、かねてより名声が高かった者でござる。ですが御上の意思に背いてまで攘夷決行を迫ろうとしたなど、言語道断」
その口元は、かつてないほどきつく結ばれている。よほど、猿田や芳之助の振る舞いが腹に据えかねているのだろう。
「藤田芳之助は、今や猿田愿蔵……いや、先日田中家の養子となった故、田中愿蔵であるか。その従者の如き働きをしているというのは、それがしも聞いており申した。その姿が大和や京にあったのならば、天誅組の一行に田中愿蔵が加わっていたのは、まず間違いございますまい」
鳴海も、眉を顰めた。かつて水戸家中へ芳之助を誘ったのはこの男だが、その男ですら知らないところで、激派は何やら事を起こそうとしている。鳴海も平八郎もそれぞれの藩において高位の者であるが、自分たちでも掌握できない方向へ、水戸浪士の激派は舵を切ろうとしているのではないか。
このままでは、藩のみならず日ノ本の在り方そのものを割り、民らの疲弊を招きかねない。
そんな鳴海の不安を読み取ったのだろうか。平八郎が、不意に濡れ縁から立ち上がった。何かを決意したかのようでもある。
「――守山藩としては、如何されるおつもりです?平八郎殿」
今までのような揶揄や皮肉ではなく、鳴海は真剣な面持ちで平八郎を見上げた。
「事と次第によっては、拙者が松川表まで出向いて藩色を鎮めまする」
その言葉の意味について、鳴海はしばし考えねばならなかった。つまり、この男は自ら松川表まで出向き、目と鼻の先にいる水戸藩の有象無象との折衝も行いつつ、激派の動きを抑える側に回ろうということか。
「それが上に立つ者の役目でござろう?二本松藩番頭の大谷鳴海殿」
そう言い切る平八郎の口元には、微かに笑みが浮かんでいた。
ふっと、鳴海の口元にも笑みが浮かんだ。恐らく、番頭の座に就いたばかりの自分であっても、平八郎と同じ選択をするだろう。鳴海は初めて、この男に対して好意を覚えた。もっとも、この男が尊攘派の一員であり、横浜鎖港の件については決して理解し合えないであろうことは、口惜しいが。
「左様でございますな、守山藩御目付の三浦平八郎殿」
鳴海の穏やかな口ぶりに、平八郎も目元を和らげた。親しげに談笑している二人の姿が余程意外なのか、権太左衛門がじっとこちらを見ている。それに肯き返すと、鳴海も腰を上げた。訊くべきことは、これで概ね聞き終えた。
「守山御家中の逗留の件は、『お構いなし』と地方にも報告致す。だが、万が一嶽で御一同が妙な動きを見せたら、直ちに拙者の手の者や他の組の者が動くことになろう。それで宜しいな?」
鳴海が下した判断は、至極穏やかなものである。鳴海の宣言を聞きつけた鎗三郎や高野、小林らが顔を歪めた。上役同士の間で、何か協定が結ばれたと気付いたらしい。あの様子であれば、やはり彼らなりに何か思惑があってこの地に来ていたのだろう。だが、鳴海はそれに気付かぬ振りをした。その緊迫した気配に気付かずに間抜けな顔を晒しているのは、元々背中の腫物の治療に来ていたという球三郎だけあでった。
「ご叡慮痛み入る、大谷鳴海殿」
深々と三浦平八郎が腰を折った。渋々、他の守山藩士もそれに倣う。そして一歩二歩鳴海に歩み寄ったかと思うと、平八郎は鳴海の耳元で「今までの数々の御無礼、誠に申し訳なかった」と呟いた。その声を聞いたのは、鳴海だけだったろう。平八郎の立場を慮り、鳴海も「過ぎたことでございますれば」と小声で囁き返した。
>嶽の出湯(5)へ続く
文/©k.maru027.2023.2024
イラスト/©紫乃森統子.2023.2024(敬称略)
これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。
