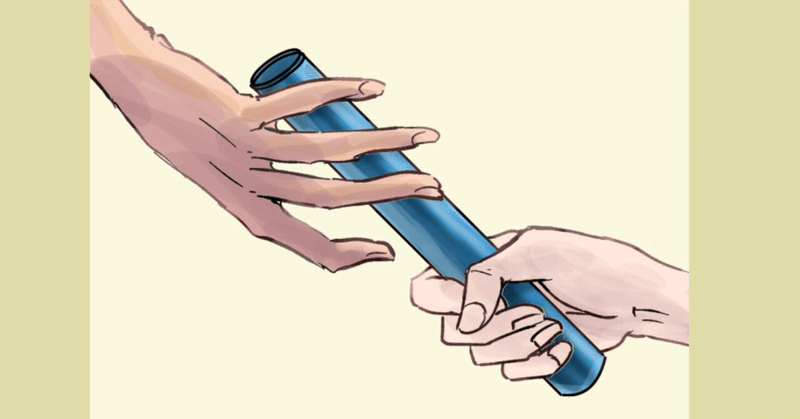
私の主張を支持する皆さんへのお願い
おかげさまで、私のnoteもフォロワーが100人を突破しました。今回はそれを機に、特に私の主張を支持・共感する方々に向けて、申し上げたいことがあります。
その灯を、絶やしてはいけない
「反フェミニズム」の中でも、このような立場から批判する勢力はまだまだ盤石ではありません。ちょっとしたパワーバランスの変化で一気に潰されるリスクは、常にあります。だからこそ、この理論・言説は誰かが語り継ぎ、絶やさないようにしなければならないのです。
先に私はこのような記事を書きましたが、本当にこの言論の世界は、一人いなくなるだけでも大きな損失です。茂澄氏に何があったかは分かりませんが、(凍結ではなく自主削除ということから)以下の見立てもあるようです。
茂澄遙人さんが垢消ししたの、ループに飽きたとかじゃなくて数々の発言の結果生活に支障が出た系でしょう。でなきゃ別に更新せずに放置して生活に専念しておけばいいだけの話だし……
— Dormeur (@nemuribito) April 6, 2023
先人の言葉を語り継ぎ、絶やさないようにする。その重要性は頭では分かっていても、実践するとしたら全く簡単なことではありません。もしかしたら(こうした見立てのように)精神的なダメージ、「傷つき」も多く背負うことになるでしょう。しかし、その重要性は今一度、皆さんにも訴えなければなりません。
こんなこと、本当はやりたくない
正直言いますと、私もこんな形、こんな立場での意見発信はやりたくないです。何度も他者(フェミ側)の反応に傷ついてきました。何度もやめたいと思ってきました。しかし、それでも、やらないわけにはいかない、言わないわけにはいかないと自分に言い聞かせて、今まで記事を書いてきました。
なぜなら、誰もやらないからです。誰もこの立場から、この視点から意見を発信しないからです。
特にこれらの記事のように反フェミニズムの「流れ」を、体系立ててまとめた人が他にいたでしょうか。その流れの中で「伝統保守・復古主義」ないしは「女をあてがえ論」の不誠実さ、問題の解決に何ら寄与しないことを語れた人がいたでしょうか。
小山狂人は確かにそれに限りなく近いことをやってきたと言えるかもしれません。しかし彼も「あてがえ論」を支持する立場である以上、完全に信用できる論客ではありません。
いわば「誰に投票しても同じなら、自分が立候補するしかない」と同じ心理です。自分が動かなければ、同じ境遇にいるであろう人々の中の、誰も立ち上がらない。だからこそ、やめるわけにはいかなかったのです。
我々は盤石ではない。しかし何故?
先にも言った通り、我々のような「伝統主義の復古を支持しない反フェミニズム」というのは、盤石な勢力ではありません。しかし、なぜなのでしょうか。ここからはその理由を深めていきましょう。
私は事あるごとに、「フェミニズムの『ただしさ』は『政治的ただしさ』が保証しているわけではない」と言ってきました。では何がその「ただしさ」を保証しているのか。それについても私は「『共同体の子産み要員であること』そのものである」と言ってきました。
皆さんは、10世紀から13世紀にかけての西欧で発生した「カタリ派」という宗教をご存知でしょうか。その特徴的な教義の一つに、出家者の生殖の完全な禁止がありました。当然カトリック教会は彼らの存在を問題視し、十字軍の出動によって彼らは滅ぼされました。その後の文献ではカタリ派は完全に否定的な文脈でしか登場しないことになります。
最近小山氏は「マルクスの階級闘争史観を男と女に当てはめただけのフェミニズム史観」を否定的に検証する連載を始めましたが、そもそもなぜこのような史観が200年も続いたのでしょうか。確かに言論界やアカデミアで一定の勢力を持ったということはあるかもしれませんが、それ以前に「母から娘・息子へその史観を引き継いできた」からではないでしょうか。
戦前日本において、女子が行けた最高学府は、女子高等師範学校でした。現在でも残っている2つの「国立の女子大学」はどちらも女子高等師範学校がルーツにあります。当然ながらこれは教員養成のための機関です。つまり教育政策的にも、当時から女性には(男性と同じことをすることは性質的に不可能と考えられていたにも関わらず)教員としてふさわしい性質があると考えられていたわけです。
また一般的に皆婚社会は夫を稼得能力に、妻を出産育児能力に全振りさせることで成り立ってきました。「女性の社会進出・性役割分業の解体」を是とするフェミニズム政策が同時に「男性の育児参加」も推進しているのはこのためですが、見方を変えれば妻(子供から見れば母)こそその信念を子供たちに引き継げやすかったと言えます。
反フェミニズム言論の最大の弱点は、その「継承可能性のなさ」にあります。伝統主義の復古も、「次世代再生産」という視点で見るならば、現状「最も正しい戦略」となっていることは否定できないのです。
早速ミグタウの歴史を解説していきたいのだが、実はミグタウの歴史を体系だって説明する事は不可能である。というのも、彼等は古今東西あらゆる偉人が残した「女性とは関わるべきではない」という思想・言葉を漁り、それをミグタウの起源として主張しているのだ。恐らく最古の起源は仏陀の「夫為女人有九悪法。云何為九。一者女人臭穢不浄。二者女人悪口。三者女人無反復。四者女人嫉妬。五者女人慳嫉。六者女人多喜遊行。七者女人多瞋恚。八者女人多妄語。九者女人所言軽挙」辺りになるのだろうが、これをもってミグタウとは表現出来ないだろう。しかしながらミグタウが体系だって説明出来ないのは、その性質上「絶対に次代を生まず継承されない」特徴があるので仕方ないと言えば仕方ないことでもある。これに関して彼等は「ミグタウは人間社会において消える事のない火であり、近年それにフェミニズムがガソリンをかけて燃え広がった」と主張している。
だからこそ、とりわけ「伝統主義に与せない反フェミニズム言論」では、継承する人材の存在が、とてもとても重要なのです。特にインターネットには、様々な言論のためのサービスが現れては消えを繰り返しています。その存在を覚えている人の数は、当然その言論のアクセス数ないしは高評価数に比例するでしょう。しかしそれでいいのでしょうか?
御田寺圭氏の活動は、昨年サービスを終了したBLOGOSというサイトから始まっていました。その最後に書かれた記事を読んでみましょう。
ネット空間から「記録」が失われてしまえば、私たちは「いま」にしか関心を持てなくなる。その時その時の「ただしさ」に脊髄反射的に反応し、言葉を消費していく世界がすぐそこまでやってきている。紙媒体が主流だった時代から活躍していた――「いまだけのただしさ」を言いっぱなしするような風潮に抗っていた――はずの言論人でさえ、SNSのコミュニケーションに最適化された「“いま”流行している正義」をためらいなく語るようになってきている。
だれもがフラットにつながる「記録係のいない世界」のなかで、一気に盛り上がる感情のうねりだけが支配していく。BLOGOSはそれに一貫して逆らっていた。新着記事はSNSで一瞬だけ言及されて、話題の肴にされることもあった。記事がSNSで話題になったことはだれも覚えていないが、しかしその記事は残っていた。それにこそ、このサイトの意義があった。
SNSの時代においては「だれが言ったかではなく、なにを言ったかが重要になる」と言われていた。だがこの時代においてもっとも大切なのは「なにを言ったかではなく、なにが記録として残されるか」だ。
思えば久米泰介氏がアカデミアを志したのも、論文や書籍なら主張を長期的に保持しやすい、後世の人が参照しやすい、そういう期待があったからでした。
今はネットメディアなどで、マスキュリズムに近い思想やフェミニズム批判をしている人も、尊敬に値する一方、10年後にではそれらの研究・論考が形として残っているかは怪しい。ネットの文章などすぐに消えてしまう。
そして今やもう、御田寺圭氏の初代ブログも、久米泰介氏公式サイトも、本物は残っていません(まあ御田寺氏の記事はサイト閉鎖に因んで書かれたものではあるので当然ではあるのですが)。
皆さんへのお願い
私が「フォロー」するべきと考える基準の一つには、「反フェミニズム/反女性たる自分の経験や感覚、持論などを記事として書いているか」があります。そういう人が増えないと意味がないからです。記事さえ書いてくれれば、全力で応援したいのに、そんな風に私が思うフォロワーやコメントしてくれた方も少なからずいます。
そして上に合致したすばらしい記事を著した方々にも、後にアカウントを消してしまった方も少なくありません。中には既に他界したという連絡のあった方もいます。
皆さんへのお願い、それは言葉で言うならとてもシンプルなものです。
語り継いでほしい。私の主張を、先人たちの主張を、そしてあなたの経験と感覚を。私の後ろに続いてほしい。それだけです。
その道がどれだけ茨の道かは、私自身もよくわかっています。それでも、お願いしなければなりません。私はこのnoteを自主的に消す予定も意思もありませんが、他者からの圧力で消される可能性は常にあります。そして消えた時点で、「語り継ぐ」責務が、皆さん一人一人に発生するのです。
「私たちにはことばが必要だ」
これは韓国フェミニズム運動のスローガンの一つとして使用されたフレーズですが、我々にこそ言葉が必要です。それは皆さんにもとても困難なことやもしれませんが、いずれは皆さんの中の、誰かがやらなければいけないんです。我々の立場を、後世に残すためにはね。
