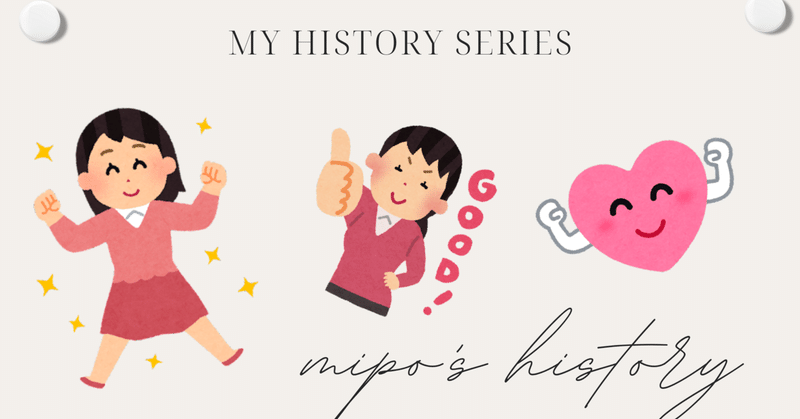
自分語り~Mさんの場合~
「自分語り」って聞いたことあります?
意外とね、「自分のことを語る」っていうとあまりいいイメージないのかな?とも思うんです。「ナルシスとか?」みたいな。
ここでいう「自分語り」は自分の歴史を語る場。
ライフステージごとのイベントや考えたことを15分ほどでアウトプットします。これ、出来れば周囲の方と一度やってみてほしい。
「この出来事でもこういう考え方をしたんだ」とか「その出来事がそうつながるの?」とか、自分では普通だと思っていることが人から見ると意外にびっくりするような思考だったり、自分の考え方にも気が付くいいアウトプット、インプットになります。
4月。
新しい出会いも多いこの時期に、お勧めのアウトプットとしてご紹介。
今日は私の友人、みぽさんの自分語りです。
自分語りの方法
オンラインオフライン問わず開催可能。
誰か一人が覚えてる限り古い記憶から話出し、15分ぐらいで現在までを語り終了。聴者は語りの後質問を投げかけてOK。深堀できます。
聴者は聞いた話をアウトプットすることで1ターン完成です。
今回お話を伺った「鋼のみぽ」さんとは。
そもそも、名前めっちゃ強そうやない?(笑)
これは私が最初に抱いた印象。
みぽさんもきっとそれも意識してネーミングつけられたのではないかと思います。面白い。「なぜその名前?」興味や会話を持つきっかけにもなりますよね♪名づけ大事だなとおもいます。
そんなみぽさんは私の大切な友人であり、いつでも優しく話を聞いてくれるお姉さん的存在です。
そんなみぽさんの幼少期。
みぽさんは大阪出身。帽子屋さんのご両親、弟さんと二人姉弟。
大阪城の近所に生まれたそうです。
在宅でのお仕事だったためご両親がずっとおうちにいる環境だったけど忙しかったのでなかなかかまってもらえなかった、っていうのはなんとなく想像出来ました。
みぽさんの一番小さなころの思い出として紹介されたのがこちら。
いつか分からないけど私はベランダでゆりかごに乗ってた気がする。
どういう状況?(笑)
現実かどうかはさておき、ご両親のお仕事が「忙しい」というみぽさんの印象がその記憶を残したのかもしれません。
そんなみぽさんの幼稚園時代。
①牛乳が嫌い。
みぽさんは牛乳が嫌い。でも幼稚園ではストーブの上で(良かれと思って)牛乳を温めて飲む習慣があった。牛乳って温めると生臭いにおいがより強くなる。そこでみぽさん家が考えたのが
粉のコーヒーを瓶に入れて持参し、牛乳に混ぜる。
なるほど、瓶か。幼稚園の時にコーヒー牛乳が飲めたのは「大人だな」と思ったけど、味変はいいアイデアですね!多分うちの家では「出されたものはそのまま頂け」と言われるような気がするので、おうちごとの考え方の違いがまた面白い。
②受験したくない。
どうにも教育熱心ではなかったご両親(本人談)なのに、ご両親の希望で近くの付属小学校への受験をすることに。でもみぽさんは当時受験なんて全く興味がなかった。ずいぶん抵抗はしたけど受験。
でも順調には進まなくて結局地元の小学校へ。
「自分の意見」ははっきり言う子だというのは、その後の小学校の生活からもわかってきます。
みぽさんの小学校時代
その頃流行った「リカちゃん人形」は髪の毛ボサボサ。勝手にはさみいれて髪の毛切ったり(笑)。
一緒に遊んだ子の態度が悪かった場合、意見したくて追いかけるみぽさん。相手は逃げまくり自宅に逃亡。そうなると諦めるのが大半かと思うけど、みぽさんはピンポン押してお母さんにご連絡。
「言いたいことは言わないと気が済まない時期」だったそう。
でも私は「しっかりした子だな」という印象を受けました。
「男勝り」を地で行ってたような子だったのかな。
そこまでではないけど、私も似たようなタイプだったかも😅

そして、中学→高校→大学へと進む。
中学では水泳部。勉強ができたのでそのままいい高校に行ったがために「それなりに」どうになかなるだろうと、あまり勉強をしなかった高校時代。
(わかるわぁ・・・・私も同じ経験をした苦い思い出が)
結果大学は思ったようなところに行けなかった。でも大学ではPCソフトのインストラクター資格を取り、その結果「ソフトウエアの会社に行きたい!」と将来の方向性も決まっていきました。
いよいよ就職!
そんなみぽさん、願いが叶い電子機器の会社に就職します。
最初は部品納品管理業務をしていたけど、どうもしっくりこず異動を願い出ます。その先は「営業」。
上司の推薦もあり意外とすんなり営業に異動。
しばらくして、関東に転勤。
その頃から、あまたある商品の中で「どれでもいい部品」から「うちでないと提供できない部品」への試行錯誤が始まります。
みぽさんらしいなと思ったのが、考え方の転換方法。
踏襲しておけばある程度の売り上げは上がるという考え方もある中で「いや、選んでもらうために自社のオリジナリティを出していきたい」と社内外各箇所を回りコミュニケーションを取りながら、商品を開発。不具合を出しながらも現況からの脱却を試みたのです。
その中で得られたのは「試行錯誤でもメンバーとの関係性が濃くなる」ということだと、みぽさんは話してくれました。
「くそがっ!」と思えることもたくさんあっただろうなと想像するけど、それより得られたものに焦点があたるあたり、学びたい姿勢だと感じました。
供給難
みぽさんが自分語りの中で初めて「数字」を出したのが、この供給難のころの話の中。
2016年、関わっている商品の部品がなかなか入ってこなくなり、いつも以上に商品の提供が出来なくなる。さらに、同僚が心の病で戦線離脱。その仕事もみぽさんが引き受けることに。
みぽさんは「悪いことって重なって起きるもんだなと思った」と当時を振り返っていましたが、それが2年も続いたと聞いて、忍耐強い人だなと感心しました。
でもここでみぽ節炸裂。
自分にとって逆境が続く状態を「これを乗り切ればスーパーサイヤ人になれるかも!」と考えていたそう。
みぽさんとお話をするといつも元気をいただきますが、それはたくさんの苦労と思考の上に成り立っているんだなと考えさせられました。
社内研修
ある日、社内研修で「共創活動」に触れます。
「共創」という言葉は英語の「co-creation」の日本語訳で、2004年に米国ミシガン大学ビジネススクール教授のC.K.プラハラードとベンカト・ラマスワミが共著『価値共創の未来へー顧客と企業のCo-Creation』の中で述べた概念が始まりと言われています。
企業がそれまで自社内だけで行ってきた企画・開発・事業化活動などを消費者、協力企業、教育機関、研究機関、自治体など、さまざまなステークホルダーと対話・協業しながら進め、既存商品の改善や新しい商品・サービスの開発、さらには新しいビジネスモデルを生み出していくことを指します。最近では「オープンイノベーション」の要素を含んだ考え方として広義で使われるようになり、新規事業の開発においても共創を取り入れていく動きが広まっています。
「なるほど、自分の興味ある分野かもしれない」と。
これがみぽさんの突破口となります。
社内でも動きを見せていこうかと思った矢先「コロナ」時代がやってきました。
イベントはなくなり、社外の方とのコミュニケーションもすべて「オンライン」。
対面でのコミュニケーションも取れない中、どうやって「共創活動」を続けていけばいいのか・・・・みぽさんは悩みます。
そんな時ふと「コミュニティづくりの教科書(河原 あず (著), 藤田 祐司 (著))」に関するイベントに目が留まります。
それは当時オンラインになっていた朝活コミュニティ「朝渋」のイベント。
早速みぽさんも朝渋に参加します。そのコミュニティの中で定期的に行われていたこの「著者イベント」は、以前はオフラインで行われていたイベントだったのですが、コロナ下でオンラインイベントが続いていました。でも登壇される著者の方々はオンラインでも様々な試行錯誤を行い、コミュニケーションのノウハウが沢山詰まったイベントを次々と開催されていったのです。みぽさんも「オンラインでもコミュニケーションは取れる!」ということを学ぶきっかけに。
さらに、朝渋内での自己を深堀する様々な活動の中で、みぽさんも「自分の強み」をどんどん発見していくことに。
「オセロが変わるようにどんどん変わっていった」
というのが当時を語ったみぽさんの印象的な言葉。
2021年、会社の組織が変わり「共創活動」に専念できる環境がどんどん整っていきました
そして今。
そんなみぽさんは、この春から大学院生。
「共創活動」の中で出会った方のお勧めで仕事をしながら共創活動に関する研究を始められることになりました。
「周りが神輿を作ってくれるので私は乗るだけ~♪♪」
とみぽさんはよく話してくれるのですが、「神輿」を見つけるのも「乗ろう!」と思いきれるのも、みぽさんの才能ではないでしょうか。
さらっと春風みたいに新しいことにどんどんトライするみぽさん。
今後がますます楽しみです☆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お話を伺って、今のみぽさんがどう成り立ったのかがわかり、ここまで来る中での様々な苦労とみぽさんの「前向き」才能とが掛け合わされ、新しい概念がどんどん生み出されてるんだなと感じました。
考えさせられるお話がいっぱい!
人生って改めて、唯一無二ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
