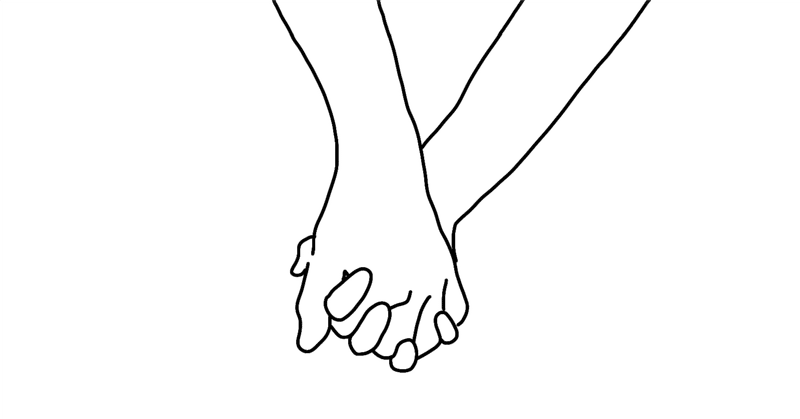
子育てには物理的な助けだけじゃなく、「共感」が必要というはなし
「子供産まれてから何かおかしいよ」
夫からこの言葉を投げつけられたとき、私は頭を鈍器で殴られたような感覚に陥った。自覚はある、こんな些細なことで声をあげなくてもいいと。それでも、「どうして分かってくれないのだろう」という気持ちが強くて、胸の底から湧いてくる不安や不満を、当時の私は抑えることができなかった。
初めての出産は、促進剤を入れてもなかなか陣痛が始まらない難産だった。丸2日眠れない状態で母子同室がスタートしたため、血圧が爆上がりしてしまい、母乳も軌道にのらないまま退院。だけど赤ちゃんは待ってくれない。自分の体とは思えないようなどうにも動かない体で、髪を振り乱しながら授乳をしていた。
里帰り出産を選んだのは、高齢出産だったことと、産後に私自身の手術が控えていたからだった。とはいえ、現役で働く両親は早朝には家を出て帰りも遅い。里帰り出産とはいえ、ほぼワンオペに近かった。
私は、親と言えども「適度な距離感は大切」だと考えていた。それぞれの家庭のリズムがあるし、親子ゆえの甘えから衝突してしまうこともある。私の手術が無事に終わったことから、予定より早く実家を離れ、夫が待つ真冬の北海道に戻ることにした。

その矢先、冒頭の夫の言葉。きっかけは、5ヶ月になった娘がミルクをどうしても飲まないことだった。哺乳瓶の乳首の形状を変えたり、ミルクの味を変えたりと試みるが、口に含んではすぐに加えるのをやめてしまう。同年齢の赤ちゃんに推奨される量のミルクの半分も飲んでくれない。
朝一番の100mlのミルクをあげるために、娘の機嫌をとりながら奮闘する毎日。スプーンで1杯ずつミルクを運びながら、ようやく50mlなくなるみたいなこともしょっちゅうだった。「ミルク 飲まない」で検索したことを一通り試し助産師に相談するも、有効な改善策はないまま、結局1人で抱え込むしかなかった。
そんな状態が1〜2ヶ月続き、娘の体重が増えなくなったとき、とうとう私も限界を迎えた。夫に、すべての不満をヒステリックに吐き出したのだ。夫も、それまでに見たことのない形相で捲し立てる私を見て、びっくりしていた。
夫は育児や家事には積極的に参加してくれていた方だと思う。しかし、ミルクを飲ませて寝かしつけをさせる担当は私だった。それは夫が私より早く出勤し、帰宅時間も遅いから。フリーランスで比較的時間に都合のつく私が「やるしかない」とずっと言い聞かせていた。
「じゃあミルクは僕が担当するよ」と夫が提案してくれた。有り難かったけれど、現実的ではないし、私の中のモヤモヤはそれでは解決しない気がした。たぶん私の中では、「誰がやるか」よりも、「分かちあえるかどうか」が大切だったんだと思う。
娘がミルクを飲まない状況を自分ごととして捉え、悩みを共有し、何ができるかを一緒に考える。それが私が望んでいたことだった。夫は、もしかしたら娘の様子を見て心配していたのかもしれない。けれど、私には夫の心の中を知ることはできなかった。
夫は静かに私の話を聞いてくれた。そして、私たちは、夫の知り合いの小児科医に相談することにした。娘がミルクを拒否する理由は分からないままだったが、幸いにも離乳食は少しずつ食べれるようになっていたので、離乳食を早めに進めれば問題ないとアドバイスをもらい、少しだけ心が軽くなった気がした。
今考えると、もっと気長におおらかに構えていても良かったのかもしれないとも思う。けれど、成長に直結する「食」に関係する問題だったがために、「解決しなくては」というプレッシャーが大きかった。そして、その思いを理解してもらえない孤独が、物理的な子育ての大変さ以上に苦しかった。
夫は、会社が導入した「フレックスタイム制」を導入したタイミングで、朝の授乳を手伝ってくれるようになった。

そしてこの件以来、私たちは子供が産まれる前以上に、「お互いの気持ちを伝えること」を大切にするようになった。子供が寝てから、5分でもいいから自分達が考えていることを吐き出してみる。
夫婦の会話を習慣づけてから分かったことは、夫も私には見えない不安や不満を抱えていたということ。私たちが「見ていたもの」は、それを構成するほんの一部でしかなかった。
初めての子育ては、私にとっても夫にとっても未知の世界で、正解も不正解もない。夫婦2人で一つの命を支えるためには、これまで以上に相手を気遣い、お互いの考えや想いを素直に伝え合うことが大切なのかもしれない。
今娘は1歳1ヶ月を迎え、もうすぐミルクを卒業しようとしている。ミルク問題は解決したが、成長するごとに新たな悩みが生まれ、子育ての不安は尽きることはない。それでも私たちは、夫婦で支え合いながら1日1日を生きている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
