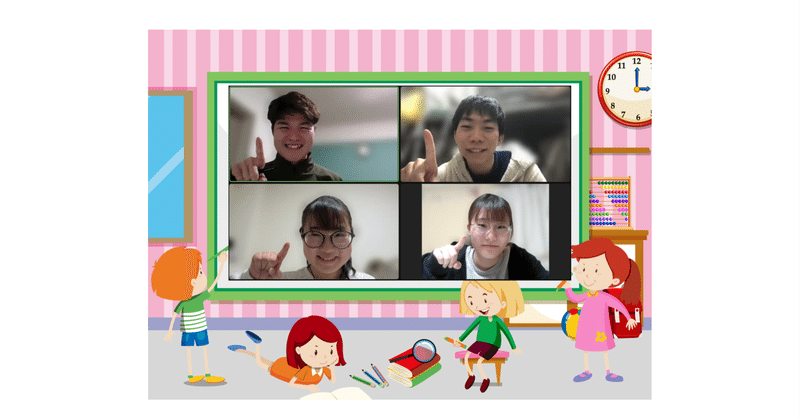
てらす実習生 活動報告
2月13日(火)にてらす実習生で勉強会を行いました。この勉強会では、中野先生の「想像力のスイッチを入れよう」の授業動画を各自で見てきて、その内容について議論をしました。各自で見てきて考えたこと、疑問に思ったことを共有し、その後に「指導技術」と「教材づくり」の2つの面から気づいたことを議論しました。
実習生で議論した、中野先生の「指導技術」
主に以下のような気づきが実習生から出てきました。
・児童を主語にした問いを出すことによって、自由な解釈ができるようになったり、自分を当事者と考えて言語化していくことができるようになったりしていた。
・先生の立ち位置について、半身で子どもを見ながら板書をしていたり、教室を動き回っていたりしていた。黒板の前にいるのは、板書したり、掲示物を出したりしたいるときだけで、それにより、どこで黒板に集中するべきなのかがわかりやすいと感じた。
・児童の発言を価値づけてたり、聞いている児童の理解がおいついているかを見て発言を止めたりするなど、児童が積極的に発言をしやすい環境をつくっていた。
・黒板に教材文を掲示することによって、指差しが可能になり、授業についていけていない児童も今どこの話をしているのかを理解しやすい。 授業内容だけではなく、児童への言葉がけや教師の立ち位置、黒板の使い方など、本当にたくさんの工夫や配慮があるからこそ、児童が積極的に学ぼうとする姿が見られるようになるのだと学びました。その中でも、児童がつぶやいたり、気づきを発言したりできるような土台を普段の生活や授業の中での言葉がけでつくられていることが児童主体の授業には大事なことなのだと感じたことが心に残りました。中野先生の解説の中で、「この子はこういう子だからこうした」といった趣旨の発言があったり、前で話した児童に対して「一生懸命話した〇〇さんもすごいし、一生懸命聞こうとしたみんなもすごい」といった発言があったりして、そのような一つひとつの児童への価値づけや理解が児童の話したいという思いや話しても大丈夫なんだという安心感を生じさせているのだと思いました。授業を「点」で見るのではなく、学級経営や他の授業といった、日々の生活と「重ね合わせて」見ることが大事だと感じたので、教員になったときに大事にしていきたいです。
実習生で議論した、中野先生の「教材づくり」
主に以下のような気づきが実習生から出てきました。
・現行の教科書の文章と1つ前の教科書の文章を比較するという教材づくりが、面白く、一人では学べない勉強のしかただと感じた。
・「読むこと」と「書くこと」を繋いだ教材づくりがなされており、言語活動とのつながりがあって、目的意識をもって取り組むことができる。 中野先生の実践されていた授業で児童が主体的に文章に向き合っていたのが印象的でしたが、その背景には、様々な工夫が凝らされた教材づくりがあったからなのだと感じました。特に、最後の「書くこと」言語活動に繋がった、児童が目の前の教材文に向き合う目的意識を明確に持つことができる教材をつくられていたことが印象に残っています。なぜなら、大学の国語科の講義で「説明文は意図的に作られたものだから読んでいても面白くない。だからこそ、児童が説明文を読みたいと思えるしかけを教師がつくらないといけない」と教わったことと重なっていたからです。大学の座学で学んだこと(理論)と実践が「線」でつながり、大学での学びがさらに深まったように感じました。最後の言語活動に向けて、教材文から学びたい、読みたいと児童が思えていたことが、児童が教材文を読み込み、自分の考えや気づきを持とうとしていた授業につながっていたのだと思いました。
実習生どうしで学ぶことの素晴らしさ
私は、今回はじめて実習生の勉強会に参加しましたが、ここに書いたこと以外にも非常にたくさんのことを学び吸収することができました。昨年の11月に授業てらすに入ってから、普段はサークルやアルバイトでセミナーなどにリアルタイムで参加することはできておらず、時間のあるときにアーカイブの動画を見て学ぶことしかできていませんでした。もちろん、それでもプロの先生の授業実践やお話から大学だけでは学ぶことのできない学びを得ることができていたのですが、今回、実習生どうしでアーカイブの動画を見て議論しあうことで、いつも以上に学びを深めることができたように思います。それは、自分一人では気づくことのできない気づきをすることができたり、自分にはなかった視点で授業を見ることができたりしたからです。新たな視点を多く得ることができて、視野が広がったように思いました。
また、学年も大学1年生から大学院2年生まで、大学も東は茨城から西は鹿児島まで、普段の生活では関わることのできない学生どうしで議論しあうことができたこともすごく貴重な時間になりました。議論の中では、それぞれが大学の講義で学んだことやサークル活動で実践していることなどと結びつけた発言をしたりしていて、大学に通う実習生ならではの視点や論点で話すことができたこともこの勉強会の良さだったように思います。全国の同じ志を持つ仲間と一緒に学べることは素晴らしいことだと改めて実感することができました。
おわりに
1時間程度の勉強会ではありましたが、将来、教壇に立つ日に向けた財産になりました。また、このインプットした学びを、将来、現場に出たときにアウトプットできるようにこれからもみんなで学び続けたいなという気持ちも高まりました。
今後も実習生どうしで、将来に向けて学びを深めていけるよう頑張っていきたいです!
(授業てらす実習生 はすみん)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
