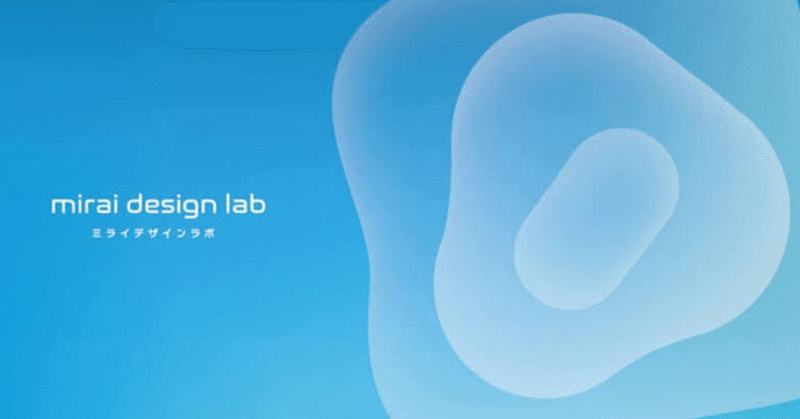
未来洞察×人類学へのチャレンジ①
こんにちは、あわたです。
今回は、「フォーサイター宣言」で紹介した「Futures Literacy:フューチャーズリテラシー=自分の頭で未来を洞察・想像し、実現していく態度やスキル」を有するフォーサイターが、同時に養うべき態度やスキルのヒントは「人類学」にありそうだ、というお話です。(人類学にもいろいろありますが、ここでは主に文化人類学を指しています)。
未来洞察と人類学。一見何の関係もなさそうなキーワードが2つ並んだように見えるかもしれませんが、私の中では密接につながっているライフワークのようなテーマなので、2回に分けて紹介させてください。実は未来洞察よりも先に、マーケティングリサーチを通じて人類学に触れていたので、1回目は人類学についてお話しします。
1.人類学は生活者を色眼鏡で見ずに理解するもの?
そもそも私は前職の広告会社でマーケッターの仕事をしていました。さまざまなマーケティングリサーチの方法を学び実践しましたが、特に興味を覚えたのは仮説検証型の量的調査ではなく仮説発見型の質的調査でした。グループインタビューや観察調査などですね。
当時の広告会社では「マーケティングエンジニアリング企業」というスローガンを掲げると同時に、「生活者発想」というコンセプトを提唱していました。これは欧米から輸入してきたマーケティングリサーチが「人間を消費者としてのみ見がち」であることを補正し、 生活者としてまるごと理解しようとするものでした。
つまり、広告表現のコンセプトを決めるために商品を店頭で手に取ってもらう理由やきっかけだけ知ればよいというものではなく、ある商品を人々が生活の中で使うことの意味や背景まで探るようなマーケティングリサーチです。
さらに、それ以上に惹かれた のが、調査結果やそこで思いついたアイデアを統合的かつ質的に分析する方法としてのKJ法でした。( KJ法は入社前研修で最初に習いました)。
KJ法は文化人類学者である川喜田二郎さんが発明した「発想法」で、フィールドワークを通じて得られた「断片的な事象や気づきを発展的にまとめる方法」です。自前の仮説に基づく分類整理ではないゆえに経験を積まないと会得しにくい方法ではありますが、ハッとさせられる瞬間が訪れるまで洞察と発想を行ったり来たりするプロセスは楽しいものでした。
こうした経験から、人類学的な方法やものの見方は
「必ずしも合理的には説明しきれない人間の行動を、その社会的背景から深く理解し」、
同時に
「自身の偏ったものの見方を補正していく」
ものとして実践的に理解するようになりました。
2.ポケベルと需要側イノベーション
こうした人類学的な考え方をマーケッターとして最も生かせた仕事が「ポケベルのプライベートユース開拓(1987~1993年)」でした。
携帯電話が一般開放される1995年以前の話なのでポケベル自体を知らない方も多いと思いますが、正式名ポケットベルは海外ではページャーと言われ、医者や弁護士、機械点検など緊急対応しなければいけない人々を「呼び出す」道具でした。
当時国内500万台ほどだったポケベル市場を大きくしたいとクライアントに言われ、どうしたら市場を大きくできるのか、海外動向も含めて情報を収集しましたが、一番興味を惹かれたのが
「渋谷センター街のチーマーと言われる人々が仲間を呼ぶのにポケベルを使っている」という事象でした。
つまり、携帯電話が普及する以前の時代において、
「仲間とつながる」道具としてポケベルを利用していたことになります。
この想定外な利用方法を未来の兆しと捉え、
より一般化すればプライベートユース市場を開拓できるのではないか?ということを思いついたわけです。
結果として、ポケベルは女子高校生のおしゃべりの道具として普及し市場は1300万台まで伸長したわけですが、この過程で毎週のように女子高校生グループインタビューを行い、街頭に立ってどのように利用しているかを観察しながら、
「親に長電話を抑止されていた彼女たちにとっては『ポケベル=私の電話』と位置づけられている」ことに気づいた(aha体験)からこその取り組みでした。
この際に、スウェーデンの消費者研究者から
「ポケベルの女子高校生利用は需要側イノベーションだよ」
と教えられました。
イノベーションというのはかつて技術革新と訳されたように先端技術(供給側)起点であることが多いですが、同時に「ユーザーによる想定外な利用」など需要側を起点としたイノベーションも少なくありません(例:火薬の包材でサンドイッチを包んでみたことでサランラップが生まれた)。
つまり、ポケベルの「女子高校生のおしゃべりの道具」という想定外利用のアイデアを普及させた仕事は、この需要側イノベーションを無意識に実践していたことになるわけです。
ただ、ある技術者からは
「女子高校生のおしゃべりのために希少な電波資源を使わせるつもりはなかった」と嫌味を言われましたが。笑
3.人類学をビジネスに利用する とは?
話を現在に戻して、欧米では企業のイノベーションやトランスフォーメーションにおいて人類学者が活躍するシーンが増えていると聞きます。
米国インテル社が文化人類学者をR&Dのラボに採用した例が有名ですね。
また、ビッグデータ活用を補完・補正するための人間的洞察を民俗学者がリードした例もあります。
先のポケベルの需要側イノベーションは「想定外利用」に着目した事例ですが、そうした消費財に限らず人類学者や民族学者が企業において活躍するとはどういうことでしょう?
需要側を消費者としてではなく生活者、そしてある社会の中に生きる一人の人間として洞察することで、
企業が見過ごしていたことを拾い集め、
企業が当たり前と思っていた事業・経営のあり方を覆すような事実を浮かび上がらせることができる。
人類学的な視点や方法を持った人が企業で活躍するとはそんな感じかなと思うと、人間を洞察することと未来を洞察することとには類似点がありそうにも思えますよね?
次回はその辺りについて、書いてみたいと思います。
(つづく)
この記事を書いた人 あわた
博多出身のモラトリアム世代。職業は旅人と言ってみたいが、英語と酒が苦手なのが玉に傷。
関心…自転車散歩/珈琲野点/里山/アウトフィッター/EDC/写真/路上観察/水平思考
→こんな記事も書いています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
