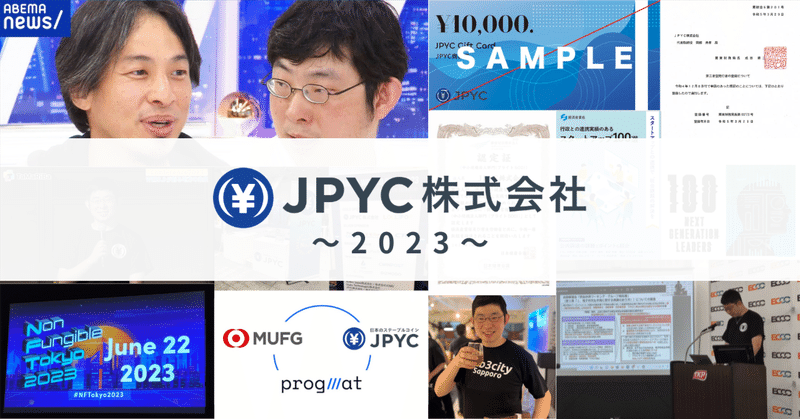
JPYCに全力を注いだ2023年の総括と2024年の展望をお話しします。
2023年は、ステーブルコインJPYCにとって非常に重要となる1年でした。
今年は多くのイベント出展や登壇、様々なメディアに注目されるなど印象深い一年になりました。これらの機会はweb3業界だけでなく、一般の方々からも大きな関心を集める大変良い機会になったと感じています。
他にも、第三者型前払式支払手段のライセンス取得をはじめ、農林水産省主催のビジネスコンテスト「INACOME」での特別賞の受賞、健康経営優良法人2023(中小規模法人部門(ブライト500))の認定や、行政と連携実績のあるスタートアップ100選に選ばれるなど、様々な方面で大きくJPYCが成長した機会でもあります。

さらにこの一年で、JPYC株式会社のステーブルコイン市場における今後の見通しを明確にすることができたと感じています。
今回のNoteではこの一年振り返りと今後の挑戦についてお話ししたいと思います。
2023年振り返り①:JPYC累計発行額24億円突破
2021年の1月にステーブルコインJPYCを発行して以来、Polygon・Ethereum・Astar・Avalanche…とマルチチェーンに対応しつつ順調に発行額を伸ばしてきましたが、今年8月にJPYCの累計発行額が20億円を突破いたしました。11月には24億円を突破しており、多くのJPYC利用者のおかげでここまで来れたと感じています。現在、国内の日本円ステーブルコインのシェアを99%以上を取っていますが、さらに2024年にも発行予定の電子決済手段のステーブルコインや加盟店での支払いが可能なJPYC Payなどでユーザーのニーズに応えていき、5年後には4兆円以上の流通を目指しています。
2023年振り返り②:信託型ステーブルコインJPYC /三菱UFJ信託銀行とProgmatとの共同検討
日本を代表する金融機関等が出資するProgmat社と、信託型ステーブルコインの実務を担当する三菱UFJ信託銀行との共同検討の発表は大きな話題になりました。Progmat社が開発を主導する「Progmat Coin」システムは、日本法上の各種スキームや、複数のパブリックチェーン(マルチチェーン)に対応する、ステーブルコイン発行・管理のプラットフォームです。スタートアップでありながらも金融業界での難しい挑戦をしているJPYCにとって、更なるイノベーションを起こす大きな一歩であったと思います。
この共同検討では、「Progmat Coin」のプラットフォームを介してパブリックブロックチェーン上でJPYC(信託型)を発行することと、JPYC社が新たに開設する予定のステーブルコイン交換サービスにおいて、今後増えるであろう「Progmat Coin」を活用した様々な”国産ステーブルコイン”を取り扱うことを発表しました。
三菱UFJ信託銀行とProgmatおよびJPYCの協業による、「JPYC(信託型)」および国内外ステーブルコイン間の交換に関する共同検討開始について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000054018.html
2023年振り返り③:資金移動業型ステーブルコインJPYC/ウニードスとの共同検討
JPYCではこれまで日本円に償還可能な資金移動業型ステーブルコインの発行を目指してきました。そして、すでに世界200カ国以上で資金送金サービスを提供しているウニードス社と、JPYC(資金移動業型)の新規発行を検討しています。
200を超える国と地域に海外送金サービス「Kyodai Remittance」を運営する株式会社ウニードスと業務提携に向けた共同検討を開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000054018.html
また、共同検討を進めると同時に、JPYC社では資金移動業のライセンス取得を目指しています。JPYCがこれまで目指してきた資金移動業型のステーブルコインは、すでに発行しているJPYC(前払式)と同様に、国際的なステーブルコインの規格であるUSDC Standard(旧Centre.io)に準拠いたします。USDC Standardはスマートコントラクトにより高度なAML/CFL機能が実装されているだけでなく、高い互換性と拡張性を持ち、マルチチェーンでの展開を可能としています。PolygonやAstar、Avalanchなど日本でも人気のチェーンを採用することで、送金における手数料を大幅に減らすことができます。また、今後上場する可能性のある取引所での利用はこちらのステーブルコインで目指していきます。
2023年振り返り④:JPYC商品券を利用したふるさと納税の開始
JPYCを用いた納税需要は以前からあり、2022年の段階でもVプリカギフトやgiftee Boxを経由して多くの方が納税にJPYCを利用されていました。JPYCで直接ふるさと納税を行うというチャレンジは2021年から行ってきましたが、2023年3月に第三者型前払式支払手段発行者としての登録を完了したことにより、今年からふるさと納税を開始することができました。関係各所と連携・相談しつつ、まずは紙型で行うことになりましたが今後は電子型にも対応していく予定です。ステーブルコインを用いたふるさと納税は国内初の取り組みであり、ステーブルコインでの地方創生など幅広い可能性があるとわかるユースケースになると思います。
JPYC商品券を用いたふるさと納税を開始。一般社団法人Disportと業務提携し徳島県海陽町で地方創生を推進します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000054018.html
また、第三者型前払支払手段の登録を完了したことでJPYC Payでの決済が利用可能となり、加盟店であればオンラインサービスだけでなく実店舗でもJPYCの決済が可能となります。これまで以上に便利な決済サービスを展開予定ですのでお楽しみにお待ちください。
今後のJPYCの挑戦
今年の6月に改正資金決済法が施行されてからステーブルコインの話題が増え、今後のJPYCのステーブルコイン事業の動きが明確になりました。これまで利用されているJPYC(前払式)とは別に、日本円に払い戻し可能なJPYC(電子決済手段)を来年に発行する予定です。
加えて、JPYCが国内外のステーブルコインを交換できる中心的な取引所として機能することも目指しています。JPYCを通して、国内の今後発行されていくであろうステーブルコインや、USDCなどの海外ステーブルコインを、自分で管理できる(アンホステッド)ウォレットで交換できる見込みです。

また、電子決済手段の信託型や資金移動業型、銀行型など発行形態の違いで、規制やスキームが異なる場合がありますが、その違いを感じさせないようなユーザー体験を大切にしていきます。状況によってステーブルコインのタイプ(信託型など)をユーザー判断で選ばないといけないのでは、ユーザビリティとして非常に大きな問題があると考えています。これは、サービス側で違いを意識させない設計や使い勝手にしていくことが、カツ!上で大事だと考えています。
電子決済手段は発行前に法律が整備され、会計や税制についても整理済という、まさに受け入れ準備万端な状態になり、この点が暗号資産の時とは大きく異なっています。ブロックチェーンが活用された金融インフラが国家レベルで整備が進んでいることは、業界にとっても非常に明るいと感じます。
JPYCにとって2024年は、ライセンスの取得、シリーズBの資金調達など複数の大きなマイルストーンがある非常に重要な1年です。「日本のステーブルコインならJPYC」であり続けるために、スタートアップでありながらも金融業界を攻めるステーブルコイン企業JPYCとして、日々挑戦し続け、日本のステーブルコイン業界をリードするサービス展開を行っていきます!
今年1年、多くの方にJPYCを利用していただき、大変ありがとうございました!
引き続き、2024年もJPYCをよろしくお願いいたします。
良い年末年始をお過ごしください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
