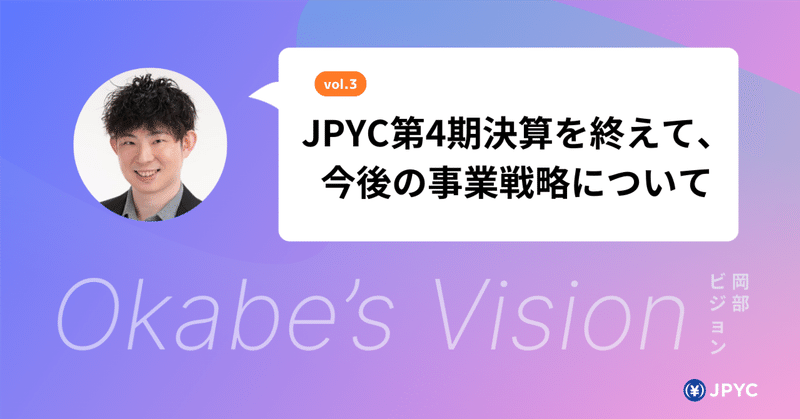
JPYC第4期決算を終えて、今後の事業戦略について
第4期決算承認、2期連続無限定適正意見をいただきました。
JPYCは7月が決算月です。そしてweb3スタートアップでは非常に珍しいと思いますが、監査法人による監査も受けています。今期も無限定適正意見をいただき、2期連続無限定適正意見を監査法人から頂くことができました。これは、取引所以外のweb3業界では初ではないかと思います。
「無限定適正意見」とは、監査における用語で、監査人が企業の財務諸表がすべての重要な側面において適切に表示されており、適用される会計基準に従っていると結論付けたという意見を指します。つまり、無限定適正意見を受けることは、企業にとって非常に好ましい状況であり、投資家やクレジットレーティング機関、その他の利害関係者に対し、その企業の財務諸表が信頼性が高く、透明性があり、適切に会計基準に従って作成されていることを示します。
JPYCはIPOに向けて現在N-2期として事業を進めていますが、まずは一つの大きな条件をクリアできたと考えています。今期も3期連続の無限定適正意見をいただけるよう、信頼性、そして透明性の高い経営を心がけてまいります。(決算については後日サイトに公開予定です。)
JPYCの多角的なステーブルコイン戦略
JPYCのステーブルコイン事業のビジョンは、よりグローバルに、世界統一規格で安全で安定した決済を提供することです。
現在JPYCは日本国内における日本円ステーブルコインのシェア99%以上をとっていますが、今後多くの事業者がステーブルコイン発行事業に参画してくることが想定されます。そこで、JPYCが変わらず大きなシェアを取り続けるためには、すべてのユーザーのニーズに応えていくことが重要であり、そのためには非常に多角的な戦略を展開することが必要であると考えています。
すでに発行している前払式ステーブルコインに加え、資金移動業ステーブルコインと、今回共同検討の提携を発表したProgmatにおける信託型ステーブルコインの発行を計画していることは、まさにその多様性と革新性の表れです。また、電子決済手段等取引業をとることも、グローバル展開していくために必須の条件であると考えています。

三菱UFJ信託銀行とProgmatおよびJPYCの協業による、「JPYC(信託型)」および国内外ステーブルコイン間の交換に関する共同検討開始について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000054018.html
Progmatの齊藤さんもご自身のnoteで今回のプレスリリースの解説記事を書いてくださっています。
【速攻解説】ProgmatとJPYCが組むって、どゆこと?USDC等を含めて一覧化します
https://note.com/tatsu_s123/n/nf6d1da39abb8
また、KYODAI Remittance(キョウダイレミッタンス)として世界200カ国以上で資金送金サービスを提供しているウニードス社との共同検討リリースからも、新しい事業展開の可能性を感じていただけたとおもいます。

日本円ステーブルコインのJPYC|200を超える国と地域に海外送金サービス「Kyodai Remittance」を運営する株式会社ウニードスと業務提携に向けた共同検討を開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000054018.html
これらの多角的な戦略により、JPYCが国内市場に留まらず、グローバルな決済サービスを安全かつ効率的に提供するための基盤を築いていくことを目指します。
例えば、これらの要素を複合的に組み合わせることにより、JPYCが提案するボーダーレスな決済環境が実現可能になります。JPYCはUSDCを発行しているCircle社からの出資を得ていることもあり、USDCをはじめとするステーブルコインの標準規格「USDC Standard(旧Centre.io)」に準拠しています。ですのでUSDCやEUROCを持った人が日本においてUSDC/EUROCのまま手数料0.1%でJPYC決済として利用できること、またJPYCを持った人が世界中で同様にUSDC/EUROC決済として利用できることは、国際的な決済の障壁を大幅に低減します。これが実現すれば、行く先々に合わせた通貨や決済手段を用意する必要がなくなり、国境を越えるビジネスや旅行者にとって、大きなメリットとなることでしょう。ボーダーレスな決済でボーダーレスな世界を実現させようというJPYCの先進的な取り組みは、デジタル通貨の利便性を一層高め、新たな可能性を開いていくと考えています。
JPYCの多様な運用モデル
JPYCは、2021年1月に発行を開始し、現在累計発行額は24億円を超えています。USDCを発行するCircleとの提携、USDC Standard(旧Centre.io)に準拠した国際基準の高いセキュリティや独自のAML(アンチ・マネー・ロンダリング)対策など、日本のステーブルコイン業界におけるリーダーとしての地位を確固たるものにしていると自負しています。今後は改正資金決済法に対応した電子決済手段ステーブルコインの発行に向け、資金移動業のライセンス申請ならびにProgmatとの提携を並行して進め、『前払式ステーブルコイン』『資金移動型ステーブルコイン』『信託型ステーブルコイン』という3本柱での運用を目指しています。
各々のモデルは、異なるニーズと規制環境に対応し、より幅広いユーザー層へのサービス提供を可能にします。

『前払式ステーブルコイン』は、現在規制が比較的緩やかで、サードパーティによる扱いやすさを特徴としています。ふるさと納税、ブロックチェーンゲーム、NFT取引、DAO運営などの様々なユースケースに対応できる柔軟性を持ちます。尚、2025年6月から発行体が都度承認または関与することが求められており、今後規制対応の為のアップデートを計画しています。
『資金移動業型ステーブルコイン』は、発行・償還時のみ1回100万円の制限を受けるものの、既存の前払式ステーブルコインと同様に、USDC Standard(旧Centre.io)に準拠したスマートコントラクトにより高い互換性と拡張性を持ち、マルチチェーンでの展開を可能としています。PolygonやAstar、Avalanchなど様々なチェーンに対応することで、GAS代を削減し、コストベースでの効率性を追求しています。また、国際的な取引所での利用はこちらのステーブルコインで目指していきます。
『信託型ステーブルコイン』は、発行・償還時の金額制限を受けないため、大口のBtoB、企業間決済に適しています。Progmatのスマートコントラクト基準に準拠し、Progmatとメインネット上での発行を検討しています。
この3本柱により、JPYCは、小規模な個人間取引から大規模な企業間取引まで、幅広い送金/決済/金融ニーズに対応することができるようになると考えています。
電子決済手段等取引業の取得とステーブルコイン専用取引所サービスの重要性
JPYC株式会社は、電子決済手段等取引業の取得も目指しています。これは2024年の第2四半期以降にステーブルコイン専用の取引所サービスを開始する計画の要です。このステーブルコイン専用取引所により、JPYCは国内で海外ステーブルコインの正規取扱いを可能にし、国際的なステーブルコイン市場における日本の地位を大きく向上させることが期待されます。
一部の海外ステーブルコインは海外発行型の電子決済手段として流通可能になりましたが、電子決済手段等取引業などの仲介業者が海外ステーブルコインを取り扱う場合、カストディ(預託)する海外ステーブルコインと同額の現金を仲介業者が日本国内で保全する必要があるため、既存の国内暗号資産取引所のカストディモデルでは、たとえ電子決済手段等取引業のライセンスを取ったとしても取扱が非現実的です。そのため、現状考えうる交換手段は国外Dex等を利用した非推奨の二次流通(利用者が自己責任・自己運用の範囲で行うもの)に限られていました。各海外ステーブルコイン事業者も日本版として異なる発行体・コントラクトで発行する方式など様々な検討をすすめているようです。
しかし、JPYCはUSDC発行体のCircle(JPYCの株主)やCircle株主のCoinbase社が提唱したUSDC Standard(旧Centre.io)の理念に賛同しており、世界のステーブルコイン規格は極力統一されているべきだと考えています。法規制上の問題で日本版として異なるコントラクトで出すということは、その理念に反しているのです。そこで、この問題を解決するために、ノンカストディ(非預託)モデルのステーブルコイン取引所の設立が絶対に必要だと考えました。ノンカストディであれば仲介業者が同額の資産を保全する必要がないため、海外ステーブルコイン流通を国内で実現可能であると考えたのです。
この取引所サービスは、Cex(中央集権型交換所)のような本人確認機能を備えつつ、Dex(分散型交換所)のようなノンカストディシステムを採用します。これにより、ユーザーは自らの資産を完全にコントロールすることができ、同時に日本の法律下で合法的に海外ステーブルコインの購入・償還や交換ができるようになります。このハイブリッドなアプローチによって、法規制と利便性のバランスを取りながら、ユーザーに安全かつ効率的な取引体験を提供可能になるでしょう。
我々JPYCが構想するステーブルコイン専用取引所によって、国内外の多様なステーブルコイン間の交換が容易になり、国際的な資金の移動や決済がよりシームレスに行われることで、企業や個人がグローバルな市場での活動をより拡大しやすくなります。
特に、海外で発行されたステーブルコインを国内で容易に利用できるようになることは、国境を越えたビジネス取引や個人の資産運用において大きなメリットをもたらします。このようにJPYCによる電子決済手段等取引業の取得とステーブルコイン専用取引所サービスの開始は、web3のみならず日本のデジタルマネー経済圏における重要な転換点となり、国内外の投資家やユーザーに多大な利益をもたらすと期待しています。
国内外ステーブルコイン間の交換サービス
JPYCの国内外ステーブルコイン間の交換サービスは、国際的な決済および通貨交換の新たなパラダイムを提示しています。このサービスにより、JPYCは国内ステーブルコインに対して海外ステーブルコインとの両替サービスを提供することが可能になります。これは、クロスボーダー取引を意識する事業者にとって大きなメリットをもたらし、JPYCをグローバル経済圏と国産ステーブルコインを繋ぐ重要なハブとして位置づけます。
特に、直接マルチチェーン対応しない国内ステーブルコインにとっては、JPYCとの交換は画期的なものになると考えます。JPYCを介することで、多様なチェーンとの接続を可能にするからです。

これにより、JPYCは多くのステーブルコイン事業者にとって、競合ではなく、事業の拡大のための重要な要として機能すると考えています。JPYCの存在によって日本のステーブルコイン市場がドメスティックなものに終始せず世界の経済圏と接続可能になることにより、業界全体の経済規模拡大が期待できます。JPYCの取り組みは、国内外のステーブルコインの流通と利用の促進に寄与し、デジタル経済における新たな成長機会を創出すると考えています。
第5期の展望と今後の収益源
JPYCの長期的なビジョンとして、ライセンスの取得、シリーズBの実施など2024年以降の展望は非常に重要です。今後の収益の柱としてステーブルコイン取引所の手数料収入を位置づけており、このためには電子決済手段等取引業のライセンス取得が最優先となります。
また、日本国債金利の上昇傾向により、裏付け資産の国債運用収益も見込めるようになってきました。国内外のステーブルコイン市場の拡大に比例してハブとして機能するJPYCの発行規模は拡大していくと考え、5年後に資金移動業と信託を合わせて4兆円以上の流通を目指すという目標を掲げています。これらの収益をもとに、今後もJPYCは、金融サービス業界における収益性と競争力をさらに強化してまいります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
