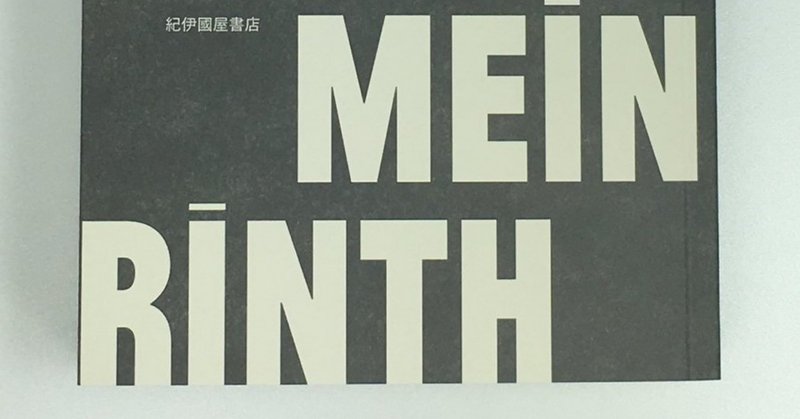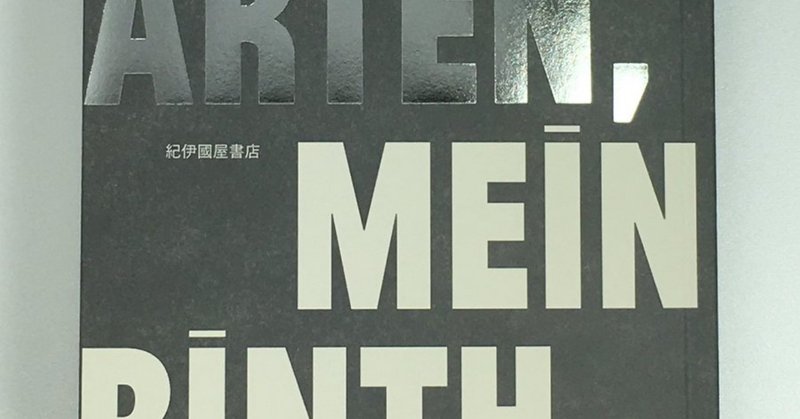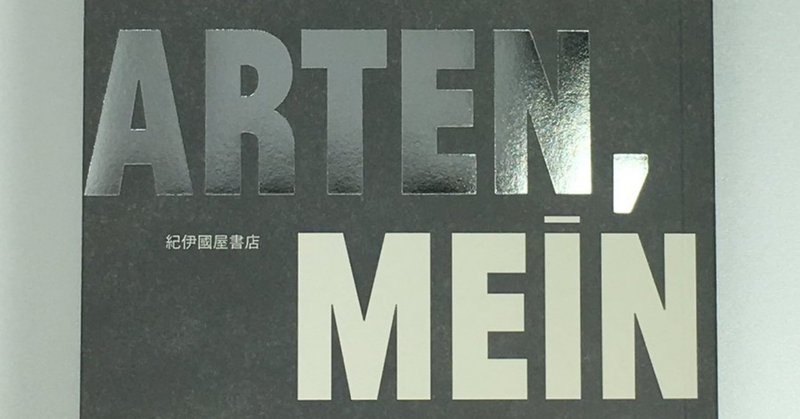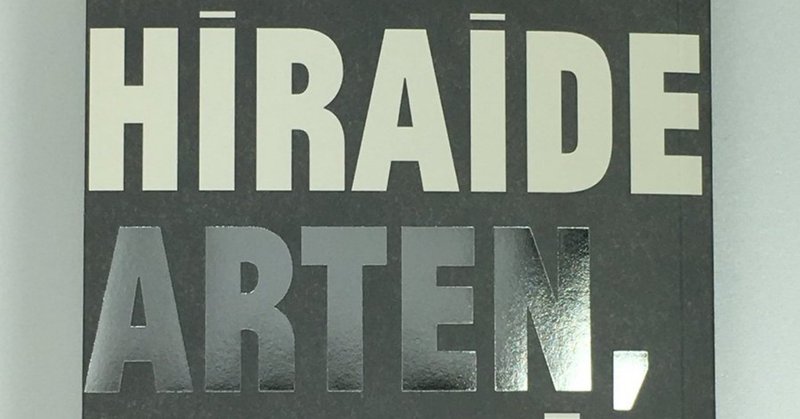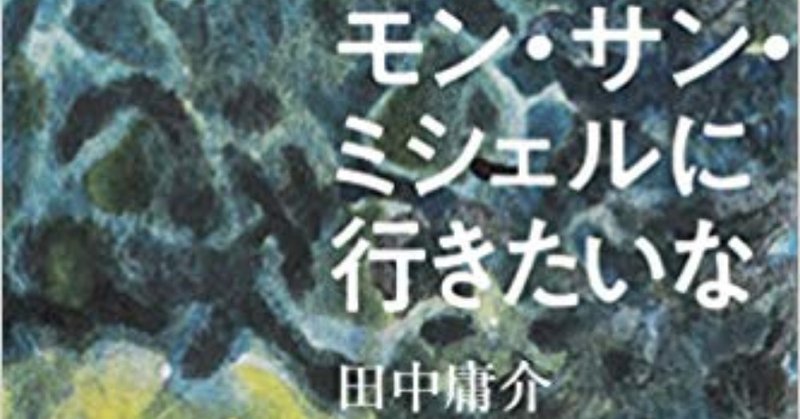2018年11月の記事一覧
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その4)
本書には実に多彩な人物たちが登場する。
前項に引いた水仙先生こと鳥山晴代先生のほか、小学校すら退学していながら五カ国語を操り植物学動物学に通じた博学の祖父・平出種作、音楽の時間にはてんで歌えないのに、休み時間になると初夏の蜂のような小さく、かつ力強い歌声を響かせる黒本君、平出少年が思わずそのまばらな顎髭に手を伸ばして触ってしまった(そしてそれを自若としていやがる風も見せず、触られるままに笑みを絶
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その3)
若い頃から詩人の書いた散文が好きだった。散文詩はむしろ苦手なのである。詩人の書いたれっきとした散文を読むのが好きなのだ。
高校生の頃は田村隆一の『詩人のノート』を(授業中にこっそり)読んでいた。リルケの『マルテの手記』を読んだのはいつだっただろう。辻邦生の初期の小説(たとえば『回廊にて』)にも、同じような匂いがあった。金関寿夫さんが訳したヨシフ・ブロツキーの『ヴェネツィア 水の迷宮の夢』は、散文
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その2)
本書を読み始めて最初に大きな衝撃を受けたのは次の箇所だった。著者が中学二年生のときの思い出である。
学級新聞が出たあと、エッセイの「除夜」を褒めてくれた二人のうち、才気煥発の生意気な文学少女の俤を隠さなかった独身の先生が、今度も授業中に「この詩は素晴らしい」とみんなの前で朗読してくださった。そのとき私が驚いたのは、「この詩は」といわれたからだった。自分には「詩を書いている」という意識が少しもなか
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その1)
平出隆という名前はもちろんよく知っていた。雑誌で詩作品を目にしたことはあったし、評論の仕事も耳にしていた。世界的なベストセラーとなった小説『猫の客』には特別な思い出もあった。二年前、病を得て入院していたとき、階下のアパートの住人が英語版を差し入れにくれたのだった。入院する少し前、彼らが家を離れているあいだ、飼い猫の世話を引き受けたことの返礼をかねた気の利いた選択だった。
だが『私のティーアガルテ
田中庸介『モン・サン・ミシェルに行きたいな』を読みたいな
なにを隠そう、ぼくは田中庸介の筆跡フェチである。彼から郵便が届くたびに、封筒の宛名を眺めてうっとりする。それからおもむろに封を切るのだけれど、中身はたいてい詩の雑誌「妃」である。
ついこのあいだも「妃」の最新号が届いた。表紙に「一番高貴な詩の雑誌」と銘打ってある。ここからもう田中庸介の気配が滲み出ている。たしか前の詩集『スウィートな群青の夢』の帯には「当代最高の詩のスピリット!」と銘打っていたっ
遅ればせながら、「びーぐる」41号 (その2): 海外現代詩紹介 Marie de Quatrebarbes
こちらも創刊以来続けているコーナー。「PIW通信」は日本の現代詩人を英訳を通じて海外に紹介している活動の報告だが、こちらはその逆で、海外の現代詩人を日本語訳とともに紹介する。僕が海外の現代詩にふれる機会はもっぱら詩祭であり、その中でもPIW の母体であるRotterdam のPoetry Internationalは最大規模の詩祭のひとつだから、いきおいそこで知り合った詩人を紹介することも多くなる
もっとみる