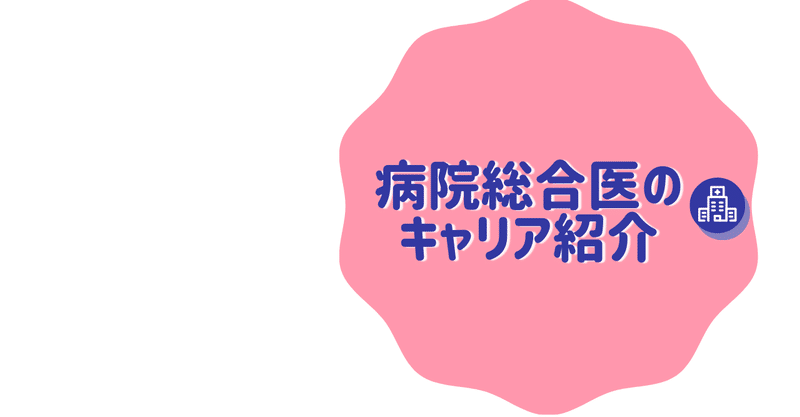
キャリアプランニングの4Stageアプローチを知ろう
皆さん、こんにちは。神戸大学地域医療支援学部門/兵庫県立丹波医療センターの合田(ごうだ)といいます。
現在は卒後8年目です。普段は350床の急性期から緩和ケア病棟まで担う地域の中核病院を中心に診療を行いつつ、敷地内にあるミルネ診療所(市の診療所)では外来診療・訪問診療、また大学にも属しており、医学生の教育等を行っています。
日本プライマリ・ケア連合学会としては若手医師部門 病院総合医チーム以外に専門医部会 キャリア支援部門にも所属しております。
今回は「キャリア」について、特に「キャリアプランニング」について紹介したいと思います。
キャリアの定義
キャリアの語源は「道」「轍(わだち)」を意味するラテン語のCarraria(カラリア)とされています。狭義には資格や職歴など履歴書に記載する職業上の経歴を指すこともありますが、広義には、仕事のみならず学び、友人・家族、趣味など人生を通じて歩んでいく経歴そのものを指します。
またキャリアの成功には満足感といった主体的なもの、給与や昇進といった客観的なものがあります。日本の医師キャリアは医学的知識・臨床経験の習得パターンと関連し、西洋医学の導入や医局制度が確立することで指導医の下で臨床経験を蓄積する時期が確保されました。さらに新臨床研修制度、新専門医制度により研修病院の自由市場化・若手医師の流動化が促進されました。今後も多様性と流動性にともない、より複雑になることが予想されます。そのため今までの「敷かれたレール」でキャリアを歩むのではなく、多くの選択肢から「自律的にキャリア確立をしていく」必要があります。その一助になるキャリアプランニングを紹介したいと思います。
より詳しく知りたい方はThe ROADS to Successをご覧ください。
キャリアプランニングとは
キャリアプランニングとは自らの人生や進路(キャリア)を、長期的に、主体的に自分らしく作り上げていく事です。キャリアプランニングを実践していくプロセスとして4-Stageアプローチがあります。
Stage1(自己分析:Self-Assessment)、Stage2(キャリア探索:Career Exploration)、Stage3(意思決定(選択・決断):Decision Making)、Stage4(キャリアプランの実行:Plan Implementation)とアプローチしていく方法です。近年はStage0(意思決定の必要性の認識)も最初のStageに付け加えられて紹介されることもあります。
Stage1(自己分析:Self-Assessment)
まずStage1は自己分析です。時間と労力をかけてまで取り組みたいことは何か?自分にとって良きロールモデルは?どんな分野に学術的興味を持つか?自分にとってストレスになる環境とは?自分の過去の経験や資質について振り返りながら、こういった自分の能力、適性、興味や価値観を分析します。
Stage2(キャリア探索:Career Exploration)
Stage2はキャリア探索です。Stage1で見極めた自己分析をもとに、自分に適した進路とは何か、いくつかの候補の中でどれが一番自分に合っているのか調べます。制度について分からないところや、自分が考えた進路が現実的なものであるかについては周りに相談してもよいと思います。キャリアにおけるソーシャルキャピタルといった概念もあります。
Stage3(意思決定(選択・決断):Decision Making)
Stage3は意思決定(選択・判断)です。計画型、苦悩型、衝動型、直感型、従順型、延期型、運命論型、無力型等の意思決定スタイルがあります。バイアスも存在することが多く、優先順位をつけ、選択肢の拡大、自分への影響の再確認、価値の再考、未把握情報の抽出、相補性、判断の修正を行うといったバイアスに対抗するマネジメント方法があります。
Stage4(キャリアプランの実行:Plan Implementation)
そしていよいよStage4でキャリアプランの実行となります。計画どおりに行動できるよう進捗管理を行います。時間と経済面で余裕があれば、望む進路
の可能性を高める為の教育を受ける事が出来ます。転職の場合では、選考が進んだ段階で入職にあたっての条件交渉についても考えます。
患者診療SOAPとの比較
実は普段診療で行っているProblem oriented systemでの患者診療と似ています。S:病歴聴取、O:診察・検査、A:診断の組み立て、P:治療計画の実行と順を追ってしていますよね。問診や身体診察をしていない患者へ有効な治療が出来ないのと一緒で、自己分析やキャリア探索がないとキャリアプランの実行はできません。もちろん、時にはステージを行ったり来たりしながらプロセスを進めていきます。一方で患者の診断・治療プロセスでは「最終的な結論」がある場合が多いのに対して、キャリアプランニングでは「個人個人の価値観は違うため、1つの結論はでない」という違いがあります。
キャリア理論
総合診療の分野は様々なフィールドで活躍している人が多いです。そのため、「キャリア」は多岐にわたります。予測しがたい環境変化を前提にして自分なりの意思決定の基準を準備し、このようなキャリアプランニングを行うことで、主体的なキャリアを歩めるのではないでしょうか。実は複数あるキャリア理論を知っていると、キャリアプランニングに有益な介入が可能になります。
クランボルツの「計画された偶発性」
クランボルツのPlanned Happenstance Theory「計画された偶発性」はキャリア理論の一例です。望ましいキャリア・ビジョンに向けて可能性を広げる継続的行動の事を指します。偶然の出来事がキャリアには大きな影響を及ぼします。「偶然の出来事を避けるのではなく、起きたことを最大限に活用する。偶然の出来事を積極的に作り出す」という理論です。日頃から望ましいキャリアを思い描き、必要な学習を行い、小さな変化に注意を向けて行動をしましょう。そうすることで偶然の出来事を捕まえる確率を増やすことができます。「計画された偶発性」が成立するための要件として4つのステップと5つのスキルがあります。このような理論を意識することでキャリアプランニングも効果的に行えるのではないでしょうか。
「計画された偶発性」が成立するための要件として4つのステップ
・Clarify Ideas:自分の興味/関心事を明確にする
・Remove the Blocks:障害を取り除く(出来ない理由ではなく出来る理由を考える)
・Expect the Unexpected:思いがけないチャンスがくると思って心構えする
・ Take Action:必要な準備をする&好機と見れば掴まえる
「計画された偶発性」が成立するための要件として5つのスキル
・好奇心(Curiosity):新しい学びの機会の模索
・持続性(Persistence):たとえ失敗しても努力し続ける
・柔軟性(Flexibility):姿勢や状況を変えることを進んで取り入れる
・楽観性(Optimism):新しい機会は実行でき達成できるものと考える
・冒険心(Risk-taking):結果がどうなるか分からない場合でも行動することを恐れない
まとめ
いかがだったでしょうか。多様化する医師のキャリアにおいて、様々なキャリア理論が存在し、主体的にキャリアプランニングすることで、後悔しない医師人生を歩んでいけるのではないでしょうか?また、自分の歩んだ道を振り返ることでしっかりと自分の「キャリア」が見えてくるのではないでしょうか。このブログでも引き続き、様々な「キャリア」を紹介していきます。引き続きよろしくお願いします。
(文責:合田建 神戸大学地域医療支援学部門/兵庫県立丹波医療センター)
※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。
LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。
当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
