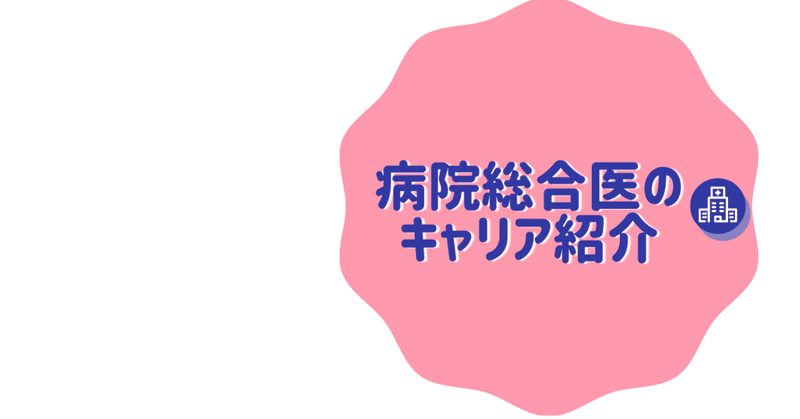
病院総合医としての多様な働き方
皆さんは「病院総合医」についてご存知でしょうか?なかなかイメージがわかない方も多いのではないかと思います。病院総合医の定義はなかなか難しいですが、病院ごとにその役割を担う科が違うこともあり、例えば「内科」、「総合内科」であったり、「総合診療科」であったりするかと思います。「病院総合医」は病院で働くgeneralistということになりますが、こちらについては他項を参照ください。私は内科をベースにトレーニングしてきた総合内科医ですが、現在福島県立医科大学総合内科で病院総合医として勤務しております。また、過去に沖縄県立中部病院、沖縄県立北部病院という規模の違う総合内科で働いてきました。私の経験から多様な病院総合医の働き方を「病院の規模」という視点で紹介していきたいと思います!
① 僻地病院での病院総合医(沖縄県立北部病院、病床数 約300床)
まず初めに僻地病院での病院総合医の働き方について述べていきたいと思います。個人的にはこの規模の病院が病院総合医として力を十分に発揮することができ、また力が試されるのではないかと思っています。
病棟での働き方ですがかなり幅広い疾患の患者さんを担当医として診療しました。受け持つ患者数も最も多くなります。やはり臓器別専門医が地域の病院ですと少ないため、感染症はもちろんのこと呼吸器、内分泌、神経、血液、膠原病疾患を持つ患者さんを幅広く受け持ち、マネージメントしていきます。もちろん高次医療が必要である場合は沖縄県立中部病院や琉球大学病院に紹介することとなります。ただし、患者さんの社会的状況や思いなどもあるため診療を続けることもあり、幅広い知識を必要とします。
また、僻地は高齢者が多かったり、社会的に困難な患者さんだったりと複雑症例が多いため、より家庭医療的な知識も必要としました。どうやって地域に戻していくかソーシャルワーカーや他のメディカルスタッフと日々ディスカッションしていました。また、医師が少ないのは内科だけでなく外科や産婦人科、整形外科なども同様であるため内科マネージメントの相談が非常に多かったです。300床という規模は科の垣根を低くし、フットワークを軽くして診療にあたることが可能な規模と言えるかと思います。
外来診療に関しても、臓器別専門医が少ないため診療する疾患のバラエティは富んでいました。また、地域のかかりつけ医的な側面もあるため新患だけでなく、糖尿病などの慢性疾患を持つ患者さんを診療することも多いです。
教育に関してはcommon diseaseを持つ患者さんを研修医に担当してもらい、実際にon the jobトレーニングをすることができます。総合内科は内科専攻医や初期研修医がローテーションすることが多いため、general mindを濃厚に教育することができました。ただし、患者数が増えるため研修医の診療のカバーをすることも必然的に多くなり、業務自体はタフになりました。
以上から、実際に診療自体の比重が大きく僻地の病院総合医は後期高齢者が急増する今後の医療において担う役割は非常に大きいと考えています。
② 地域中核総合病院での病院総合医(沖縄県立中部病院、病床数 約500床)
地域中核病院での病院総合医の働き方について述べていこうと思います。当時、中部病院では総合内科は病棟を持っていなかったため外来診療が中心となります。外来では研修医が新患を担当することになり、その指導を行うことになります。より教育的な側面が強く、研修医教育に十分関わることができます。専門的な疾患に関しても臓器別専門医が多いため協力していきながら診療することが可能です。
病棟に関しては整形外科の患者さんの内科プロブレムをco-managementし、診断困難症例の患者さんのコンサルテーションの対応をしていました。
上述のように病院にもよるとは思いますがこの規模の病院は臓器別専門医が多く、外来においては新患の対応が増えるため、病院総合医はそれを利用し研修医の教育をより濃厚に行うことが可能となります。さらに中核病院でもあり、全ての科で重症疾患や難しい疾患を抱える患者さんが増えるためそちらのマネージメントの支援を行なっていきます。
③ 大病院での病院総合医(福島県立医科大学、病床数 約800床)
最後に大病院での病院総合医の働き方を述べていきます。大病院ですので全ての臓器別専門医が揃っているため、診療内容はかなり特殊になります。
病棟では診断困難症例の診断が中心となります。疾患頻度が極めて低い疾患から、非典型的なプレゼンテーションを呈した患者さんを診療することが多いです。他科からのコンサルテーションも非常に多く、診断に難渋している症例が中心です。また、皮膚科や整形外科などの科から重症患者の内科マネージメントを依頼されることもあります。Common diseaseを診療する機会はかなり限られます。
外来でも開業医、地域中核病院で診断がつかなかった症例の紹介がメインとなります。また、必然的に精神科疾患の頻度も増え、内科疾患はもちろんのこと精神科疾患の知識も必要となります。病棟、外来ともに非常に難しい症例が多く、総合内科医として「診断学」の軸が非常に伸びていると感じています。
また、大学の特徴として、外勤での地域中核病院・僻地病院の診療支援が挙げられます。現在、福島県では病院総合医、総合内科医が非常に少ないため診療支援の要請が非常に多いです。外来・病棟ともにマネージメントに難渋している患者さんの診療を行います。同時に研修医の教育も担うことが多いです。
教育に関しては僻地病院、地域中核病院と同様に病院総合医が担う役割が大きいのですが、大学ではさらに学生教育もあるため、早期にgeneral mindへの曝露を行うことができ将来の病院総合医、またgeneral mindを持った臓器別専門医を養成することに寄与できているのではないかと考えています。
最後に研究を行う機会も増えます。貴重な症例に出会う頻度が増すため症例報告はもちろんのこと、Academicな機関であるため同僚を含め研究マインドを持った医師が多いためより研究の軸を強めることも可能です。
以上が、様々な病院総合医としての働き方を述べさせていただきました。いかがだったでしょうか?これはあくまで私の働き方ではあり、働く地域も異なるため一概にみなさんに当てはめることは難しいかもしれませんが、病院総合医の働き方は多様であり、そして何よりたくさんの役割を担うことができるということがわかっていただけたのではないでしょうか。働く場所に合わせ、働き方を変えることができる。それが「病院総合医の強み」であるとも感じています。私は今後の医療にとって「病院総合医」はkeyになると考えています。一人でも多くの仲間が増えることを願っております!
※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。
当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。
(文責:會田哲朗 福島県立医科大学総合内科)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
