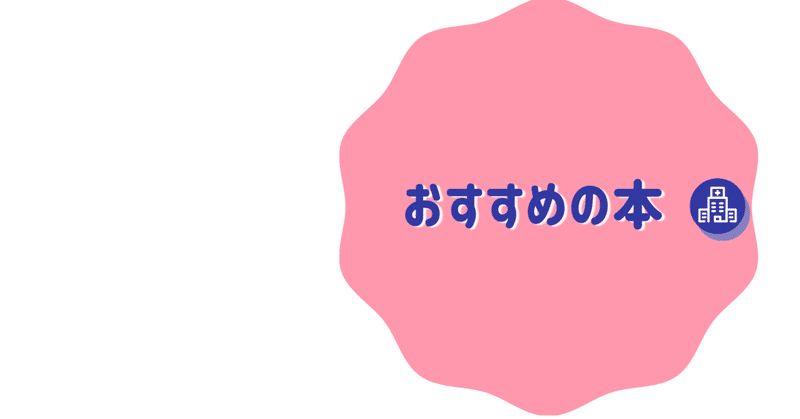
おすすめの本〜「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開〜
今回は、ホスピタリストとして日々の診療を改めて見つめ直す機会となった本を紹介します。
この本の舞台は精神科病院ですが、わたしたちホスピタリストの勤務する"非"精神科病棟でも、高齢の認知症患者さんやせん妄患者さんに対する身体拘束は日常的です。
わたしはこれまでずっと急性期医療に携わってきて、当たり前の様に、入院時に身体拘束の同意書にサインをもらっていました。治療完遂のために身体拘束は「止むを得ない」と、知らず知らずのうちに思い込んでいたのです。
しかし、一方で、「本当にこの患者さんに身体拘束は必要なのだろうか?」と疑問に思う場面にも幾度となく出くわしました。拘束具を外してくれとせがむ患者さんに「ごめんなさい」と謝りながら部屋を後にした時の形容し難い感情、共感する方いらっしゃいませんか? その感情をなんとかしたくて、かつては「身体拘束具を外すべきか否か」で病棟看護師と揉めたこともありました。
共感します、という方に、この本はとてもおすすめです。
1章 日本の身体拘束の現状と、松沢病院の改革
この章では、まず、身体拘束の定義の曖昧さという問題点に触れられています。病院によっては「抑制」や「安全ベルト」といった呼称を用いていることもあると思いますが、それは患者さんにとっては自由を奪われるという意味では同じこと。表現によるグレーゾーンを無くし、患者さんにとっての身体拘束を最小化するため、松沢病院では身体拘束を以下の様に定義しました。
身体拘束とは、一時的に当該患者の身体を拘束しその運動を抑制する行動の制限をいう。この拘束用具には、マグネット式の拘束用具および車椅子安全ベルト、ミトンを含む。
身体合併症のために必要な身体拘束などについても、当院の特性や、行動制限を最小限にするために、精神保健指定医の判断のもとに行うこととする。
身体拘束「ゼロ」ではなく、「最小化」と書かれているところもミソです。
「身体拘束最小化」は目的ではなく、患者さん1人1人の人生に寄り添った治療目的を達成するための1つのステップだということです。ですから当院では、現在でも、治療目的を達成するために必要だと判断した「身体拘束」は、基準に則って慎重に実施されています。
続いて、上記を目標に身体拘束最小化に取り組む過程で、松沢病院が直面した3つの壁、①医療安全の壁(医療安全を守るために身体拘束が正当化される)、②治療方針の壁(終末期患者の治療方針設定)、③こころの壁(職員1人1人の心の中にある弱さや不安・偏見)について触れられています。
管理者の立場として、院長、看護師長らがどのように取り組んでいったか、対談形式で書かれており、とても読みやすいです。
2章 松沢病院が身体拘束最小化を実現した25の方法
ここから具体的な方法の紹介に入っていきます。
25個の方法のうち、わたしが特に良いと感じたものを赤色で示しています。

支えるリスクマネジメント
患者さんが転倒するとインシデントレポートを書くことになり、図らずともその時の勤務者が責められる様な構図になり、「転倒させないために身体拘束をしっかり行おう」という悪循環に陥りがちですが、「医療安全」は、医療者にとっての安全ではなく、患者さんにとっての安全を考えた策であるべきだということの理解が必要です。管理者や医療安全委員会が、職員は患者さんにとってのベストを追求しているのだという信頼のもと、仮に転倒してしまったとしても、むしろ身体拘束を減らそうとした職員の努力を評価し支えたことが成功の鍵だったと書かれています。
「当院では身体拘束をしません」という同意書
多くの病院で行われている「身体拘束をします」という同意書の真逆の策が紹介されています。これが、わたしにとって一番驚きました。
患者やその家族も、転倒を防ぐためなら身体拘束をすべきだと考えている人は多いです(Gerontology. 2005;51:66-70. PMID: 15591759)。
身体拘束のリスクや病院の理念を丁寧に説明し、家族にも理解してもらったうえで、入院になるという仕組み、逆転の発想が素晴らしいと思いました。
とにかく対話
患者さんがなぜ点滴を抜いてしまったか? なぜベッドから離れ歩き出してしまったか? そこには理由があるはずです。根気強く対話することで、患者さんの考えや欲求を理解すれば、身体拘束以外の適切な対策が見えてくるかもしれません。治療の必要性をしっかり説明し、患者さんが理解してくれたら、行動も変わるかもしれません。そして、そのプロセスを通して患者さんとの良好な関係が築かれ、結果として、職員の心理的・身体的負担も改善されたという声もあるようです。
こうやって読むと、そんなの当たり前のことだろうと感じるかもしれませんが、今一度「ちゃんとできているだろうか?」と振り返ってみてください。
できない理由を探さない
今回取り上げたのはほんの一部の策だけですが、すでに「こんなの急性期病院では無理でしょ」「うちは人手が足りないから無理だわ」「事故があったら責められるから無理」…という気持ちが湧き出ていませんか? きっとそのような方が大多数だと思います。痛いとこついてくるなぁって感じですよね。でも、この本にはこう書かれています。
最小化できない理由はいくらでもある。人や物があっても身体拘束はなくならない。職員の倫理観が何よりも大切。
3章 こんな工夫と考え方で身体拘束を外せた15の事例
この章では、実際の経験症例をもとに、現場の職員がどのようにアセスメントし、どのように対策を講じた結果、どのように患者が変わっていったかが紹介されています。工夫はカラー写真付きで、とても参考になります。
例えば、車椅子の安全ベルト。座面からずり落ちてしまうから、という理由で装着することもありますが、それだけならば、ベルトじゃなく100円ショップで売っている滑り止めシートを弾くだけで解決できるといった工夫が紹介されていました。他には、ミトンにもさまざまな種類(メッシュ製で通気性と動きの自由が確保されるタイプ、指先だけ外に出せるタイプなど)があのでなるべく拘束感が減るものを選ぶ、など。
実際に担当した看護師がそれぞれのケースでどんなジレンマを感じていたか、どのような手応えを感じたか、なども書かれており、改革の過程がよりリアルに感じられました。
この本を読んで、自分の心構え、考え方は変わりました。この本を読んだことをきっかけに身体拘束についてさらに調べてみると、勇気づけられる文献も見つかりました。

病棟を預かるホスピタリストとして、いっそう身体拘束最小化へ取り組まねば、という気持ちになりました。
興味が湧いた方は、ぜひ読んでみてください。
文責:平松 由布季(東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科)
※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。
LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。
当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
