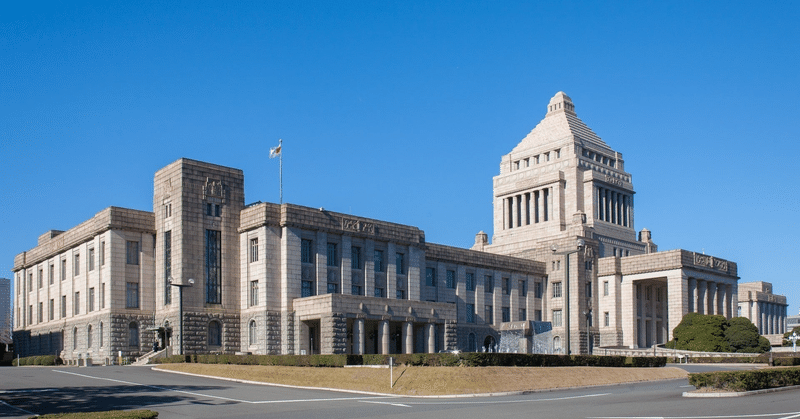
じいじ 保育士を目指す! 福祉政策
福祉関連を勉強して
ちょっと硬い話題にならざるを得ないのですが、お許しを。
保育士試験の勉強をする中で、福祉政策に関するどうでもいい年表を覚えさせられる苦痛を経験者として、これから勉強を始める方々、勉強中の方々に「お見舞い申し上げます。」としか言えません。
要するに福祉政策、少子化対策の政策上の失敗を年表にした結果を覚えさせられる訳で、この年表から問題が出る以上覚えるしかない。。。となってしまいます。
今まで、福祉系の世界とは全くかけ離れた世界に生きてきた人間が初めて目にする児童福祉法の文言を目にした時の感動と同時に、これ実現していたら世界最高水準の福祉国家になっているはずじゃん!とツッコミを入れたのを覚えています。
だってそうですよね?最善の利益が優先されているなら、なんで児童虐待による死亡事件が起こり、食事も満足に食べられない子供達が存在し、路上で行き場のない子供達が存在するのか?
私が保育士を目指す原点だった園バスの死亡事件も!もし、この基本法の精神(要するに日本国憲法の規定する基本的人権)が完結しているのだとしたらその様な事は存在していない事柄です。
勉強を進めると見えてくるこの国の矛盾と社会政策の失敗に憤りと、自分が如何に無知であったかを改めて自覚させられた事か。
為政者にとっての最大の力は、国民が結局無知でいる事とその無知でいる状態を維持し続ける事なのだと。もし、有権者が、少しでも自分の世界のちょっと外を見る事ができれば、この国は変われるのではと思ったのでした。
だから、保育士試験を受ける、又は受験中の皆様はこのチャンスを手にしているのだと思うのです。確かに苦痛な勉強ですが、知らないでいた世界を知るきっかけを手にしているのだと私は思うのです。
さて、勉強中の方々へちょっとしたアドバイスを
法律制定年次を覚える事のポイントは、基本になる法律、例えば児童福祉法が日本国憲法制定直後にできた事(法律の文言が格調高く理想に燃えている)、そして子供の権利条約の批准に合わせて改訂されたという歴史的経緯をストーリーとして理解する事で問題に対処できるはずです。
保育士試験は論文記述式の試験ではない為、法律の制定順序を問う事か、法律文書の穴埋め問題ぐらいしか問題にできません。その事を逆手に取れば、ポイントとなる法律や条約の年次を覚えておけば、正誤問題は解けるという事です。
さて、今日はこの辺で。
児童福祉法(抜粋)
第一章 総則
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
(平二八法六三・全改)
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
(平二八法六三・一部改正)
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
