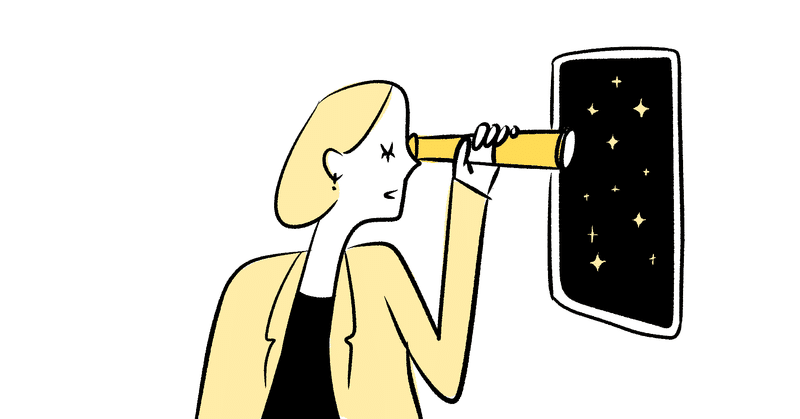
じいじ 保育士を目指す! 第三者評価
第三者評価委員
私がそもそも保育士を目指したのは、あの事件がきっかけでした。
自分が勉強を進める中でどうすれば子供達を守る事ができるのか?
どういう方向に自分が進めばいいのか?全く手探りのままでした。ただ、保育の現場に行く近道は、保育士試験合格で保育士資格を得る事という今思えば短絡的な発想だったと思うのですが、勉強して知識を得ればその道は自ずと拓けると勝手に思っていたのです。
そんな折、勉強する中で保育園の第三者評価というモノが出てきました。
評価委員になれば、保育園の質を担保し、結果として悲惨な事故が起きる事を防げるのではないかと考えました。
しかし、そもそも第三者評価は努力義務だけど、改善命令等の強制力が出せるものでもないし、評価機関は評価される側が任意に選べるし、ISOの様に国際標準規格に則った評価基準ではない事、園長等職員の適切な評価を与えるものではないという事を知りました。
だから、初心を実現できる保育士になる為に勉強を進める中で、更に実現可能な方向がどういうものか模索しながら勉強を進めました。
現在もこの模索は続いています。
でも、自分が目指す方向としてその数mm(μm?)程度は前進させたと思っています。
だって保育士になったんだから!
さて、今日この辺で。
あの事件
2022年9月5日の午後2時10分ごろ。牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」は降園時間を迎えていた。園の送迎バスが細い道を後進ギアで入ってくる。園児が待つ園舎の前まで。いつもならゆっくり、真っすぐ。ただ、その日は違った。
結局、二度目の死亡事件が起こり、その事件の教訓がバスのハードウェアとしての安全システムという点に単純化してしまえば、この事件の本質は闇の中という事に。
保育の本質を問うべき問題の核心に目を逸らすとすれば、同質の事件はやがて起きるという事だろう。
そうさせない為に、私は1mmでも前進したい。。。
第三者評価
第三者評価とは、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
ISO
「ISO」とは何を指すのでしょうか?
ISOとは、スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称です。ISOの主な活動は国際的に通用する規格を制定することであり、ISOが制定した規格をISO規格といいます。ISO規格は、国際的な取引をスムーズにするために、何らかの製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう」という国際的な基準であり、制定や改訂は日本を含む世界165ヵ国(2014年現在)の参加国の投票によって決まります。身近な例として、非常口のマーク(ISO 7010)やカードのサイズ(ISO/IEC 7810)、ネジ(ISO 68)といったISO規格が挙げられます。これらは製品そのものを対象とする、「モノ規格」です。
一方、製品そのものではなく、組織の品質活動や環境活動を管理するための仕組み(マネジメントシステム)についてもISO規格が制定されています。これらは「マネジメントシステム規格」と呼ばれ、品質マネジメントシステム(ISO 9001)や環境マネジメントシステム(ISO 14001)などの規格が該当します。つまり、「ISOマネジメントシステム規格」とは、“ISOが策定したマネジメントシステムに関する規格”ということになります。
もし、保育に関する品質とマネージメントの標準化が存在し、国際基準で評価が可能なら、少なくともマネージメント側の品質悪化は内部統制の明確化という組織としての保証という意味で、理事長の私物化等の組織的腐敗を防ぐ事ができる可能性はあったと思います。
標準化は、形式主義に陥る事も。。。万能な方策はなくとも幾重にも張られた方法によってシステムの健全性は担保されるものです。
もちろん、保育園というシステムも同じ事だと考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
