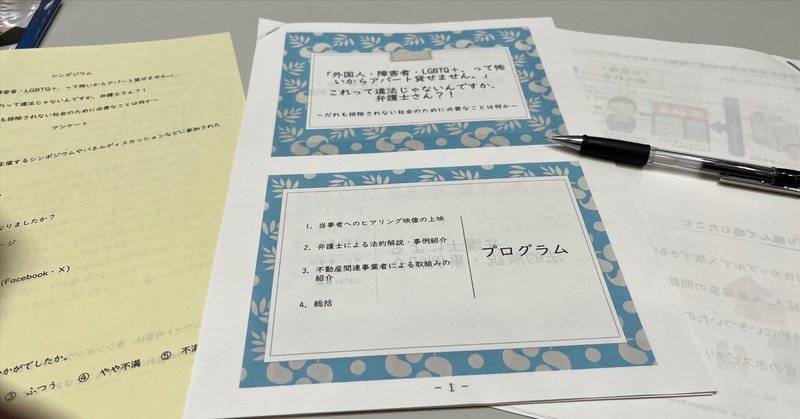
【所感】シンポジウム 「外国人・障害者・LGBTQ+、って怖いからアパート貸せません。」 これって違法じゃないんですか、弁護士さん?! ~だれも排除されない社会のために必要なことは何か~
先日とあるツテでこんなシンポジウムに参加してきた。
東京弁護士会の主催ということで前回聞きに行った下記のパネルディスカッションよりは中身がありそうだと思い、参加申し込みをした。
参加前、私の想像では内容はこうなるだろうと思った:
人権派弁護士が出て来て、特定の社会属性に含まれることを理由に賃貸への入居を断られた事例を紹介し、いかに酷いことが行われているかを訴える
判例を例に事例を解説
こういった問題のために何ができるか、実践されている事例を紹介
「困っている人がいます」「同じ人間です」「差別はいけません」「ダイバーシティ、インクルーシブな社会を目指しましょう」とまとめる
結論から言うと想像通りの内容だった。申し訳なくなるくらい想像通りすぎて引いてしまった。私は彼らの話を聞いて、20年外国人として生き、精神障害を抱え、性的嗜好もストレートとは言えない人間として思うところは多くあったのでここに記しておきたいと思う。
不動産業界の現状
私はかつて親戚の零細不動産会社に勤めていたことがある。
「不動産会社」と一口に言ってもその世界はとても広い。売買を中心に商っていたり、賃貸を中心に取り扱っていたり。そして住〇、東〇、三〇不動産のような駅周辺や街全体の開発を担う大手企業から、いわゆる「町の不動産屋さん」と言われる従業員が5人程度の会社もある。私が働いていたのは後者。
まずそういった不動産屋やそもそも大家さんの地位は日本では実はとても低いということを知ってほしい。不当に多額な敷金・礼金を請求したり、悪いことをする事例、いわゆる「悪徳不動産」が出てきたがために、彼ら全体の地位は下がってしまった。入居者は権利が強く、素行に問題があり追い出したいような例があっても、そういうことをすると裁判に持ち込まれ、業者側は入居者の権利を奪ったとして罰せられてしまう。
昔話をしよう。
ある日、文献退去に立ち会った営業が「部屋が酷いことになっている。緊急で見てほしい」と事務所へ電話があった。私は事務員で何もできないし、会社に一人しかいないため持ち場を離れることができず、私を雇った親戚である社長と父親であるマネージャーに戻り次第見てもらうことにした。
私は私で保証人に賠償を求める必要があるため、社長とマネージャーと立ち会いのもと部屋に入った。いや、部屋に入る前から様子がおかしい。金属でできている玄関ドアが歪んでいた。内側から何かで突いたかのような陥没ができていた。中に入ってみると部屋の窓は割られ、扉はボロボロに破られ、壁は汚れまみれで壁紙が剥がれていた。床も多くの箇所が陥没しており、修復には多額の金銭がかかること間違いなしの案件だった。入居者本人と営業は会話が成立しなかったらしく、私は保証人である入居者の母親へ電話することになった。電話口で母親は叫んだ。「うちの息子が何をしたって言うんですか!!お金なんて払いませんからね!!!」「そう言われましても部屋が大幅に損傷しておりまして、原状回復は敷金では賄えない状況です。回復料金をお支払いいただく必要があります。」「払わないから!!息子が何したか知らないけどね、そんな金ないんだから!!」怒鳴られてしまった。途中で電話を社長に代わってもらったが、案の定話にならなかったようだ。弁護士もいない零細企業にとって裁判を起こすこともできず、この件は泣き寝入りになったと聞いた。
また別のマンションでの話。長らく家賃を滞納しているご家族がいた。窓口は奥様。旦那様は仕事で常に不在。私は何度も督促状を送った。電話も何度もしたが誰も出ない。ある日、私が不在中、奥様が事務所へやってきて「支払い方がわからないんです!!」と泣き叫び、床に崩れ落ちたらしい。社長から聞いた話だ。どう見ても心神耗弱な状態だったようだが、こちらから通院を進めることも人権的に問題があるため、そのままお引き取りいただいた。契約更新時期が近かったので、社長は更新しない、そして未納の家賃を請求するという選択をしたようだが、それがうまく行ったかは知らない。私はこういった入居者たちのおかげで心身を病み、職場を離れざるを得なかったからだ。
人権派弁護士先生方は私の話を読んでくださったとして、どんな感想を抱くだろうか。支払い能力のない心神耗弱と思しき入居者たちと、それにより精神障害が重症化した私の人権、どちらが大事なのか。どうか教えてほしい。
外国人の入居拒否は日本特有の問題ではない
一応言っておくが、私の出身国では大家の権限が最も強い。大家が嫌だ、貸さない、と言ったら貸さないのだ。
私たちは日本人家族だから酷く嫌がられた。台所を使うからである。台所は大理石などでできていることが一般的で、物件所有者にとっては大切な資産だ。現地人は油物、炒め物などはほとんどやらず、パンとハムとチーズを切るくらい、しっかり料理したとしても煮込み料理程度で終わるため台所は汚れにくい。一方でアジア人は炒め物はするし、揚げ物はするし、とにかく料理を作る。文化の違いによる拒否である。
ちなみにアジアの某国出身の人々は最も家を借りることが困難で、理由は「一人で契約したにいつの間にか家族が住んでいたり、下手すると別の家族に入れ替わっていることがあるから。」これはそういうことをしてきた側が完全に悪いと私は思う。「私はそんなことしません!」と言ってもその保証がどこにあるのか。
私たち外国人にできることは現地語(これは大前提)を使い、大家と直接密にコミュニケーションし、自分たちが現地のルールを理解していることをアピールすることだ。
法の枠組みだけでは何も解消できない
弁護士先生は法の枠組み内でしか物事を語らない。
上記のような現場の実情は頭にないのだ。しかし問題解決に必要なのは法というルールと、現場の実情への理解だ。
そして入居拒否された側が「酷い扱いをされました」「納得できません」と叫ぶだけでなく、その被害者意識を取っ払い、貸す側の不安の解消に努めてあげる必要があると、私は考える。
この記事でもメンションしたが、差別というのは必ずしも嫌悪感だけからくるものではなく、本来は人間の防衛本能に由来するものであるというのが私の意見だ。
シンポジウムで紹介された外国人入居拒否の判例
実際にシンポジウムで紹介された判例はほとんどにおいて「合理的理由なく契約締結を拒絶することは許されない」「人格的利益を毀損する」「信義則上損害賠償が認められる」と入居者側に非はないと言った判決がくだっていた。
「ならいいじゃない。」そんな気がしないでもない。弁護士先生は「こんな酷いことが起こっている」という意図で判例を出してきているんだとは思うが、これは外国人が日本国の法のもと守られていることの証左に他ならない。
強いて私の体験談からコメントするとすれば「肌の色を執拗に聞かれた」事例で、これは仲介会社から「皮膚の色はなんですか」「普通の色ですか」という言葉を使われた問題について一言行っておきたい。この場合、言葉選びは超絶最悪なのだが、仲介会社の意図としては「肌の色が日本人に近い東アジア人で文化的価値観がかけ離れすぎていないか?」もしくは「先進国の出身か?」というものがあった可能性があり、上記で記したように防衛本能に由来するものであるように感じた。
最後の一例だけは「国籍又は民族性による差別を受けたが(…)これは(…)人種差別禁止法等の立法不作為に原因があるとして慰謝料を求めた事案」であったが、これに関しては請求棄却され「立法作為義務を負っているとは認められない」とした。
これに関しては私も(いくらお前はネトウヨか?と詰問されようと)棄却で正当だと思っている。この訴訟を起こしたのは在日韓国人2世の方だそうだが、人種差別禁止法で自分が何がなんでも守られるかと言ったら大きな間違いだ。すでに述べた通り、法の枠組みでなんでも解消できたらなんら苦労はない。
詳細は後述するが「いじめはやめましょう」と言っていじめがなくなるなら教育は万能なはずだし、「悪ことをしてはいけません」で事件が起こらないなら刑法も万能はずだ。しかしそうではない。死刑という極刑を持ってしても殺人事件は起こるし、道交法をどんなに整備しても交通事故は無くならない。法は万能ではないことをこの方には覚えておいてほしい。海外でありとあらゆる差別やいじめを経験・見てきた身としての忠告だ。
身体障害者への設備投資
障害者は常に支援を必要としている。それは人による支援かもしれないし、金銭的支援かもしれないし、それ以外かもしれない。私も無職になってしまったので障害者年金を申請準備中だ。
現実問題、賃貸に入居したいが設備が車椅子などに対応していないことは少なくない、というか圧倒的に多い。そこで、より多くの車椅子ユーザーが賃貸物件に入居できるようにするには何が必要か。
答えは簡単、改修工事である。
しかしこの改修工事は決して安くない。特に耐震基準などが絡んでくると丸ごと建て直しになったりして、下手すると莫大な費用がかかる。ただ住めればいいというわけではなく、安全も担保しなければならない。これを誰が支払うというのか?大家が「ダイバーシティ&インクルージョン」というお題目のもと全額負担させられたのではたまったものではない。
ここはやはり障害者年金、障害者雇用納付金同様、国や地方自治体の出番なのではないのだろうか。その金がどこから出てくるんだという問題はあるが、そういった仕組みづくりは今後の社会課題になるはずだ。
同性カップルとルームシェア
これに関しては私は当事者であったことはないのでコメントできることが少ない。
最初は消防法に関する部分もあるのかな?と一瞬思ったが、シェアハウスはその対象になるのだが、ルームシェアはただの同居なのでこれに当たらない。
パートナーシップ制度のある地域ではもっと理解が得られるかもしれないがそうでないと難しいかもしれない。
そもそもラブホテルなどでも同性、特に男性同士のカップルがお断りされるケースは読んだことはある。一方で男性同士のカップルの利用を断ったことに対し行政指導が入ったという話も読んだことはある。一般的なホテルでも
「3 宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮すること。」
と定められるようになったようである。
このテーマについてはまだまだ過渡期であると感じる部分が大きい。そもそも同性婚を認めるのか、認めるとしたら日本国憲法第24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」を改憲するのか、そういった様々な壁が立ちはだかっている。
個人的にはあまり焦らず、大袈裟な被害者感情を訴えずに、経過を見ながら現実的に何ができるかを当事者と当事者以外、地方自治体と探っていくのが良いと感じる。
引っかかったこと
これは人によっては揚げ足取りだと感じるかもしれないが、シンポジウム中、いくつかの例で「〇〇であることが理由で入居拒否されたとは伝えられなかった。でも納得していない。」という声が紹介された。
果たしてこの証言にどこまで根拠があるのか、正直疑問だった。詳しくは後述するが、これはただの疑心暗鬼であり、一度入居を拒否されたから「そうに違いない」という思い込みが働いている可能性を排除できない。
またとある不動産屋が外国人、障害者、LGBTQ+の入居者を支援する体制をとっていることを紹介していた。しかしたった一社の成功体験ではこの取り組みは広がっていかないのではと感じた。
社員に多数の外国人を雇っているそうだが、それはそれだけの人数雇える会社であるところに限られる。私がいたような零細企業では人一人雇うにしても相当困難を極めた。私とマネージャー2人合わせて、英語、フランス語、ドイツ語ができるため外国人対応もしていて、フィリピン人ご夫妻のお客様を契約を取り付けたり、突然ヘブライ語のメールが送られてきてもできる範囲でなんとか対応したり、色々したが、これは偶然私たちが外国語を使えて、外国の文化に理解があったために他ならない。ちなみにトルコ人が集団でやってきて「店舗を開きたい」と(かなり無理のある)相談に来たこともあったし、日本に出稼ぎに来た陽気なネパール人たちも入居できるところを見つけてあげた。事務所近くのマンションに入居したインド人ご夫妻はゴミ出しルールに頭を悩ませていたため、私が英語で説明書を作ってあげたこともある。零細の不動産屋でできることなんてこんな程度しかないのだ。
全体的な所感
外国人、障害者、LGBTQ+の事例が挙げられたが、今回の話に出てくる人々は全員「同じ人間」であることを意識することが必要である。「社会的障理や差別をなくそう!」と叫ぶことは簡単だが「誰かに皺寄せがいく差別解消」はサステナブルではないし、逆に不満を溜め込みヘイトを増長する可能性があることが懸念される。
一方で「外国人」として暮らしたことがある身としては、「外国人差別」とくくりにするのでなく今回のシンポジウムで登壇された不動産会社のように、「言葉の壁」「ルールがわからない」「連帯保証人がいない」等々、何で困っているのか、何が問題なのかを細かく切り分ける必要があると考える。
最後に、国交省の差別解消対応方針の不当な差別取り扱いの例にある「物件告等に審者不可などと記載」してはいけないという方針はとても表面的で、好ましいとは言えない。結局説明なしで入居を断わられ、「外国人だからに違いない」「障害のせいに違いない」と互いを疑心暗鬼にさせるだけだと思う。
#不動産 #法律 #差別 #賃貸 #入居 #外国人 #障害 #LGBT #LGBTQ #シンポジウム #弁護士会 #異文化 #海外生活
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
