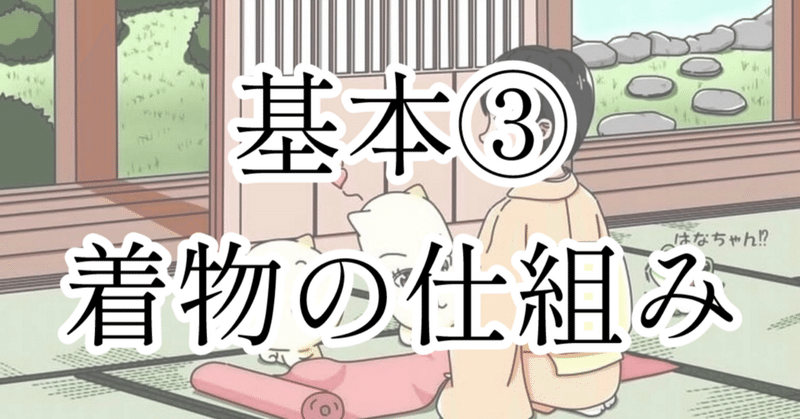
和裁のきほん③【着物の仕組み】名称と仕組みを図解
和裁の基本として知っておきたい着物の仕組み【成人女性用・長着】の紹介です。
▷▶︎このnoteを読むと分かること🍀
・着物の名称
・着物の名称の覚え方
・着物の仕組み
この二つを、じっくり絵を見て頭に入れることができます⭕️
特に着物・和裁が初めまして。の方にオススメの内容です
◯はじめに【和服と着物】

【和服】とは日本の民族衣装の総称で、洋服と分けるために生まれた言葉。
【着物】という言葉は和服を総称することもありますが、一般的には↑上図で着用の衣服を【着物】と呼び、【長着】とも言い換えられます。(着物=長着の解釈で通常は問題ない)
◯女物・袷着物の名称
着物、和裁で【目を通しておきたい15個】をご確認ください。


1 身丈 9 後幅
2 裄 10 前幅
3 袖丈 11 衽幅
4 袖幅 12 合褄幅
5 袖付 13 褄下
6 袖口 14 くりこし、衿つけ込み
7 袖丸 15 衿肩開き
8 身八つ口
※洋服と捉え方の変わる部位は【袖丈・肩幅】です。和服では袖山〜袖底にかけてを袖丈と呼びます↓

着物初めましての皆様、不安に感じる心配はありません。まずは下記2つの基本の概念を覚えれば問題ないです⭕️
①横方向が【幅】
②縦方向が【丈】
この二つだけです!
あとは衿や袖やら各パーツ名に【丈・幅】を付ければ、呼び方に相違はあっても意味は充分に伝わります⭕️

洋服では耳を切り落と、各パーツをバイアス取りする場合があるなどして、布目の縦横が分かりにくいのですが、和服はシンプルで分かりやすいのです。
解いて布の状態になっても、耳を見て・触って確認すれば丈と幅を間違えることはないでしょう。
まずは【丈と幅】。覚えてみてくださいね^^
◯着物の仕組み
「着物の仕組みと」言うと大それた事のように聞こえますが、まずは各パーツがどの様に裁断されて縫合されるのか?絵を見て想像してみることがステップアップの近道です⭕️
⬜︎全てが【直線裁断】の和裁
通常一反として売られている着物は、長さが約12mあります。

着物として仕立てる場合は8枚の部品に切り分けられます。

先の裁ち図を着物の形に倣って置いてみるとイメージが湧くのではないでしょうか。
・身頃が2枚
・袖が2枚
・衿が大小2枚
・衽が2枚 計、8枚です
これらを事前に当てがわれた【基本の寸法】に合わせて縫合すれば着物の完成です。

次回noteでは【基本の寸法】をご紹介いたします。引き続き応援宜しくお願いします🙇🏻♀️
どう縫えば良いの??
手縫いとミシン縫製の違いはこちらをご覧ください↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
