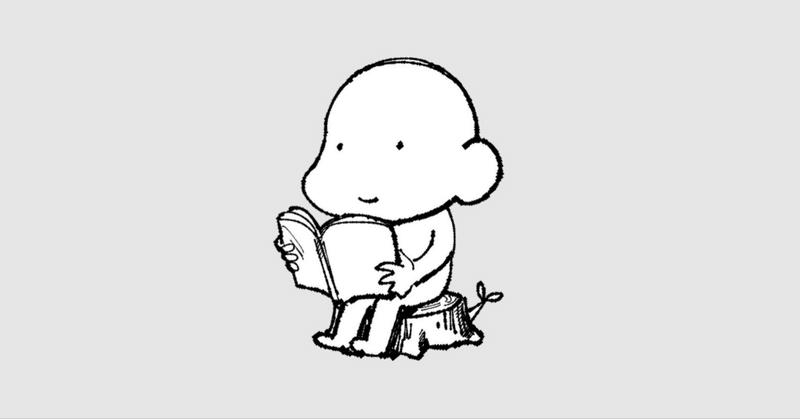
「分かる!」を書きたい
昔から設定が受け入れられない。
小説を読み出すと、
『「今日のご飯何作る?」と田端綾が言った。』
みたいな、架空の人物や世界観の設定をすぐに受け入れることが出来ない。
文字だと特にそうだ。アニメやドラマでも受け入れられない設定はあるが、ほとんどのアニメやドラマの作品は受け入れることができる。
だからこそ、小説のように設定がないエッセイが好きなのかもしれない。
主に1人の登場人物の思考が書かれているし、登場人物が出てきたとしても、実在しているものだからと、安心して受け入れることが出来る。
小説は、話の内容を理解することに頭を使う上に、設定自体を受け入れることにもエネルギーを使う。
もう小説読むなよ、と思うかもしれないが、それでも設定が自分の中に溶け込むような本を探している。
受け入れられないものには何か共通点があるのかもしれない。
共感だ!
星野源のエッセイを読んでいる今、ピンと来た。
ガチガチに設定を作られたものは、現実とかけ離れすぎていて、読んでいて全くイメージがつかない。
現実と離れている方が現実逃避できるからいい、という人もいるのかもしれないが、どうやら私は共感するかどうかを軸に本を選んでいるのかもしれない。
だからこそ、共感を得られるんじゃないかと思う記事を書けたときにこそ、満足感がある。
これは本選びに留まらないということにも気づいた。
本選びと友達選びは似ている。
相手が話していることを理解出来なければ、共感もできないし、共感し合える話がないのなら私たちの感性は違うのかもしれないな。と思ってしまう。
よく、人によって話す話題を変えるという人がいるが、それを聞いてあまりピンとこなかった。
なぜなら私は、友達と言える友達に全てのジャンルを話しているからだ。
1つでも話したいジャンルが相手に話せないと、なんだか穴が空いたまま話している気になるのだ。
あれ話したいけど、できないなぁ。この子にはできないよ。下ネタなんて話せない…。
と思っていると、本当の自分じゃなくなっていく気がするのだ。
今まで話してなかったジャンルを持ち出すのって勇気がいる。
だから手探りで新ジャンルを恐る恐る話そうとするのだが、やっぱり反応が薄かった。
こんな話しなければよかった…!大事な友達だったのに。
謎の自己嫌悪に陥り、古参の友達にこのことを話す。
結局この繰り返しだ。古参の友達とは何でもかんでも話せるからこそ、相手の話も共感できる。
何の話か分からなくなったけど、これが共感して貰えたら嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
