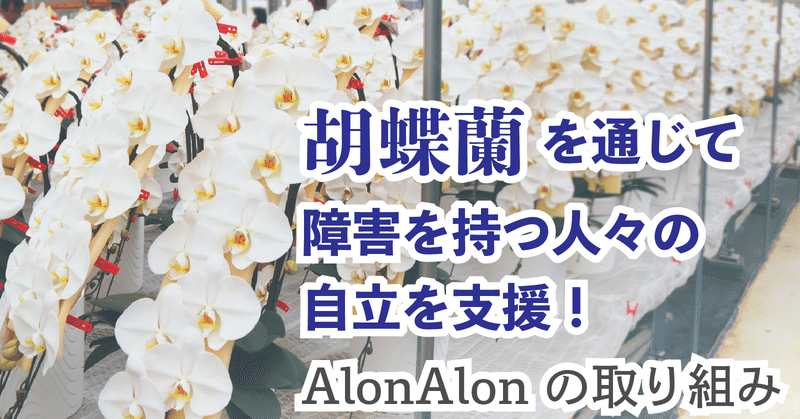
胡蝶蘭を通じて障害を持つ人々の自立を支援! AlonAlonの取り組み
おつかれさまです、鶴橋です。
今回はデジマケ女子部番外編! 会社を飛び出して外に取材に来ました。

ここは千葉県富津市にある
「AlonAlon(アロンアロン)オーキッドガーデン」。
最寄駅はJRの大貫駅で、そこからバスと徒歩で15分の場所にあります。

大きなビニールハウスの中では、贈答用の胡蝶蘭が苗から丁寧に育てられています。アイビーシーがお花を贈るときにはいつもこちらの通販を利用させていただいています。
このオーキッドガーデン、ただの農場ではありません。本日は、こちらを運営するNPO法人AlonAlonの髙橋さんに案内していただきました。

AlonAlonオーキッドガーデンは「就労継続支援B型事業所」にあたり、知的障害を持つ人々と職員が働いています。
みなさんが想像される一般的な障害者支援施設とは大きく違うかもしれません。ここでは障害者の方と職員の区別がつかないくらい、全員が活き活きと働いているんです。
本日は皆さんが働く様子と、支援の輪を広げていくための仕組みについてご紹介したいと思います。

よろしくお願いします!

アイビーシーも、このような AlonAlon の取り組みに賛同し、障害を持った方々の一助になればと、胡蝶蘭を贈る際には AlonAlon で購入をしております。就任祝や移転祝等、お取引様へ胡蝶蘭を贈る企業様も多いかと思います。そんな大切な方へ贈るお花だからこそ、意味のあるお花にしてみてはいかがでしょうか?
AlonAlon でお花を購入していただくと、その代金が AlonAlon で働く障害をもった方々の所得となり、社会貢献活動に簡単に参加することができます。胡蝶蘭を贈る機会がある際はこの記事を思い出していただけると幸いです。

全ての商品に「障害者の自立支援活動に貢献しています」と記載のある AlonAlon オリジナルステッカーがついています。
AlonAlon フラワープロジェクトの全ての商品に「知的障害者支援活動に参加しています」と記載のあるステッカーを貼っていますので、特別な広報活動をしなくても社内外に「伝わる・見える CSR 活動」ができます。

はじめに:『障害者に月収10万円を』
身体や脳に障害があり一般企業で働くことが難しい方々は、どのように働いてどのように収入を得ているのでしょうか。
厚生労働省が定める障害者総合支援法では、障害を持つ方が働くことを後押しするためのサービス「就労移行支援」「就労定着支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」を提供しています。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html)

これらの支援サービスから一般企業への就職を実現した人数は毎年増加しており、令和元年では初めて2万人を超えました。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000760686.pdf)
しかし、就労移行支援サービス利用者のうち55%が企業等へ就職出来ているのに対し、就労継続支援A型からの就職は利用者の25%、B型では13%にとどまっています。
就労継続支援A型とB型は、どちらも企業就職(一般雇用枠で働くこと)が現状困難な場合に、個人のペースに合わせて就業訓練や仕事を行うことができるようにする支援です。この2つの一番大きな違いは「雇用形態を結ぶか、結ばないか」です。
雇用形態を結ぶA型では最低賃金以上の給料が保証されていますが、B型で得られる収入は軽作業(手工芸、農作業、クッキーをはじめとするお菓子作り など)に対する成果報酬となり、最低賃金の額を下回っていることがほとんどです。
令和3年のB型事業所の全国平均工賃は月額16,507円です。時給に直すと233円。これでも前年よりは4.6%増となっているようですが、とても自立して生活出来るレベルには達していません。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001042285.pdf)
先述のとおり、一般就職への移行例も一部はありますが、ほとんどは軽作業等の就労を継続させることが精いっぱいであるのが現状です。
令和5年(2023)版障害者白書によると、知的障害を持つ方は全国で約109万4000人。
(参考:https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r05hakusho/zenbun/pdf/ref.pdf)
日本全国の人口(1億2456万人)から計算すると1000人に8.7人です。
重度・軽度の差はあれど、ざっくり四捨五入しておおよそ100分の1と考えると、意外と身近だと思えるのではないでしょうか。将来自分自身の大切な人が、あるいは近しい会社の人の家族が、そのような特性を持って生まれてくるかもしれません。
いつか自分が年老いたり、世を去ったりして面倒を見られなくなっても、わが子の過ごす未来が開けたものであってほしい。既存の日本の仕組みでは一定の生活を過ごすための収入が得られない。
贅沢ができるほどではなくても明るい暮らしをするための収入を得る仕組みを、どうにか作れないだろうか?
そんな思いを持った障害のある方々の保護者が中心となり、『障害者に月収10万円を』を目標としてできた団体がNPO法人AlonAlonです。

企業とWin-Winになれる仕組みで社会全体に貢献
一定の利益を得られる障害者就労の仕組みのため、商材として注目したのが、単価が高く販売価格が安定していて、企業が購入することが多い胡蝶蘭でした。

法人向けの贈答用のイメージが強い胡蝶蘭。
東南アジア原産のこの花が日本に入ってきたのは明治時代で、イギリスから渡ってきたそうです。寒冷期のある日本で南国出身の花を育てるためには、温度管理を徹底し、栽培方法にも気を配らなければなりません。
このため量産が難しく、胡蝶蘭は上流階級向けの珍しい高級花として定着していきました。
現在ではビニールハウスでの徹底した温度管理のもと、年間を通して鮮度の高い胡蝶蘭を安定的に生産できるようになっています。
AlonAlonの胡蝶蘭栽培では、段ボール箱を組み立てたり支柱の針金を曲げたりする単純な作業から、花の茎を支柱に合わせて曲げたり、花が咲いた苗を鉢に上げて見た目を整えたりする繊細な作業まで、様々な難易度の仕事があります。施設に入所した人はまずは簡単な作業から仕事を覚え、次第に難易度の高い作業もできるようになっていきます。
AlonAlonの仕組みの特別なところは、そうして栽培の技術を学んだ人が企業に就職できることです。形式としては「胡蝶蘭栽培の研修出向社員」という形になります。
ご存知でしたか? 障害者法定雇用率は2023年から順次引き上げに!
厚生労働省は、障害者が社会の中でともに働きやすい環境を作るための仕組みとして「障害者法定雇用率」という値を定めています。社員数が一定以上の規模の企業は、社員の全体数のうち何%かは障害者を雇用しなければなりません。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201963.pdf)
雇用すべき人数は企業の規模や事業主区分、雇用する障害者の障害の種類や障害の程度によって変わります。例えば、常時雇用の社員数が400名の民間企業の場合、10名の障害者を雇用しなければなりません。
詳しくは上記のパンフレットのPDFを参照してみてくださいね。
この法定雇用率を達成できていない企業は、代わりに「障碍者雇用納付金」という一定の金額を支払わなければいけません。この納付金は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に収集され、雇用率を達成している事業主に対する助成金等として再配布されます。
上記の例の企業の場合、納付金として年間600万円(月額5万円×12ヶ月×10名分)を支払うことになります。
この企業がAlonAlonのメンバーを社員として雇用し、その方が研修出向という形式でAlonAlonに出向して自社利用のための胡蝶蘭を育てるとすると、「障害者法定雇用率」を達成した上、社会貢献活動にもなり、企業にとって大きなメリットとなります。
また、AlonAlonで働く人々にとっても、環境を変えずに企業就職が叶うことは大きなメリットです。
こちらはAlonAlonから企業就職を叶えた方のインタビュー動画です。
本人の思い、採用した企業の方の思い、ご家族の思い。
これら全てに寄り添うことができ、さらに長期的な持続や将来性も望める仕組みとなっています。
AlonAlonの胡蝶蘭が育つまで
それでは実際に栽培施設を見ていきましょう!

AlonAlonでは、台湾から入荷した胡蝶蘭の苗を約半年育て、製品として出荷しています。
ビニールハウスの地面は土ではなくコンクリートの埋め立てになっていました。土から虫が入ってくると、苗や花がかじられてしまうためです。胡蝶蘭はお祝い品として送られることが多いため、細かな傷もついてしまわないように慎重に・丁寧に育てられています。
ひとつのビニールハウスで育つ苗は5000本。
胡蝶蘭用のハウスは2基あるので、1年で2サイクル回すと年間で20000本の胡蝶蘭を出荷できる計算になります。

こちらは入荷から約4か月ほど育てられた苗です。芽が長く伸びていますね。胡蝶蘭の芽は一鉢から複数本出ますが、一番元気な1本だけを残してトリミングされます。
伸びた芽の隣に芯を立てて専用のクリップで留め、まっすぐ上に伸びるように矯正します。

こちらでは伸びた茎をカーブさせる作業をしていました。


この作業が一番難しいんです!
無理にカーブさせようとすると、せっかく何か月もかけて育てた茎が折れてしまうこともあります。
絶妙な力加減が必要な職人技です。


根に近いほうのつぼみから順番に花が咲いていきます。先のほうまで満開になる前に出荷します。

咲いた花の後ろにはウレタンのクッションを敷いていきます。これは花を真正面に向かせるための矯正で、これをしないと花の向きがばらばらになり、隙間がスカスカ空いているように見えてしまうそうです。こんなところまで考えられているんですね。

こちらは仕上げの工程です。フラワーベース(鉢)に胡蝶蘭を入れていく作業です。
贈答用胡蝶蘭には3本立て、5本立て、10本立てなどがありますが、先述したように胡蝶蘭の芽は苗ひとつあたり1本だけにトリミングされています。フラワーベースに入れる苗のポットの個数を変えることで、何本立てに仕上げるかを自由に調整できるのです。

フラワーベースの中に2本目の苗を入れて、

高さや向きのバランスを見る。
ベースの底にはポットのおさまりを良くするための発泡スチロールの土台が置いてあります。また、せっかく整えたバランスが運送中にずれてしまわないように、ポットとポットの間には発泡スチロールの切れ端を隙間なく詰めています。

3本立ての胡蝶蘭は、真ん中が一番高く、端は低くなっています。
さらに5本立ての場合、中央と端以外の2本は少しだけ芯を曲げる必要があるんです。
正面から見たときに綺麗になるように、満足がいくまでバランスを調整していきます。

贈り物として頂くお花は美しければ美しいほど嬉しいもの。仕上がりを高めるためのこだわりの作業ですね。
AlonAlonの新たな取り組み
最後にマンゴー農園を案内していただきました。
胡蝶蘭と同様に単価の高いマンゴーは、AlonAlonの新たな主力商品とするために数年前から専用のビニールハウスで育てているといいます。栽培を始めて3年、今年ようやく実を収穫できるほど大きくなりました。

今年は木がまだ成長途中であることと、栄養を集中させてより甘くするために、1本の木につく個数を3個に厳選しているそうです。来年、木がもっと大きくなれば、より多くの個数を収穫できるようになります。

大きいですね!!

実が重くなってくると、地面に落ちないよう実ひとつひとつにネットをかけていきます。
実が枝から外れるまで熟してネットの中に落ちたら収穫し、追熟させ、出荷するための準備に入ります。
マンゴー農園では、将来的にIoTの導入を検討しているとのことです。
センサー付きのドローンで実のなっている木を探す
実を見つけたら糖度センサーを使って糖度を測定し、収穫の頃合いを計算する
採り頃の実の位置をマップに表示させることで、今日はどれを収穫すればいいのか一目でわかるようになる

ベテランの農家の方が長年の経験値で測っていた収穫のタイミングをコンピューターで計算してもらうことで、障害のある人でもノウハウの少ない職員でも誰でも最高のタイミングで収穫ができるようになります。
ITの進化が仕事におけるハードルを無くし、の生活を支えていくのです。

見学を終えて
お花を購入するだけで社会貢献につながるAlonAlonのフラワープロジェクト。これからも活動の輪がさらに広がることを願っています。

髙橋さん、本日はありがとうございました!

最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の取材は、私個人としても大変勉強になりました。ビニールハウスで作業をする皆様のいきいきと働く様子が今でも印象に残っています。
お花を購入するだけですぐに社会貢献活動に繋がるので、多くの企業にこの活動の輪が広がるといいなと思いました!
また、アイビーシーではこの他にも様々な社会貢献活動に取り組んでいます。詳しくはこちらのページをご覧ください!

それではまたお会いしましょう。
鶴橋
