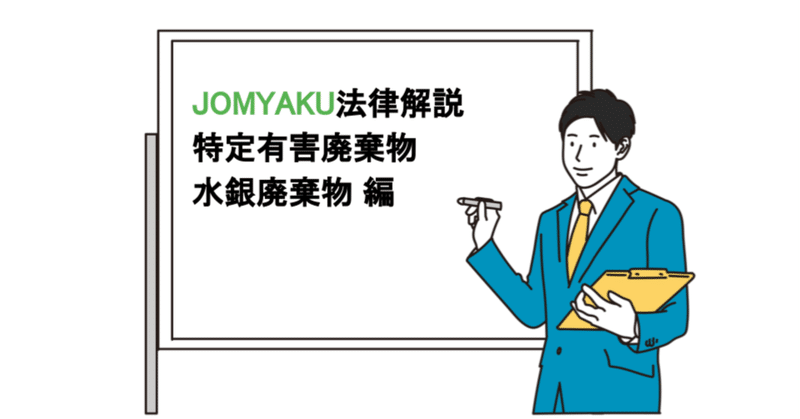
【廃棄物処理法解説】特定有害産業廃棄物3 ~水銀廃棄物編~
皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回は特定有害産業廃棄物の1つである水銀廃棄物について解説していきます。
水銀とは?

水銀は常温で液体であるただ一つの金属です。
体温計、血圧計の医療用器具や蛍光灯、水銀灯、電池などなど幅広い分野で使用されていました。
秦の始皇帝が不老不死の薬として水銀(赤色硫化水銀)を飲んでいたとも言われています。
水俣病の発生と水俣条約
水俣病は、熊本県水俣湾周辺で工場排水中のメチル水銀に汚染された魚介類の食物連鎖によって生物濃縮し、この汚染された魚介類を摂取したことにより起こったメチル水銀中毒です。
四大公害病の1つであり公害の原点とも言われています。
新潟県阿賀野川下流域でも水俣病と同様の症状が確認されたため、第二水俣病、新潟水俣病と呼ばれています。
1956年(昭和31年)に水俣保健所が原因不明の奇病発生を公表し、これがのちに水俣病の公式確認となりました。水俣病は主に脳など神経系を侵し、手足のしびれ、ふるえなど様々な症状を引きおこします。
また、母親の胎内でメチル水銀に侵され、障害を持って生まれた胎児性水俣病患者も発生しました。
水俣病患者は1969年(昭和44年)に制定された公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(旧救済法)及びその後継となる 1974年(昭和49年)に施行された公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)に基づき補償が行われました。
その後、公健法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者としその救済を図ること、また水俣病問題を最終解決することを目的とした水俣病救済特別措置法も2009年(平成21年)に成立しました。
なお、公健法に基づく被認定者数は2020年10月末までで2,998人、水俣病被害者救済特措法に基づく救済措置には64,836人が申請し、一時金等対象該当者は32,249人、療養費対象該当者は6,071人となっています。
2017年(平成29年)8月16日に水銀に関する水俣条約(水俣条約)が発効されました。
これは、2001年(平成13年)国連環境計画(UNEP)が地球規模の水銀汚染に係る調査活動を開始したことがきっかけとなったもので、水銀および水銀化合物によって引き起こされる健康、および環境被害を防ぐために水銀の採掘、貿易、製品や製造プロセスへの使用、排出等の規制等を定めた条約です。
同日には水俣条約を担保するための国内法である水銀汚染防止法が施行されています。
2013年10月に熊本市、水俣市で開催された外交会議で条約を採択“水銀に関する水俣条約”と命名されました。
水銀廃棄物の分類と処理
水俣条約の発効に伴い廃棄物処理法も改正され2017年(平成29年)10月1日から水銀を含む廃棄物の取り扱いが変わりました。

上記の方にある廃水銀等、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物が法改正により新たに加わったものです。
水銀を一定以上含んでいるもの、または水銀使用製品産業廃棄物の一部に水銀回収が義務付けられていることに注意が必要です。
回収が義務付けられている廃棄物の中間処理方法は、ばい焼またはその他加熱工程により発生する水銀ガスを回収する設備で処理をしなければなりません。
また、廃水銀等を埋立処理する場合は、その前処理として硫化及び改質硫黄による固型化をすることが義務付けられています。
処理委託契約書、マニフェストについても水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が委託する産業廃棄物に含まれる場合は、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれていることを明記することが義務付けられています。
●デジタル配車サービス「まにまに」
