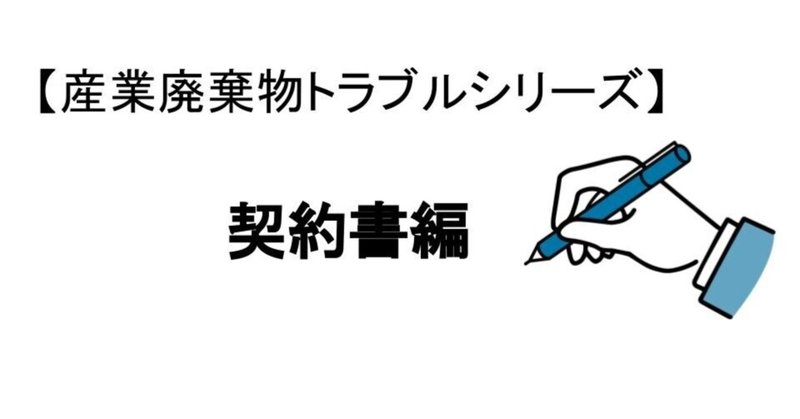
産業廃棄物のよくあるトラブル「契約書編」
皆さんこんにちは!元産廃ドライバー兼営業マンの宮尾です!
今回は産業廃棄物のよくあるトラブルシリーズ「契約書編」について書いていこうと思います。
10年以上産業廃棄物業界に関わってきましたが、契約書に関するトラブルはマニフェストと同じくらい多く見てきました。近年では電子契約が徐々に浸透しつつあり、紙ならではのトラブルは少しずつ減っているかと思いますが、それでも紙の契約書の普及率は圧倒的です。未だに多くのトラブルがあると思いますので、参考になれば幸いです。
委託期間の記載ミス
工場から排出されるような産廃の委託契約書は自動更新になっているものが多く、委託期間は1年間の日付を記載します。本来であれば、
「2022年4月1日〜2023年3月31日」
という記載が正しい自動更新の契約書の委託期間になります。
しかし、先方担当者が慣れていない場合、
「2022年4月1日〜2023年4月1日」
と記載されてしまうことがあり、こうなってしまうと作り直しもしくは訂正印等での対応が必要になってきます。
回収日に契約書が間に合わない
廃棄物を回収するまでの流れは、
①見積もり→契約締結→回収日調整→回収
となりますが、排出事業者側の都合、運搬業者側の都合、処分業者側の都合、商社の都合など、さまざまな要因により、
②見積もり→回収日調整→契約→回収
となることがしばしばあります。
回収日に契約締結できていれば何の問題もないのですが、②の手順で進めてしまうと、回収日当日に契約が間に合わないのでは?という事態に陥る可能性があります。
そういう場合は営業がハンコをもらうために1日中車で駆け回るということをしたりします(笑)
近年の処分場は契約締結できていないと運搬させてもらえないところも増えてきましたが、契約未締結状態で運搬し、後日契約書を巻くという会社もまだまだ耳にすることはあります。
許可証の製本ミス
産業廃棄物の委託契約書には該当の都道府県の許可証を添付して製本することが一般的です。
しかし、品目が多かったり、排出場所、降ろし場所が多数になると添付する許可証も多くなり該当の許可証を添付し忘れたりして、再度契約を作り直すこともあります。
自社の押印だけしている状況で分ければいいのですが、これが両社の押印が済んだあとですと、再度押印手配をするなどもう一手間かかります。
収入印紙の金額ミス
産廃の委託契約書は基本的には印紙税法上の1号文書もしくは2号文書に該当します。
契約金額は、運搬契約であれば、年間で予定している「回収回数×単価」
処分契約であれば、「年間排出予定数量×単価」で算出することができ、その金額に応じて印紙額が決まります。
その計算を間違ってしまう場合もあれば、印紙はすべて200円でOKと思っている方もいらっしゃいました。
その他にも各社約款について修正するうちにどのデータが正しいのかわからなくなってしまったり、細かいものを含めるともっとあると思います。
電子契約導入を進めることで、郵送の手間や印紙が不要になるのでぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
▼JOMYAKUサービスページ
