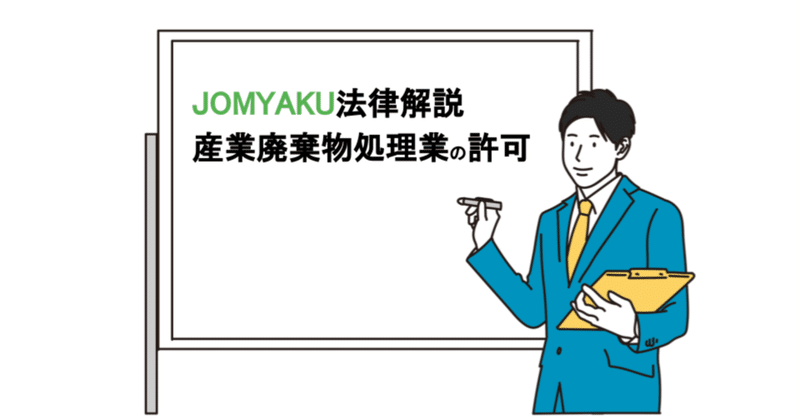
【廃棄物処理法解説】産業廃棄物処理業の許可
皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回は産業廃棄物処理業を営む上で必須のアイテムの“許可”をテーマに解説していきます。
産業廃棄物処理業許可
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可は収集運搬業許可と処分業許可の2つに分かれます。
この許可は後述するする15条施設の許可との対比で14条許可、業の許可と呼ばれることがあります。
収集運搬業許可は(特別管理)産業廃棄物の積卸しを行う区域(都道府県)の許可が、処分業許可は施設を設置する場所の都道府県または政令市(中核市)の許可が必要になります。
積替・保管を含まない収集運搬業は申請書、添付書類を用意し都道府県の所管部署へアポを取って申請をすれば審査を経て許可証を取得できます。
審査期間は標準60日ですが、都道府県によってはより長い場合もあります。
また、積替・保管を含む収集運搬業や処分業については、前述のとおりに所管部署へアポを取って申請できるというわけではなく、事前協議を求める自治体が大多数です。
事前協議では設置予定の施設や施設建設予定地に関すること等が資料として求められ、廃棄物処理法以外の法律に関する手続きなども精査されます。
許可を取得した後もメンテナンスが必要で、会社名、本社住所、役員の変更や運搬車両の増減などに関しては変更届出書を提出する必要があります。
許可が不要となる場合もあります。
専ら物(古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う場合、環境大臣の認定(再生利用・広域的処理・無害化処理)を取得した場合などが該当します。
話が脱線しますが、最近環境省より解釈の明確化を図る通知が出されましたので興味のある方は下記リンクよりご一読ください。
『環循適発第2302031号・環循規発第2302031号専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)』環境省
産業廃棄物処理施設
特定の廃棄物や処理方法、処理能力により産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になる場合があります。
これらの施設はいわゆる15条施設と呼ばれるもので、生活環境影響調査(ミニアセス)の実施や建築基準法51条但し書きによる都市計画審議会の決定を受ける必要があるなど産業廃棄物処分業許可よりも難易度と提出書類の厚みが一気に跳ね上がります。
どのような施設が15条施設に該当するかは、下記のリンクを参照してください。
世間で廃プラスチック類の5トン/日未満の処理能力の破砕施設をよく見かけるのは、15条施設の要件を回避し速やかに事業を開始したい処理業者の苦肉の策と言えるでしょう。
参考『15条許可が必要な施設について』埼玉県
許可を必要としない特例制度
廃棄物処理法では許可を必要としない特例制度が存在します。
簡単ではありますが触れていきます。
許可が不要となるといいつつ、広域認定では処理施設の設置の許可は必要になるので特例制度に挑戦される方は十分ご注意を!
1.再生利用認定制度
廃棄物の減量化を推進するため、一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度です。
認定を受けると処理業及び施設設置の許可を不要となります。
対象となる廃棄物は環境省告示で決められており、廃ゴム製品、廃肉骨粉、コークス及び炭化水素油の製造を目的とした廃プラスチックの再利用などが認定を受けています。
参考『産業廃棄物再生利用認定制度の認定状況』環境省
2.広域認定制度
製品を製造しているメーカー等が、製品が廃棄物になった際に広域的に処理を行うことで、効率的な再生利用等の推進や廃棄物の減量、適正処理を確保することを目的とした制度です。
情報処理機器、自動二輪車、住宅設備機器などなど多様な廃棄物が認定を受けています。
参考『産業廃棄物広域認定制度の認定状況』環境省
3.無害化処理認定制度
従来の無害化処理である1,500℃以上での溶融以外の1,500℃未満で他物質との混合溶融処理等を促進し廃石綿や石綿含有廃棄物の不適正処理等を防止し、無害化処理を促進するために設けられた制度です。
後に低濃度PCB廃棄物に関しても無害化処理認定がなされるようになりました。
参考『廃棄物処理法に基づく石綿含有廃棄物等無害化処理認定施設』環境省
『廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設』環境省
最後に許可証についての注意点に触れたいと思います。
ITが発達しツールも充実している昨今、許可証の偽造がたまにニュースになります。
過去には画像編集ソフトを利用して許可の有効期限等の日付、許可品目の改ざんや許可証そのものを偽造した事例がありました。
許可証の写しを取り寄せた際には、許可証を発行している自治体のwebサイトで公開している業者名簿を念のために確認することをお勧めします。
●デジタル配車サービス「まにまに」
