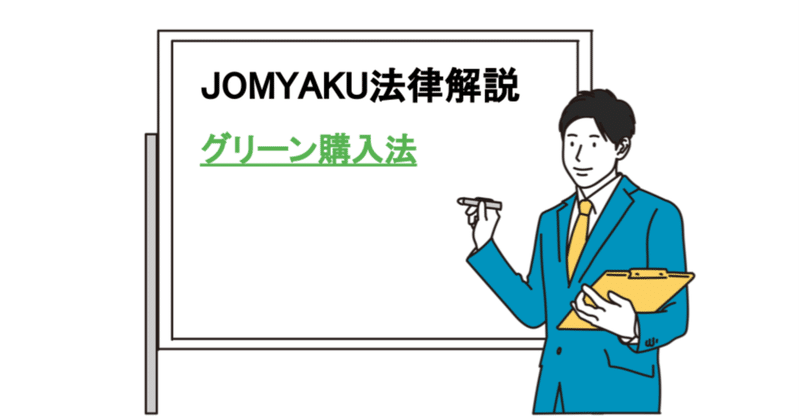
JOMYAKU法律解説シリーズ 第11回 グリーン購入法
皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回はグリーン購入法について解説していきます。
制定までの背景
グリーン購入とは、製品やサービスを購入する前に必要性を熟考し、環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。
持続可能な発展による循環型社会の形成を目指すには、供給面だけでなく、需要面からの取り組みも重要であることから、国等が自ら率先して環境負荷の低減に寄与する製品やサービスを優先的購入し、その市場を促進することを目的としてグリーン購入法が平成12年(2000年)5月に制定、翌年の4月より施行されました。
なお、環境負荷の低減に寄与する製品やサービスのことを法律では環境物品等と呼んでいます。
概要
1.国、地方公共団体の責務

グリーン購入法における国や地方公共団体の責務は、上の表のとおりとなっています。
国や国会、各省庁等の各機関については法律の目的からグリーン購入は義務となっていますが、地方公共団体については努力義務となっていることが異なっています。
事業者、国民の責務についても法律にはありますが、 できる限り環境物品等を選択するよう努めると書かれるに留まっています。ですが環境に対して関心の高い大企業ではこの法律に基づいてグリーン購入を推進している例も見受けられます。
2.特定調達品目
重点的に調達を推進すべき環境物品等の分野・品目のことを特定調達品目と呼びます。
2022年2月現在で、22分野285品目の特定調達品目があります。
特定調達品目は製品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて適宜見直しがされることになっています。
下の表が特定調達品目の22分野になります。

22分野の各品目については割愛しますが、興味のある方は下記のリンクよりご確認ください。
意外なものが特定調達品目になっていて結構楽しいですよ。
参考 『特定調達品目及び判断の基準等の改定一覧』グリーン購入法.net
また、各品目については 判断の基準 が定められており、その基準を満たすものを購入しなければなりません。
3.エコマーク
22分野285品目に及ぶ特定調達品目をどれがグリーン購入法に適合しているかを調べるのは大変です。
そこで、グリーン購入法に適合しているかどうかを簡単に確認することができるものが エコマーク になります。
エコマークは、商品の生産から廃棄までのライフサイクル全体を考えた認定基準が策定され、多くの商品分野でグリーン購入法の判断の基準に対応しています。
エコマークとグリーン購入法の特定調達品目の対応表は公開されていますので下記リンクより参照してください。
参考『2022 年度版エコマークとグリーン購入法調達品目パンフレット 』公益財団法人日本環境協会
エコマーク事務局またグリーン購入法適合商品については、グリーン購入ネットワーク(略称GNP)が運営するえこ商品ネット でも検索できます。
GNPはグリーン購入に率先して取り組む企業、行政民間団体等の緩やかなネットワークとして1996年に設立された組織です。
4.グリーン契約法(環境配慮契約法)
略称にグリーンが付く法律がもう1つあります。それはグリーン契約法です。環境配慮契約法とも呼ばれています。
グリーン契約法は、製品やサービスを調達する際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、温室効果ガスの削減やその他環境への負荷低減に配慮した契約を促し持続的発展が可能な社会を目指す法律です。
グリーン購入法と同様に国やその機関については義務、地方公共団体には努力義務を課しています。
また、グリーン契約法の対象分野は以下の7分野になります。
電気の供給を受ける契
自動車の購入及び賃貸借に係る契約
船舶の調達に係る契約
ESCO事業(省エネルギー改修事業)に係る契約
建築物の設計に係る契約
建築物の維持管理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約
①から の分野に関しては政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画(政府⑤実行計画)の温室効果ガス総排出量の約90%に関係しているといわれています。
今回はグリーン購入法についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
今回を持ちましてJOMYAKU法律解説シリーズは一旦終了となります。
皆さんの環境法への理解の一助になれば幸いです。
●デジタル配車サービス「まにまに」
