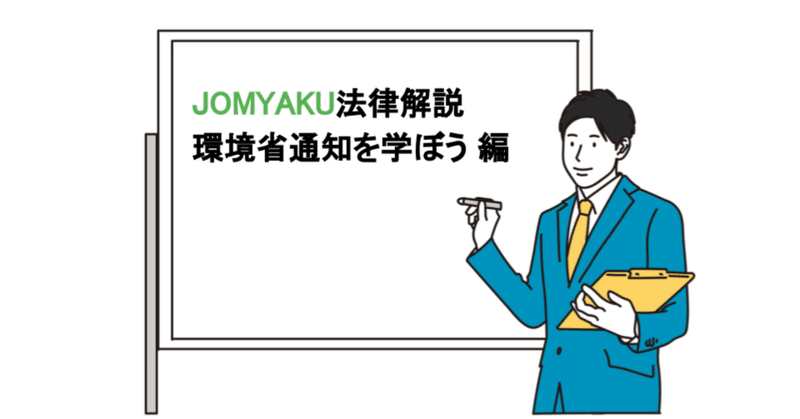
【廃棄物処理法解説】環境省通知を学ぼう『油分を含むでい状物の取扱いについて』
皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回は『油分を含むでい状物の取扱いについて』について解説します。
『油分を含むでい状物の取扱いについて』についてとは?
この通知は昭和51年に発出されただいぶ古いものです。
当時は環境省が存在していないので環境庁と厚生省の担当部局の連名で発出されています。
産業廃棄物処理業界で「油分5%以上だから廃油!」というような突飛な話を聞いたことはないでしょうか?そのような話の元となっているのが本通知と思われます。
余談になりますが、本通知本文に「なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。」という文言がありません。
これは2000年4月の地方分権一括法、改正地方自治法施行までは廃棄物行政は機関委任事務と言って国から委任され、国の機関として処理する事務とされてきました。
国の機関として処理することから中央官庁と都道府県の間には上下関係が存在し、当時の通知は中央官庁から地方自治体への指導的な意味を持ちました。
地方分権一括法、改正地方自治法施行により機関委任事務は、法定受託事務と自治事務に分類され自治体の事務となり中央官庁と都道府県は対等平等の関係となったことから通知についても指導から”技術的な助言”に変化したのです。
概要
通知のタイトルそのまま”油分を含むでい状物”(以下「泥状物」)の取り扱いについて書かれています。
通知自体も文章にして20行にも満たない短いものなのですが、行政独特の言い回しを端折って引用します。
1 産業廃棄物分類上の取扱い
(1)油分をおおむね5%以上含む泥状物は汚泥と廃油の混合物として取り扱う
〔例示〕
・石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまった泥状物
・廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土
・廃油処理のための遠心分離施設から生ずる泥状物
(2) (1)に示す汚泥と廃油の混合物に該当しないものは、汚泥(油分を含む汚泥) として取り扱う
〔例示〕
・ガソリンスタンドから生ずる洗車汚泥、
・油水分離施設から生ずる汚泥、
・含油廃水処理に伴い生ずる汚泥
〔注意書き〕
(1)の汚泥と廃油の混合物の中の油分を抽出、分離等により除去した結果、汚泥と廃油の混合物に該当しなくなった泥状物は、汚泥(油分を含む汚泥)として取扱う
2 埋立処分の方法
(1) 汚泥と廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、焼却設備を用いて焼却しなければならない。
(2) 汚泥(油分を含む汚泥)の埋立処分を行う場合には、廃棄物施行令第六条第一号に定める汚泥に関する基準に適合する方法によらなければならない。その際特に次の点に留意すること。
ア 当該汚泥をそのまま又は脱水のみを行った後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
イ 当該汚泥の性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚泥をそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによっては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。
1(1)の”油分をおおむね五%以上含む泥状物は汚泥と廃油の混合物として取り扱う”が本通知の眼目です。
混合物なので許可証も汚泥と廃油の許可がある業者、契約書、マニフェストも汚泥と廃油の記載が必要になります。
ここから派生する言説として”油分が“5%以上あるから廃油として取り扱う!”とか” 廃油と〇〇との混合物だ!” というものが散見されますが、本通知ではあくまでも”油分をおおむね五%以上含む泥状物は汚泥と廃油の混合物” として取り扱うことを定めているものですので、前述のような突飛な言説に惑わされず必要であれば管轄する自治体に確認することをお勧めします。
また、続いて埋立処分の方法として汚泥と廃油の混合物は焼却してから埋立処分すること。汚泥(油分を含む汚泥)を埋立処分する場合の注意事項が書かれています。
〇廃油との混合物
廃油との混合物でよく話題になるのが油付着のウエスです。
公開されているQ&Aがあるので紹介します。


油付着ウエスや軍手はウエスや軍手が合成繊維の場合は廃油と廃プラスチック類の混合物、天然繊維の場合は廃油と繊維くずの混合物となります。大阪府のFAQでは”油が滴り落ちる程度”付着していれば混合物に該当するという具体的な判断基準が示されています。
油付着のウエスには今回紹介した通知は適用されないと丁寧に注意書きがされています。
大阪府内でも突飛な説を唱える人がいたのかもしれません。
●デジタル配車サービス「まにまに」
