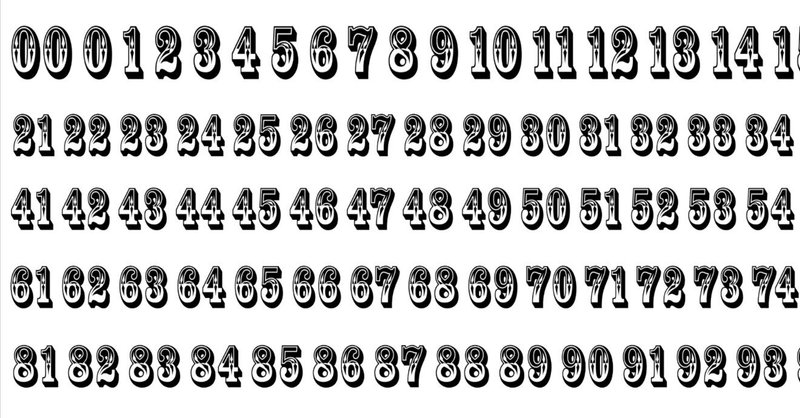
プロ野球背番号の話7番
左打者の番号
前回の予告で「今回の裏になると思う」と言ったのは、こういうことです。背番号6が「右打者の番号」というイメージが強いのに対し、今回のテーマである背番号7は、明らかに「左打者(あるいはスイッチヒッター)の番号」と言いたいですね。
実際、昨年(2022年)の例を挙げると、空き番号だった巨人、日本ハム、右打者だった広島(堂林翔太)、ヤクルト(内川聖一)を除いた8球団で左打者(あるいはスイッチヒッター)が7番を着けていました。ではなぜ今年の例を挙げないかと言うと、オリックスで吉田正尚→空き番号、阪神で糸井嘉男→ノイジー(右打者)、巨人で空き番号→長野久義(右打者)、日本ハムで空き番号→松本剛(右打者)と右打者の比率が大幅に上がったからなんですけどね(汗)。もっともヤクルトの内川聖一→長岡秀樹(左打者)というケースもありますが。
まあ、これからどう転がっていくかはわかりませんが、まずは各チームについて左打者という視点をメインに語っていこうと思います。
レジェンド・福本豊
昭和からの野球ファンの中には、背番号7といえば上掲の「左打者」以外に「瞬足」「外野手」のイメージが強い人が多いと思います。そのイメージに大きく貢献したのが、「ジャイアンツV9時代のトップバッター」柴田勲(この方はスイッチヒッターですけど)とこの福本豊(阪急)のツートップです。
背番号を40から7に変更した1972年に「年間106盗塁」を記録。これは二年後の1974年にMLBのルー・ブロック(119盗塁)に塗り替えられるまでの世界記録であり、1983年には同じくルー・ブロックの記録を塗り替える「通算939盗塁」を記録。最終的に「通算1065盗塁」まで記録を伸ばし、これは1992年にリッキー・ヘンダーソンに破られるまでの世界記録でした。このことから「世界の盗塁王」の異名をとり、世界記録を更新した1983年には当時の中曽根康弘首相より国民栄誉賞の打診を受けるも、「そんなもんもろたら立ちションできへん」との秀逸なコメントと共に固辞しています。
もちろん上記の盗塁記録は日本記録であり、「13年連続盗塁王」と共に未だに破られることのない記録として語り継がれています。
また、現在主流となっている「クイック投法」は、当時南海ホークスの捕手だった野村克也が、福本の盗塁対策として進化させたものです。
もちろん、福本本人が「塁に出なけりゃ盗塁はできへん」と言うように、盗塁だけの選手ではありません。「通算安打2543」で名球会入りしているだけでなく、「通算三塁打115」も日本記録です。しかも昭和当時の狭い球場での記録ですから、現在の広い球場だとどれだけ記録を伸ばしたのか興味深いです。
また俊足を生かした外野守備にも定評があり、本来なら左中間や右中間を抜けるような打球でも容易に追いつく広い守備範囲を誇りました。
これほどの名選手なので、引退後は永久欠番になることも検討されましたが、ちょうど阪急→オリックスへの身売りのタイミングと重なったことから「準永久欠番」扱いとなり、2004年の近鉄との合併を経て失効しました。その間、「恐れ多い」と田口壮、イチローといった名外野手から固辞され、糸井嘉男、吉田正尚といった名外野手かつ左打者の背中で輝くも、現在は空き番となっています。
柴田以降の巨人
福本と同時期にセリーグで活躍したスピードスターが上述の柴田勲(巨人)です。福本ほど華々しい記録はありませんが、6度の盗塁王を記録、「通算安打2018」で名球会入りしています。また通算盗塁数は福本、広瀬叔功(南海)に続く3位です。
NPBにおけるスイッチヒッターの草分けのような存在で、スイッチヒッターでは初の名球会会員となりました。奇しくも、同じくスイッチヒッターで後に名球会入りした松井稼頭央(西武→MLB→楽天)も背番号7が代名詞でした。
柴田引退後は、同じくスイッチヒッターの外野手であるレジ-・スミスが2年間着用し、柴田とはだいぶタイプの違う左打者である吉村禎章が長く着けました。
しかし、吉村引退直後に入団した右打ちの内野手・二岡智宏が着けたことで流れが消滅、二岡が移籍するとこれまた右打ちの外野手・長野久義が着け、自分の代名詞としました。長野がFA人的保証で広島に移籍後も空き番となり、今年巨人に復帰してそのまま着けています。
左打ちの外野手にして安打製造機
なんとなくできた伝統を何のかんので守り続けているのが、大洋→横浜大洋→横浜→横浜DeNAです。
1961年に入団した左打ちの外野手・長田幸雄は2年目にレフトのレギュラーを奪取すると、そのまま一軍に定着。守備と走塁に難があるもコンスタントに二割後半の打率を残し、16年の長期に渡って在籍しました。
長田がほぼ川崎時代のホエールズと運命を共にすると、横浜大洋前半の象徴となるのが同じく左打ちの外野手・長崎慶一(啓二)です。入団一年目からセンターのレギュラーに定着。打順は安定しないものの、田代、松原、高木由一などのクリーンナップに割って入ることもあり、1982年には田尾安志(中日)とのデッドヒートを経て首位打者も獲得しています。守備位置は主にセンターで、状況によってレフトという感じでした。1985年、阪神にトレードされ、外野の控えおよび代打の切り札として日本一に貢献します。
長崎の次に背番号7を着けたのが、カルロス・ポンセです。その風貌が当時大ヒットしていたゲームキャラに似ていたことから「マリオ」の愛称で親しまれ、俊足巧打の外国人選手として当時としては長期の5年間在籍、そのうち2年は三割越えを記録しました。本職の守備はサードでしたがチーム事情でファースト、のちにレフトに定着しました。ちなみにポンセはチームで背番号7を着けた唯一の外国人選手であり、「外野手」「安打製造機」の伝統は引き継いでいるものの残念ながら(?)「右打者」でした。
ポンセ帰国後に背番号41から昇格したのが、宮里太です。もともとは捕手で後に不動の正捕手となる谷繁元信のドラフト同期でした。谷繁は高卒、宮里は大卒社会人とキャリアには差がありましたが、ドラフト1位と2位が両方捕手というのは、現在の編成ではおそらくあり得ないと思います。結局、谷繁は一年目から頭角を現し、宮里は一年目の時点で事実上外野にコンバートされました。しかしこれが功を奏し、二年目から一軍に定着、三年目にはレフトの定位置を奪取し、同年オフにポンセが帰国して空き番になった背番号7を与えられます。しかし、ここから宮里は成績を落とし、「左の代打の切り札」に活路を見出しました。入団時それなりの年齢だったこともあってか、比較的短い在籍9年で引退しました。実質レギュラーだったのは1年だけでしたが、「左打ちの外野手(レフト)にして安打製造機」の流れを引き戻したのは宮里と言えます。
宮里引退後に背番号51から昇格したのが、「うっかりタカノリ」こと鈴木尚典です。吉村禎章に憧れ左打者になった鈴木は、「ハマの安打製造機」の異名をとり、二年連続で首位打者を獲得。その二年目はチーム悲願の日本一の年にあたり、「マシンガン打線」における不動の三番打者として大いに貢献、日本シリーズではMVPに輝きました。反面、「うっかり」の異名の通り守備面に難があり、特に弱肩がウイークポイントで後にレフトのレギュラーを奪われる要因ともなってしまいました。
晩年成績不振に悩んだ鈴木は、移籍してきた仁志敏久に背番号7を譲り、自身は原点である背番号51に戻しました。そこで流れは一度途切れ、仁志再移籍後に同じ内野手の石川雄洋が引き継ぎます。石川は仁志と違い左打者でした。主に二遊間を守り、一番打者を務めることが多かったです。しかし成績不振に陥った石川は心機一転背番号を42に変更します。
その空いた背番号7を着けたのが、現在も着用している佐野恵太です。大学時代はファーストを守っていましたが、プロになってからはチーム事情で主にレフトを守るようになり、「左打者」「外野手(レフト)」「安打製造機」の伝統をしっかりと守っています。まだ二十代と若く、チームリーダーにしてムードメーカーを兼ねていることから、今後のさらなる活躍が期待されます。
実は左に殉じた近鉄
と言ったら大袈裟ですが、2004年に合併消滅した近鉄の背番号7も左打者が多かったことで知られています。
1968年に外野手として入団した小川亨は、入団から17年間背番号7を着け続けました。キャリアのほとんどを中心打者として過ごし、1979~1980年のV2時はファーストのレギュラーとして優勝に貢献しています。
小川引退後に跡を継いだのが、巨人から移籍してきた淡口憲治。巨人ではレギュラーに最も近い位置にいながら一歩足りない状態でしたが、近鉄に移籍後はレギュラーを獲得。しかし、移籍時33歳と当時としてはピークを過ぎていたため年々成績を落とし、四年目である1989年、古巣巨人との日本シリーズを花道に引退しました。
淡口引退後のドラフト2位で入団したのが淡口と同じ左打ちの外野手である畑山俊二です。社会人住友金属時代の華々しい実績から、ドラフト2位&一桁背番号と非常に期待されましたが結果が出せず、4年で売り出し中の右打ちの外野手中根仁に奪われる形で背番号7を剥奪されました。
その中根は、小川入団以降球団消滅までの期間で背番号7を着けた唯一の右打者です。しかし、背番号7になってからの中根はケガなどもあって思うように結果を出せず、1997年オフに請われる形で横浜にトレードされ、翌年の横浜優勝に大いに貢献することになります。
近鉄最後の背番号7になったのが、大村直之です。1994年に高卒で入団し、二年目から一軍に定着。1998年にセンターのレギュラーに定着して打率三割一分すると、翌年に中根の移籍で空いていた背番号7が与えられました。俊足強肩巧打と三拍子そろった左打ちの外野手で、2004年の近鉄球団合併消滅までレギュラーを貼り続けました。その後、近鉄と運命を共にし合併球団のオリックスにも新興球団の楽天にも移籍せず、福岡ダイエーが身売りした福岡ソフトバンクにFA移籍します。移籍後も背番号7を着けますがこれは後述ということで。
左にはこだわらないが外野手にはこだわる
東映→日拓ホームを経て日本ハムファイターズになった2年目の1975年にヤクルトから移籍してきた左打ちの外野手・内田順三がそれまで着けていた白仁天の跡を継ぎ背番号7を着けました。内田は2年で広島に移籍し、そこでも背番号7を後々着けることになります。
内田の後を継いだのが同じ左打ちの外野手である岡持和彦でした。岡持は現役生活で一度も規定打席に到達しませんでしたが、19年の長きにわたり在籍し、「東映→日拓ホームの最後の生き残り」となりました。
岡持が引退すると、その年のドラフト1位中島輝士に与えられました。もともと内野手として入団し、新人時代はチーム事情で外野を守ったもののすぐにサードにコンバートされましたが、結局外野手登録に変更され、引退までそのままでした。期待が大きすぎた故にそれに見合った活躍ができず、近鉄にトレードされます。
中嶋移籍後に背番号7は中島同様ドラフト1位の外野手・中村豊に与えられました。期待されましたが入団4年目まではほとんど戦力になれず、5年目6年目と2年続けて100試合以上に出場しブレイクのきっかけをつかみましたが、7年目に失速しそのオフに阪神にトレードされました。
中村の交換相手ではないのですが、同じタイミングで阪神から移籍してきたのが坪井智哉でした。ここで再び左打ちの外野手の背に背番号7が戻ってきます。坪井は移籍初年度から活躍し、打率3割3分を記録。実は阪神の新人1年目にも3割2分7厘を記録しており、史上初の両リーグ入団1年目でシーズン打率3割越えを達成しました。しかしチームが北海道に移転すると外野手の選手層が厚くなり、坪井自身も「戦力外通告後再契約」という奇異な体験を経て、最終的に戦力外通告を受けオリックスに移籍しました。坪井と言えば印象的なのが応援歌前のファンファーレ。「PL~青学~東芝~坪井~」とコールしてから応援歌が始まるのですが、阪神応援団の厚意か移籍後も各応援団に引き継がれ、最終的に「PL~青学~東芝~(阪神!日ハム!)坪井~」となったのには腹を抱えて笑いました。
坪井の移籍後、投手から外野手に転向し新庄剛志が引退した後の穴をすっぽりと埋めた糸井嘉男が引き継ぎました。攻守走三拍子そろった天才選手で、その類まれなる身体能力も含め、柳田悠岐(ソフトバンク)と並び「左打ちの外野手の最終形」と呼んでもいいんじゃないかと思っています。糸井はその後交換トレードでオリックス、FAで阪神に移籍しますが、移籍先でも背番号7を着け続けています。
糸井の交換相手だった大引啓次は移籍翌年にヤクルトにFA移籍し、外国人選手を経て、もともと糸井が着けていた背番号26を前年に8に変更していた
西川遥輝が志願して着けます。変更とほぼ同じタイミングで外野手に転向。「左打ちの外野手」としてポスト糸井の道を歩もうとしました。西川の売りは俊足とそれを活かした守備範囲で、それに伴い出塁率も非常に高い選手でしたが、長打力はなく、弱肩という欠点がありました。それもあってか、MLB挑戦を前提にしたポスティング不成立の翌年オフ、4度目の盗塁王に輝いたにもかかわらず「ノンテンダー」と称する自由契約となり、楽天に移籍しました。
現在は、前年に首位打者になった松本剛が背番号12から昇格して着けています。松本は右打者なため、このまま長期政権が続けば「左にはこだわらないが外野手にはこだわる」というチームの伝統が踏襲されることになりますね。
最近左が続いている
のが千葉ロッテと福岡ソフトバンクです。
ロッテは昭和期だとどちらかというと「外国人番」の印象が強く(詳細は「背番号7の外国人選手」の項にて)、近年になって「TSUYOSHI」こと西岡剛(スイッチヒッター)、鈴木大地、福田秀平と左打者が続いています。期待されてFA移籍してきた福田は、ケガもあってほとんど期待に応えられずこのオフに戦力外となりましたが、果たして次に背番号7を着けるのは誰になるのでしょう?
ソフトバンクも、もともとは「チャイ」こと藤原満、前ロッテ監督の井口資仁(忠仁)といった「右打ちの内野手」が長期にわたって着けていました。流れが変わったのは、井口がFAでMLBに移籍し、代わってFAで大村直之を獲得してからです。近鉄の合併騒動のタイミングで移籍してきた大村は「俊足巧打の左打ちの外野手」という背番号7のイメージにピッタリの選手でした。移籍後4年間外野の一角を占めましたが、FA再取得で古巣ともいえるオリックスにFA移籍。その年のドラフト2位だった高卒内野手の立岡宗一郎に大抜擢で与えられるも期待に応えられず背番号降格(のちに巨人に移籍)。外国人投手のバリオスを経て、当時大混戦だったライトのレギュラーを奪取した中村晃に与えられ現在に至ります。高校時代はファーストを守っていた左投げ左打ちの中村は、現在チーム事情により外野手登録ながら古巣のファーストのレギュラーについています。
新興球団の楽天は、これまで4人しか背番号7を着けていませんが、創設以来着けていた山崎武司を除けば、スイッチの松井稼頭央、1年で変更させられた辰己涼介、現在も着用している鈴木大地とこれも「最近左が続いている」という流れになるのでしょうか。
むしろ右が伝統
なのがそれぞれ「チームレジェンドの右打者」である山本一義を擁した広島と豊田泰光を擁した西鉄~西武です。
60年代から70年代中盤の長きにわたって外野の一角を占め続けてきた山本は、同姓にして母校の後輩でもある山本浩二(浩司)とは晩年はライトとセンターで肩を並べる形になりました。年齢的なものもあり、1975年のV1を花道にして引退→コーチとなりました。
その後は3~4年周期で選手が入れ替わる状態でしたが、1988年のドラフト1位で野村謙二郎が入団し、17年の長きにわたって着用、のちに監督にまで上り詰めます。野村は山本と正反対の「左打ちの内野手」だったため、その時点で流れは断ち切られています。野村引退後、「ふさわしい選手が入団するまで」と準永久欠番状態になっていましたが、2009年ドラフト1位の堂林翔太が野村監督自身から期待を込めて贈呈され、その期待に応えられているかどうかはさておき、現在も着用中です。堂林は「右打ちの内野手」なので、もうこの時点でナンセンスですね(最近は外野を務めることが多いようですが……)。
西鉄の豊田の場合は、サードを守る背番号6の中西太と共にチームの看板ともいえるショートでした。しかし、兼任監督となった中西と兼任コーチとなった豊田が対立し、結果豊田がサンケイに移籍することになります。
有名選手が不穏な理由で退団すると、空き番にするか外国人選手に塗りつぶさせるかのどちらかになることが多いですが、西鉄の場合は後者でした。豊田の跡を継いだロイ・バーマについては「背番号7の外国人選手」の項で後述します。バーマ退団以降、広島同様3~4年で選手が入れ替わる状況でしたが、それにストップをかけたのが豊田と同じ「右打ちのショート」石毛宏典でした。廣岡政権では「一番ショート」として、森政権では「六番サード」として、それぞれチームリーダーとして黄金時代を支えました。石毛が引退を断り福岡ダイエーにFA移籍後は、ダリン・ジャクソンを経てショートのレギュラーを奪取した松井稼頭央が昇格して受け継ぎます。「一番ショート」とかつての石毛をほうふつさせるポジションでしたが、松井はスイッチヒッターでした。松井は文句のつけようのない実績を残し、MLBにFA移籍します。
松井移籍後、数年の空白を経て背番号7をつけたのは2004年ドラフト3位の片岡易之でした。片岡はショートではなくセカンドでしたが、石毛や松井同様リードオフマンとして活躍、盗塁王を四回獲得しています。その後巨人にFA移籍し、その人的保証として獲得した脇谷亮太がそのまま背番号7を着けましたが、2年で再び巨人にFAで戻っています。
現在背番号7を着けているのが外野手の金子侑司。入団から移籍を経ずに2→8→7と非常に贅沢な背番号変更をしている選手ですが、スイッチヒッターということで松井稼頭央への憧れもあったのでしょうか。なら「監督を男にするためにもっと働け」って話ですがね。金子は外野手なので松井のフォロワーというわけでもないですが、いまのところ「右打者→スイッチ→右打者→スイッチ」とつないでいるので、次に右打者が着けたら面白いとは思います。
阪神はやはり逆張り?
まだ一桁しか語っていない段階で、数々の背番号における「逆張り」を印象付けてしまった阪神タイガースですが、背番号7においても逆張りを展開しているようです。
戦後すぐに背番号7を着けたのは、のちに監督も務める左打ちの外野手・金田正泰です。一年間別の番号を着けましたがすぐに復帰し、述べ13年着けました。
金田の引退後に引き継いだのが同じ左打ちの外野手である並木輝男です。並木は7年間着用しましたが、東京(ロッテ)にトレードされます。
並木移籍後、移籍選手の西園寺昭夫、投手の鈴木皖武をそれぞれ2年ずつ挟み、ふたたび左打ちの外野手の背に戻ります。それが池田純一(祥浩)です。1973年の「世紀の落球」という不本意な形で名前が知れ渡った選手ですが、巨人V9時代の阪神を支えた名外野手でした。しかし、世紀の落球が公私ともに悪影響を及ぼし以降成績が急降下、32歳で現役を引退しました。
池田が引退した1978年オフにクラウンライターから移籍してきたのが真弓明信です。昭和の野球ファンには説明不要の、阪神1985年V1時の不動のリードオフマンです。結果的に「阪神の背番号7」は真弓の代名詞になったので結果オーライではあるのですが、これまで「左打ちの外野手」でつないでいたのをいきなり「右打ちの内野手」に与えるのが阪神クオリティだとは思いました。この真弓の着用年数17年が阪神における背番号7の最長記録です。
真弓の引退後、一年の空き番を経て1996年ドラフト逆指名の新人、今岡誠が引き継ぎました。チーム事情によって内野ならどこでも守れるユーティリティプレイヤーとして扱われましたが、2003年には打率三割四分を記録し首位打者を獲得しています。今岡はロッテに移籍するまで14年間着用し、真弓と二人で「右打ちの内野手」の伝統を作ってしまいました。
今岡移籍後、2009年ドラフト5位の藤川俊介に与えられましたが、これはドラフト指名時の阪神側の不手際(3位以内の指名制限破り)のバーターと見られており、3年でMLBより復帰した西岡剛によって剥奪されています。
しかしその西岡もオリックスからFA移籍した糸井嘉男によって背番号が剥奪され、昨年限りで糸井が引退した現在は「球団史上初の背番号7外国人選手」ノイジーが着けています。西岡(スイッチ)、糸井(左打者)と流れが変わったところを、右打ちのノイジーで軌道修正したとは思いませんが……。
流れが作れていない二球団
西鉄から内紛でサンケイに移籍してきた豊田泰光は、移籍先でも継続して背番号7を着けます。その豊田に背番号を明け渡したのが、スワローズレジェンドの一人町田行彦です。1952年に国鉄に入団した町田は、3年目の1955年に21歳の史上最年少で本塁打王に輝きます。この記録は奇しくもチームの後輩である村上宗隆に2022年に並ばれるまでは単独記録でした。
豊田引退後はあまり落ち着きませんでしたが、個人的には1978年V1期の左の代打の切り札、福富邦夫が印象に残っています。なんならあくまでも私見ですが、福富のおかげで「背番号7は左打者という印象が強まっている」まであります。
福富引退後は、苦労人の内野手・渡辺進が入団10年目で昇格して着用、ショート以外の内野のユーティリティとして活躍しました。
その後は移籍選手が着けたり、逆に着けた選手が移籍したりで定着せず、ようやく落ち着いたのは2004年ドラフト自由枠で入団した田中浩康が着けてからです。それまでのレギュラーセカンドだった城石憲之からポジションを奪う形でレギュラーに定着、のちの山田哲人の台頭まで二塁のポジションを守り続けました。
田中移籍後はふたたび移籍選手である内川聖一が着け2年で引退。今年2023年からはショートのレギュラーを掴んだ長岡秀樹が着けています。渡辺、田中と長期政権は右打ちの内野手が続きましたが、左打ちの内野手である長岡はどこまで着け続けることができるでしょうか。期待しています。
流れを作れていないもう一チームが中日です。それまでも長期着用の選手が出ませんでしたが、70年代に捕手である新宅洋志が8年着けて最長記録タイ。新宅が引退すると、ショートのレギュラーを掴んだ宇野勝が代名詞としました。守備に難があるものの長打力には定評のある「ロマン砲」。史上初の「遊撃手による本塁打王」でもあります。また、守備に難があると言っても、とてつもなくイージーなミスはしつつ、強肩且つとんでもないファインプレイを魅せることもあり、非常に人気のある選手でした。結局宇野の付けた14年がこのチームの背番号7着用最長期間です。
そのため、印象に残る選手はいても代名詞的選手はおらず、現在着用している投手の根尾昂が長期着用して代名詞にできるかどうか。
背番号7の外国人選手
日本では「ラッキー7」と呼ばれる良番なこともあってか、一桁の中でも特に外国人選手が着けることが少ない番号です。現在阪神ではノイジーが着けていますが、実は「球団初の背番号7を着けた外国人選手」だったりします。
ちなみに「外国人選手ゼロ」なのは歴史の浅い楽天に加えて広島とオリックス。なおオリックスは近鉄を加えてもゼロと徹底しています。
他にも二年以上着けた選手がいない中日、ヤクルト。ダイエー創設年に鳴り物入りで入団したものの「水島漫画にミソつけて帰国しただけ」のウィリー・アップショーと上述のバリオスのみのソフトバンクと死屍累々。
それぞれ上述のスミス、ポンセのみの巨人、DeNAや、ジム・バーマが「ロイ&バーマ」で西鉄後期に一時代を築いたものの、その後はダリン・ジャクソンのみと「少数精鋭」の西武はかなりマシなほうという印象です。
そんな中、独擅場ともいえるのが千葉ロッテ。といっても、千葉移転前どころか東京オリオンズからの話です。東京は南千住にたったの十年だけ燦然と輝いた「光の球場」東京スタジアムを本拠地としていた1968年に来日したジョージ・アルトマンは、そのルックスと福祉活動に熱心だったことから「足長おじさん」というそのまんまなニックネームを与えられ、7年間という長期にわたって在籍しました。1972年にはコーチも兼任しています。入団初年度にいきなり最多安打と打点王に輝くと、その後も一年を除いてすべて三割以上を記録し、本塁打も20本以下になることはありませんでした。敬虔なキリスト教徒で酒もタバコもやらず、性格は真面目そのもので練習熱心、常に全力プレーと他の外国人選手どころか日本人選手全員のお手本にすべき選手でした。しかし1974年に初期の大腸がんを患い途中帰国して手術。手術は成功するも、リーグ優勝~日本一の輪の中に入ることはできず、また当時41歳という高齢だったことから金田正一監督の構想から外れ、阪神に移籍しました。アルトマン退団以降、二年続けて外国人選手(マクナルティ、ブリッグス)が背番号7を着けるも、それぞれ一年限りで解雇されました。
東京オリオンズの「背番号7外国人」の象徴がアルトマンなら、川崎オリオンズの「背番号7外国人」の象徴が「リー兄弟の弟」ことレオン・リーです。前年にロッテに入団していきなり本塁打王と打点王の二冠(+打率三割一分七厘)に輝いた兄レロン・リーの紹介で1978年にロッテに入団すると、5年間の在籍で4年連続三割越えに加え、3年目の1980年には本塁打41本を記録しています。ちなみにこの年は兄のレロンが三割五分八厘で首位打者を獲得、自身は三割四分で「兄弟ワンツー」を達成しています。しかし交換トレードで横浜大洋に移籍、その後ヤクルトに移籍するも「三球団で本塁打30本以上」という珍しい記録を達成し、兄同様日本での通算打率三割以上という輝かしい記録を持っています。引退後、日本語の堪能さを生かしてオリックスの監督を務めますが、指導者としては結果が出せませんでした(背番号の話5番の「背番号5の外国人選手」の項もご参照を)。
レオン移籍後、15年以上日本人選手が続きますが、1995年に一度退団したものの1998年に復帰したフリオ・フランコが一年だけ着けました。フリオ・フランコについてはいつになるかわかりませんが「背番号の話21番」で語りたいと思います。
復帰したものの高齢による衰えを隠すことができなかったフランコが一年で退団すると、その代わりに入団したのがフランク・ボーリックです。千葉マリーンズにおける「背番号7外国人」の象徴ですね。1999年に入団すると、一軍昇格最初の試合でいきなり「来日初打席初本塁打」を記録、翌日には「逆転サヨナラツーラン」を放ち、ボーリック不敗神話を作りました。長打力を併せ持ったスイッチヒッターはそこから三年間で26本、29本、31本としり上がりに本数を増やし3年目の2001年にはベストナイン(DH)に選ばれました。しかし翌年成績を大幅に落とし夏前に二軍に落とされるとそのまま解雇されました。「レッツゴー・ボーリック」の応援は今でも耳に残っています。
背番号7の投手
このコーナーでは毎度おなじみの阪神から(この言い回し、果たしてどこまで続くのか)。1969年に西園寺昭夫外野手とのトレードで国鉄から移籍してきた鈴木皖武(きよたけ)投手が背番号7を2年間着けています。といっても、これは単に交換相手の背番号をそのまま引き継いだもので、2年着けた後背番号13に変更しています。
近年では上述のバリオス(ソフトバンク)が育成昇格直後に一瞬着けていますが、すぐに67番に変更しています。
そして忘れちゃいけない現役投手の根尾昴(中日)。もともと打者転向前提で背番号7を与えられましたが、某監督の迷走により、まさかのシーズン途中で投手再転向。転向初年度の昨年は主に敗戦処理を中心に25試合に登板しましたが、シーズン最初から投手登録にした今年は一軍での登板はゼロに終わりました。かつての控え投手だった横川凱(巨人)が今年着実に実績を上げているのをどう見るか……。ちなみに根尾も左打者だったりします。
長期ブランク明けで、書き方をちょっと変えてみたところ、やはり裏目に出て連載最長となってしまいました。申し訳ありません。
次回「背番号8」はもう少し短くできるよう頑張ります。
《バックナンバー》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
