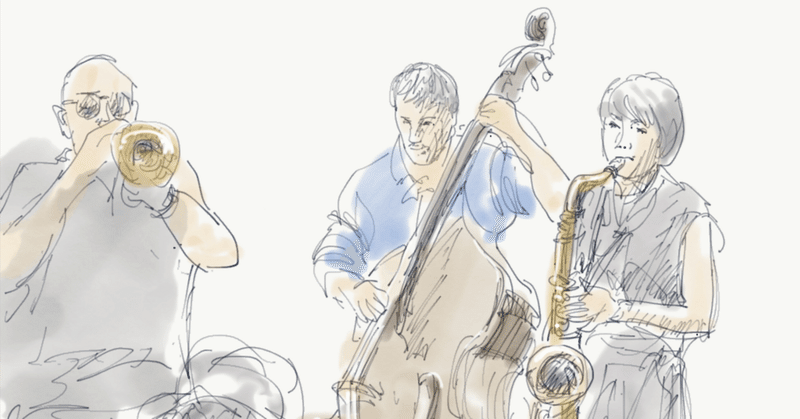
JAZZって、何だろう?? って思うのが、JAZZ
先日、雑誌「BRUTUS」で、以下のような特集号が出た。
これは、昨年に出た特集号の続編的な位置付けで、内容はもう少し、ディスクガイド寄りになっている印象だった。
JAZZは、聴き方がわからないジャンルだった。ロックのように、ビートが乗りやすいというわけでもないものだった。しかし、この雑誌に書いてあるマニアックさは、何となく心をくすぐられるものだった。
それは、鉄道模型とか、サッカーの戦術とか、切手とか、懐石料理とか、流体力学とか、地図とか、歴史とか、哲学とか、数学とか、とにかく、そういった「専門性」に惹かれる傾向にある私にとっては、必然だったかもしれない。
昨年買っておきながらほとんど読めていなかったことを反省し、2冊を通して読み、そして、そこに書いてあるディスクを選びながら、聴き始めた。多分、30枚くらいは聴いただろうか。
結果としては、「あれ? なんかわかるかも?」というものだった。これは非常に驚いた。
一番好みだったのは、Dexter Gordonの「Go!」だった。
それは、一様に、明瞭な音、ポジティブな音に感じたためだろう。素人なので、コード進行とか、複雑さとか、そんなものは一切わからない。
しかし、素人ながらに、定型っぽくないな、と思った。これもJAZZか、とわかったのが大きかったと思う。
ラスト曲なんかは、聴いたことのあるフレーズ満載で、面白かった。「聴いたことがある」というのは、かなり大きな作用なのだ。
一方で、Bud Powellの「The Scene Changes」は、そこまで面白いとは思えなかった。いわゆるJAZZの定型っぽく聞こえてしまったからかもしれない。
でも、素人が、定型なんて知るはずもない。でも、勘違いとは思えない。
そこで一つ考えた。もしかしたら、流れが読める、ということが、定型っぽいとイコールになりかねない、ということなのではないだろうか。次はどの楽器、次はどれ、そして戻る、この一連の流れが読める。
それが悪いわけではもちろんないし、大別すれば音楽はすべてこの流れだろう。ただ、そこに重きをおいているような印象を受けただけである。そして、JAZZはそれだけがすべてだろうと思い込んでいた。
つまり、定型なんてない、と考えれば良い。それは「≒聴き方もない」ということに他ならない。一流の評論家やプレーヤ、例えば、柳樂光隆さんや石若駿さんも上原ひろみさんも、「こう聴け!」みたいなことを言っていることは(おそらく)一度もないではないか。
それがわかってからは、例えば、Miles Davisなんかも、少しわかったような気がするが、まだ自信がない。やはり、彼以前のJAZZをもう少し聴けば、当時の先進性がわかるような気がする。特に電子化までの流れは抑えておきたい。それはロックやポップミュージックの歴史にも影響するはず。
元々、Fusionは好きだった。Larry Carltonの「Room335」とか、Wether Reportの「Birdland」なんかが好きで、ずっと聴いていた。そこから、Return to Foreverにも入るのだが、なるほど、Chick Coreaなんてまさにこの電子化プロジェクトの中核を担っていたわけで、すべては繋がっているのだなあ。
ただ、Fusionは、技巧に入りすぎるとちょっとなあ、という感じもある。それが顕著なのは、The Brecker Brothersだった。いや、もちろん好きなんだけれども。そこがJAZZとの境界線なのかなと思う。JAZZは、聴衆を意識している。Fusionは、ベクトルが少々内向き気味なのかも。
「Way Out West」も何冊か読む機会があった。これもまた、愛ゆえの賜物。明らかに「同人誌」だが、これがフリーなのが信じられない。でも、このマニアックさは、明らかに、JAZZというジャンルの懐の深さを物語っている。慌ててバックナンバーをいくつか揃えましたとも。
奥様は言いました。「表紙がめちゃくちゃかっこいいじゃん」
近作で言えば、Melt Yourself Downとか、Sons of Kemetが素晴らしいと感じた。この明るさがJAZZの本来の一つであると想像する。ロックだって、プログレとかUSインディとか暗い曲調のものもあるけど、元々はThe Beatles周辺だったわけで、「陽気な音楽が欲しい時もある」のです。
さて、ここからどちらへ行こうか。しばらくは「Blue Note」を掘り進めるか、それともRobert Glasperをもう少し勉強してみようか。それともHIP HOPへ進んで、いまいちわかっていない「To Pimp a Butterfly」に行こうか。あるいは、Samara Joyなどのボーカリストへ行こうか。そう言えば、The Manhattan Transferは大好きだったけど、あれもJAZZか。
うーん。こうしてみるとやはり必要なのは「掲示板」「道路標識」「家系図」のようなものかもしれない。こちらにいけば何につながる、というものがあれば、ああ、なるほどね、とわかる。それもいい。
ロックで言えば、ブルース、ロカビリがあって、ロックンロール、ハード、プログレ、パンク、グランジ、リバイバルなどといった流れがあるように、JAZZにも何かあるはずだ。そうした体系化が、学問として成り立っていると想像する。それを読むのも楽しそうだ。
JAZZって何だろう?? と考える。そのこと自体が既に、JAZZのことを考えている。数学的に、あるいは集合論的に言えば、そうなる。それでいいじゃん、と割り切れた。そして、わからないながらも聴き続けた。それが、もしかしたらわかるかも? と思えたきっかけだった。
これを一般化して、多方面への応用とするならば、「石の上にも三年」と言えるだろうか。続けてみないことにはわからない。その前段階で止める人がいかに多いか。あるいは、批判する人がいかに多いか。仕事だって、結婚生活だって、そうではないか。鬼嫁と思っていてもそれは愛情からのものだと気がつくには、時間がかかるものだ。もしかしたら、三年では効かないかもしれない。その間に、あれこれ試してみればいいのだ。「これは怒られる」「これは怒られない」と見極める計画性と度量が必要だ。何の話だったか・・・。
最近、Bob Marleyの「Exodus」を初めて聴いて、感動して涙したのだが、あの曲も、フレージングの繰り返しやベースラインなどが、どことなくJAZZぽくないだろうか。聴きながら、よく子供と踊っていますとも。
つまりは、音楽の根底にある共通する何かを突き詰めたもの、最も濃く、ピュアな(同じ意味だ!)抽出物が、それぞれ、JAZZやロックやHIP HOPと呼ばれるのかも。
すべては、繋がっているのだなあ・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
