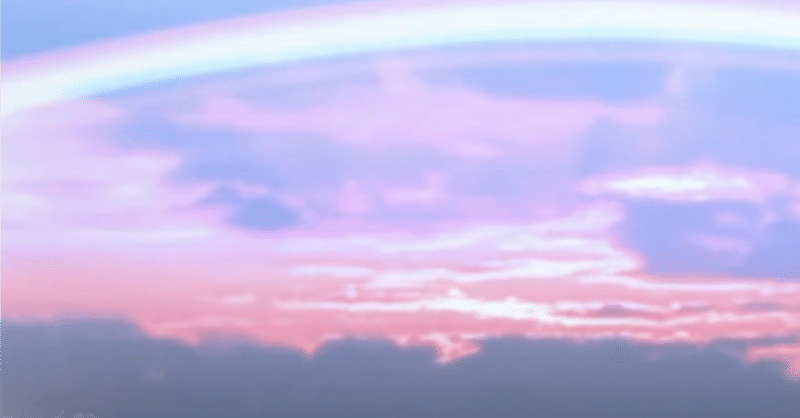
自分だけの色を探す旅路——にじフェス2023前夜祭の夢追翔さんのステージに寄せて
2023年12月23日、24日。大盛況で終わったにじさんじフェス2023(以下:にじフェス2023)。
その盛り上がりを間違いなく後押ししたのは、最高の仕上がりで観客を魅了したにじさんじフェス2023前夜祭(以下:前夜祭)だという事実は個人の主観抜きで断言してよいと思っています。
この前夜祭という、にじさんじという事務所、ひいてはANY COLLARという会社の一大イベントの先頭に立つトップバッターに抜擢された四ユニットのうち、メジャーデビューから数々のタイアップもこなしてきた樋口楓さん、デュオユニットへ形を変えてからも勢力的に楽曲・アルバムリリースを続けるNornis(町田ちま、戌亥とこ)のお二人、2023年6月にZeppYOKOHAMAでのワンマンライブを大成功に終えたVΔLZ(弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴)のお三方に並び立ってステージに上がられた、バーチャルシンガーソングライター(以下VSSW)夢追翔さん。
箱の全体ライブを通して数々のソロパフォーマンスの機会こそあれど、彼がひとりの”アーティスト”として初めて呼ばれたのがこの前夜祭。彼に与えられた5曲分という短いとも短くはないともとれる時間は、それでも彼にとって初めての”ソロライブ”の時間だったように思います。
彼のためだけにすべての観客の時間が、視線が捧げられる晴れ舞台。彼自身配信チケットの告知ツイートなどにて「2023年の集大成」とたびたび口にしていたのも心の底から頷けるほどの全力のステージは、言葉をひとつも飾らすに言えば本当に最高の時間でした。
ライブ会場現地にて真の意味で浴びたパフォーマンスから得た幸福感、高揚感を2週間ほど感想を言葉に落とすのを躊躇ってしまうくらい大事にしてしまったのですが、2024/01/08を最後に見返すことが叶わなくなってしまう(円盤化心よりお待ちしています)こともあり、簡単にですが感想を覚書として残しておこうと思いこのたび筆を執りました。
長々前置きをしましたが、このnoteは前夜祭でのVSSW夢追翔さんのソロステージ、ひいては楽曲に関してあれこれ感想を書き連ねただけのものになります。
個人の主観を大いに含むほか、X(旧Twitter)にて拝見した自分以外の方のポストから得た感想・着想を自分の中で解釈し纏めることを目的としておりますので、偏った視点からの内容となっている側面があることはご了承ください。
全体雑感
ソロステージの構成、演出に限って言うとしたら、”彼自身がやりたいことを詰め込んだ”ものであり、”ファンが見たかったもの”を最大限最高の形でお出ししてきた、という感想に尽きるなぁと。
開演前の四ユニット分のインスト音源で繰り返し流されていた『人間じゃないよな』をイメージしたようなダークな雰囲気の出囃子で幕を上げて、まさにその曲とおそらく一番練り上げられたであろう舞台演出と歌声で一気に会場全体を自分の空気に惹きこむ。緩急をつけつつも掴んだ空気を決して離さずに最後まで駆け抜けた姿は本当に見事でした。
そして、イベントの前段の意気込み動画からもそうだったんだですが、曲間のMCでコールについて事前に触れておいて、現地・配信問わず、自分のファン・他の演者のファンすべての観客がみんな最大限楽しめるよう心配りをされていたり。MCでも隙間なく笑わせたり、けれど他の演者への配慮も欠かさず……と、どこまでも”彼らしさ”に満ちた、彼だからこその時間を作っていてよかったな、としみじみ思います。
それでは、ここからはパフォーマンスについての感想をつらつら纏めていこうと思います。セットリストは以下。
1.人間じゃないよな (作詞作曲:夢追翔)
2.Overdose (作詞作曲:なとり)
(MC1・告知)
3.オリジナリティ欠乏症 (作詞作曲:夢追翔)
4.音楽なんざクソくらえ (作詞作曲:夢追翔)
(MC2)
5.虹の在り処 (作詞作曲:夢追翔)
MCパートについては一旦触れず、曲ごとに区切って触れていきます。
1.『人間じゃないよな』

ドラムの3カウントの直後、静かな歌い出しとともに真っ赤な緞帳が上がって開幕したステージ。
まさかこの曲から始まるとは。そんな虚を突かれた感想と、開幕前インストや出囃子から既に予兆は確かにあったのだと膝を打ちました。てっきり今までのようにガツンとロックをかまして樋口さんからのバトンを繋ぐと思っていたので……。
ただ、このまさに”夢追劇場”と言うべきか、”夢追翔onStage”と言いますか。がらっと空気を変えて観客の心を掴む、目を奪う選曲とパフォーマンスは本当にすごかったです。
まず立ち振る舞い。豪奢な椅子に脚を組んで腰かけて歌う姿も、恭しく下げられた頭や歩き方でさえも気品を纏っていて、煌びやかにマイナーチェンジされた共通衣装も相まって貴族・支配者めいた様がたいへん素敵でした。サビでバレエを踊るように舞台上を舞う姿も軽やかで美しく、これまでの彼の舞台上でのパフォーマンスとはまた一線を画したものであったように思います。
歌声はこれまでより力強く、のびやかに。ただ端々に乗った感情は苦しいほど繊細で、こちらもまたぐっと聴き手を惹きつける声にパワーアップして……片鱗はあったけどこれが身体づくりの成果か……すごい……と後日TSを見直して呆気にとられました。現地ではそんな余裕はなかった。
そして演出。この曲が一番こだわったと話していた通り、背景映像もなにもかもが瞬きの瞬間すら惜しいほど細かく作られていました。ひとつの舞台、ひとつの芸術作品として仕上げられたステージは彼至上"最高"のものであり、ある意味では"最悪"の演出で幕を閉じたことに戦慄したことを覚えています。
正直2週間たった今でもまだ咀嚼はできていなくて、無料視聴分でまだしばらく見れるだろうしいいか……と胡坐もかきかけたのですが、これだけの作品を見たうえでそれは誠実でないとの思いに勝手に駆られつついくつか、印象深いところを綴っておきます。
背景映像と舞台上の”夢追翔”

緞帳が上がったあとの舞台奥に飾られた大きな額縁と絵画。その天辺から伸びた糸で開幕からAメロまでの間は力なく四肢を下ろした人形が吊られています。その人形の前では恭しく頭を下げた夢追翔さんの姿は舞台の観客に挨拶をする支配人のようにも見えました。
1サビでは人形は動きはじめますが、始まりはかなりぎこちない。ただ、歌詞が進むごとに徐々に滑らかに動くようになっていく。1番の歌詞の通り、反応を見て動き方を学習していっているようなうすら寒さがあります。
2番Aメロで額縁の中で世界に絶望したようにこと切れて落ちた人形は、間奏にて再び吊り上げられるも、首は力なく落ちたまま左右に揺れている。そうして突入した落ちサビの歌詞「あなたが望むならどんな形にもなろう だけど覚えていて 私もあなたが見えて」その通り、はっきりとした自我を持って踊り始めた人形の動きは、不気味なほど滑らかなものに変わっている。
その踊りを背に弾かれた引き金を終止符とするように、ゆっくりと緞帳が降りていく。舞台はここで幕引きのようにも思えたが、そうではない。
アウトロで再び上がった緞帳、カーテンコールかと思いきや背景の人形は消え去っていて、残ったのは空っぽの額縁だけ。その前に立つ夢追さんの腕が片腕ずつ吊り上げられて、困惑したあとに覚悟を決めたように一度瞼を伏せた彼の身体はゆっくりと宙へと浮いていく。
先ほどまでそこにいた人形の代わりのように額縁の中へ彼が吊り上げられた直後。曲の終わりとともに、何か重いものが落ちるように一瞬で緞帳が落ちる。鮮血で染まったように赤色だけが取り残された舞台に悲鳴と困惑の声が上がるところまで含めて曲が完成されたように見えました。
主観込みで演出をざっと言語化してみたのですが、これ、いや~……何食べたらこんな演出思いつくんですか……人の心がない……いやあるからできるのか……思いついた末実現できるフットワークすら恐ろしい……。
個人的な解釈としては、始めは舞台を支配していた、ないし人形を踊らせる立場にいた人物が知らず知らずのうちに人形の方に支配されていて、最後には断頭台に晒し出されて幕を引かれる。誰の手とまでは言わないけれど……、という印象でしょうか。イントロ・アウトロは”かつての支配者”を、それ以外では”人形”、と夢追さんは舞台上で二人の人物を演じていたことになりますね。
これを、自分の歌を聴きに来た人間を前にやるのだから恐ろしいの一言に尽きるというか。言ってしまえば絵画の中に磔にされてギロチンにかけられる自分を見せるわけですよ。覚悟なんてする暇もないわけで、もう残酷どころの話じゃない。そしてついでに言うと、自分を絵画の中に吊り上げるのもバーチャルだからこそできる演出の一つ(リアルだと事前・直前にワイヤーを繋ぐ必要がある)で、なんでもなくそれを組み込むところも恐ろしい。このひと、技術が進めば進むほどどこまでも進化する舞台を作りますよ。わくわくしてきたな!
2.『Overdose』

「解像度の悪い夢を見たい」という歌詞がたびたび「解像度の悪いゆめお見たい」と聞こえてしまうというTwitter等でのネタが選曲の一番最初のきっかけだったらしいこの曲。
直前までは優雅に座っていた椅子に、どかっと大きく脚を広げて座る豪快さがダウナーで低音ベースの曲調と相まって程よい意味で”男性的な色気”を前面に出した姿がかなりの温度差でぶつけられるのはなかなかのサウナでした。たまに見せる笑顔が爽やかでさらに憎らしい。
広いステージの中心に置かれた椅子からは動かず、曲に合わせて揺らめくだけ。シンプルで贅沢な舞台の使い方は、単曲ないし2-3曲しか持ち時間の与えられないこれまでのライブでは決して選択されなかったパフォーマンスのひとつだったように思います。
ニコニコ生放送のコメントでは「セルフプロデュースが上手い」「自分をわかっている選曲」といった褒められ方をされていて、後日TSを見た時にはたいへん勝手ながらにやりとしました。そう、普段トランペットめいて響く高音歌唱の印象が強いんですが、中低音の響きが丸くてきれいなんですよね。発音と発声の心地よい英語の歌詞が含まれているのもとても合っていて、彼の声で聴きたいと思ったことが一回でもある人間、多いんじゃないでしょうか。知りませんけども、現地の悲鳴とコメントの歓声を見るにたぶん合ってそう。
唯一のカバー曲としてこれを持ってきた彼のセンスが好きだな~、と笑顔になった曲でした。
3.『オリジナリティ欠乏症』

コール予習曲1曲目。
あらかじめ公開されたセットリストとしてこの曲の存在を知らされた瞬間の感想としては「声が出せるライブで絶対に聴きたかった」し、「聴くのが恐ろしかった」という相反するものに尽きます。
ただ、実際に現地で聴いて。とびきり楽しそうな笑顔で件のコール「What's your original?」を浴びる彼の姿を見て、水色のレーザーが飛び交う景色と、赤色のペンライトの海にちらほら点在する水色のペンライトの光を見て。ああ、本当にこの舞台でこの曲が聴けてよかったという思いでいっぱいになったことを覚えています。
もともと事前動画で話されて、ライブ中に他の演者から散々弄られた「バトルだと思っている」という言葉があったと思います。ご本人がMC中に「僕と、観客の皆さんとのバトル」と笑いながらも訂正されていましたが、正しくこの曲がそれのワンシーンに当たるなぁと後から思いました。
原曲のMVが公開された時点では、自分の個性、自分だけのメロディを死に物狂いで探している人物に投げかける言葉としてあまりに残酷なコールだという印象が強かったんですよね。お前の個性はなんだ、と重なった声で問い詰められているような印象を受けたせいかもしれません。
ただ、今回のライブで聴いて、いや自分でも声を上げたからかもしれませんが「お前の歌を聴きに来たんだ」「もっと見せてくれ」と熱を煽るような印象を受けて。そしてそれを浴びた夢追さんが笑顔で負けじと声を張り上げるから、ボルテージがもっと上がる。ただ残酷な言葉じゃない、いわば”煽り”のように思えて、何度でもこの曲を生で聴きたいとすら思いました。バンド陣の熱い演奏も相まって一体化していくこの感じ、生ライブって本当に良くて……。「やっと掴んだこの場所だからもう少しだけいさせて」という歌詞に何度でも立ってくれと願ってしまうほどに。
この曲に関して言うと、ラスサビの歌詞にぎゅっと心臓を握られたことも忘れずに覚えておきたいです。
「ほらねあの娘も 誰も僕など願っていない けど願っていたい」という歌詞があるのですが、ライブ特有と言いますか、歌詞の一部の改変がありまして。
「ほらね”お前”も 誰も僕など願っていない」と、観客を指差して歌い上げた彼に息を呑んだのは自分だけじゃあなかったと思っています。どうでしょう。
この曲の直前MCでファンミーティング開催が発表されて歓喜の声が多数上がっていたり。彼のイメージカラー・好きな色たる赤色のペンライトの海、かつて夢みたいだと語った光景を再び目の当たりにしてもなお、願われているのは「自分自身ではない」と突き放す声は、ある種。「お前を見に来たんだよ」「お前じゃなきゃだめなんだよ」とファンの熱をさらに煽るものとも捉えられるでしょう。
暴論かつ持論に過ぎませんが、アーティストってそのひと自身が教祖足りえる宗教を作り上げたものが生き残る世界で、熱狂的なファンの存在がさらに大衆を煽る(良い方向にも、悪い方向にも転がりますが)ものだと思っているので。もし彼がそれすら狙っていたならどこまで強かで強くなったのか、と感嘆の念すら覚えます。一応付け加えておくと、今の彼はその熱量もコントロールできるくらい強かでもあると思うので、とにかくいいね! という感情の話と纏めておかせてください。
4.音楽なんざクソくらえ

コール予習曲2曲目。
前曲から間髪入れずに続くこの曲、真っ赤に染まり切った会場はもうフルスロットルです。そりゃ炎も出る。魂からの叫びに応じて何十発も出る。サイコーの景色ですがひとつ五万は飛ぶらしいですねあれ。とんでもない。
暗転からカッと白く光った舞台に仁王立ちした彼の叫ぶような歌い出し、痺れました。飾らず身一つでぶつかってくる姿、まさに音楽と真っ向から勝負している様そのものでとても良かったです。見たかった景色すぎる。
いつかのnoteでも書きましたけれど、この曲って音楽が好きで好きでたまらなくて、それがないと生きていけないしそれで生きてこうとしているのに、ただ好きなだけじゃ見向きもされない、返事もない、いらないこと考えないとやっていけない世界ほんとクソ! そんな生き方しかできない自分もクソ! でもそれしかない! みたいな、不器用で天邪鬼な男があらゆることを腐しながらそれでも音楽を愛しているって叫びの歌だと思うんですね。
この曲、ライブで披露することによってかつてはひとつも聞こえなかった歓声が盛大に返ってくる光景に変わるのがとてもいいですよね。一度は崩れ落ちても再び立ち上がって、命を燃やして歌い続けよう、音楽に向き合い続けようとする様が物理的な炎で補強されるのもとても良い。
歌詞こそなかなか攻撃的であっても、それを歌う彼が本当に心の底から楽しそうに笑っていたのが本当に印象的な一曲でした。これもライブで何度だって聴きたい曲かもしれません。会場を沸かしてボルテージをさらに上げるために作った曲でもあるのは間違いないでしょうから。
5.『虹の在り処』

「最後に一曲、やりたいことを持ってきましたので皆さんついてきてくれますか!?」
「新曲です! 『虹の在り処』!」
温めきった舞台の上でファンやすべての人への感謝を言葉にしたあと、最後に彼が打ち出したわがまま。
きっと念願だった”ライブで新曲を披露する”こと。延期になってしまい機会を逃した2年弱前からずっと狙っていただろう機会で満を持して披露されたこの曲は、まさに”今、2023年末の等身大の夢追翔”の思いを赤裸々に綴ったもののように思いました。

ライブ直後に公開されたMVでの英題は『Where my color is』。単純に訳すと「自分の色の在り処」が近いかな、と勝手に思っています。
先日(2024/01/07)のミューコミVRにて、解釈のひとつとして捉えてほしいと前置きをして「虹っていうものをどう捉えているかをいろんな表現で入れています」と話されていましたが、日本語タイトルと合わせると「虹」こそ「自分の色」なのかもしれないという見方もできます。
この曲、歌詞に空、雨、雲、太陽、虹と空に関わる単語が含まれているのもあって、ライブでの歌唱時のVJでは空が様々に表情を変えながら映されていました。リリックモーションも雨が水たまりに落ちるような波紋を纏っていて、これがまた綺麗で……。これもきっと監修されてこだわられているんだろうなぁと勝手ながら思いました。
ステージ上部に虹を模したバルーンがあるのもまた、歌詞の通りに虹が頭上を塞いでいるようで皮肉でもありました。最後に空を見上げる振りがあるところも、背景モニターだけでなく頭上のバルーンすら見上げているようでもあってとても良くて。そこまで考えてたらこの人の思考の広がりに恐れおののくところですが、ありえなくもないのがすごい。

この曲、開幕で「気づかれなくてもいい あなたが見てる限り(『人間じゃないよな』)」と歌い、自己の個性を問う曲(『オリジナリティ欠乏症』)→意志を貫くために向き合っている最中の曲(『音楽なんざクソくらえ』)と続けてきた最後を締めくくるものとしては最上すぎる歌詞で。初見で聴いたときはラスサビの「其処に居るならどうか焼き付けていて僕の姿を 偽りに塗れてても虹はそこに」という歌詞で完全に泣き崩れてしまってそこで印象が飛んでしまったんですけど、聴き返せば聴き返すほどしみじみと、前三曲を含むこれまでの彼の道のりの轍すべてが見えると同時に、これから先を見据えた背中が眩しく思える曲だなと思います。
歌詞に関して細かく掘って追っていくのも一興なのですが、一旦今回は保留で。
雨降りの空の雲が一瞬切れて青空が覗いても、虹が塞いでその向こうは見えない。また降り始めた雨も、強く吹く風も険しく襲ってくるけれど、どれだけ苦しくても耐えて、踏みとどまって空を睨み続ければいつか黒い雲は晴れて、雨上がりのやさしい夕焼けとともに綺麗な虹が見えるから。少なくとも僕には見えたけれど、君はどうだろうか。一緒に見てはくれないか。そんな風に己の生き様を見せながら語り掛けてくれているようでもあるなと感じました。
比喩的な表現から少し焦点を戻せばこの曲、VSSW夢追翔の真骨頂、反骨精神と泥臭い生の渇望もよく見えている歌詞でもありますよね。
「馬鹿にされたままでは死ねないから」という言葉が彼から出てきたことにぐっと胸が熱くなったのもひとつ。
死にたくないだけで生きてもいいと語り、未完成でも生きていたいと駆け出した彼が新たに天高い空を見上げた。漠然とした生への渇望がより具体的に変遷しつつある彼の背中は随分と力強くなったように思います。かつてのいつ消えるかもわからない不安定さが少しずつ減って、意志を固めつつあるというか。終わりを迎える日を待つだけじゃなく、自分の足で人生を進めに行ったというか。
その背中を押して支え続けるのは、雲の切れ目を塞ぐ虹=唯一無二の才能たちに負けてたまるものか、容赦のない太陽=無慈悲な現実社会に折れてなるものか、自分だって光を放てる、自分だけが持つ光の色を認めさせてやるという反骨精神。
目を向けるのが苦しいような感情たちもすべてまっすぐな言葉で語ったうえで立ち続ける彼が、彼の世界の外にいるものに対して、死ぬまで生きてやるからこんなやつがいることを忘れないよう焼き付けてくれ、と優しくも強く語り掛けてくれている歌は、彼がまた一歩先の世界へ足を踏み出した姿そのものであるように思います。
そして、見ている存在がいるから逃げない、逃げずに向き合い続けるという、彼の退路を断つ一端を聴き手が担っているという風に思える歌詞もまたどこか苦しくて。もっと良い表現をするなら、彼がここにいること、ここにいたことの証人のひとりになるのだと思わせてくれるようなものではあるのですけれど。
君の姿を見ていると発することが毒にも薬にもなる。支えにもなれば退路を断つことにもなる。ずっと自ら背負い続けているもの、ライブというステージにすべてを賭けること、歌を書くという行為から逃げずに向き合い続けることは楽な生き方ではない。けれど、そこから逃げない、逃げて馬鹿にされて死ねるかという硬い意志を見届けるのは、それを彼に期待するからにはこちらも背負うべき責なのかもしれません。
ここまで綴ってきて思う事としては、どれだけ他者から変え難い色を持っていると言われようときっと彼は満たされないのだろうということがあります。それは、空虚な心には他者の言葉は完全には響かないということかもしれないし、ひとつの到達点に達した瞬間すでにもう次の遠い夢が、遠い未来が見えているから完全には満足できず、果てなき旅を続けていくしかないということでもあると思います。
音楽の中でしか息をできない彼の心のうちの一部分は、そうやって走り続けることでしか生きられないし生き続けられない。それを諦めて終わりを待つだけなのは、死んだのと同じなのでしょう。
彼が自身に架し続けるものは苦しみに満ちているかもしれないけど、きっとそれすらも乗り越えてステージで歌うことを、言葉と音を紡ぐことを楽しめるくらいに今の彼は強い意志を携えて己の脚で立っているのでしょう。そんな安心すらも与えてくれるようなのびやかで澄み切った歌声を、一年の終わり、冬の澄んだ空気のもとで聴くことができてよかったと思いました。
おわりに

だらだらと纏まりなく書き連ねているのでこんなところまで読まれた方はいらっしゃらないのでは……、と思いますが、もしいらっしゃいましたら本当にお時間をありがとうございます。改めてになりますが、あくまで一個人の感想でしかありませんので、こんな風に思ったやつもいるんだなくらいに受け止めていただけると幸いです。
さて。曲とは関係のない、今回のライブのごく個人的な印象を最後に纏めておいて、結びとさせてください。
今回のライブの彼は終始ずっと楽しそうだったな、と思いました。
ご本人も振り返り配信で仰られてましたが、一番緊張しなかったライブだった、というのもそんな印象に繋がっているのかもしれません。それだけ入念に準備を重ねた証拠でもあるでしょうし、共演する他の演者さんたちも信頼のおける方々で、場慣れされている方が多かったのも一端にあるかもしれません。
少しずれましたが。特に、歌っている間が一番楽しそうで。最後の曲の間奏で、とびきりの笑顔とともに「ライブって楽しいなぁ!」と声を張り上げながら言った姿が本当に本当に眩しくて、そこまで堪えていた涙が溢れたことをよく覚えています。
ライブ出演が決まった時からそれに目掛けて数か月単位で努力を続けて(2023年3月からずっとジムに週2-3?回以上通って身体づくりもされていたそうですね)、このステージに向けて綴った曲(8月頃にラフができていましたね)も無事披露できて。まさに2023年の彼の集大成、努力が大いなる実を結んだ姿としてこれだけ楽しそうな、幸せそうな笑顔と声として見せてくれたことに、一ファンとしても心の底から嬉しくなりました。
いつかのライブの振り返りや作業配信などで、たびたび「音楽の中にいる時が一番生きていると実感する」という主旨のことを話されることがあったように思います。その言葉の通り、文字通り頭のてっぺんからつま先まで、空間を共有するすべての人間とともに音楽以外のことを考えずに浸って楽しみ続けることができるライブステージは、きっと彼にとっては一番心地が良い空間となりつつあるのかもしれません。
そんな機会に、これから先もずっと恵まれ続けることを祈りたくなるほど、今回の彼は楽しそうで本当に良かったです。
前述の通り、尽きない反骨精神と生への渇望に突き動かされ続ける彼が自分だけの色を見つけて、真の意味で満たされるということはないのかもしれません。満たされたときが彼の人生の終わりなのかもしれないし、どこまでいっても満たされないからこそ彼なのかもしれない。人の夢はひとつ叶うたび、尽きずに生まれ続けるものですから。
2024年、ひとりのアーティストとして、作曲者のひとりとしての彼の躍進をまた楽しみに、自分もまた生きていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
