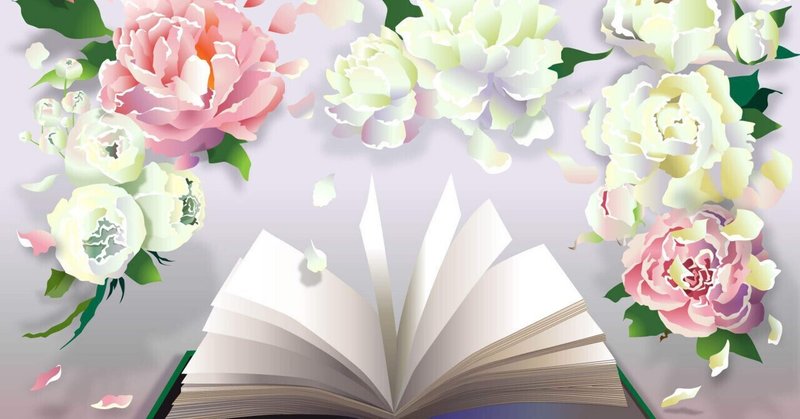
エッセイ研究(金原ひとみさん他)
最近は金原ひとみさんのエッセイを読んでいるが、彼女の美しい文章は、よく「物質」が主語になっている。
例えば。
臨界点を超えた関係の根拠は、どんなに丁寧に言葉にしても全てこじつけにしか聞こえないのだ
多彩なボキャブラリーと表現力により、その物質には誰もが納得する形容が添えられて、やるせなさ、無気力、つらさを伝えさせてくれる。
あぁ、わかるその気持ち……と、急に金原ワールドに引き込まれてしまう。
改めて思うが、モノが主語になると、人は「感じさせられる」立場になる。相当な想像力や表現力がないと、書けない。
コーヒー一杯がここにあるとして、そのコーヒーを見て何を思うのか。何を思います?
コーヒーだな……以外に、私は今のところ何も感じない。全然だめだめクリエイターだ。
比べる相手が違うのはわかってる。研究していくほかない。そのうちコーヒー一杯から切なさでも、エロスでも、怒りでも、何か感じられて表現できるようになりたい。
ちなみに私は今、金原ひとみさんだけでなく、さくらももこさんと向田邦子さんのエッセイを並行して読んでる。急にエッセイを研究したくなったからだ。
金原ひとみさんの気怠い空気に酔いしれた後に、子供の頃から好きだったさくらももこの「ももの缶詰」を読み返すと、人間の視点は各々全然違う、違い過ぎると愕然としてしまう。
カフェで隣に座ってるカップルのキスは性行為前の前戯みたいとか書いてる文章から、「私のパンツのシミは黄色でございました」と報告する男の話が出てくる文章へ移動する私は、もしかしたら鬼畜なのか?
どっちもカフェで見た人の話をしてるだけなのに、異世界に行くくらいの不思議体験をしている気分になる。
そして向田邦子さんに回ると、自分の小説に樹木は出てこない、その理由は樹木を書くとドラマ化のときに制作費が積み上がってしまうからだとか書いてある。
私はそんなこと考えて文章を書いたことなんて一度もない。これも愕然とする。
世の中にこんだけいろんな人がいて、交わりそうで交わらない世界で生きている。
そう思うと、普通に生きていく中で生きづらさがあっても「当たり前じゃん」と流せそうな気もした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
