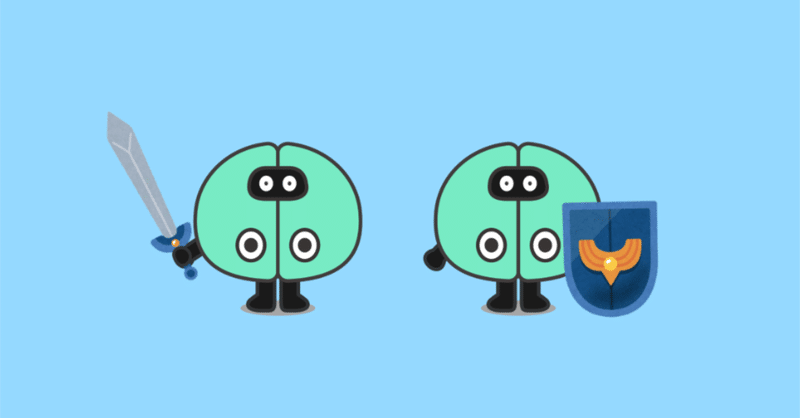
同じスキルの人が、同じ仕事をしてるのに個々のパフォーマンスに差が出るのはなぜ?
こんにちは。Jobgram公式キャラクターの「おみそ」です。

人が目標達成をする動機のポイントには、ポジティブな結果を目指す促進焦点と、ネガティブな結果の回避を目指す予防焦点の2つがあります。
この制御焦点理論について、以前の記事でお話しました。
今回は、「シチュエーションが違うと促進焦点 / 予防焦点 で結果のパフォーマンスが変わるのか?」を、研究論文を紹介しながら考えてみたいと思います。
調査の概要
【調査対象】
57名の大学生を対象に、計算問題に取り組んでもらう。
【課題内容】
第1課題:解決可能な問題(10問)
(解答時間7分)第2課題:解決可能な問題(8問)解決不可能な問題(12問)
(解答時間16分)第3課題:解決可能な問題(10問)
(解答時間7分)
【調査の狙い】
これらは、解決不可能な第2課題に取り組ませることで実験参加者に失敗を経験させ、“学習性無力感”を生じさせる課題です。
学習性無力感が実際に生じたか否かは、第1課題に比べて第3課題のパフォーマンスが低下するか、学習性無力感の症状とされる認知の問題・動機づけの問題・感情の問題が第2課題を経験した直後に生じるかによって確認しています。
また先行研究において、計算課題のパフォーマンスは制御焦点の両者(促進焦点 or 予防焦点)で有利さに差はないことが示されています。
【仮説】
『解決不可能な第2課題を経験した後の第3課題において、防止焦点条件のほうが促進焦点条件よりも課題パフォーマンスが低い』
解決不可能な問題が混入している課題という文脈でのパフォーマンスにおいて、促進焦点と防止焦点のどちらが優位となるのかを探索的に検討している調査です。
【対象者に提示した条件】
促進焦点条件:
実験参加者の課題成績が、これまでに収集したデータの上位30%以内だったら、報酬として500円分のクオカード1枚を受け取ることができるが、上位30%以内でなければ、クオカードは受け取れない。
予防焦点条件:
実験に参加してくれた謝礼として500円のクオカード1枚を渡した上で、実験参加者の課題成績が、これまでに収集したデータの下位70%以内であったら、その500円のクオカードは返却してもらうが、下位70%以内になること を回避できたら、クオカードは返却する必要はない。
調査の結果
解けない問題でも簡単に諦めない促進焦点・解けない問題を諦めて次にいくのか防止焦点
促進焦点条件:
第1課題ならびに第3課題が第2課題よりもパフォーマンスが高かった
防止焦点条件:
第1課題が第2課題ならびに第3課題よりもパフォーマンスが高かった
促進焦点条件のほうが防止焦点条件よりも、解決不可能な問題に取り組んだ時間の割合が有意に高かったという結果でした。つまり、解けない問題にかける時間がすごく長かったのです。
先行研究でも示されていた通り、計算課題のような基本的な認知能力に関しては、促進焦点と防止焦点の両者で差は見られないと考えられているわけですが、今回の調査でも、解決可能な問題のみの第1課題においては、促進焦点条件と防止焦点条件においてパフォーマンスに差は見られませんでした。
すでに手にしている利益を守りたい防止焦点・これから手にする利益を取りに行く促進焦点
そして、学習性無力感を経験した後の第3課題においては、 促進焦点条件よりも防止焦点条件のほうがパフォーマンスが低いという結果になりました。
したがって、「解決不可能な第2課題を経験した後の第3課題において、防止焦点条件のほうが促進焦点条件よりも課題パフォーマンスが低い」という仮説は支持されました。
解決できない課題に取り組んで、心が折れてしまったんですね。よって、「防止焦点の状況下では、学習性無力感の影響を受けやすい」「促進焦点の状況下では、学習性無力感の影響を受けにくい」ということが示されたわけです。
解決可能な問題と解決不可能な問題とが混在している第2課題においては、防止焦点のほうが促進焦点よりも、パフォーマンスが高い傾向にあった。
第2課題において高いパフォーマンスを示すためには、解決不可能な問題から自らを早く解放することがキーとなる。
わからない問題は捨てて、わかる問題から解こう!というのは、受験対策などでもよく聞く考え方ですよね。試験のような時間の限られた
解決不可能な問題に従事していた時間は、防止焦点条件のほうが促進焦点条件よりも短いことが示された。
防止焦点状況下では、解決不可能な問題にいつまでもとらわれることなく、切り替えて次の問題に進むことができ、その結果、解決可能な問題を解くことに時間をかけることで高いパフォーマンスを収めると考えられる。
防止焦点の人は、損失しないことへの責任感が強い傾向があります。貰ったクオカードを手放さなくていいよう、わからない問題に時間を費やして点数が下がることを不安に思った結果、すぐに切り替えて確実にわかる問題から解いたため心が折れずに済んだんですね。
それに対して促進焦点の人は、獲得することへの責任感が強い傾向があります。可能性があるならすべて挑戦したい姿勢で上から順番に解いた結果、どんなに考えてもわからない問題についても「もう少し頑張れば解けるかも……!」と多くの時間をかけ、心が折れてしまいました。
結論
促進焦点:挫折や失敗から回復するレジリエンスが優れていた。
(※示唆の段階にとどまる)
防止焦点:解決不可能な問題が混入している文脈での課題のパフォーマンスが優れていた。
「同じ作業も、条件の示し方によってパフォーマンスは大きく異なる」ということですね。
そして、この研究には「状況による制御焦点しか調べられていない」というところに限界があると論文には書かれています。
最後に、本研究の限界を述べる。
本研究では状況による制御焦点しか扱っていないという限界が挙げられる。既述した通り、制御焦点には、特性として捉える場合と、状況要因として捉える場合がある。
先行研究では、特性と状況の両者において同様の結果が得られることによって結果の頑健性を示すことが多いため、今後は、特性的な制御焦点を扱った場合に、本研究の結果と同様の知見が得られるかどうかを検討することで、本研究で得られた結果の一般化を検証していくとともに、先に述べたように、制御焦点とパフォーマンスのメカニズムについて検討していく必要があるだろう。
Jobgramでも導入してくださっている企業に対しては、まず募集ポジションの役割などをヒアリングして「状況」を把握した上で、性格診断によって候補者の方の「特性」を明らかにし、互いにマッチするかを分析しています。
このように、「状況」と「特性」の両方で以って、その人に合ったポジションがわかるのです。
おみそのまとめ

今回は、「制御焦点とパフォーマンスの関係性」についてあれこれお話しました。
解けない問題をすぐ諦めて解ける問題と向き合う防止焦点、解けない問題にも可能性がある限り取り組む促進焦点。同じ課題に対しても、パフォーマンスがこんなに異なるとは驚きです。
Jobgramが主にサポートしているスタートアップは、社会にまだない新しいビジネスモデルを創り出すため、存在自体が「解けない問題」といえます。
防止焦点の人は、そもそも解けない問題に取り組むことをせずに目標を達成するタイプなので、スタートアップという環境においては離職に繋がりやすかったりします。(おみそが見てきたスタートアップで起こる短期離職のうち、体感だと7割くらいがこのパターンです)
解ける問題は能力さえあればみんな解けるので、能力以外の部分が大事なのです。だからスタートアップにおいては、解けない問題にぶち当たった時、諦めずに進み続ける促進焦点の人が活躍しやすいようです。
でもここで忘れないでほしいのは、「わからない課題に取り組めない防止焦点の人」はスタートアップ企業において不要かというと、全くもってそうではないということ。会社として必要になる時期・場面が必ずあります。
つまり、ポジションが持つ役割を明確にし、それぞれのポジションに適した人を配置することがいい組織を作るためには大切だということですね。
また余談ですが、選考プログラムの中に「お試し副業」がありますよね。これは転職のミスマッチをなくすための方法ですが、スタートアップで必要とされている0→1を作るポジションに対して、今回の調査でいう第1課題のような「能力だけでこなせる仕事」だけをしても、ミスマッチを減らす施策としてはあまり意味がないはず。
でもお試し副業のメンバーという立場上、そういった能力だけでこなせる仕事だけ担当するケースも多いようです。
今回参考にした研究論文でも、
本研究の結果は、計算課題といった基本的な認知能力を測定する課題のタイプにおいては、促進焦点と防止焦点でパフォーマンスに差は見られないものの、文脈によってどちらの制御焦点のパフォーマンスが優位となるのかが異なることを示した点において、意義深いと考えられる。
とあります。お試し副業という取り組み自体は有効ですが、その期間で何をしてどのように判断するかがとても重要なのです。
おみそはこのお話を通して、「スキルさえ一致すれば採用!」という構造は絶対間違っている!と改めて感じました。
我々は、能力だけでなく社内の状況や、そこで働く人の特性を考慮した採用を実現するプロダクトをつくっていきます。
制御焦点をはじめとする性格特性を診断したい人はこちらから(無料・所要時間の目安5分)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
