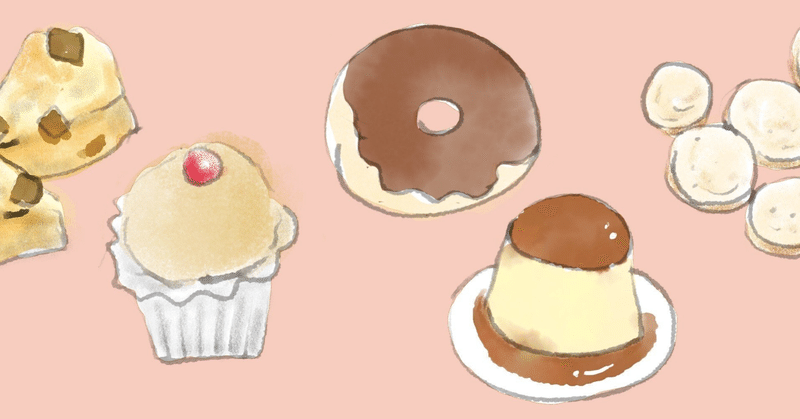
子育て、今思えば……。別に好きなことがなくても大丈夫です③
「好きなことがあるのはすばらしい」
「好きなことがあれば大丈夫!」
そういう風潮の中で、〝そこまで好きなことがない〟息子を育てながらずっと引け目を感じてきました。
そして今思うのは、別にそれで問題ない、ということです。
たとえば勉強なら、超得意や超苦手がなくても好き嫌いくらいはいずれ出てくるもの。だからそれに合わせて入試のタイプを選べば良し。何か1つ秀でた人のための入試も増えていて、それはどこかキラキラして見えますが、ふつう組はふつうの入試を選べばよいのです。
今はいろいろなパターンがあるから、自分がとりやすい戦略を考えればOK。
たとえば趣味なら、you tubeばかり見ていて心配とは言っても、やはり好みのジャンルは出てきます。うちの息子は野球系が面白かったようで、今はメジャーリーグを真剣に追っています。それに、音楽を聴くならV tuberメインのようで、そちらも大のお気に入りがいる模様。
息子はこの春高校を卒業しましたが、以前より趣味がはっきりしてきたように思います。
高校まではやはり生活も決まりきっているし、学校の行事やスケジュールも細かく決まっているので、〝好き〟がそこまで極まっていない子にとっては、「こういうのが好きかな」程度にしか表に出ない。けれども大学生になると時間割も自分で決めるし、生活時間の使い方もかなり個人の自由になってくるから、〝好き〟が見えやすいのかもしれません。
今になってみれば、小さいころに〝好き〟が薄かったことは1つの特徴でしかない。それがずっと気になっていたのは、私自身のコンプレックスのせいだったのだなと、最近になって思いました。
よくよく考えると、私自身も「何しろこれが好き!」「こればっかりしている」的なことがなくて、それを心の奥で気にしていました。
推し活するほど推したい人もいないし、やりたいからといって仕事や家事が滞るほど熱中してしまうものもない。そういう自分をどこかで〝つまらないな〟と評価していたから、息子に対してもいらだって、焦っていたのだと思います。
子育てって、本当に自分の隠れた気持ちや願望を子供にぶつけてしまいやすい。「子供に対してそれを望むなら、じゃあ、自分はどうなの?」と聞いてみたらよかったのに、なかなか気づけませんでした。
というわけで、子供に特に好きなことがなくても大丈夫、成長するにつれて勝手に自分が楽しいことをしているようになります。大人も好きなことに対していろいろな熱度の人がいるように、子供もそれぞれ。
あと、我が子にいらだってしまう時は、自分自身にそれに関するコンプレックスがないか振り返ってみるのもヒントになるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
