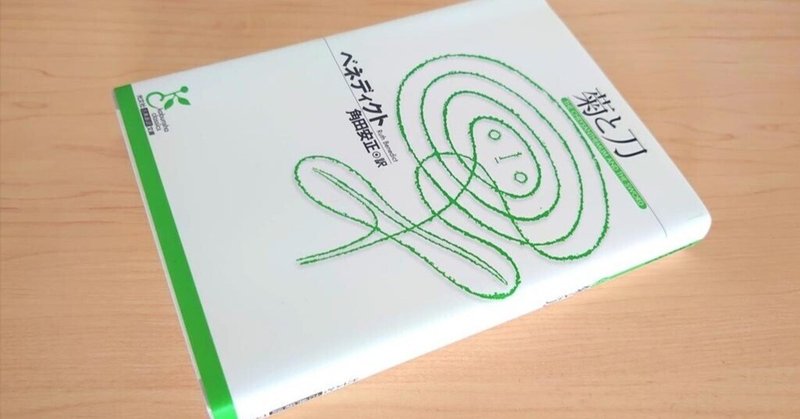
読書記録|ルース・ベネディクト『菊と刀』
読了日:2023年7月27日
1946年に出版されたもの。著者はアメリカの文化人類学者で、第二次世界大戦中の1943年、勤務していたアメリカ戦時情報局からの依頼で、アメリカ人から見て”不可解”な日本人の気質や生活、行動を研究する。
彼女は実際に日本へ来て、日本の文化と日本人を直に触れることは叶わず、日系人を対象としてインタビューを繰り返し、その報告書を仕上げた。そのわりに日本人とその生活、日本人が好きな事柄、苦手な事柄、自分の欲望よりも人目を重要視する文化、無言の同調圧力などで空気を読んで周りに合わせる性質、”恥”に対する概念など、様々な件についてとても詳細に描写されており、膨大な日本の文献、歴史書などにも目を通したであろうことが伺える。
その研究結果である報告書を、手直しして書籍にしたのがこの『菊と刀』である。副題は「Patterns of Japanese Culture(日本文化の型)」。
日本人というのは、アメリカ人から見るととても理解に苦しむ民族らしい。確かに私自身、「日本人のこういうところは不思議だなぁ」と思うこともままある。が、大抵のことについて、「〜だから、〜する」というロジックというか、心理的動機があるのはわかる。これは日本人だからだろうか。
日本人である自分がアメリカ人が書いた(しかも今から78年以上も前に)、日本人についての解説書のようなものを読むと、改めて気付かされることがある。しかし、その殆どは過去の時代の日本人についてであり、本の中で書かれる子育てや、家庭の在り方、家族の食事風景などの内容については、現代の頭で読むと時代錯誤に陥る。よって、『菊と刀』は第二次世界大戦の頃の日本文化、風景を思い描きながら読む必要がある。すると、本の内容を違和感なく受け止めることができる。
とはいえ、歴史というのは途切れることのない”時”の積み重ねなので、日本人の根本にある思想、連綿と受け継がれてきた礼儀作法など、現代日本人にも当てはまる部分も書かれている。
戦前の日本の歴史に関しては、偏りのない事実そのままが綴られており、更に『忠犬ハチ公』や『坊っちゃん』など、実話を元にするものも含む著名な作品の引用もあったりするため、多くの小説などもベネディクトは熟読していたことを思わされる。
特に印象に残ってるのは、第10章「徳目と徳目の板挟み」で引用される『忠臣蔵』で、これはもはや引用というより物語の終始を簡潔に書き切っていて、この部分だけで映画を一つ観た気分にさえなる。何なら何度も映画で観て、何度も同じシーンで「吉良のやつめ…」と思ったあの時の感情まで湧いてくる(笑)。
この本を読み進めていくと、言葉では綴られていないが、時々、白人至上主義というか日本人を見下げたようなニュアンスを感じる部分がある。これは全く個人的な感覚で、私が日本人だから批判的な内容に感じてしまっただけなのかもしれないが、なるべく中庸な意識で読むように留意した。
しかし考えてみれば、この本が出版されたのは終戦直後で、著者はアメリカ人。実際に日本に来て生活をした人でもないわけで、潜在的に敵国である日本人を多少は見下げる意識があっても、それは人間の行動心理として当然とも言える。
そういった意味で、当時の日本人の観察とは逆に、「当時のアメリカ人は、日本人のことをこう見ていたのか」という逆の観察もできるのかもしれない。
そもそもこの本の原型となる”報告書”は、日本人をどのような方法でアメリカの都合の良いように統治すべきか、そのための研究材料だったのだから、日本人を見下げたような部分が見えても何の不思議もないことだ。それが良いとか悪いとかではなく、勝戦国が敗戦国に対する当然の振る舞いだろう。著者の職業からしても。
以前に読んだ『「空気」の研究』は日本人が書いたもので、私にとってはとても面白く思えた本だったが、『菊と刀』のように、別の国、別の人種から見た日本と日本人像も知ることは、自分自身や日本人全体、そしてこの国を俯瞰する上でとても良い教材となると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
