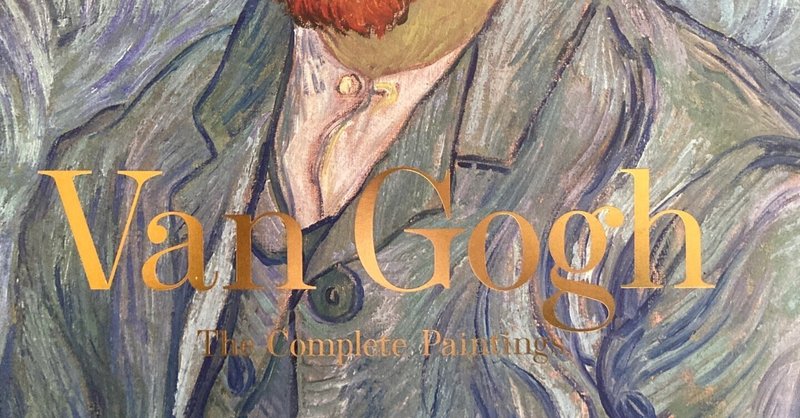
ヴァン・ゴッホについてのメモ
近代絵画とは19世紀に始まる絵画史の重要なジャンルであり、現代の芸術は近代絵画を基礎として発展した。
その代表的な作家ゴッホについて、断片的に書きます。
画題について
・宗教的類型にもとづいて対象を理解し、画題とすることがみられた。画題のリアリティは、対象に置くのではなく、対象の解釈に置かれた。解釈の手立てとなるのはバイブルである。象徴としての、多くのモチーフが、画面に現れたが、ゴッホにとり絵の対象となった人物は、関わりのある生身の人間ではなかった、との記述が見られる。(pp.22 'The complete painting Van Gogh')
神を太陽に、信仰心を向日葵に、といったように、宗教理念と自然物との間に象徴、意味生成がある。
・文学
ゴッホはフランスの自然主義者を賛美している。(ゾラ,フロベール、ギ・ド・モーパッサン、ド・ゴングール、リュシバン、ドーデ、ユイスマンス)
ゾラは、印象派の画家にとってモチーフである家具がリアルであるのと同じように、対象としての家具のリアリティを自身の文章の中に描写している。
ゴッホが求めたのは「ありのままの人生」だと言われている。従来のキリスト教世界には求めても得られなかった「ありのままの人生」は、自然主義文学の中に見出された。
・協同
南仏に画家の協同生活を作る願いがあった。従来の画家たちの社会を、お互いの画家としての特質を学び合う繋がりを作り、変化させることで、従来にない絵画を創作しようとした。
・ゴッホの日本
自己を、小さな花のように自然の中に咲いているものと感じながら、描く。小さな芽の観察からはじめて、次に自然の雄大さ、最後に人間を観察していく。
また、ゴッホにとっての日本の中では、人間の間に調和があった。ゴッホの日本は規範である。絵としての規範と、社会としての規範の両面を担っている。
理念を現すために、ものに即しているということを大切にした。ものを「現出させる」つまり、手で掴めるようにリアルに描くこと。
混色による泥のような画面の制作。
色彩の研究をした結果、純色の色面から更に進んで、混色を用いた。
感情の極にある、ふるえるような線を生み出した。線の可能性を高めた。
象徴する色彩を使用したのはゴッホが最初である。
闇の中に光があるとの着想は、旧来のキリスト教にあり、また、ゴッホにもあった。様々な象徴が生み出された。
「近代絵画」は、意味生成という虚構でありかつリアルであるという、複合した特質を持つと言える。このことは、形相が、現実の中に生成している、ということの、確かな証拠としての絵画の成立を意味している。
つまり、神はこの世界を美しく作った、ということ、これが「近代絵画」の持つパワーである。
参考図書『ゴッホ 日本の,夢に懸けた芸術家』圀府寺司 平成22年初版 角川文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
