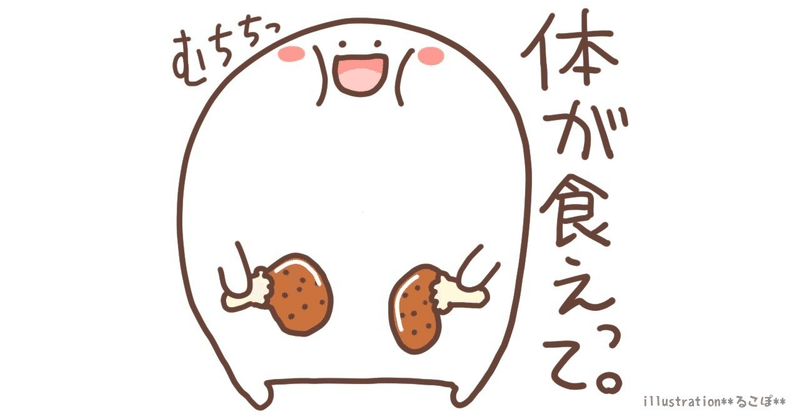
なぜ「ついやってしまう」のか
「またやっちゃった…」
「本当は良くないと思うんだけどな…」
本当はあまり良くないと思っているのに、
「ついやってしまう」
そんな経験は、ありませんか。
私は、大いにあります。
体によくないのに、
ついコンビニで揚げ物を買ってしまう。
目が休まらないのに、
ついスマホを見てしまう。
「わかっちゃいるけど、やめられない」
これは、
私たちの意志が弱すぎるのでしょうか。
お寺に行って、坐禅を組んで
背中を叩いてもらうべきでしょうか。
いえ、そうではなく、
私たちが「ついやってしまう」問題は
人間の「行動のしくみ」に
ありますよ。
というのが、
今回の記事です。
ACTに関する記事で少し触れたのですが、
もう少し一般的なところを書いております。
行動するには理由がある
なぜ、私たちは、
「やめたい」と思う行動を
「ついやってしまう」ことがあるのでしょうか。
結論から言うと、
「ついやってしまう」ことにも
メリットがあるからやってしまうのです。
心理学の応用行動分析という分野では、
私たちの行動を
「ABCフレーム」という枠組みで分析します。
(下図)

ABCとは、3つの文字の頭文字です。
「A」はAntecedent = 先行事象
(行動のきっかけとなる状況)、
「B」はBehavior = 行動、
「C」はConsequence = 結果事象(行動による結果)です。
例を入れて、見てみましょう。

例えば、
「ついやけ食いしてしまう」
という人がいるとします。
何の理由もなく、
その行動をとるわけではありません。
振り返ってみれば
会社で嫌なことがあったとき
ストレスがかかったときに
やけ食いをしているようです。
やけ食いをして、
その人がどのような結果になるか
考えてみましょう。
やけ食いをすることで、
お腹がパンパンになった満足感があり
気持ちがスッキリするでしょう。
でも、食べ過ぎは健康によくないことも
周知の事実です。
だからこそ、
この人は「よくないよなぁ」と
思い悩んでいるのです。
でも、やっぱり
気持ちがスッキリするんですよね。
この場合、
「気持ちがスッキリする」という結果が、
「やけ食い」という行動を
またやりたくさせているのです。
これを、心理学では「強化」と言います。

でももし、やけ食いの結果
「胃腸を崩して入院した」
となったらどうでしょうか。
結果事象の「健康に損ねる」が
強くその人の印象に残り、
やけ食いをやめるようになるでしょう。
このように、
自分にとってよくない結果から
行動をしなくなることを
「弱化」と言います。

意図的に「弱化」しよう、
ということは難しいですし、
よくない結果に陥ることもあります。
なので、
多くは「強化」によって
よい行動を増やしていこう
という方向へ考えていきます。
さてここで、
あなたが「やめたい」と思う
行動について考えてみましょう。
先ほどの表を
空欄にして載せますね。

やり方としては、
まずBの部分に「やめたい行動」を記入します。
次に、その行動をとるときの状況を
Aの部分に記入します。
ここには、
「誰かに何か言われた」という外的なものも
「何かを思い出した」「◯◯な気持ちだった」
という内的なものも書いてみてください。
最後に、
Cの部分に行動の結果を記入します。
ここにもAと同じく
外的なもの(自分や人に与える影響等)と
内的なもの(気持ちや考え等)を書いてください。
Cをいくつか書いたら、
おすすめなのはそれを
短期と長期という視点で分けることです。

多くの場合、やめたい行動は
短期的にはプラスだけど、
長期的にはマイナス、というものです。
気晴らしのやけ食いとか、
やけ酒、衝動買いなど。
まず、こうして
紙に書き出して客観視することが、
自分の行動を変えていく第一段階です。
頭の中だと、
わかっているつもりになってしまい
なかなか変えられないものです。
こうして書き出したら、
同じような状況のときに、
その行動を取らずにいる方法を考えます。
といっても、
「やけ食いをしない」というのは
よい目標の立て方ではありません。
私たちは、
否定の目標をうまく達成できません。
なので、
同じような状況のときに
「気持ちがスッキリする」
他の行動を用意しましょう。

あなただったら、
「?」に何を入れますか?
運動をする
カラオケに行く
音楽を聴く など
スッキリするけど、
健康を損ねないものを
用意しておきましょう。
実際にやってみて、
「やけ食いよりいいな!」という
感覚が得られたら、
その行動をとるようになります。
おわりに
このABCの枠組みで、
自分の行動を分析してみましょう。
人生は、行動によってつくられます。
だからこそ、行動を変えることは
人生を変えることにつながるのです。
こうした行動の問題は、
こちらのACTの記事でも触れています。
ぜひご覧ください。
最後に、短期的・長期的に
何がプラスかマイナスか、
というのは、その人によって異なります。
これはつまり、
人生で何を優先するかという
価値基準の問題です。
私は、テツガクという言葉で
この価値基準の問題についても書いています。
ご興味ありましたら
お読みくださいませ!
よろしければサポートをお願いします!いただいたサポートは活動費に使わせていただきます。
