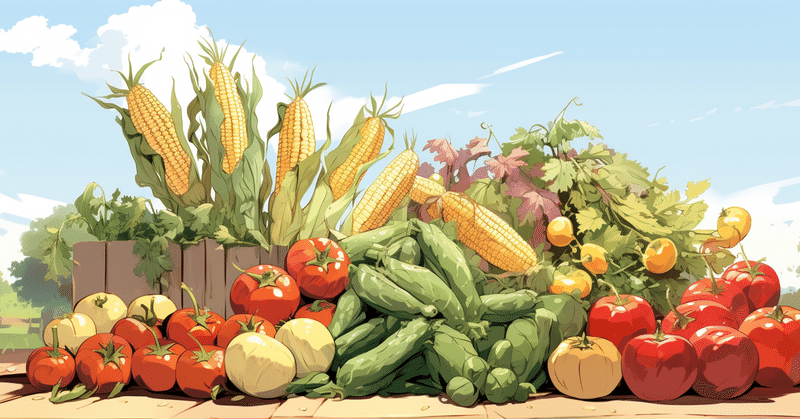
「成長」マニアが知るべき2つの視点
成長マニアになっていないですか?
就活で「圧倒的成長」という言葉が持て囃されている。
「今日も成長できました」
「仕事を通して成長できました」
悪い言葉ではないが、あまりにもこれを神聖視すると、足元を掬われる。
かと言って成長以外にも大事なことがあるとか、スローライフをしようとかそういう話ではない。今日気づいたのは、成長速度と成長の加速度の話だ。
これについてはここ1年ほど、よく考える事が多くあり、いくつかのnoteを書いた。このノートではなにかに備える事について以下のような事を書いた。
「次のステップで使う」ならやってもいい。だが「いつか使う」はダメだ
また種を蒔く時期から収穫の時期へ移り変わる変化として青春から朱夏への移り変わりついて考えた。
今日はこの2つの点と点が繋がったので忘れないうちに言語化しようと思う。
まず、勉強や何かに備えることの取捨選択について
大学院での学びの終わりが見えてきた頃から、「何もしなくても成長する時代」が終わったことに気づき始めた。基本、生きていれば何かしらの学びがある。人生の序盤においては何をしても学ぶ事になるし、適当に生きていてもそれなりに幅広く経験と知識が積み上がっていく。この薄く広い経験の蓄積は、その後の専門性を積み上げる時の土台になる。より堅苦しい言葉で言えば、広い意味での「教養」にあたる。
でも途中から、既に学んだことの繰り返しになる。また自分とあまりにも関係のないことを見聞きしても、教養こそ広がるが、自分の専門性に繋がらない。だから成長を続けるためにはちゃんとある程度戦略を組んだ学びをしないといけない。
これは別にそんな難しいことでもないし、専門バカになれという話でもなく、今自分が何かに注いでる労力がちゃんと自分の専門性なりキャリアにどうつながるか説明できれば、実際につながるかどうかは別にいいと思う。
極端な話、宇宙物理学が好きな医者がいたとして、趣味で日経サイエンスを読んでるなら教養だけど、「もしかしたら太陽フレアの活動の周期と特定の疾患日がリンクしているかもしれない」「その仮説を検証するために自分は太陽フレアについて学識を深めるぞ」であれば成長だろう。
何をやっても学べる時期というのは、成長速度も大きいが、成長加速度も大きい。そしてやがて、大人になって成長が止まるように見える、もしくは最盛期を超えて衰え始めるようにみんな思っている。でもそれは多分正しくなくて、正確には0になったりマイナスになるのは成長速度ではなく、成長加速度なんじゃないかと思ってる。
つまり成長をぐんぐん進める勢いは止まるけど、個々人の能力というものは、適切にケアすれば、勢いこそ落ちるが、壮年期もゆるやかに伸び続けるものだと考えてる。その適切なケアというのが難しいが、これは有限のリソースを正しい方向に分配する、つまりは学びやトレーニングの取捨選択をするということだと理解している。
もう一つは成長から収穫を意識したリソース管理について。
子供の頃、世界中の偉人たちの伝記を読んだ時、乱世の英雄などを除けば、多くの者が30歳(もしくは30代)の時までに成し遂げた事が人生を通して強力に本人を押し上げているイメージがあった。パッと思いつくのはハイデッガーの教授就任年齢が34歳だったりとか。
そうなると単に成長させるだけじゃなくて、ちゃんと何らかの成果として目に見える形で成長を可視化する視点が必要になってくる。それは別に受賞だとかSNSでのインプレッションとかに限らず、業界内においてXXならこの人に聞こう、という信頼だったりなんでもいいのだけれど、このあたりから所属組織の肩書よりも自分の存在感を出していく必要なんだろう。リクルート社員とかコンサルはだいたい30から35くらいで独立していく人が多いし。
そうなると、単に成長だけではダメだということがわかる。数学のテストで100点を取るのは立派だが、食ってくためには未知の問題を解いたり、あるいは他の人が100点を取れるようにしなければならない。同様に、筋力があるだけではダメで、ホームランを打ったり、誰よりも速く100mを走らないといけない。種をまき、芽吹いたものが実を結ぶように成長をマネジメントしないといけないし、収穫するだけならいつか枯れてしまうので、ちゃんと次の種もまいて、時流にキャッチアップしておかないといけない。
こうやって書くとわかるけど、やることが多すぎる。そして同時に、それらのやり方はもうだいぶ知っている年頃でもある。だから何をやったらいいかわからずに途方に暮れるということよりも、やるべきことはわかっていて、それをいつ、どこで、どのようにやるかを常に考えて動き続ける事になる。そしてだからこそ1つ目で述べたように、戦略的に動かないと成長スピードを鈍化させてしまう。
一見すると今日言及したこの2つの視点は相反する事に思える。「いつか役に立つかもしれない」事を後回しにすることは学びの軽視でもあるし、収穫を意識して次や次の次の収穫のために種を撒くことは学びの励行でもある。でもこの2つは表裏一体で、学んだ知識を活かす事に忙しくなるからこそ、わざわざ「学ぶ」ということにリソースを消費するからにはそのリソース配分を戦略的に考えて学ぼうね、という話につながる。
これは今日の気づきを忘れないように書き起こし、自分の思考を整理するために書いたものなので荒削りではあるけれど、多分同い年くらいの人々には役に立つんじゃないかと思います。楽しめたならイイねして。
それじゃ、また。
よろしければサポートをお願いします。主として生活の再建と研究の継続のためにありがたく使用させていただきます。また記事にて報告とお礼いたします。
