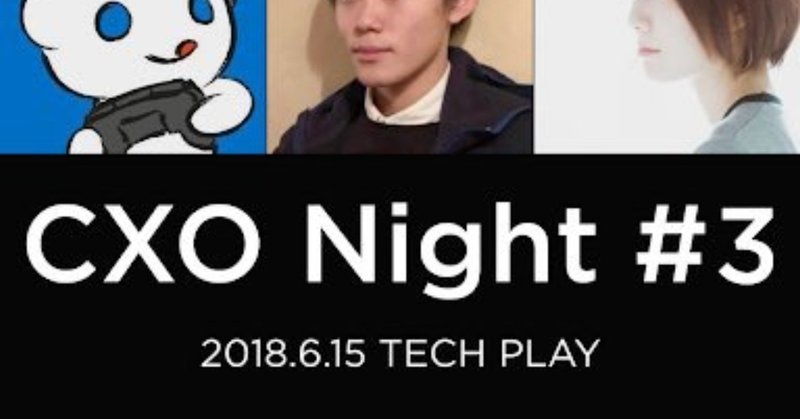
デザインを越境せよ CXO night 「デザインが越境するのだ」

Takram田川さん、Ideoの田仲さん、the guild代表の深津先生、豪華すぎるメンバーによる、純度100%の蜂蜜よりも濃い50分のトークイベントでした。
あまりの濃さに進行役の塩谷さんでさえ取り残されてしまったご様子。しかし、あの三人に話の種を装填し続けるその姿はまるで戦場の指揮を執る軍師のようでした。恐れ入った。
CXO night
感想を言えと言われると、なんとも濃い時間だったとしか言えません。僕も流されてました。隣の人の立派なヒゲに見とれていたときもありました。僕も前までは立派なヒゲを持っていたのですが、朝起きたらどっかへ行ってしまいました。どこへ行ったのか検討もつきません。旅にでも出たのでしょうか。
本題に戻りましょう。CXO night のトークをnoteに写してくれる方はいるので、美大生である僕が感じたことを話させていただこうと思います。
今回の話の主題は、もちろんCXO nightなのでCXO系の話です。今回はタイトルの通りデザインを越境する事がテーマです。何を越境するか、とても多くのことが話されてましたね。統一した一つの事を話し合うという
デザインがビジネスを喰い殺す
「デザインがビジネスを喰い殺す」初っ端からブッ込んできた深津先生の核心をついた言葉から始まりました。恐れ入った。天晴。
クリエイティブの力を使って、本来はビジネスを助ける役割だったデザインが、良い美しいデザインを求めすぎて、ビジネスを破壊してしまう。ということらしいです。なんと恐ろしいことか。ビジネスマンがデザインが理解してもらうのは大事ですが、デザイナーもビジネスを理解するのも同じくらい大事ですね。
そのまま、その三人で様々なジャンルでのトークが始まりました。
デザインが超越する
僕がとても気になったのが、「デザイン」というものがビジネスで、ユーザーにとって、どういったものなのか。でした。
Takram田川さんは、御社デザインエンジニアなどの例をあげつつ、デザイナーの役割や会社におけるデザイナーがいまどんな立ち位置にいるかなどを解説されました。そこで面白かったのが「デザインを越境する」のではなく「デザインが越境するためのメソッド」と捉えました。
でかい課題があってそれを分解して分解してたくさんの小さい課題にして、それを処理するのがエンジニアやデザイナーに処理してもらう。それが一般企業の理想的なモデルだとおっしゃられました。しかしリアルでは上手くいかない。
「デザイナーの立ち位置は、ユーザーの立ち位置になって楽しんだり体験したりすることをユーザーのように考えてプロダクトをよくする事」

「デザイナーは一つの狭い領域ではなく、唯一飛び越えて大きな課題に対してデザイン的アプローチを全体に持たせることである
その点で行くと、デザインを越境するのではなく、デザインが(ビジネスの垣根を)越境するというべきなんです」

確かにその通りであります。デザインがですねガガガガガ
多摩美でたくさんの有名なデザイナーの方から教えをいただいていますが、ビジネスと絡んだ話をしてくれる方はいません。100%デザインの話をします。もちろん、ちゃんとした技能や思考が身についていないと、デザイナーとしてやっていけないので当たり前ですね。ビジネスが絡んだ話は応用編といったところでしょうか。しかし大学で学んでいても悪くない内容だと思います。
ユーザーはメーカーの都合なんて知ったこっちゃない
心に残った言葉をもう一つ紹介します
「ユーザーにとってデザイン思考とか、広義のデザインとか狭義のデザインとかどうでもいいんです。むしろユーザーが見るのはで全く言及されないデザインの色や形なんです。」

ユーザーが結局見るのは1つのプロダクトだけです。メーカーの都合なんて知ったこっちゃないんです。もちろん、そういうのはあってもいいんですけど、最終的にプロダクトのクオリティを良くして、って話ですね。まさにデザイナーの真骨頂といった感じですね。こういった大事なことを、デザイン思考を育んでる学生時代に教えていただくのがとてもありがたかったですね。
個人的に心に強く残っているのはこの二つですね。とても勉強になり、素晴らしい講義でした。
これだけじゃなく、他にも様々なお話をいただきました。また次の機会を楽しみにしています!以上美大生から見たCXO nightでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
