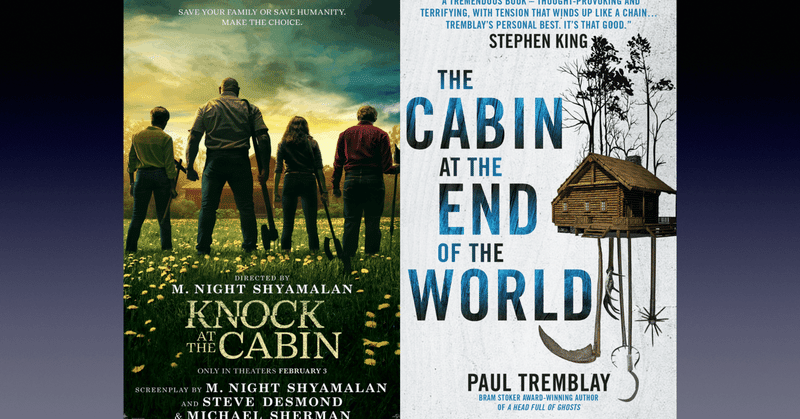
映画と原作小説で比較してみよう【ノック終末の訪問者】
ネタバレ全開で語りますのでご注意を!
▼あらすじ(映画版):
第一幕
森の奥の小屋でバカンスを過ごす3人家族(ゲイ夫婦のエリックとアンドリューと養子のアジア系少女ウェン)のところに、カルト的な信仰者4人組(教師レオナルド、看護師サブリナ、料理人アドリアネ、電機技師レッドモンド)が訪れる。4人組は小屋を強盗してゲイ夫婦を拘束し、アポカリプスを防ぐために3人の中から1人の犠牲者を選ぶことを迫る。4人組はある日、共通の『ビジョン』を得て集まったのだと主張する。
第二幕
ゲイ夫婦は拒否するが、4人組は代償として順番に仲間を殺していく。最初にレッドモンドを殺して、テレビをつけると世界で大地震と津波が起こる。早く選択しないとこのまま世界で犠牲者が増えると主張する。
次にアドリアネを殺して、テレビをつけると新種のウイルス感染症が特に子供達に有害であり大量に死んでいると報道される。アンドリューはいずれも偶然の一致であり、4人組の教義はデタラメであると主張する。
縄を解いて飛び出したアンドリューは車から銃を取り出し、サブリナに致命傷を与えるも、小屋でレオナルドに銃を奪われる。レオナルドがサブリナにトドメを刺すと飛行機が次々と墜落する様子が報道される。
第三幕
レオナルドは「自分が死んでから数分あるから選択しろ」と言い残して自殺する。雷と嵐が勢いを増す。
小屋を強盗された時に後頭部を床に打ちつけて脳震盪を起こしていたエリックは光に敏感になっていたが、レッドモンドを殺すときに鏡で見た閃光は宗教的啓示であり4人組は「ヨハネの黙示録の四騎士」であるろ確信して、自分を犠牲者に選べと主張する。今やエリックも『ビジョン』を得たのだ。彼には将来幸福に暮らすアンドリューとウェンが見えている。
小屋でエリックを射殺したアンドリューはウェンを連れて車で小屋を後にする。小屋が落雷で燃える。近くのダイナーのテレビで2人はアポカリプスが終わったことを知る。…エリックの死に意味はあったのか、真相は分からない。
▼あらすじ(原作小説):
第一幕は同じなので省略します。
第二幕
ゲイ夫婦は拒否するが、4人組は代償として順番に仲間を殺していく。最初にレッドモンドを殺して、テレビをつけると世界で大地震と津波が起こる。早く選択しないとこのまま世界で犠牲者が増えると主張する。
アンドリューは偶然の一致であり、4人組の教義はデタラメであると反論する。エリックは光を見て、4人組の言い分を信じ始める。
次にアドリアネを殺そうとした時に、縄を解いて飛び出したアンドリューは車から銃を取り出し、屋外でアドリアネを射殺する。
小屋に戻ったアンドリューはレオナルドと銃の奪い合いになり、はずみでウェンを射殺してしまう。しかし自ら選んだ犠牲ではなくて事故死なので、これでアポカリプスは止まらないとレオナルドは言う。
第三幕
子供の死に絶望して信仰心を失ったサブリナがレオナルドを殺す。サブリナはゲイ夫婦を4人組の車まで誘導して、「自分が死んでから数分あるから選択しろ」と言い残して自殺する。
車に残されたゲイ夫婦は、ウェンの遺体を抱き抱えながら話し合い、アポカリプスを信じる信じないに関わらず2人から犠牲者を選ばないと決意する。…これから何が起きるのか、2人には知る由もない。
▼シャマランぽくない?:
本作はシャマラン映画なのにシャマラン映画っぽくない、と評価されがちです。確かに撮影監督が『スプリット』以来の相棒マイク・ジオウラキスから、ジャリン・ブラスキー(ロバート・エガースの全作品を担当)に変わっていることもありビジュアルの雰囲気が少し違ったかもしれません。
しかし一番の原因は、ラストで「大どんでん返しが起きない」ことでしょう。絶対に何か裏があるやろ、と思って観ていたオーディエンスは「素直に終わるんかい!」とツッコミを入れたくなる人も多かった筈です。
ただ、本作に関しては、これまでのシャマラン映画と異なり、原作小説が存在するというのが特色だと言えます。ストーリーがオリジナルであれば最後にド派手なちゃぶ台返しも出来るかもしれませんが、他人の作品ならばラストの変更は難しそうです。
しかし調べてみると、先にあらすじに書き出したように、原作小説とシャマラン版映画ではラストが大きく異なることが分かりました。
▼変更点の整理:
映画版では以下の通り変更されました。
映画版
1)ウェンが死なない。
2)レオナルドが最後に残る。
3)エリックが自ら犠牲になることを選ぶ。
4)事後にアンドリューとウェンが犠牲について考える。
小説版
1)ウェンが事故死する。
2)サブリナが最後に残る。
3)エリックが自ら犠牲になることを望む。
4)アンドリューとエリックで相談して犠牲を選ばないと決める。
見た目上のインパクトが一番大きいのは少女が死なないことでしょう。
実は本作はシャマラン監督作品としては『アフター・アース』から10年ぶりで2作目の共同脚本の監督作品となっています。この小説からの変更点については共同脚本を務めた2人(スティーブ・デスモンドとマイケル・シャーマン)がVarietyに理由を語っています。
「私達は少しだけ本に変更を加えた。それでシャマランも真新しいビジョンに基づく結末を持った。小説は小説、映画は映画だ。そしてどちらも傑出していると思う。これは世界に広く公開される映画だから、非常に多くの観客の目に触れることになる。それには小説の内容はやや暗すぎて、やり過ぎだろうと判断したんだ。これにはシャマランもすぐに同意してくれた。今じゃ素晴らしいエンディングになったよ」
“We adapted it slightly different than the book, and then [Shyamalan] had a whole new vision for what the ending could be,” Desmond and Sherman told Variety at the “Knock at the Cabin” premiere. “The book is the book, and the movie is the movie, and we think they both were exceptional mediums. This is a big, wide release movie that is meant for a very large audience. There are some decisions that the book made that were pretty dark and may have been a little too much for a broader audience. That was a decision that [Shyamalan] immediately recognized. It’s a great ending now.”
なるほど、ダークすぎる展開を弱めるために子供の犠牲を無くしたと。しかし、映画全体のメッセージという意味では、より大きなインパクトを持っていたのは、結末で「エリックを犠牲者に選んだ」ということでしょう。
▼結末の意味が完全に逆:
原作者(ポール・トレンブレイ)は、小説では「わざと曖昧にすることで残した希望」が、映画版では失われた(むしろ絶望的になった)と話しています。
私が恐ろしいと思うのは、特定の誰かを否応無しに、皆のために犠牲するような強大なパワーがあるということです。それはモラル的に良いと言えるものじゃないですし、だからこそ私はそれを絶望的だと思います。私が小説の中で描いたのは、2人の主人公がそうしたパワーを拒否したことなのです。「違う。僕らは犠牲を払わない。そんなのは間違いだ。僕らは僕らの道を行く」ってね。そちらの方が希望があると思います。
“I find it horrific there’s this higher power that is just going to willy-nilly sacrifice humans for everybody else,” he said. “It doesn’t seem like a very moral thing to do, so I don’t find it that hopeful. I find the idea of what happened in my book — that the two characters reject that, like ‘No, we’re not going to sacrifice. That’s wrong. We’re going to go on.’ That’s a little bit more hopeful.”
小説版では、アポカリプスがこのまま最後まで進んで人類が滅亡したのか、実はアポカリプスは嘘っぱちで世界には何も起きなかったのか、結末までは描かれません。しかしこうして曖昧に残しておくことで、人間には宗教や思想を押し付けられない選択肢があるという「希望」を残しています。
一方で映画版では、主人公ゲイ夫婦が4人組の教義を受け入れて犠牲を払っていますから、これはゲイ夫婦が思想的にカルト教団に屈したことを意味します。つまり作品全体での人間の「思想の自由は奪われた」と言えます。
たしかに映画では「10歳の少女が命を奪われる」という痛ましい展開は回避できましたが、もっと究極のテーマまで広げれば、人間の自由の敗北であり、希望が失われたとも言えるでしょう。原作者はそこに重きを置いてのコメントだと読み取れます。とても業の深い話ですね。
▼小説版だけに描かれた人間の業の深さ:
そういう意味では、小説版のサブリナの行動も興味深いです。4人組だったサブリナが、少女の死に際して信仰心を失い、寝返ってレオナルドを殺します。これは『一度は信じた教義があっても人はいつでも考えを変更できる』ということを表していて、やはり人間の思想の自由を描いていると言えます。
さらに小説版ではサブリナは寝返ったように見えながらも、結局は4人組の計画通りにビジョンに従って自殺しますし、ゲイ夫婦には「アポカリプスを防ぐために犠牲を選べ」と遺言を残しているので、『宗教を信仰しながらも人は間違いを起こすことはあるし、その上で再び信じていた教義に戻って行動して良い(神は人間を許してくださる)』という側面を描いていて、これも物語に深みと厚みを与えています。
宗教を信じる側の人達にも揺らぎや乱れは起こりうるというのは、すごく人間臭い描写になっていて、私は良いと思います。
2時間の映画にまとめるためにサブリナのエピソードはカットせざるを得なかったなど意図は色々と推測できますが、少なくとも映画が物語をシンプルにしているのは確かですね。
▼そもそもタイトルが異なる:
これは結構重要なポイントです。
映画:
Knock at the Cabin
(ノック・アット・ザ・キャビン)
(小屋での強盗)
小説:
The Cabin at the End of the World
(ザ・キャビン・アット・ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド)
(世界の終わりの小屋)
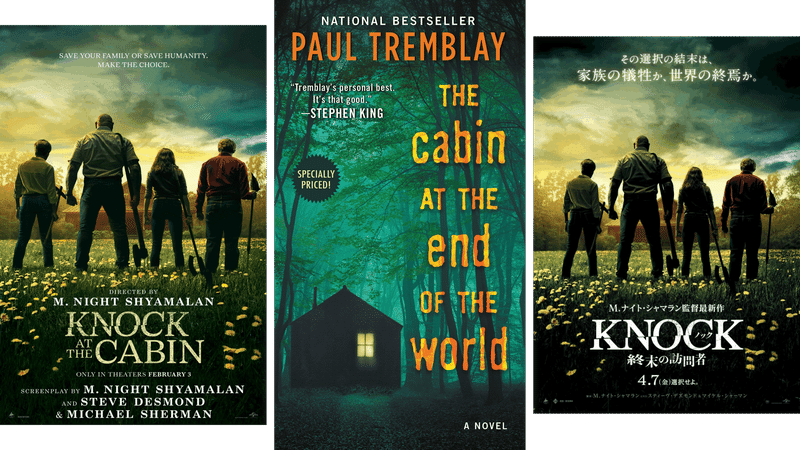
日本版映画のタイトル(ノック:終末の訪問者)は小説版と混ぜたようなヘンテコな題名ですが、原題ではそれぞれがフォーカスするものを的確に表しています。
映画版は「強盗」であり、小説版は「小屋」です。
英語では前置詞で付け足された句はあくまで修飾(かざり)ですから重要度は下がります。また英語では重要な名詞ほど前方に持ってくる傾向もあります。
映画:Knock (at the Cabin)
小説:The Cabin (at the End of the World)
日本:Knock and Visitors (of the End of the World)
映画:強盗
小説:小屋
日本:ノック、そして訪問者
こうして日本語タイトルをもう一度英語に変換すると、どのくらい本家に忠実なのか分かりやすくなります。「訪問者」という要素は完全に日本オリジナルであり、厳しく言えば『余計な付け足し』です。
また日本語で「ノック」と言うと、ドアを行儀良くコンコンと叩く意味になりますが、そもそも行儀が良いのは日本独特の文化で、英語で「ノック」と言うと、もっと相手に注目させるために激しくドアをガンガン叩くイメージになります。日本と違って欧米は家が広いので奥まで声が届くように大きな音を立てる必要がありますからね。
ノック(knock)は相手を殴る意味にも使われる単語で、ボクシングの「ノック・アウト」とか「ノック・ダウン」という言葉にも使われます。そして、ここから転じて、ノックという単語だけで「強盗」という意味にも使われます。日本語でも強盗のことを隠語で「タタキ」と言うのと同じですね。

もしドアを優しくノックするという意味にするなら、前置詞をATではなくてONにするべきです。ONには(ピタッとくっつける)という意味があり、ATには(広い範囲から一点を決める)という意味があります。ATにすることで、「森の中にポツンと佇む小屋でノック(叩き)があった」という客観的なニュアンスが生まれます。
逆にONにしていれば、目の前のドアを叩くニュアンスになります。

さらに日本語タイトルでは日本配給の独断で「訪問者」とも追記されています。これでは訪問販売員のイメージが付き纏うので、まさかノックアウトのノックだとは想像が及びづらくなります。日本人の多くが「誰かが行儀良く家を訪ねてきて優しくノックした」というニュアンスを感じるしょう。しかし実際に映画で起きているのは強盗です。ドアや窓を押し破って4人組は強行突破してきます。
例えばサッカーの国際試合を一つ見るだけで海外勢はファウルやマイボールのアピールが大袈裟なように、海外ではそもそも他人のことを引き止めて自分に注目を向けさせるという態度が普通なので、ノックも日本人が想像しているよりはかなり激しめなアクションを含みます。
シャマランの映画版も、その国際標準の「ノック」がタイトルになっているので、ある小屋で起きた「強盗」にフォーカスを置いており、だからこそデイヴ・バウティスタのような屈強な俳優を使って、ある小屋がカルト宗教の4人組に襲われる光景を刺激的に描いています。
この映画には複数種類のポスタービジュアルがあるのですが、日本版と異なるデザインのものでは小屋が襲われる部分にフォーカスしているのがよく分かります。

もし本作でも往年のクラシック映画のように、全て翻訳して日本語タイトルをつけるなら『小屋強盗』とか『小屋たたき』あたりが適切だと思います。(…現状よりも客入りが悪くなりそうですけどね:笑)
一方でトレンブレイの小説版では、世界の終わりがきた時の「小屋」にフォーカスしています。
こちらもイメージで分かりやすくするために書籍のカバーをいくつか並べてみましょう。見て分かる通り、原作小説での主題は強盗でも終末でもなくて、小屋です。

つまり「世界の終わり」が訪れたときに、その「小屋」で起きる事件について描いたのが小説版であり、そこでは強盗に入る(入られる)という一つの要素の主観的な視点よりも、人間が宗教的な啓示とどのように向き合うのかという客観的で突き放した視点に重きが置かれています。
逆に言えば、シャマランが敢えて主観的で劇画チックなタイトルに変更したことから、映画版でシャマランや共同脚本担当者がやりたかったことが見えてきます。このようにタイトルだけでも深読みすると面白いですね。
▼その上でシャマランはミスリードもしている:
エンドクレジットは最後まで観ましたか?
最後は音楽がなくなって、劇中でレオナルドがしていたドアノックの音が響きます。私の記憶が確かならば、本編でドアを叩いた時と同じ音が使われていたと思います。リズムと音程が一致しているように聴こえました。
ここから映画版のタイトルは強盗とドアノックのダブルミーニングだったと思われます。そうでなければ、あそこまで強調しないでしょう。
ゴン、ゴン、ゴン、ゴン、ゴン、ゴン、ゴン。
私が観ていて気になったのは、叩く回数です。
7回叩いています。
回数については本編を観覧しているときから異様に感じたので、すぐに音声を脳内再生して7回だと確認したのでよく覚えています。エンドクレジットの最後でも7回でした。
キリスト教で7と言えば思い出すのは「七つの大罪」です。おそらくレオナルドが7回叩くのは、それに肖ったのかなと思います。

このような宗教的な意味づけは他にもありそうで、キリスト教に詳しくなればもっとたくさんのディティールが見えてくるのかもしれないですね。
了。
最後まで読んでいただきありがとうございます。ぜひ「読んだよ」の一言がわりにでもスキを押していってくださると嬉しいです!

