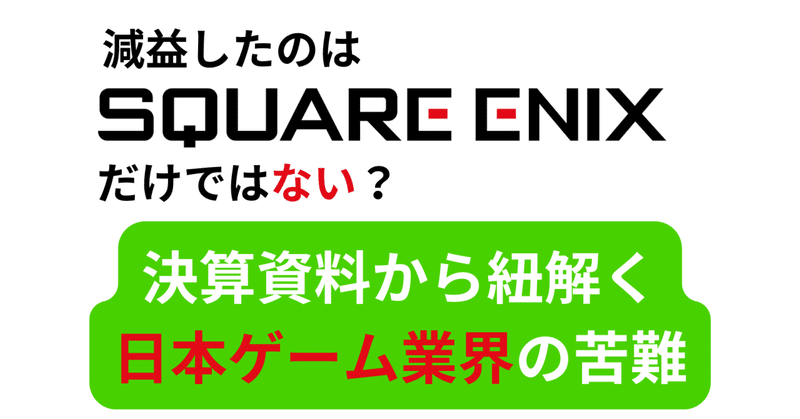
「減益したのはスクエニだけではない」決算資料から紐解く、日本ゲーム業界の「真実」
スクウェア・エニックス(以下、企業名は一部省略)が苦しんでいる。24年3月期決算によれば、営業利益は前期443億円から325億円と26.6%減らした。このため、数々のゲームメディアやSNSでは同社に対し嘲笑的な風評が寄せられ、5月13日まで約6300円だった株価も約5300円と急落した。結果、スクエニは今日本で特にネガティブなイメージのある企業となったことは否めない。

しかし筆者は、この報道には疑問がある。
スクエニが減益で苦しんでいるのは事実だが、それは何も、スクエニだけの問題ではないからだ。
具体的には、コーエーテクモの営業利益も前期比で391億円から284億円と、27.2%減らした。
セガサミーの営業利益は全体では21%の増加だが、これは遊技機事業(パチンコ)の大幅な利益増に支えられたもので、エンタテインメントコンテンツ事業(ゲーム)では411億円から307億円と25.3%減少している。
バンダイナムコはより深刻であり、ゲームを含むデジタル事業の利益は493億円から62億円と約87%もの大幅減益となった(この原因は後述する)。
少なくとも営業利益、つまり主にゲームを中心とした事業による利益だけでみれば、決してスクエニだけが減益しているわけではない。それどころか、コーエー、ナムコ、セガと日本を代表するゲーム企業がいずれも25%以上の大幅な減益を迎えており、日本ゲーム業界全体が「まずい」状態にあるのは否定の余地がない。
そもそも営業利益と純利益の区別も曖昧な一部の報道はともかく、実のところ、国際的にみてもゲームビジネスを適切に「批評」している場所は、あまり多くない。
そこで、「ファミ通ゲーム白書」の一部執筆に携わるなどゲーム市場に対する一定の取材経験を持つ筆者なりに、今回は2023年における日本ゲーム業界の大幅減益を皮切りに、2010年代後半から現在に至る約10年もの間、日本国内におけるゲーム市場がどう変化し、今後どう至るのかという「日本ゲーム経済への批評」を行いたい。
先に断っておくと、今回扱う問題の原因は「ゲームが面白い/つまらない」という作品批評的な問題だけではない。もちろんゲームが面白ければ売上も伸びるが、純粋にゲームビジネスという観点において問題はそう簡単ではない。(余談だが、ゲハに毒された独占プラットフォーム云々という議論もあまりに的外れであり、ここで扱わない)
なぜゲーム市場は不況に苦しんでいるのか
先に断っておくと、本稿は絶対的・究極的な解答ではない。経営的な議論はどう転んでも様々な利益の観点から複合的に論じられるべきであり、そもそもあらゆる経営上のファクターを十把一絡げに論ずることは物理的に不可能だからである(もし可能なら、私は株取引で大金持ちになっているか、インサイダー取引で牢獄の中であろう)。
以下に論じる見解はあくまでJini個人の見解であり、「これを読めば株で儲かる」というよくある有料noteとは全く異なる点をご了承いただいたうえで、お読みいただきたい。
さて、まず経済の基礎として、競争市場を左右するものは需要と供給である。そしてスクエニやセガが減益を余儀なくされた原因は、このうち特に需要にもある。
ゲーム市場の需用を知るべく、単純に、ゲームの市場規模から概算してみよう。ファミ通ゲーム白書によれば、2018年、世界のゲーム市場規模は13兆1774億円だった。それからゲーム市場は爆発的に拡大し、2021年には21兆8927億円、2022年で26兆8005億円と成長している。つまり、ゲーム市場はたった4年で倍増という未曾有の好景気にみまわれていたのだ。
つまり、ゲーム市場は実のところずっと好景気だったのである。言い換えれば、この好景気に陰りが生じた……早い話、バブルが弾けたことが後の問題につながってくる。では、この背景に一体何があったのか?これは大きく分けて2つ考えられる。
まず1つ目として挙げたいのが、「①Switchの成功」だ。2017年、任天堂が発売したハード「Nintendo Switch」は誰もが知るように、ゲームハード史上でも稀な成功を収めた。
2024年3月現在、Switchは約1億4000万台の販売台数を記録しており、1位のPS2の約1億5500万台に次ぐ約1億4000万台を記録。先日、次世代機の存在が発表されたといえ、その名前も姿すらわからない現状とあっては、恐らくSwitchは今後も売れ続け、PS2の記録を塗り替え「史上最も売れたゲームハード」として記録される可能性が高い。

Switchの成功は任天堂のみならず、サードパーティにとっても大きなチャンスとなった。単純にハードの数だけリーチできる消費者が広がるからだ。そのためSwitchのヒットがゲーム市場全体に好景気をもたらしたと考えるのは自然なことだろう。
もう1つ、ゲーム市場の拡大に大きく貢献したのが「②コロナ禍の巣ごもり需用」だ。
既に記憶にも新しいように、新型コロナウィルス感染症により、人々は自室での「自粛」を余儀なくされた。その結果、外食、観光、レジャーといったアクティビティが制限されてしまった。そこで注目されたのがゲームのように家から出ずに楽しめる娯楽、いわゆる「巣ごもり需要」である。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する「東京アラート」の発動を受けて、都庁舎が赤色でライトアップされていました。
— 東京都 (@tocho_koho) June 2, 2020
不要不急の外出を控えること、夜の繁華街など3密の危険がある場所には十分注意することなど「新しい日常」の徹底にご協力をお願いいたします。#今日の都庁 pic.twitter.com/dnuG1285J0
コロナ禍の本格的な流行は2019年、自粛を余儀なくされたのが2020〜2022年だ。これは世界のゲーム市場が倍増した頃とぴったり重なる。ゲームの他にも、映像、音楽、YouTubeなどウェブプラットフォームの伸びも顕著であり、巣ごもり需要がゲーム市場に好景気をもたらしたことは客観的に明らかだ。
この2つの条件を整理するうえで、以下のデータを見てほしい。これは「ファミ通ゲーム白書2023」内に掲載されたデータ「総評:ゲーム産業をとりまく経済動向」から引用し、再度グラフにしたものだが、これを読めば明確に①、②の理由から、特に日本のゲーム市場規模が好景気を迎えたことを理解いただけるだろう。

まず、2016年までの日本の家庭用ゲーム市場規模は4年で4464億円から3439億円まで縮小するなど、著しく衰退していた。一方GDPは微増といえ、528兆円から542兆円と微増している。
しかし、2017年にNintendo Switch(②)が発売するとゲーム市場規模は一転して4464億円と1.3倍近い成長を果たす。
更に2020年、コロナ禍(①)による自粛が始まると、GDPは552兆円から528兆円と大きく転落したのに対し、ゲーム市場規模は更に1.3倍、2016年当時の1.6倍という、(特に家庭用ゲームでは)極めて対照的な成長を遂げている。
このように「①Switchの成功」「②コロナ禍の巣ごもり需用」という2つの点でゲーム市場は前代未聞の好景気に恵まれた。
しかしこの好景気は、2023年突如として停滞してしまう。
Newzooのデータによれば、2023年の市場規模は2022年とほぼ横並びの約26兆円。しかもこれは為替を考慮しない日本円であり、ドル計算であれば、2022年の市場規模が2035億ドルに対し2023年は1840億ドル。2022年まで順調に伸びていた市場規模は、2023年に突如として衰退を始めたのだ。
一体何があったのか。実はこれこそ、先程述べた「好景気の要因」を考えれば、逆引き的に理解できる。
つまり、大成功を収めた「①Switchの成功」も発売から6年経過した2023年では勢いが失われた上に(ただし他のハードと比べると、6年後もなお驚異的な勢いを残している)、競合から発売された次世代機の「PlayStation 5」「Xbox Series S/X」は、半導体不足による初動の躓きや、コロナ禍における初期ラインナップの乏しさなどによって、「Switch」ほどの勢いは作り出せなかった。また同時期には、日本でも「5類」に以降されるなど事実上の終息宣言が出されており、それによって「②コロナ禍の巣ごもり需用」も無産してしまった。
このように2022年までゲーム市場の好景気を支えてきた「①Switchの成功」「②コロナ禍の巣ごもり需用」は、それぞれ①→発売から6年経過した上での失速、②→コロナ禍の事実上の終息という形で、それぞれ失われ、各社の減益へと繋がっていった。言い換えれば、ここ数年の好景気は偶然の重なった「バブル」的なもので、いずれは弾けることが前提の偶発的なものだったとも言える。
またこの需用のバブル的な増減と同様に、ゲーム企業が苦しむ要因はいくつもある。一つはゲーム開発費の主たる要因である、人件費の高騰。日本は世界的にみて賃金の伸び率が悪いといえ、それでも国税庁の調査によれば、2014年の平均給与が約421万円だったのに対して、2022年の平均給与は458万円と1.08倍に増加している。そのうえ昨今では、ゲーム開発に携わる人数が増えたり、開発期間が伸びることによって、更にこの人件費は増していく。
他にも苦しむ要因があるのだが、これは一旦置いておく。とにかく、バブル的な好景気が弾けた上での不安材料もいくつか残っており、総合的にみて、ゲーム市場は束の間の好況を終えてしまったことこそ、スクエニのような大企業がいくつも減益になってしまったことの真の要因であり、作品ごとの売上や「面白さ」だけで判断するのが早計であることは理解できるだろう。
しかしこれはあくまでゲーム市場全体を、かなり俯瞰的に見た分析ならない。単にSwitchやコロナ禍だけでは説明できない問題が、別に存在するのだ。
「沈むゲーム業界」の中で、「浮かぶ」ことに成功した日本ゲーム企業の正体
ここまで述べたように、ゲーム業界はバブル的な好景気にみまわれたが、その要因がはじけるとともに急落した。しかし、この一般論では十分な説明とは言えない。なぜなら、このバブル崩壊後においても、はっきりと減益していく「沈み企業」もあれば、逆に増益し続ける「浮かぶ企業」があることを説明できないからである。
冒頭で論じたように、スクエニのほか、バンナム、コーエー、セガといった日本企業は一律減益した。彼らはまさに「コロナ禍の終息」「Switchの長期化」に加え、開発費の高騰などの悪影響によって減益を余儀なくされた。ここまでは、ある程度ゲーム市場に詳しければ知っている一般論だ。
しかし、実は全ての日本企業が減益したわけではなく、むしろ、さらに増益に成功した「例外」が存在している。では、その「例外」とは一体どんな企業なのか。
───────────────
以下、有料部分では
・増益に転じた「浮かぶゲーム企業」の紹介
・「浮かぶゲーム企業」増益した理由の分析
・減益したスクエニやセガと「浮かぶゲーム企業」の違い
・2010年代から顕著な日本ゲーム市場の特徴
・これらを踏まえ、減益したスクエニやセガはどうすれば増益できるのか
について、本格的に論じています。いずれも、経済的な掘り下げが不十分なゲームメディア、逆にゲームの知見が不十分な経済紙にはあまり掘り下げきれていない、ビデオゲームを取り巻く経済への分析・洞察となっており、ゲーム業界の関係者、ゲーム市場に関心のある方には、かなり興味深い内容になっています。
購読いただければ、「The Last of Usの真実」などの作品批評を含めた記事もまとめてお読みいただけます。
───────────────
ここから先は
「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。
