
Ubisoftとアサシンクリードの「真実」──欧州ゲーム産業から『シャドウズ』問題まで
日本を舞台に、アフリカ人の「弥助」を主人公の1人にすえた『アサシンクリード シャドウズ』。その作中描写や開発者に対し、国内外で大きな批判が展開され、ついに先日Ubisoftが公式に謝罪するに至った。
しかし、SNSやYouTubeなどでこの『シャドウズ』問題をめぐる意見を読んでいても、ゲーム文化にきちんと立脚した意見はあまり見られない。仮にゲームに詳しくともUbisoftやアサシンクリードまで理解した意見は多くないし、先日放送されたAbemaでも問題提起したゲストを含めた全員が「アサシンクリードは知らないけど」と前置きされていた。

現在、『シャドウズ』を取り巻く問題はすでに国際的なものに発展し、ゲームコミュニティを飛び出している。また問題の対象も、Ubisoftが『シャドウズ』開発に参考にしたと思われる一部の歴史家やその著作をめぐる史学的問題まで拡げられるなど、もはや収拾ができないほど拡散してしまっており、筆者もこれら全てを認知できているわけではない。
しかし、問題に対してどんな立場を取るにしても、ゲーム文化やゲーム産業に立脚した知見──とりわけ、『シャドウズ』を開発した当事者であるUbisoftや、『シャドウズ』以前から続く「アサシンクリード」シリーズへの知見、ひいては「なぜUbisoftが『シャドウズ』を作ったか?」という仮説──がないまま、議論が進んでいることには、一人の作家として危機感を覚えずにはいられない。
日本ではあまり知られてこそいないが、実はUbisoftは欧州最大のゲーム企業であり、その経済的・文化的影響は絶大だ。さらに「アサシンクリード」シリーズも17年以上続くシリーズで累計2億本も売れるなど、日本でいう「ファイナルファンタジー」に匹敵する(FFは累計1億8500万本)ほどの人気ゲームだ。

そこで本稿では、この『アサシンクリード シャドウズ』の問題を「きっかけ」として、Ubisoftとアサシンクリード、ひいてはこれらを生み出した欧州ゲーム産業という構造について、ゲームジャーナリズム的な立場から膨大な資料と論理をもちいて「真実」を追求したいと思う。
皮肉だが、今や『シャドウズ』問題によって、日本人にも本来その影響力から注目されてしかるべきだったUbisoftと「アサシンクリード」が大きな注目を集めている。だからこそ、この記事では『シャドウズ』問題を理解するヒントのみならず、ゲームファンなら知るべき欧州ゲームの本質について理解できる、かつてないゲーム批評に挑戦できたと自負している。
また、筆者はUbisoftの作品には20年以上に渡ってプレイし、特にアサシンクリードはナンバリング本編すべて(13本)をプレイするほか、実際に何本も批評した経験があるなど、この企業とシリーズに対しては一定の知見があり、だからこそこの企業の持つ魅力や課題を理解している自負がある。
もし特定のイデオロギーに対する賛同ではなく、純粋にビデオゲーム文化や産業に関心があり、今回の問題を冷静に理解したいと考えている人がいれば、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いである。きっと今回の問題が落ち着いた後にも、役立つ知見が必ずあるはずだ。

シャドウズ問題の整理
まず今回『アサシンクリード シャドウズ』(以下、シャドウズ)を巡って展開された論点は、おおむね以下のようなものがある。
・『シャドウズ』トレイラーで散見された歴史的正確性を欠いた描写
・インタビュー等で発信された『シャドウズ』の開発者の発言
・「弥助」と呼ばれるアフリカ系を主人公にしていることの恣意性
・Ubisoftが参考にしたと思われる「弥助」伝承の学術的根拠
・Ubisoftが参考にしたと考えられる歴史家とその著作『信長と弥助 本能寺を生き延びた黒人侍』への疑問視
・コンセプトアート等に著作物を無断使用とした実例
こうした現在指摘されている問題に対し、筆者個人としての結論は、本稿の末尾まで控えておく。
第一に、どの立場であれイデオロギーありきの結論には賛同しないし、その結論だけで記事を「切り抜き」されることを避けたいこと。第二に、上記の論点やそれに対する反論そのものに一部疑問が残ること。第三に、この議論にはゲーム文化に対する理解(Ubisoftとアサシンクリード)が不足しており、その状態で結論を出すのは早計だからである。
だから筆者はあくまでこの問題を理解するうえでのヒントとして、今回の記事──特に、欧州最大のゲーム企業「Ubisoft」と、その看板タイトルにして『シャドウズ』も類する「アサシンクリード」、それらを生み出した「欧州ゲーム産業」──の本質について議論したいと考えている。
ではUbisoftと「アサシンクリード」の本質を、どういう順番で議論していくべきか。それは、以下の順番で考えている。
・Ubisoftとアサシンクリードの客観的な説明、特にUbisoft創業の1980年代から「アサシンクリード」が誕生した2000年代まで
・Ubisoftと「アサシンクリード」が誕生した土地、「欧州ゲーム産業」の日本・北米と異なる、歪な構造
・Ubisoftの肯定的な補足 特に2010年代、フランス・カナダ系ゲーム企業としてもたらした、オルタナティブの批評性
・『シャドウズ』に至る2020年代におけるUbisoftの「衰退」と、その主な2つの原因について
このように、筆者にとって、あくまで『シャドウズ』問題はUbisoft、アサシンクリード、それらを生み出した欧州ゲーム産業の、結果的な帰結に他ならないという立場を前提に議論を展開していく。累計約2万字のかなり長い批評となるため、ある程度、時間に余裕のあるときに読んでほしい。
(なお歴史的な問題に関しては、本稿では扱わず、原則として専門家である歴史研究家の方々に委ねたいと考えている)
良くも悪くも今回の問題は『シャドウズ』というタイトルに限った話ではない。偶然、「日本」という我々が当事者となる文化が土台となったことで、これまでUbisoftとアサシンクリードが抱えてきた矛盾と魅力が表面化したことにあると思う。
では具体的に、Ubisoftとはどのような企業で、アサシンクリードとはどんな作品だったのか。こうした客観的な歴史を振り返りながら、上記の問題へと踏み込んでいきたい。
Ubisoftとアサシンクリードはどう生まれたのか──1980〜2000年代のUbisoft
最初に、前提知識としてUbisoftとアサシンクリードはどう生まれ、どう発展していき、どんな立場にあったのかという事実を整理したい。
繰り返すように、Ubisoftは世界でも有数の大企業でありながら、不思議と日本では会社そのものに注目が集まることは稀だ。そんなUbisoftだが、実はなかなかにユニークな出自である。実はUbisoftはヨーロッパ、それもフランスのゲーム企業なのだ。
Ubisoftはブルターニュで農家を営むギユモ家の5人の兄弟(クリスチャン、クロード、ジェラール、ミシェル、イヴ)によって創設された。ギユモ家はもともとはゲームと全く縁がなく、農具などを扱っていたが、やがてIT時代を見越して農家相手にCDやパソコンを扱っているうちにゲームソフトに手を出すことになったという。

ギユモの兄弟たちが創業した1980年代当時、すでにアメリカのアタリや日本の任天堂を筆頭にコンソールゲームビジネスは勢いがあったが、フランスではまだコンソールゲームに馴染みがなく、流通も少なかった。そこに好機があると考えた農家の5人兄弟は、最初に輸入代理店として会社を創設、後にUbisoftとする。こうしてゲームをフランスに輸入していくうち、自分たちでゲームを開発したいと考えるようにもなった。
そしてUbisoftは1987年に初めて『ゾンビ』を開発し、1995年には『レイマン』と呼ばれるアクションゲームを生み出し、これがヒットした。
コミカルなルックスと、美しいアニメーションと音楽、そんなフランスらしいアート重視のスタイルが評価され、世界的な称賛を得る。以降、「レイマン」は現在まで続くゲームシリーズとなり、累計で2000万本を売れるなどUbisoftの看板タイトルとなった。

(※余談だが、マリオシリーズなど伝統的なアクションゲームに触発を受けた「レイマン」は、現在では「スーパーマリオ ラン」や「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」などの現代マリオシリーズにも大きな影響を与えているなど、批評的にも価値が高い。)
「レイマン」のヒットにより、Ubisoftはフランスで頭角を表す最初のゲーム企業となった。フランスのゲーム企業で初めて上場した(1996年)のも、Ubisoftだった。
しかし、フランスのゲームマーケットはとても小さく、限界がある。そこでギユモ家が考えたのが、アメリカを含むグローバル市場への売り込みと、その手段としてアメリカのゲーム企業Red Storm Entertainmentの買収と「トム・クランシー」ブランドの確立だ。

Red Storm Entertainmentは冷戦を背景に、アメリカの軍事・歴史小説を手掛けてきた作家、トム・クランシーが経営する会社だ。同社はそんなクランシーの軍事へのこだわりが全面的に反映されたゲーム『Tom Clancy's Rainbow Six』などを販売し、一定の評価を得ていた。「レイマン」を看板タイトルとするUbisoftにとって、Red Stormはまさに正反対の企業だったが、だからこそ海外進出には必要だと考えて彼らを買収することにした。

このUbisoftの目論見は大正解だった。Red Storm Entertainment買収以降、Ubisoftは「トム・クランシー」のブランドから「レインボーシックス」のみならず、広大な戦場における攻略を楽しむ「ゴーストリコン」、ステルスゲームの新解釈「スプリンターセル」など、今も続く人気シリーズを何本も確立。これにより、FPSや軍事ジャンルの需要のあったアメリカで、Ubisoftの名は一気に広まることになる。

こうして子どもが楽しめる「レイマン」、大人向けの「トム・クランシー」という2本の柱を確立したUbisoftは、もう一つの主力商品を手に入れるべく買収に動いた。
それが玩具企業マテル社傘下のSoftkeyで、同社には大衆的なゲームIPがいくつか所有あった。中でもUbisoftが目をつけていたのが「プリンス・オブ・ペルシャ」で、買収によって権利を得るとUbisoftは同シリーズの続編『プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂』を発売。アラビアン・ナイト的な異国情緒あるファンタジー作品として同作はヒットし、Ubisoftの3本目の柱となった。

さらにUbisoftは買収と並行して、開発スタジオの多角化も進めた。1997年にはカナダ・モントリオールに開発拠点「Ubisoft Montreal」を設立。モントリオールはカナダの中でもUbisoftと同じフランス語の話者が多いケベック州にあること、またケベック州がゲーム企業への財政援助を申し出たこと、さらにアメリカへの地理的な近さなど、様々なメリットがあった。このUbisoft Montrealは後にUbisoft最大の開発拠点となる。
ここまで長くなったが、ここからようやく登場するのが本題の「アサシンクリード」である。
すでに3本の柱を確立したUbisoftではあったが、ここまでのゲームはあくまで欧州のゲーム企業としては大作でも、ActivisionやTake-Twoなどアメリカの大企業が手掛ける大作と比れば中規模の作品が多かった。そこで、いよいよ本格的な大作……わかりやすくオープンワールド作品を手掛けようと試みた。
そこで着目したのが「プリンス・オブ・ペルシャ」だ。実は本シリーズのスピンオフとして「アサシンクリード」は開発されていた(開発当時のタイトルも「Assasin's Creed」ではなく「Prince of Persia: Assassin」というものだった)。しかし、開発を進めながら成功が見込めるとなると、これまでUbisoftが培った資金や技術、そして新たに作ったUbisoft Montrealの開発力を総動員し、単なる外伝ではなくUbisoft最大のオリジナルAAA級タイトルとして開発することになった。
このUbisoftの技術と予算を注ぎ込んだ「アサシンクリード」は、発売するとたちまち成功を収める。すぐ続編の『2』を出すと、こちらは一層のヒットを飛ばし「アサシンクリード」は人気シリーズとして確立。累計で2億本も売り上げるUbisoftを象徴するゲームシリーズにまで成長した。

この「アサシンクリード」の成功で手応えを得たUbisoftは、後にも「アサシンクリード」と同じシステムを流用したオープンワールド作品……「ファークライ」「ウォッチドッグス」「ゴーストリコン」へと展開し、Ubisoft=オープンワールドゲームの印象を強くするに至った。
ここまで、簡単にUbisoftとアサシンクリードの略歴を説明してきた。ここまでで、おおむねこれらの概要については理解できたと思う。特に要点として、
・Ubisoftはフランスで創立されたが、米国市場で成功することで欧州ゲーム企業として唯一無二の地位を確立した企業である。
・Ubisoftの歴史は「レイマン」により輸入業者からオリジナル開発へ移行した「導入期(1986〜1999)」、「トム・クランシー」「プリンス・オブ・ペルシャ」により米国市場での成功を掴んだ「成長期(2000〜2007)」、「アサシンクリード」によるオープンワールドAAA級タイトルの成功を経た「成熟期(2007〜)」という、主に3つの時期に分類できる。
・「アサシンクリード」はUbisoft最大の成功作であり、象徴作でもある。以降、Ubisoftは「アサシンクリード」に倣ってオープンワールド大作(ファークライ、ウォッチドッグスなど)を生産していく。
といった事情を、ひとまず踏まえておくことができた。(他にもUbisoftの手掛けた作品……例えば、Annoシリーズなどのシリーズも紹介したいところだが、ここでは割愛する)
もっとも、ここまではあくまで一般論として、事実の整理にすぎない。ここからは、こうした前提知識を踏まえつつ、より批評的にUbisoftとアサシンクリードの本質とはどういうところにあるのかを考えていこう。
「欧州ゲーム産業」の正体──Ubisoftとアサシンクリードの真実
ここまで、Ubisoftが創業してから2000年代に「アサシンクリード」を作るまでの簡単な歴史を確認してきた。これはあくまで表面的な前提知識として伝えたものだが、ではこれがどうして『シャドウズ』の問題に繋がるのかと疑問を持った方も多いだろう。ここからはUbisoftと「アサシンクリード」のより本格的な批評へ踏み込んでいきたい。
ではUbisoftとアサシンクリードの本質とは、ずばり何なのだろうか。ここで重要になってくるのが、Ubisoftは米国でも日本でもなく、「欧州」というゲーム文化として非常に独特な地域に根差した企業である、ということだ。
上述したとおり、Ubisoftはフランスの片田舎、ブルターニュで創業した。以降もフランスに本拠を置き、開発拠点も世界各国にありながら、フランス語圏であるカナダのモントリオールにある。つまり生粋の、ヨーロッパゲーム企業なのである。
ではこの欧州、ヨーロッパが一体どのように「アサシンクリード」および『シャドウズ』の問題に繋がってくるのか。ここで重要になるのが、ゲーム産業における欧州の特殊性だ。
ゲーム業界において、ながらくゲーム市場の中心は日本・米国・欧州の三大地域だった。
モバイルにゲーム市場が拓かれて以降は中国も有力な市場となったが、コンソールゲーム市場においては依然この三大地域が中心となる。実際、「ファミ通ゲーム白書2023」によれば、コンソールゲームのソフトの市場規模の割合は米国が44%、欧州が32%、東アジア(ほぼ日本)は9%。つまり欧州は米国に次ぐ、2番目に大きな市場ということがわかる。

しかし、欧州はこれほど大きなシェアを持っていながら、実際に市場で人気のあるゲームは「欧州のゲーム」ではない。
同じく「ファミ通ゲーム白書2023」に掲載された、欧州イギリスにおける企業別シェア率を見ると、1位がEA(15%)、2位がTake-Two(10%)と米国の企業が続く。そこで辛うじて欧州のUbisoftがランクインするものの、それ以下は任天堂、スクエニ、カプコン、ソニー、ワーナーなど日米の企業が続き、Ubisoftを除く欧州企業が「一社も」ランクインしていない。

しかも、ソフトの販売本数でも、2022年に大ヒットした『エルデンリング』を除けば、「FIFA」「GTA」といった米国の定番タイトルが上位を占めている。

このEUの市場状況は、日本・米国・欧州のゲーム三大市場の中でも「異例」だ。日本においては、言わずもがな任天堂を筆頭に日本企業による日本ゲームが売上の上位を占める。米国においても、日本ゲームが一部ランクインするが、多くは米国産のゲームだ。
対して欧州は、Ubisoftを除けば米国産ゲームと日本産ゲームばかりで、欧州産のゲームはほとんど遊ばれていない。しかも米国産ゲームの中でも、もっとも売れているジャンルが「FIFA(EA SPORTS FC)」「NHL」「F1」などスポーツゲームで、いわゆる”ゲーマー向け”なゲーム=Ubisoftの扱うゲームがほとんど売れない。
つまり欧州は、長年ゲームを「輸入」するばかりで「輸出」できなかった唯一の「ゲームの貿易赤字地域」なのである。もちろん欧州にはCD Projekt、Guerrilla Games、DICE、そして数多のインディースタジオなども優れたスタジオが存在するが、地域全体では日本と米国に遥かに及ばないというのが実情だ。
それどころか、欧州における任天堂のシェア率がおおむね10%前後なのに対し、北米においては20~30%を占めるなど、日米の企業が拮抗している。つまり欧州は米国を差し置いて、もっとも米国産ゲームが強い地域なのである。
さて、ここで問題となるのがUbisoftの立ち位置である。
ここまで確認したように、欧州ゲーム産業には日本や米国のような有名ゲーム企業が少なく、そのブランドもあまりない。それどころか、欧州内ですらもっぱら米国と日本のゲームが遊ばれており「地産地消」も難しい。こうなると欧州ゲームが成功するには、欧州の外=日本と米国への売り込み、つまり「輸出」により儲けるしかないことがわかるが、すでに日本は任天堂が大きなシェアを共有しているので、必然的に米国に特化した戦略を練らざるを得なくなる。
事実、Ubisoftの決算資料によれば、Ubisoftの地域別売上は欧州が28%、アジアが12%に対して、なんと北米は60%も占めている。しかも2009年のIR資料に掲載された地域別売上でも、欧州が39%、アジアが6%に対して、北米が55%占めている。15年もの間、Ubisoftは米国に強く依存していたのだ。

必然的に、Ubisoftはフランスの企業であるにもかかわらず、「アメリカ市場」+「アメリカゲームばかり売れる欧州市場」で売るための戦略を、取らざるを得なかった。フランス・カナダ企業でありながら、アメリカ・欧州どちらの市場に向けても、「まるでアメリカ企業」かのようなゲームを開発するほかなかったのだ。
ここであらためてUbisoftの歴史を思い出してほしい。1990年代、Ubisoftは「レイマン」という独自のタイトルで資金を得ると、2000年代からこれを元手に米国のフランチャイズを買収していった。
そうして生まれたのが、米国市場に最適化されたミリタリーシューターの「レインボーシックス」「ゴーストリコン」のような「トム・クランシー」シリーズだった。いずれも「レイマン」と正反対の、ガチガチに硬派なミリタリーシューターであり、ストーリーもトム・クランシーらしい、アメリカ保守層が好みの米ソ冷戦の対立に乗じたフィクションだったわけだが、これも欧州発のUbisoftがいかに米国市場で成功するかが重要だったことを踏まえると筋が通る。

「プリンス・オブ・ペルシャ」にしても同様だろう。本作はもともと『カラテカ』のアメリカ人ディレクター、ジョーダン・メックナーが「インディー・ジョーンズ」に触発されて作ったゲームであり、内容も極めてアメリカナイズドされた「アラブ風味の西洋ファンタジー」とでも呼ぶべき内容だった。これはUbisoftによって踏襲された続編でも変わらず、どちらかといえばディズニーの「アラジン」のようなアメリカ大衆エンタメとしての性質が強い。

その他にも「バットマン」「アバター」「スターウォーズ」のようなアメリカの版権モノを手掛けたり、アメリカのポップソングを詰め込んだ「Just Dance」シリーズ、またレースゲームにしてもアメリカ全土を舞台にした「The Crew」シリーズやサンフランシスコを舞台にした「ドライバー:サンフランシスコ」など、Ubisoftの売れ筋を鑑みるとほとんどが「アメリカ市場に特化したゲーム」であることがわかる。
そのため皮肉にも、Ubisoftのアイデンティティとは「(自国で消費されない)フランスのゲーム企業だからこそ、まるでフランス企業だとわからないレベルで、徹底してアメリカ人向けのアメリカ的なゲームを開発・販売に特化した企業である」という点に尽きる。

そして「アサシンクリード」とは、まさにUbisoftの「アメリカ市場への特化」を象徴すると同時に、その問題性を発揮してしまった作品だと考えている。
まずアサシンクリードは、『プリンス・オブ・ペルシャ』の外伝をオープンワールドとして開発することを企図して発売された。そして2000年代の北米は『GTA3』(2001年)の大ヒットに端を発するオープンワールドブームで、次世代機の発売と併せ『オブリビオン』(2006年)『ライオットアクト』(2007年)『セインツロウ2』(2008年)などのオープンワールド作品が立て続けに発売されており、『アサシンクリード』はこうしたアメリカのオープンワールドブームに欧州Ubisoftとして初めて乗り出した企画だ。

また、アラブ社会(シリア・イェルサレム)における冒険活劇という面では、アメリカで生まれた『プリンス・オブ・ペルシャ』から続く(極度に)西洋社会に都合よく解釈された世界観(=エドワード・サイードのいう〈オリエンタリズム〉的な)地続きといえるし、そこにヒストリカルな中世要素を込めるのはリドリー・スコット監督『キングダム・オブ・ヘブン』(2005年)のような、2000年代前半のハリウッド映画の影響も考えられる(開発者は同作にも触れている)。
総合的に、「アサシンクリード」はゲームデザインもフィクションもどちらも「アメリカ市場」におけるトレンドをよく分析し、自分たちなりに解釈した結果生まれたものであることがわかる。
ただし「アメリカ市場」を意識した問題点として、発売前のプロモーションは徹底して「リアルな歴史上のイェルサレムを、伝説的なアラブ人(シリア人)のアサシン主人公を通じて生きるゲーム」とみせかけておきながら、実際には全てが仮想空間であり、本当は「アメリカ人青年」のデズモンド・マイルズが大企業になりすました現代のテンプル騎士団と戦っていくという、荒唐無稽な陰謀論だったという物語・プロモーションの問題だろう。

まず、陰謀論の要素そのものが致命的に面白くない。初代ディレクターのパトリス・デジーレは「これは歴史のゲームでなく(this is not historical game)、歴史設定に基づくSFゲームだ」と言い張るが、肝心の「SF要素」がとてもSFとして評価できないほどお粗末で、安易に陰謀論やオカルト伝説を盛り込んだだけに他ならない。
少なくとも、アシモフやクラークのようなSFに触れた人で、「アサクリ」をSFとして評価した人はほぼいないだろうが、この設定は初代『アサシンクリード』から最新の『ミラージュ』まで続いている。
確かに全てのフィクションが史実に即する必要はないが、史実に即しなかったことがエンタメとしての面白さにただちに貢献するような彼らのロジックは、歴史以前にクリエイターとしてあまりに無礼ではないだろうか。
またアートディレクターの二コラ・カンタンが認めるように、この「SF要素」は発売直前までマーケティング上の懸念から意図的に伏せられていたのだが、これはプロモーション詐欺である以上に「SF」要素が退屈極まりないことの後ろめたさがあったからではないか。

しかしここでの最大の問題は、この「歴史→〈SF〉」の変転によって、本当の主人公をアラブ人(シリア人)と見せかけて実際はアメリカ人(白人)にしてしまうことだ。
これは今問題となっている「ホワイトウォッシング」に他ならず、ましてそれを事前のプロモーションで伏せていることに関しては、もはや「アラブベイティング」的でさえあり、明らかに「アメリカ市場」を最優先する手前で「非アメリカ文化」「非アメリカ人」を軽視・搾取しているといわざるを得ない。
しかも「アサシンクリード」のアジア軽視は初代に限った話ではない。
2011年に発売された『アサシンクリード リベレーション』では、歴史的にきわめて重要なオスマン帝国を舞台としており、同国の歴史に強い関心を持つ筆者も発売を楽しみにしていた。しかし、主人公は『2』に登場したイタリア人のエツィオで、現地トルコ人(アジア人)ではなかった。もはや歴史パートでさえ、明確に「白人視点」で貫き通してしまったのである。
つまり「アサシンクリード」シリーズで「史実」を扱うとき、シリーズを通じて、それらはあくまで「アメリカ人」が消費しやすいよう加工されてきたのである。(なお、筆者個人としてオスマン帝国史に関心があったからこそ『リベレーションズ』には期待していたし、その期待に対するUbisoftの裏切りも忘れ難く記憶している。まぁエツィオが魅力的な主人公なのも認めるが)

このように、実は『シャドウズ』問題で日本で指摘された「アサシンクリード」の本質的な問題──アジアの歴史・舞台を借用しながら、そこに敬意を示さず、アメリカ的に解釈する姿勢──は、実は2007年に発売された「アサシンクリード」の時点で無縁ではなかったといえるだろう。
要するに「アサシンクリード」とはUbisoft作品の中でも際立って「アメリカ人(とそれに近しい感性を持った西欧人)に遊ばせるために最適化されたゲーム」であり、その問題も「アメリカ市場への最適化」に甘んじた開発陣の怠惰さに依拠するものである。
だからこそ、『シャドウズ』のみを批判するのは正しくなく……Ubisoft、アサシンクリード全体を通じてその問題がどこから生じたのか考えることが重要だと考えたのである。
「米国ゲーム文化へのオルタナティブ」として──2010年代のUbisoft
ここまで、Ubisoftの客観的な経歴を振り返りながらも、その裏にあった「アメリカ市場への依存」という前提からUbisoft作品、特に「アサシンクリード」のシリーズに通底する問題を考えてきた。
「シャドウズ」で日本人が抱いた疑問とはすでに初代「アサシンクリード」のオリエンタリズム的軽蔑を否定できず、それらはアメリカ及び同盟国(日本・西欧を含む)が「エンタメとして消費」するうえで踏み倒されてきたリスクだったということも、確認できたと思う。
さて、ここまでUbisoftに対するかなり厳しい見方を提示してきた。これは「日本・米国ゲームの輸入に偏り、自国だけで発展しきれなかった欧州ゲーム産業の限界」と「数少ない巨大欧州ゲーム企業として、アメリカに対する経済的依存を強くしたUbisoftの限界」という構造的な限界を鑑みれば仕方ないものといえ、看過しがたい。
一方、Ubisoftが常にアメリカ市場に甘んじ、アジアを搾取するようなゲームばかりを作ってきたかといえば、そうではない。
むしろUbisoftが一定の資金と実力を確立した「2010年代」においては、むしろフランス・カナダというUbisoftのアイデンティティに立ち返り、特に支配的なアメリカ文化へのオルタナティブを掲げた作品も作ってきた。
例えば、ここまで批判してきた「アサシンクリード」。少なくとも本シリーズには『リベレーションズ』のような問題ある作品もあった。しかし、そんなシリーズの中でも際立って批評性が光った随一の名作が存在する。それが、アメリカそのものを舞台にした『アサシンクリード3』(2012年)だ。

『アサシンクリード3』の舞台は、18世紀の独立戦争下におけるアメリカだ。主人公はコナー/ラドンハゲードンというモホーク族の少年であり、テンプル騎士団のヘイザムを父に持つという複雑な経歴を持つ。コナーは英軍により故郷を焼き払われた過去から、アメリカ独立のためにジョージ・ワシントンらに協力し、暗殺に手を染めるというのが大筋になる。
すでに主人公が白人ではなくネイティブ・アメリカンであるという時点で批評的なのだが、そこからコナーがワシントンらの「愛国心」を高揚するアジテーションに誘われ、さながら少年兵のようにアメリカのイデオロギーに動員されていくにも関わらず、コナーの故郷を焼き払ったのは英軍ではなく、ネイティブ・アメリカンを脅威に思ったワシントンの大陸軍であることがわかる展開は白眉だ。

つまりコナーはアメリカ人の欺瞞に踊らされ、己の仇のために命をかけていたのであるが、これは決してファンタジーではない。実際、アメリカ独立戦争(およびフレンチ・インディアン戦争)では白人たちの都合により、ネイティブ・アメリカンは敵味方に分断され戦争に動員された。
当然、ワシントン率いる大陸軍は敵・中立問わずネイティブ・アメリカンを虐殺・略奪。それどころか大陸軍に与したオネイダ族やタスカローラ族など与した部族であっても、独立後には裏切り、収奪したという歴史がある。

このように『アサシンクリード3』は明確に、アメリカによるネイティブ・アメリカン(およびアフリカン・アメリカン)に対するアメリカの暴虐的歴史を、「アサシンクリード」というフォーマットを活かして批評的に描いている。独立戦争前のアメリカ史をこれほどオルタナティブとして扱った前例はアメリカのビデオゲームにはなく、まさにフランス・カナダのUbisoftにしか作り得ないアメリカ批評となっている。
もう一つ、Ubisoftの中でもフランス・カナダらしい批評的作品といえば『ウォッチ・ドッグス2』(2016年)だ。

本作は監視社会となった近未来のアメリカを舞台にしたゲームシリーズ。主人公はハッカー集団「デッドセック」の一員として、監視社会から市民を解放することを志す。しかし、ここで興味深いのは「デッドセック」の矛先が、監視社会を作り出した架空性の高い企業「ブルーム社」のみならず、そのブルーム社と癒着した様々なテック系企業にも向くことである。
具体的には、検索エンジンやマップアプリを作る「ヌードル」、ロボットなどハイテク家具を扱う「ホーム・エレクトロニクス」、ソーシャルメディア最大手の「インバイト」といった企業が、実は経営の裏で「ブルーム社」の監視ネットワークから得た個人情報を代価と引き換えに買収し、経営に役立てているという背景があることで、主人公はこうした企業とも戦っていく。

そしてこれらの企業は表面的には架空の存在だが、明確にモデルが存在する。つまり「ヌードル」は業務内容、オフィス、ロゴに至るまでどう見てもGoogleであるし、ホーム・エレクトロニクスはAppleやiRobotなどの西海岸製造業、そしてインバイトもまたTwitterとFacebookを足したような企業である。
つまり『ウォッチ・ドッグス2』は「テロリスト」や「モンスター」の代わりに、実在するアメリカの大企業(テックジャイアント)と類似した敵を相手どり、物理的に叩きのめすというのが目的となっている。
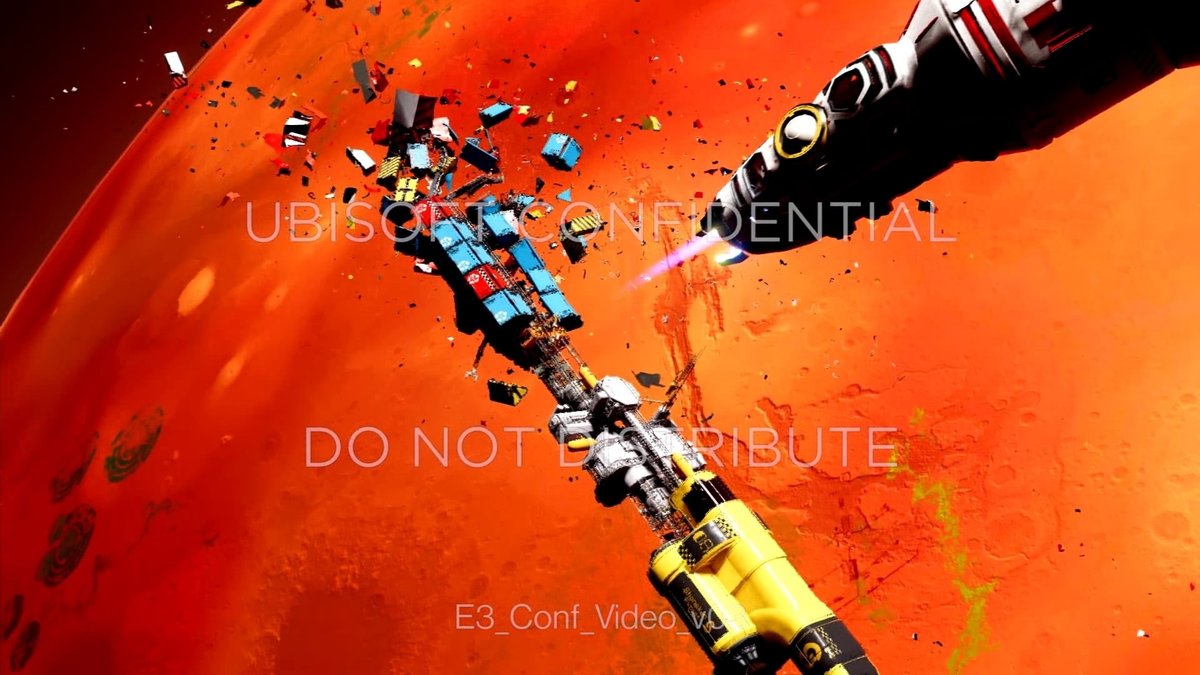
これもまたアメリカのゲームでは絶対に考えられないような、痛烈な現代アメリカ批評だ。今やアメリカのテックジャイアントが個人情報を使用し、ビッグデータとして活用していることは「一般データ保護規則」など世界各国で大きな問題として扱われているし、それを差し引いてもテックジャイアントの「リベラルな欺瞞」をよそに人種的・性的な差別を行っていたり、独占によって下請けや開発者を搾取している事実を堂々と糾弾した事例はビデオゲームではほとんどない。
『ウォッチ・ドッグス2』は西海岸を舞台にしたオープンワールドゲームであると同時に、その美しい西海岸の(現実に存在する)闇を照らし、それと戦っていくという鋭い批評性を見せている。これもまたフランス・カナダのUbisoftだからこそ持ち得た批評性であり、今もゲーム史に残るべき名作だと言えるだろう。
このように、Ubisoftはアメリカ市場に向けた安易な娯楽作品を手掛ける一方で、全く無批評的にアメリカ文化・社会に迎合してきたわけではない。
少なくとも『アサシンクリード3』『ウォッチ・ドッグス2』は、アメリカの当事者でなく隣国のフランス・カナダでなければ実現できなかった痛烈なアメリカ批評ゲームであり、彼らの主な「お客」がアメリカ人であることを鑑みても、時に勇気と独創性のある作品を手掛けてきたのも事実だ。
(ここでは説明しなかったが、他にも『ファークライ2』(2008年)や『スプリンターセル:ブラックリスト』(2013年)もやはりアメリカに対するアイロニーを籠めているし、一方で第一次世界大戦を独仏両側から描いたADV『バリアント ハート ザ グレイト ウォー』(2014年)のような、フランスのアイデンティティを反映した作品も存在する。)

しかし、こうしたUbisoftの独創性は長く続かなかった。2020年代に入り『シャドウズ』に至るまでのUbisoftは、様々な課題や問題を浮き彫りにしていくことになる。
「2つの課題により迎えた衰退期」──2020年代のUbisoftの問題
この問題を整理するうえで重要なのが、2020年代からのUbisoftの変化だ。
実際、筆者は2010年までのUbisoftは「ゲームメカニクスへの理解はまちまちだが、挑戦的なテーマの作品も手掛ける、欧州らしいゲーム企業」という印象だった。しかし、2020年代からのUbisoftの作品はこうしたフランス・カナダのオルタナティブ性を失い、「米国市場に特化しただけの、数ある大企業」になってしまったと考えている。この衰退はUbisoftの個別作品を批評してく中でも見えてくる。
───────────────
以下の内容は、Ubisoftとアサシンクリードの真実について、このような論点で整理しています。
・2020年代のUbisoftが「衰退」している客観的な「2つの証拠」──投資家向け資料と作品批評から考える
・Ubisoft衰退の原因となった「2つの問題」──「人材」と「経済」
・総論として『シャドウズ』問題をずばりどう思うか?
・終わりに──Ubisoftとアサシンクリードの「真実」とは
いずれもUbisoftとアサシンクリードを理解する知見・批評であると同時に、特に2020年代現在のゲーム文化とその未来について考える上でも、重要なヒントになると考えています。
このほか、ゲームゼミでは「The Last of Usの真実」「スクウェア・エニックスの真実」など、既存のゲームメディアでは扱えない高度な批評を数多く扱っており、一度有料会員になることでそれらもお読みいただけます。ジャーナリズム活動をご支援いただくうえでも、ぜひメンバーシップ加入をご検討ください。
───────────────
ここから先は
「スキ」を押すと私の推しゲームがランダムで出ます。シェアやマガジン購読も日々ありがとうございます。おかげでゲームを遊んで蒙古タンメンが食べられます。
