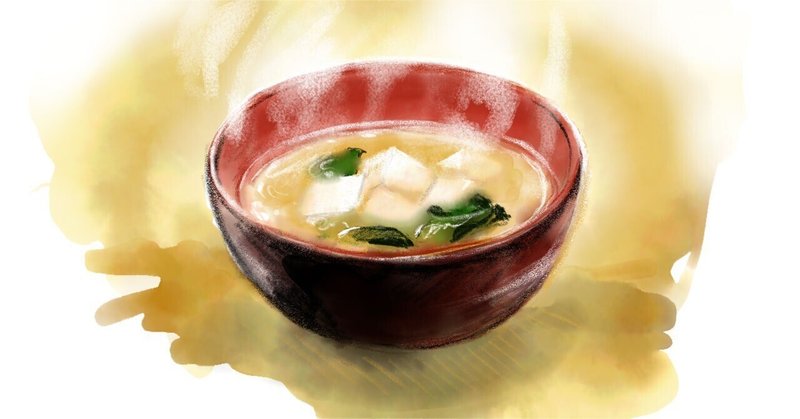
味噌汁365日【書く習慣DAY7】
味噌汁を作ってみた
有賀さんの本の中で、味噌汁を煮干しだしでとることについての記事があり、試してみました。
今までは、かつお節と昆布だったのですが、煮干しの頭とわたを取って、30分浸水し、そののち火にかけ、沸騰してきたら火を弱めてアクを掬い、5分ほど煮出して濾せば、煮干し出汁の完成です。

さらに凝りたいときは、沸騰して煮出し終わったところで、真っ赤に焼いた金火箸を湯の中に差し込みます。ジュっという音と共に、もうもうと湯気が立つと、瞬間的に100度を超えた水蒸気とともに、魚の生臭さを完全に飛ばすことができます。
今日は、豆腐とワカメで作りましたが、これ呑んじゃうと、顆粒出汁で作ったのは呑めなくなりますね!!
うまみがぜんぜん違って驚きました。
有賀さんの本を読んでよかったなーとこころから思いました。
味噌汁が面白くなってきた私は、だいぶ前に購入したのに、積読になっていた「味噌汁365日」という本を引っ張り出してきました。
味噌汁365日
味噌汁の美味について
味噌汁の美味は要約すると、味噌特有の旨味を汁とし、「み」が汁と渾然一体となって舌の上を通り、吸い口が味の転結をはかって、しめくくりとなる。ということになります。
そして、これをつらぬくに季節感という日本固有の高度なセンスがあります。
この「味噌汁三六五日」という本は婦人画報社から昭和34年に発行された本です。1959年、今から63年前ですね。
著者は京都の懐石料理店「辻留」の二代目 辻嘉一さん
辻嘉一(つじ・かいち)【1907年~1988年】
昭和時代の料理人、料理研究家。京都の懐石料理「辻留」二代目主人となった辻嘉一は、14歳で包丁を握り、以来60余年庶民の味づくりに精進してきた。「辻留」は、裏千家からの指導をもとに京都・東山に開いた懐石料理店である。三代目は実子の辻義一。著書『料理心得帳』『味覚三昧』『料理のお手本』など。
こちらの本には、味噌汁を美味しく作る方法が、贅沢に余さず載っていて、ページをめくるたびに、感嘆の声をあげるばかり。
だしの取り方、味噌の選び方と季節による混ぜ方、具材の適切な包丁の仕方、器の選び方、そして360日分のお椀の作り方。
なんと贅沢な本だろう、なんで積読しちやってたかなあと後悔しきりですが、有賀さんの本を読んだことからスープ作りが始まって、美味しさを追求することへの興味が連鎖的に繋がって初めて、この本の価値がわかったので、本の読みどきとわかりどきというのは、どうしてもあるのです。
わかった今は、この宝物を参考にして作るだけなのであります。
レシピ本は作ってナンボですから。
本の中で、特に感銘を受けた記事があったのでちょっとご紹介します。
口に含むこと 味覚神経をフルに使うということ
味噌汁を口に含んだ瞬間、ふくよかで豊かなものを感じる、このひらめきに似た味覚の動き、この感情が本当においしいという食感情なのでありましょう。
皆様もお試しになると、よくわかりますが、すうーーと一口啜りこむとき、まずくちびるに触れて、舌の上にいき、それを上顎へ運び、それをさらに上顎の奥へ流しいれるようになるわけで、この「ふくむ」ようにして味わう瞬時の動きが、ものの優劣を決めてくれるのだと思います。
中略
この「ふくむ」という食べ方ですと、舌の上の感覚だけでなく、口の中の全部の味覚神経が動員されるのだと思います。
おいしいと感じて、それが全神経に伝わり、それが消化吸収の助けになるのです。
味噌汁が本当に美味しい場合には、釣鐘の音の余韻が嫋々(じょうじょう)として長く尾を引くのに似た、後味の良さを感じさせてくれるのでして、真のうまさはこの後味にあるのでありまして~後略
このように、味わうことをしみじみと考えたことが、恥ずかしながら、いままでなかったように思います。本職なのに!
これ以外にも、味噌汁を美味しくする知恵、ひいては、すべてのものを美味しく味わう技術と心構えが学べるので、後日また実践していきたいと思います。

365日の味噌椀作成の顛末は、また別の日の講釈で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
