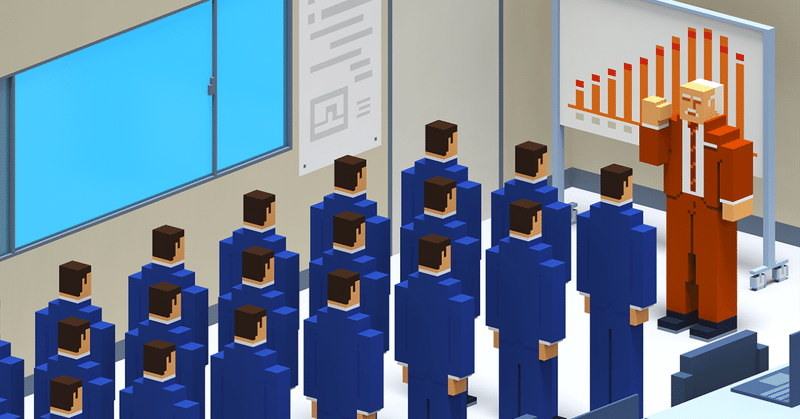
ピーターの法則とミドルアップダウンマネジメント
【 ウチの部長はなぜ使えない? 出世レースの悲しき法則 】という記事より。
ピーターの法則とは?
サラリーマンは、ヒラ、主任、係長、課長、部長、役員・・・と出世の階段を上っていくなか、無能さが露呈したところで昇進が止まることになります。その結果、多くのポジションは、無能な人で占められる事態になるわけです。
これがアメリカの教育学者L・ピーターが提唱する社会学の法則です。「人は無能になるまで出世する」「組織は無能な管理職で埋め尽くされる」と言うのです。(記事より:ピーター法則の説明)
記事では、改善策として
1 昇進をむやみやたらにせず、最も能力を発揮する地位に留める(適材適所)
2 上記1でモチベーションが低下しそうであれば、地位ではなく「昇給」制度を改良する
というものを挙げていました。
---
組織が大きくなればなるほど、この問題は出てきますよね。私の友人で大手勤めから転職した者が多数います。転職の理由は、やりたいことが見つかった!というものが一番多いですが、次に多いことが、「上司との人間関係」です。ハラスメント的なものだけでなく、上司を尊敬できなかったり、やり方が合わなかったり。
私も20代の頃、ちょこっと大きな組織に属していましたので、まあ、いろいろ分かるところもあります(・・私自身の上司は皆、素晴らしいお方でしたが!)
---
中小企業のように大手ほど人数がいない場合には、それだけ社員の「顔」が見えるというメリットがあります。反対に、1人でも無能な管理職が生まれてしまえば、その影響力も大きいです。
記事にあるように、適材適所を把握したり、昇給制度でモチベーションを挙げるのも良いですが、「顔」が見えるメリットを生かし、「人材育成」を強化する手もあると思います。
管理職(ミドル)を単なる「形式的な役職」ではなく、明確な意義・役割をもたせ、会社の成長の重要ポジションである旨を周知させること。(ミドルアップダウンマネジメント的な見方)。
(参考)ミドルアップマネジメントについて書いたnote
管理職がその場の「真のリーダー」となれているか否か。会社としての期待も、現場や当事者である管理職、経営陣が共通認識として理解し、特に経営陣と管理職がコミュニケーションをしっかりとる。自覚をもって、自己を高めてもらうことが、中小企業には頼れる管理職の育成に必要不可欠ではないか、と思います。
---
魅力的な管理職がいることは、会社の成長だけでなく、次世代の社員育成にもつながります。先ほども書きましたが、人材の流出には、会社の社風等もそうですが、直属する上司との関係が強く影響するからです。
原点に帰り、なぜこの役職があるのか?この役職に何を求めるのか?その役職を担う者は、どういった人材であってほしいか?
年功序列や経験年数、出世という曖昧な理由でなく、昇進の具体的な根拠を改めて見つめなおすことも重要かもしれません。
---
また、組織の大きさによって、管理職に関する問題も様々な要因があり、解決策も異なると思います。
各成長段階の企業について、その苦悩を「成長の痛み」と表現し、具体的な解決策を示した書
例えば、本書はベンチャー企業向けであり、かつ日本的な企業にすべて合致する内容とはいえませんが、こういった組織論の視点も経営する上で重要でしょう。管理職がなかなか育たないな~、役職がいろいろ出来すぎて訳が分からんというような時は、一種の「成長痛」が起きているのかもしれません。
痛みに気づいて伸ばすか。
痛みを一時的な処方箋でごまかして止まるか。
---
(参考)管理職を機能させる「味の素の経営」
お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/
