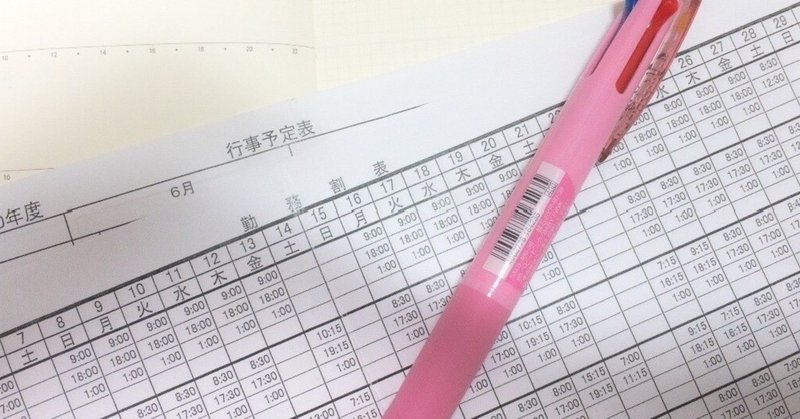
サラリーマン、6月は住民税が変わる月 【 NIKKEI 】
〇 概要
6月の給与明細。まだ先でしょうが、いざ給料日がきて、・・・あれ、なんだか控除額が多いな?先月より手取りが少ないな?という人は、昨年の年収が多い人かもしれません。
サラリーマンのような給与所得者の住民税は、この記事にあるように、昨年(平成30年分)の所得に基づくものを、今年(令和元年)の6月から令和2年5月までの12ヶ月間で按分して支払います。
先月まで支払っていた住民税は、平成29年の収入に基づくものだったということです。
1 給与天引きされない人
住民税なんて控除項目ないよ?という人は、記事にあるように、年収が一定額未満の方か、補足すると例えば群馬県なら以下の方が該当します。
私のいる群馬県公式のサイトより

上記の赤枠に該当し、経営者があなたを「普通徴収」とした場合、給与天引きではなく、あなたのご自宅宛に住民税の通知書・納付書が届きます。
あとは、今年転職した人は、会社が住民税の手続きをしていなければ、ご自身の自宅宛てに住民税の通知書・納付書が届きます。
2 気を付けたい事例
例えば、定年退職後に再雇用となった人。こういった方は、現役時代の収入に基づく住民税が、引き続き、再雇用後の低い賃金から控除されます。
また、我々税理士へのよくある相談が、転職者です。
社長「転職してきたAさんは、Bさんと同じ月給なのに、住民税2倍近く違う。計算間違いでしょうか?」
これも結局、昨年の年収に基づきますし、昨年の年収とは当然、転職前、転職後関係なく全て合算した金額です。このケースの場合は、転職前の年収が高かったということです。
サラリーマンの皆さんは、6月の給与を受け取る前に、会社から納税通知書を受け取るはずです。
私も、顧問先には必ず5月の給与明細と一緒に同封するなど、早期に必ず社員全員に配るよう伝えています。が、結構、転職した方とかは「初めてこんな通知書をもらった」というケースがあるようです。もし、「私ももらっていないな。。」という方は、会社に確認してみてください。
3 ふるさと納税していると・・
以下の図は、私がお客様に対して、ふるさと納税の仕組みを説明するため作成したものです。・・4年前の資料(平成27年)なので、税額計算が現在のものと異なりますが、説明用ということでご了承ください。(・・この資料も更新しないとな。。)

古い資料ですが、例えば年収1000万円の人は、社会保険等何も控除するものが無い仮定で、税額計算をすると、国税(所得税)と地方税(群馬県・高崎市への住民税)で合計約1,833,000円納めることになります(通常は社会保険等控除項目がありますので、もっと納税額は低いです)。
このA氏が生まれた町、A町にふるさと納税10万円を実施すると以下のようになります。

税金は、国税と地方税、そしてふるさと納税額併せて約1,835,000円納めることになり、ふるさと納税しなかった時と比べ2,000円納税額が増えます。
要は、2000円は追加負担になるけれど、Aさんは、国や、今住む群馬・高崎にのみ税金を納めるのではなく、自分が指定したA町に税金を納めることができた。この税金を納める先を選べることが「ふるさと納税」なのです。

私が作成した図の「ふるさと納税有り」の方を見ると、群馬県と高崎市が当時の換算で、Aさんからもらえるはずだった納税額が合計76,000円減少しています。
よって、昨年ふるさと納税をたくさんやった人は、6月からの住民税にその効果がでてくるはずです。(なお、上記の説明は、ふるさと納税あり、なしで約2000円の差額でしたが、その人の所得によって、ふるさと納税による税額控除の限度もありますのでポータルサイト等よく確認してください。
この納税先を「選べる」ことがポイントでしたが、その後、返礼品の過剰化が起こり、今に至ります。
上記の事例も金額だけ見ると「ああ、Aさんは故郷に納税したかったんだな」となりますが、これに例えばA町の特産品30,000円相当がお礼としてついたらどうでしょうか。Aさんは、2000円の負担で30000円相当の品をゲットできるわけです。これがギフトカードだったら?50000円相当だったら?
また、この制度は、税金を多く収める人ほど、当然、納税先を選べる税金の額は増えます。例えば、返礼品を3割相当とすると、2000円負担をベースにした場合、50000円が限度くらいの納税額の人は7,500円相当の返礼品ですが、500,000円納めても2000円負担の高所得者なら75,000円です。これが結局、趣旨とは異なり、高所得者への優遇策となっていないか・・といわれる点です。
4 最後に・・
ここ数年、クラウドファンディング等、世の中が寄附に対して、以前よりも積極的になっているような気がします。大手や組織がドーン!という寄附ではなく、SNS等を通じて少額でも取り組みを応援したい、参加したいという風潮が。ふるさと納税もまた、特産品ばかりだけではなく、各町が実施したい活動を掲示し、寄附したい側が見るという環境があります。多くの賛同を受けられた取り組みは寄附の金額を通じて評価される。これは地方活性化や地方自治体内部の活性化にも良い取り組みでは、と思っています。
お読みいただき、ありがとうございました。 FB:https://www.facebook.com/takayoshi.iwashita ㏋:https://ibc-tax.com/
