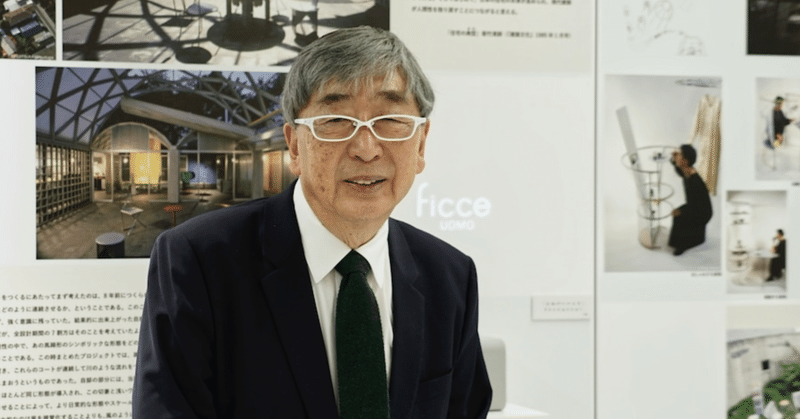
文化人物録54(伊東豊雄)
伊東豊雄(建築家)
→日本を代表する建築家の一人であり、世界的にもその名は広く知られる。主な作品に「せんだいメディアテーク」「みんなの森 ぎふメディアコスモス」など。日本建築学会賞、ヴェネツィア・ビエンナーレ金獅子賞、プリツカー建築賞など多数の賞を受賞。2011年、「伊東建築塾」を設立し、まちづくりや建築を考える場を提供。愛媛県今治市には伊東豊雄建築ミュージアムがある。
僕がお会いしたのは伊東さんにおける生涯最大作品のひとつとなった「台中国家歌劇院」(台湾)の完成披露時。非常に難しい計画・工事だったのを覚悟の上で、伊東さんは自らの意志を貫き通して自らを体現したといえる素晴らしい建築物を生み出した。建築は芸術であり思想であり哲学である。それを強く実感した瞬間だった。
(2016年、台中国家歌劇院完成披露)
・台中国家歌劇院のコンペがあったのは2005年っだったが、今まで11年間もかかってしまった。3つの劇場があり、大が2千席、中が800席、小が200席。元々は複雑な形状ではなかった。世の中の建築物の大半は単純なフリットで、幾何学的に作らざるを得ないところがあるが、今回の建築はいつもダイナミックで渦巻くような、幾何学とは全くかけ離れた構造でできている。ジオメトリーとダイナミックなナチュラルシステムの融合を目指した建築モデルといえると思う。
・この歌劇院、地域の人々などには「サウンドケーブ(音の洞窟)」とでも呼んでほしいと思う。洞窟のように音海光も遠くから伝わってくる。3つのシアターだけが劇場ではなく、エントランスも階段も屋上も、建物全体がシアターのようなコンセプトだ。プレオープンの時も小さなコンサートやパフォーマンスなどを歌劇院内のあちこちでやった。
・建物はカテノイドであり、切ったパートの構造は弱いので、壁を工夫している。トラスウォール工法というもので、しきちに建てられた工場で、二次元の鉄筋トラスを造る。2次元カーブに水平のカーブを継いで、3次元カーブのような形にしている。
・中劇場は大劇場よりも創造的行為がやりやすい。客席と一体で作品を作ることができるのではないか。劇場の入り口はステージと同じレベルで、ステージと客席の間隔をできる限り小さくした。10月1日にラ・モードというパフォーマンスアートを上演するが、この作品は客との一体感を意識している。凸面の集合体で各劇場ができていて、カーブで乱反射するので、どのホールも基本的に音響はいい。ホールの音響はあの永田音響設計であり、音響デザイン的に問題ないという結果も出ている。
・施工に100%満足したわけではないが、なんとか作ってくれた。これは奇跡的なことなので私としてはハッピーです。デザインの後繰り返し施工が難しいということで建築会社が決まらず、最終的にはローカルな台湾の会社が手を挙げてくれた。設計からは1年半ほど空白期間もあった。トランスウォール工法も未経験だったので、手取り足取り指導しながら彼らが進化していきました。できるだけギグが見えないように配慮した。全体が白くカーブしているスペースなので、どこかに明かりがあると壁に伝わり、完全化される。
・小劇場については実験的な小劇場ということで、フロア構造とは独立している。ブラックボックスのような感じ。建物全体を造った後に小劇場を造った。ドアが開くと外につながり、円形劇場のような形になるため、面白そうな作品ができそうな場だといえる。石段の客席も現れる。芸術監督のヴィクトリア・ワンは思い切ったことをする人だ。
・ステージセットはテキスタイルデザイナーの安東陽子さんの手によるもので、椅子も彼女のデザインだ。衣服の拡大のようにも生き物のようにも見えると思う。この建物はサウンドスケーブと言われるが、洞窟のような構造は内側だけで、外側は造ると境界線になってしまうので、少しでも境界は曖昧にしようと考えた。
・僕の最大の狙いは皆さんがこの劇場に集まってくれることだ。こんな建築はもう二度とできないでしょうね。自分が思っているだけでは実現できないので。できたのは自分でも不思議なくらいです。建築という枠を越えて、建築と自然が出会う、いろんな境界をなくしていく場所であってほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
