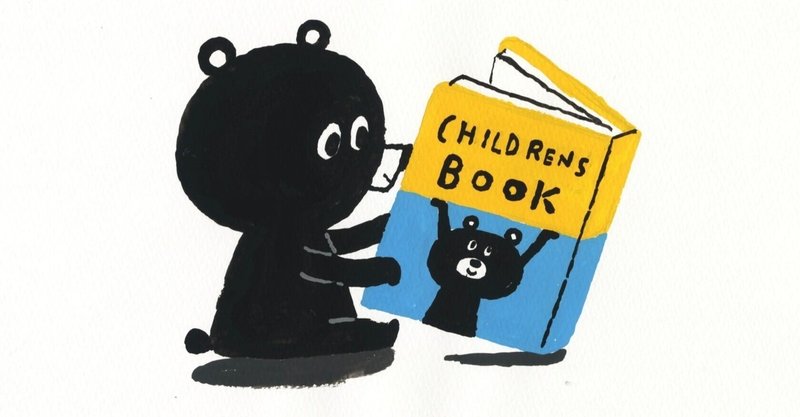
2020年読んだ好きな本21冊まとめ|スタートアップ広報PR
2020年は、スタートアップの広報PRとして2年目を過ごして、いろいろ新しいことに挑戦する中でたくさんの本に助けられました。ビジネス本が中心ですが、読んだ本の中でも好きな本を21冊まとめてみました!同じような挑戦をしている人の力になればと思います^^
基本的に紙の本を買っているので、もし気になるものがあればお貸しできます。中古で買っているものもありますし、付箋はさまったりしてますが、お気軽にご連絡いただけたら嬉しいです◎
■ビジネス:PR/コミュニケーション
1.私とは何か 「個人」から「分人」へ
・たった一つの「本当の自分」は存在しない
・一人の人間は、対人関係ごとに複数に「分けられる」存在(=分人)
・どれくらいの数の分人を抱えるのが心地いいかは人それぞれ
・分人の構成比率は環境によって変化する
2020年も、その前から何度も読み返してる本。相手の存在で自分を好きになれ、複数の分人を持つことでバランスを取ることができるーー自分らしさに悩む必要がなくなり、生きることが楽になる。
PR(Public Relations)目線でいうと、パブリックによって自社の顔は複数あり、そのパブリックとの相互作用の中で組織の存在意義が生まれると理解できる。河 炅珍(ハ・キョンジン)氏の『組織の社会的自我』の話とつながる。
2.具体と抽象
・具体をみている人と抽象をみている人は見えている世界が違う
・考えることは具体と抽象を往復すること
・上流の仕事は抽象度が高く、下流の仕事は具体性が高い
社会人1年目で出会いたかった本。上司の言っていることが理解できないのは抽象度の違い。
広報の目標設定では抽象的な定性目標を掲げつつ、具体的な行動目標をおいている。経営に資する広報にするためには、常に視座を上げて抽象と向き合うことが求められてると思う。
あと、取材やライティングでは常に具体と抽象のバランスを考えてる。具体的であるほど手触り感があって面白いし、抽象的であるほど役立つコンテンツになる。
3.カテゴリーキング
・カテゴリーキングとは新たなカテゴリーを創り、発展させ、支配した企業
・ソリューションではなく問題を市場にもたらす企業が勝つ
・人々の考えを変えることは一定の時間がかかるが、考え方を変えられたら、その会社がカテゴリーキングだと認識される
新しい概念を啓蒙するPRを仕事にする方は必読の本。もっと早く読めばよかった。PRコンサルの山田さんのおすすめ。
なぜ”カテゴリー”を創るのか、例えばなぜ「MyRefer」でなく「リファラル採用」のPRをすることが大事なのか、どうすればいいのかについて腹落ちします。
4.戦争広告代理店
ボスニア紛争における代理店の動きに関する実話
・ニュースで流してもらうために一つの発言の塊「サウンドバイト」を
・記者会見では○項目の新提案を行う
・特定のジャーナリストとの単独インタビュー
・「民族浄化」というキャッチコピー
PRプランナーの試験勉強で、プロパガンダとPRについて興味をもって読んだ本。山田さんや大崎さんのおすすめ。PRが政治に密接に関わることを感じた。
特に今年はコロナ禍での政治家の発言やフレーズから人がどのように動くのか考えさせられることが多かったから、日々勉強になった。
5.はじめての編集
・編集とは、「企画を立て、人を集め、モノをつくる」こと
・基本要素は、「言葉、イメージ、デザイン」
・デザインとはきまりをつくること。それが美しさをつくる
#インハウスエディターコミュニティ で教えてもらって読んだ本。言葉とイメージとデザイン、つまり編集に自分の興味がかなりあって、そこに到達できるようにキャリアを積みたいかも。と長期的なキャリアを考えるきっかけになった。
6.広報・PR担当者のためのデザイン入門
・広報物の目的と意図を明確にする:広報物を作ることで到達したいゴール・そこまでの道筋となる4W3H(いつ、どこで、誰に、何を、どのように、どれくらい、いくらで届けるか)
・広報する対象の魅力(独自性、話題性)を発見する
・ターゲットを具体的にイメージする、ターゲットが好むデザインを調べる
デザイン(&デザイナーに依頼すること)への苦手意識を克服するために読んだ本。目的と意図と打ち出したい魅力とターゲットが大事って、言われてみたら当たり前だけどできてなかった…。2021年はもっとデザインを活用していきたいし、自分もデザインできるようになりたい。
7.トリガー 人を動かす行動経済学26の切り口
・ユーザーを広告塔に(バンドワゴン効果)
・社会的トピックに(ハロー効果)
・新たな「敵」の紹介(損失回避性)
・新習慣をつくる(プライミング効果)
・いい言い訳の提供(確証バイアス)
・第三者レコメンド(ウィンザー効果)など、26個の切り口が掲載。
何となく知っている行動経済学の理論を実践的に活用するための事例が盛りだくさんな本。アソビューの内田さんのおすすめ。PRの企画を考える上でも、仲間になってもらうためにも、”人”を理解することが最重要。だから心理学や行動経済学はもっと学んでいきたい。企画に行き詰ったときに教科書的に見返したい本。
■ビジネス:組織/社内広報/カルチャー
8.企業文化
・文化がリーダーシップを定義し、リーダーが文化を創る
・文化の3つのレベル「文物:目に見える組織構造、行動パターン」、「標榜されている価値観:戦略、目標、哲学」、「暗黙の仮定:信念、認識、思考、感情」
・新しく入ってきた人のどのような態度が期待され、どのようなことをすれば制裁を受けるのか
採用広報の仕事をする上で、企業文化について学ぶために読んだ本。知らないことばかりで本当に面白かった!3つのレベルを意識しながら、企業文化への取り組みをしていかないといけない。
9.WHO YOU ARE
・企業文化とは、「正しい答えはない」ものに対してどう答えるか
・大事なのは、完璧にすることではなく、昨日より良くすること
・意識して企業文化を作らないと、3分の2はたまたま出来上がったものになり、3分の1は失敗に終わる
これも企業文化を学ぶために読んだ本。奴隷文化、武士道、刑務所の文化、チンギスハンのエピソードをもとに語られていてめっちゃ面白い。ただ、よりよい文化をつくるのは本当に難しいことだと実感したので、社内広報や日々の行動で向き合っていきたい。
10.ザ・モデル
・「ザ・モデル」は、SMB市場向けのマーケティング・インサイドセールス・フィールドセールス・カスタマーサクセスの分業体制
・共同で作業をすることで達成可能な共通の目標が有効
自社の組織が拡大して部署間のレポートラインが作られたときに読んだ本。何となく依頼していた広報の相談も、他部署の目標・KPIにどのようにつながるのか意識するようになった。もちろんこのモデルのとおりではないから、自社の組織や事業課題に応じて直接コミュニケーションとって向き合うことが重要だけど、前提知識が足りなかったので役立った。
11.採用基準
・リーダーシップとは、ビジョンを掲げ、本質を見極め、仲間を巻き込んで進めること
・全員がリーダーシップをもつ組織は高い成果を出しやすい
・リーダーがすべきことは、目標を掲げる、先頭を走る、決める、伝える
お客様との会話で”地頭”の定義が話題になって読んだ本。リーダーシップの定義が腹落ちした。例えば、他部署を巻き込んでプロマネするときに目標を掲げる中でも、「ゴールをわかりやすい言葉で定義して、メンバー全員に理解できる形にすること」を心がけるようになった。
あと広報部1人でまだ部下はいないけど、リーダーでなくてもリーダーシップを持つことはできるんだと分かってモチベーションが上がった。
12.ホットペッパーミラクルストーリー
・戦略戦術が全員で共有されて、日々の行動で実現される
・成功モデルに名前をつける「敦賀佑介の創刊事業計画パッケージモデル岡山版」
・「ホットペッパー通信」成功ノウハウを共有する仕組み
コロナで社会が変化する中筋肉質な組織への成長を目指して、社内広報や人事施策を学ぶために読んだ本。代表・鈴木さんのおすすめ。例えば6月からMyReferの社内報で定期的に発信を始めた「表彰者インタビュー」の参考にした。月次の締め会や表彰、半期に一度のIKITAI(粋な仕事大賞)もいい文化だけど、まだまだ他にも活かせる余地がある。。
■ビジネス:経営
13.起業家の勇気
ワシより働くもんがおったらそいつが社長や
代表の尊敬する起業家であり、MyRefer投資家でもある宇野さんのことを知りたくて読んだ本。とにかく壮絶なドラマでわくわくした。その中でも印象に残ったのは、上の宇野さんのお父さんの言葉。代表が誰よりもたくさん働いている理由が少しわかって尊敬が深まった。
14.任天堂”驚き”を生む方程式
・ちゃぶ台返しの精神:納得できないものを世に出せない。1つのテーマについて長くしつこく考え続けることが大切で、考え続けていることの蓄積の量がヒットを生んでいる。試行を重ね、時に捨て、また重ねる。
・枯れた技術の水平思考:枯れた技術を上手に使って人が驚けばいい。最先端かどうかではなく、人が驚くかどうかが問題だから。
人事・原田さんからのおすすめ本。ちょうど自分の提案した企画が的外れで実力不足に落ち込んだときに読んで勇気をもらった(笑)。一度ボツになった企画が数年後にヒット作になることもある。変化が激しいスタートアップだからこそ、過去に固執せず柔軟に変化させて、その時の最高のものを出すスタンスを持ちたい。
15.IPOを目指す会社のための資本政策+経営計画のポイント50
・資本政策で勘案すべきポイント:株主構成、創業者利潤、資金調達、インセンティブプラン、発行株式総数・流動性
・エクイティストーリー:
(冒頭)だれのどんな課題を解決するのか、なぜ起業するのか
(事業計画書)テーマ、背景、市場規模、優位性、実現性、将来性、収益性
資本政策系の話の理解を深めたくて読んだ、さあやさんのおすすめ本。初心者の自分とっては、ファイナンス系の本の中で一番分かりやすかった気がする。エクイティストーリーの設計やVCからのQ&A集などは、投資家目線を理解することはもちろん、コーポレートPRを設計する上でかなり近しい内容だった。
■プライベート
16.サーチ・インサイド・ユアセルフ
・自分の思考プロセスや情動のプロセスを客観的に認知する
・誰もが幸せになりたいと望んでいる
・思いやりは偉大な徳であり、最も幸せな状態
・リーダーは個人の利益を超えた善に対する野心と謙虚な態度をもつ
プライベートとビジネスのはざまだけど、他者とのコミュニケーションや自己管理に興味をもって読んだ本。これもさあやさんのおすすめ。まだここまでは到達できていないけど、自分のごきげんを自分でとって、いつでもどんなときでも相手の背景を想像して”思いやり”を持つことが出来る人でありたい。
17.分断を生むエジソン
・世界は西の国、中部、東の国、南部に分断され、1:2:10:100の割合で存在している
・西の国:「テクノロジー」や「個人」を主義におく革新派の集まり
・中部:「国家」や「公益」を主義におくルールを執行する存在
・東の国:「経済」や「組織」を主義におく実利を好み歴史を重んじる存在
・南部:「生活」や「家族」を主義におく実生活に紐づくものを好む人々
もともと北野唯我さんの「天才を殺す凡人」が大好きなのでこの本も読んだ。スタートアップ2年目になり、周りの友人と自分の違いを何となく理解しつつも、孤独を感じることがあって。それが、西の国の割合が小さいから当たり前か!と気楽になった本。
それぞれ役割が違うだけで、本来分断ではなくつながるべきもの。私は東の国、中部、南部のいろいろな友達とどうか仲良くさせてもらいながら(お願いします)、もう少し西の国で頑張っていこうと思う!
18.イノベーション・オブ・ライフ
・達成動機の高い人が陥りやすい危険は、いますぐ目に見える成果を生む活動に無意識のうちに資源を配分してしまうこと(=キャリア)
・仕事でこうなりたいと思う自分になることに没頭して、家庭でなりたい自分になることをおろそかにしがち
・家族や親しい友人と育む親密な関係が与えてくれる、ゆるぎない幸せを大事に
仕事のことを好きすぎて(笑)悩んでいたときに、タイミーの釜谷さんに教えてもらった本。「イノベーションのジレンマ」のクリステンセン教授が、経営論をもとに人生の話をする。めちゃくちゃいい本。相変わらず仕事には夢中だけど、プライベートをないがしろにはしないように、何より大切な”人とのつながり”を大事にしようと思う。
19.無理の構造 この世の理不尽さを可視化する
・天岩戸の法則:扉は内側からのみ開けることができて、外側からはどんなに努力しても開けることはできない。○○に影響を受けたのではなく、岩戸を開けようと思ったときにいたのが○○だった。
「具体と抽象」が好きで読んだ同じ著者の本。いろいろな法則が書かれているけど、一番ハッとしたのは「天岩戸の法則」。私は人に影響を受けやすいタイプなので、いろいろな人に出会って影響されて道を選んできたと思ってたけど、それは自分が考えて準備をしていたからなんだなと気付いた。いい出会いが生まれるように、これからも自分でいろんなことを考えて準備していきたい。
20.13歳からのアート思考
・アート思考とは、自分の内側にある興味をもとに自分のものの見方で世界をとらえ、自分なりの探求をし続けること
・アートという植物にとって、花は単なる結果にすぎず、興味の種と探求の根がアート思考
・これが「アート」だという定義はなく、ただアーティストたちがいるだけ
・アーティストは、他人のゴールへの課題解決ではなく、自分の関心や内発的好奇心から価値創出をしている
美術館に行くことが好きなので読んでみた本。「アウトプット鑑賞」を知ったのでもっと楽しくなりそう(音楽を聴いたときに作詞作曲の裏話ではなく、作品そのものと自分の思い出を紐づけるのと同じこと)。
一般的な尺度や”正解”がない世の中で、一人ひとりの”問い”やその表現が大事になってくる。自分がどう思うのかを掘り下げて表現することは美しいなーと思う。(バチェロレッテの杉ちゃんのつむぐ言葉も本当に素敵だったな!笑)
21.哲学の先生と人生の話をしよう
・世間が面白くない時は勉強に限る。失業の救済はどうするか知らないが、個人の救済は勉強だ
・ 運がいい人は計算量が多い:大量の情報を受け取り、処理していて、日常生活の選択の場面にそれが役立っている
・プラス志向の人はあまりものを考えていない:悪い方向に向かっている多くの事柄を見ないように抑圧し、周囲の人間を考えることに使われるエネルギーはわずか
・モテるとは、敷居が低く、心の穴をうめてほしい人が殺到すること/憧れとは、その人の力になりたい、その人がいてくれて嬉しいと思われること
何となく買ったらめっちゃ人生の勉強になった本。私は楽観的な人間だけど、広く周りをちゃんとみて考えられるようにしなきゃと思った。いろいろな人の人生相談に答えてて、恋愛系もかなり勉強になった。今年は哲学の本もっと読みたいな。
おわり
2020年も、たくさんの新しい挑戦と学びがあった1年でした。一緒に働いてくださった皆様、相談にのってくださった方、コミュニティで一緒に勉強させていただいた方、プライベートで仲良くしてくださった方、本当にありがとうございました。
いろいろな出来事を通じて”自分”と向き合うことが多かった1年だったので、2021年は、自分の役割や組織を超えて、相手への”優しさ”を考える一年にしたいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします!
おすすめの本があったらぜひ教えてください。☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
