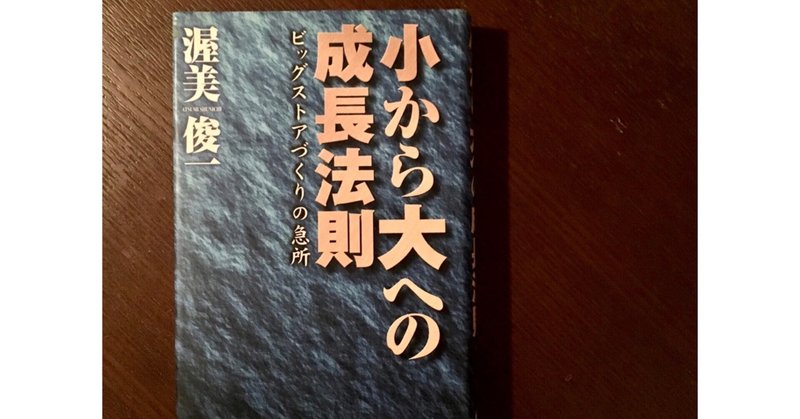
チェーンストア理論とカジュアルダイニングブーム
※ こちらの内容は、ウェブサイト(現在は閉鎖)にて2016年~2019年に掲載したものを再投稿しています。内容等、現在とは異なる部分があります。ご了承ください。
チェーンストア理論についての小難しい内容をぼくがここで説明できるというわけでもないけれど、それでも素晴らしいものということが何となくでもわかるのは、20代前半のころや店をやってからもチェーンストア理論の書籍を何冊も読んでいたから。
もし興味を持たれた方がおられたなら、日本における第一人者である渥美俊一さんがたくさんの著書を遺されているのでお薦めする。
また渥美さんのお名前やペガサスクラブとググるだけでもこれまでの功績をある程度知ることができるし、渥美さんが設立されたペガサスクラブに加盟され学んでこられた企業名を見てもそれが外食企業だけのものでないことや、そのほとんどが「誰もが」というほど名の知れた大企業ばかりなのもわかる。
それもたった一代で、その規模にまで成長した企業の多いこと。これもチェーンストア理論が根底にあってこそ可能にしたものだった。
日本へ上陸する70年代までは水商売と呼ばれていた飲食業界を、この短期間で産業と呼ばれるまでの規模へと成長させたのは紛れもなくチェーンストア理論だった。
ところが近年、「チェーンストア理論の限界」「脱チェーンストア理論」といった言葉を散見するようになった。
外食産業に限っていえば、ぼくの記憶だとこういったことを見聞きしはじめたのは、2000年前後のカジュアルダイニングブームのころからだった気がする。
当時、「多店舗化は志向してもお店のつくりや商品は画一的ではない」といった考え方がイケてるとされ、現在にも続く潮流となりはじめたころだったと思う。
こうなると画一的であることこそが真髄だったチェーン店は、その最大の武器であったはずの標準化がイメージとして裏目となり、真逆を行く新興勢力(チェーンでなく多店舗化する外食企業)からすれば、「チェーンストア理論は、もう古い」「イケてない」「これからは個性の時代」と自分たちの正当性を喧伝するための恰好の当て馬のような存在となり、時代の空気もまたそういったものになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
