記事一覧
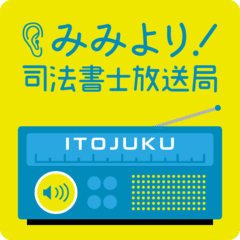
2023年 本試験分析会 記述式~場外乱闘編~第2回
分析会で触れられなかったことや解説レジュメに掲載できなかった点などを、問題解説制作者の立場から、伊藤塾の答練や模試の制作者でもある杉山講師・筒井講師の両制作者と蛭町講師が対談形式でお話しします。 第2回は、不動産登記法の残りの部分です。 第1回はこちら>> https://note.com/itojukusyoshi/n/n60d6898bdf63 第3回はこちら>> https://note.com/itojukusyoshi/n/n5ba9109824b5 第4回はこちら>> https://note.com/itojukusyoshi/n/n0d4995098612
















